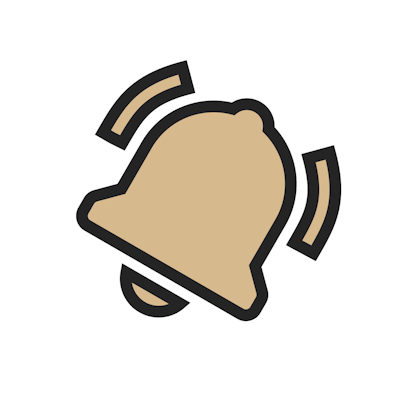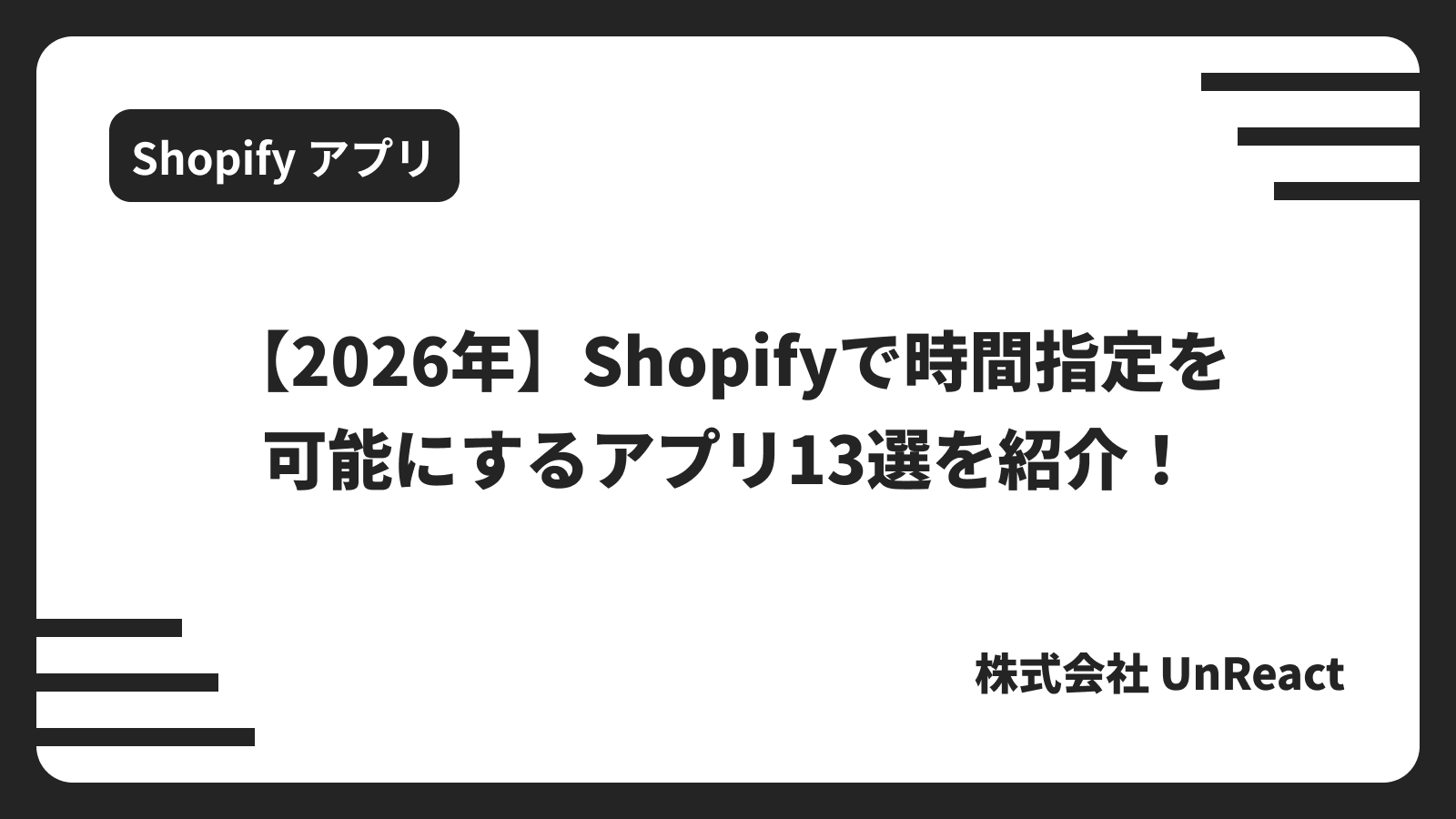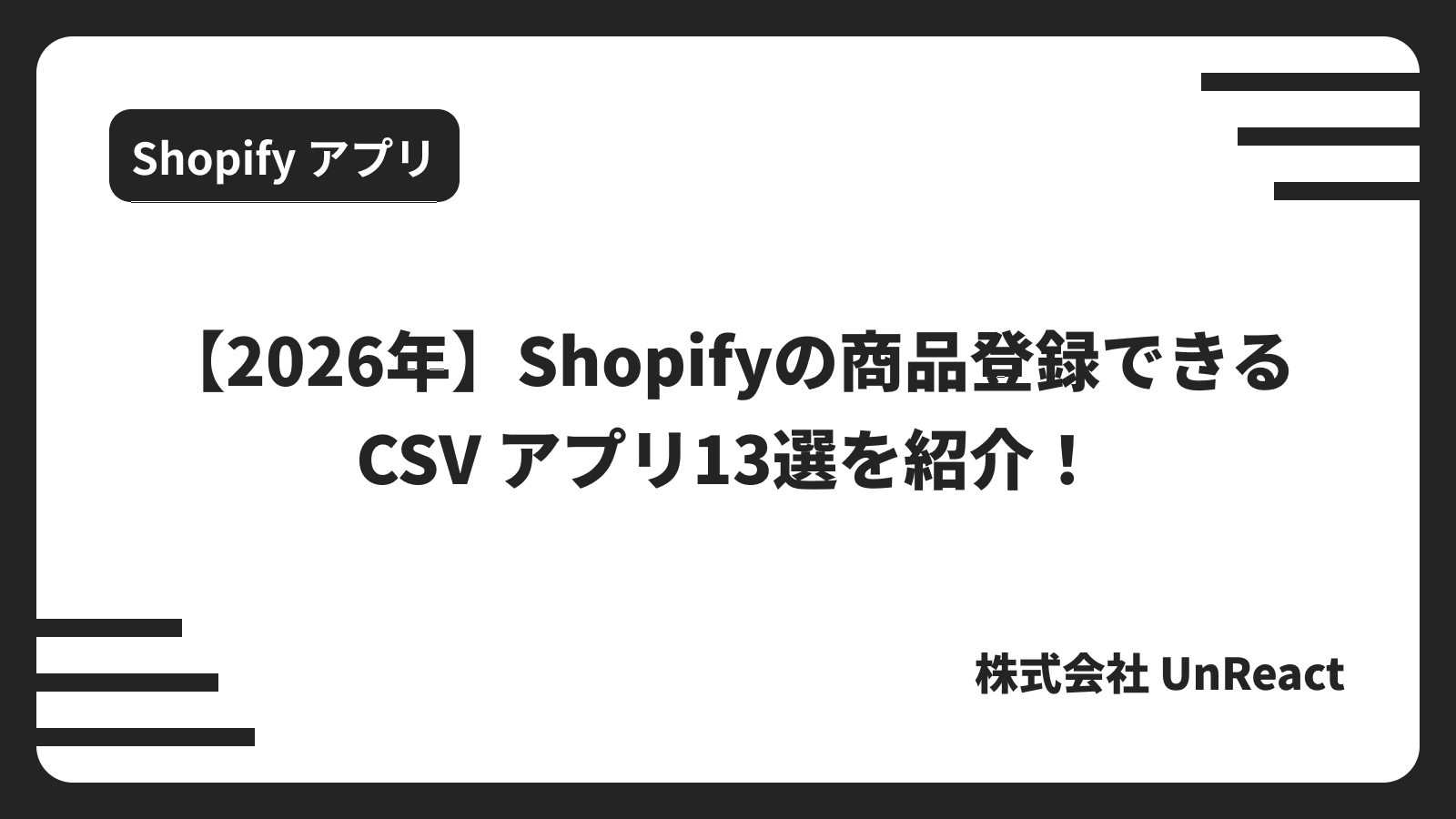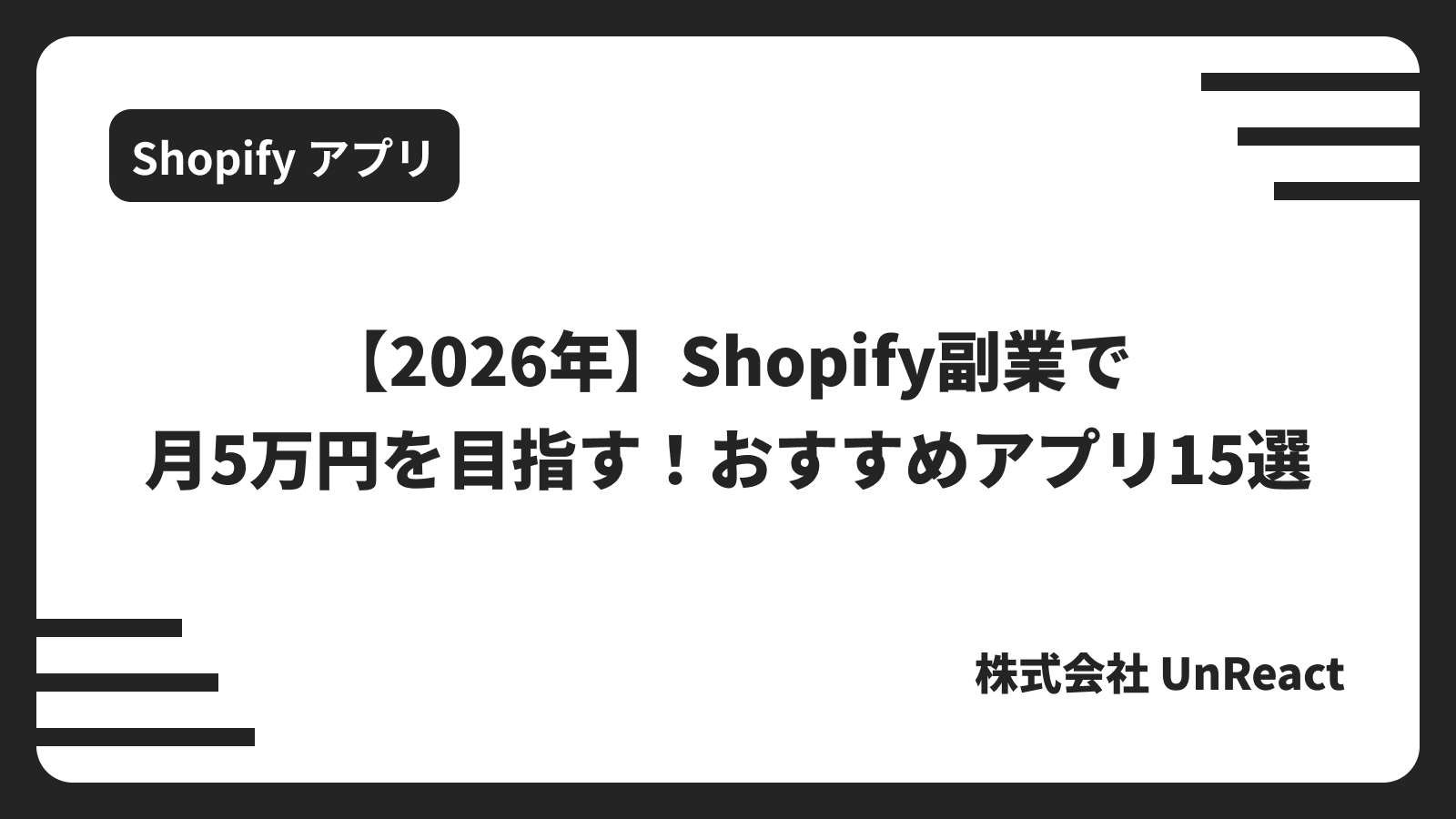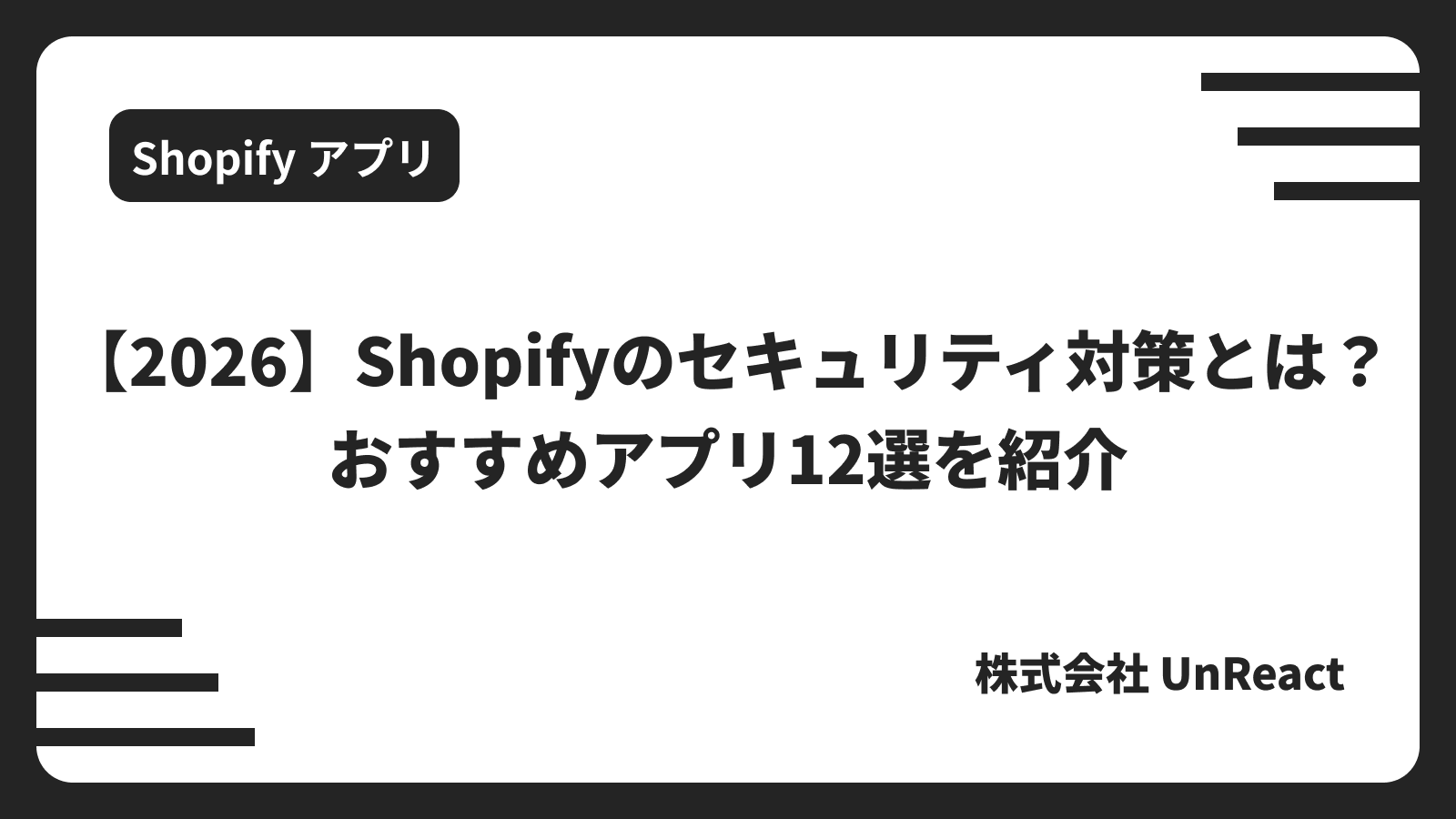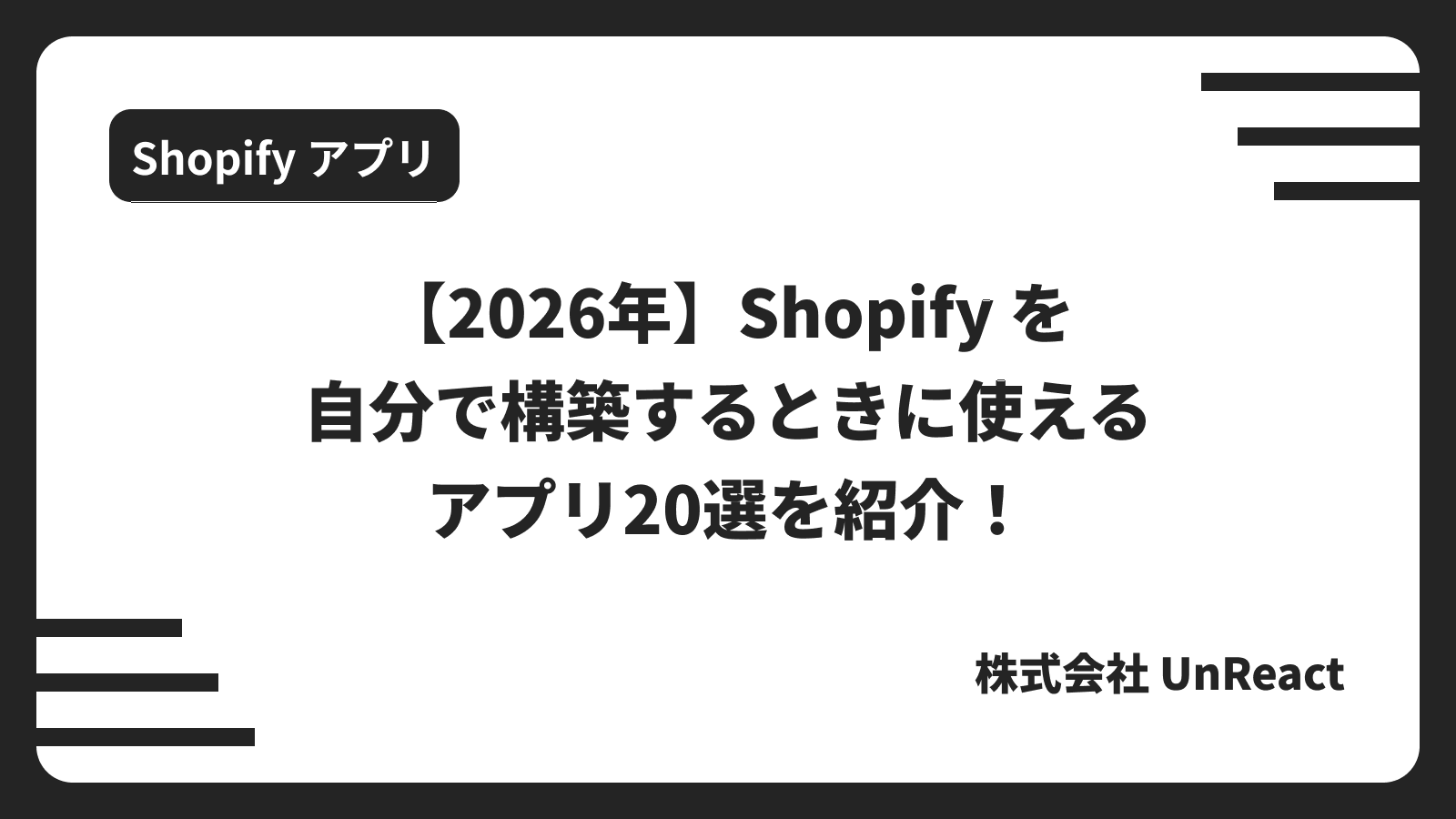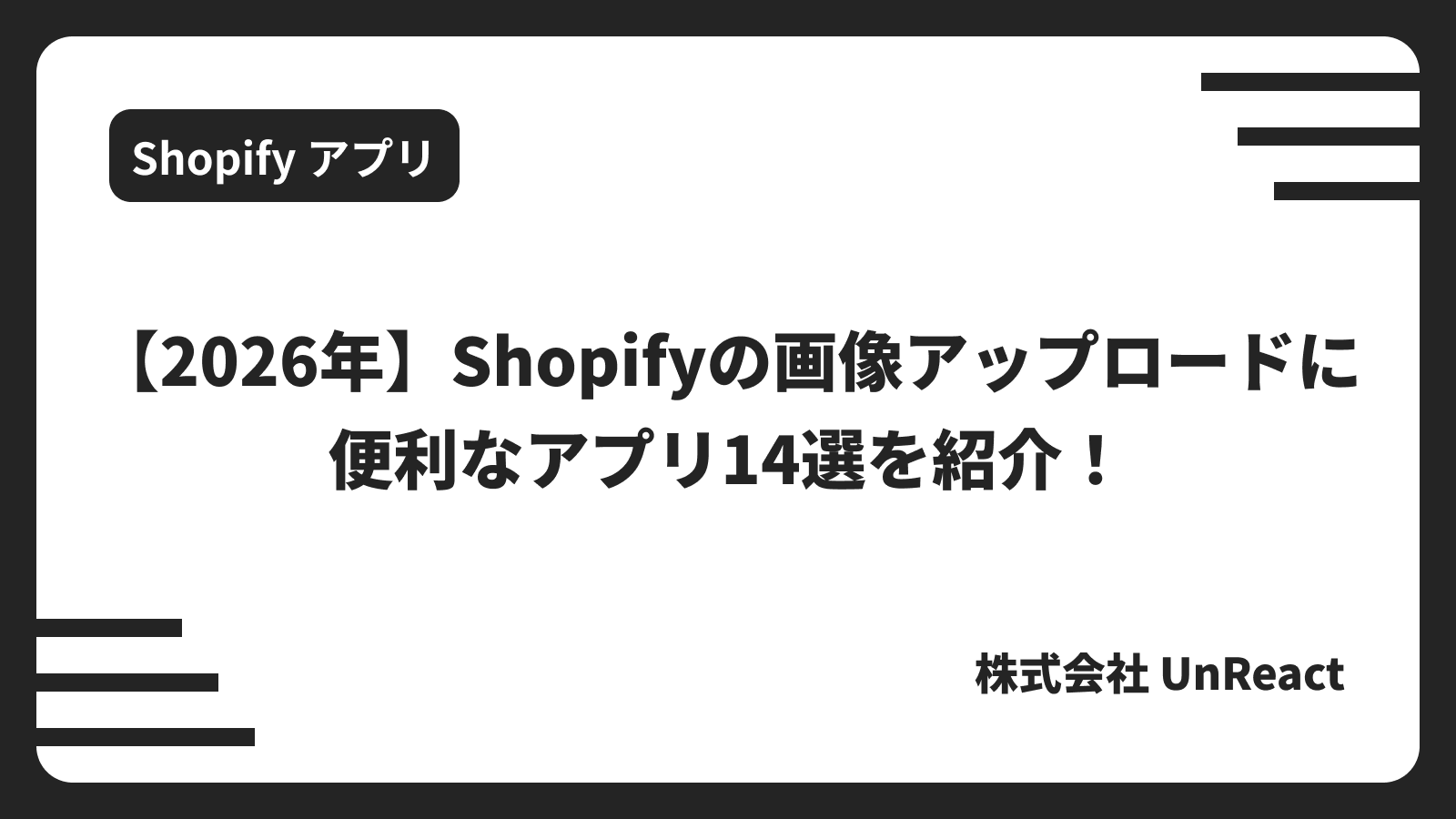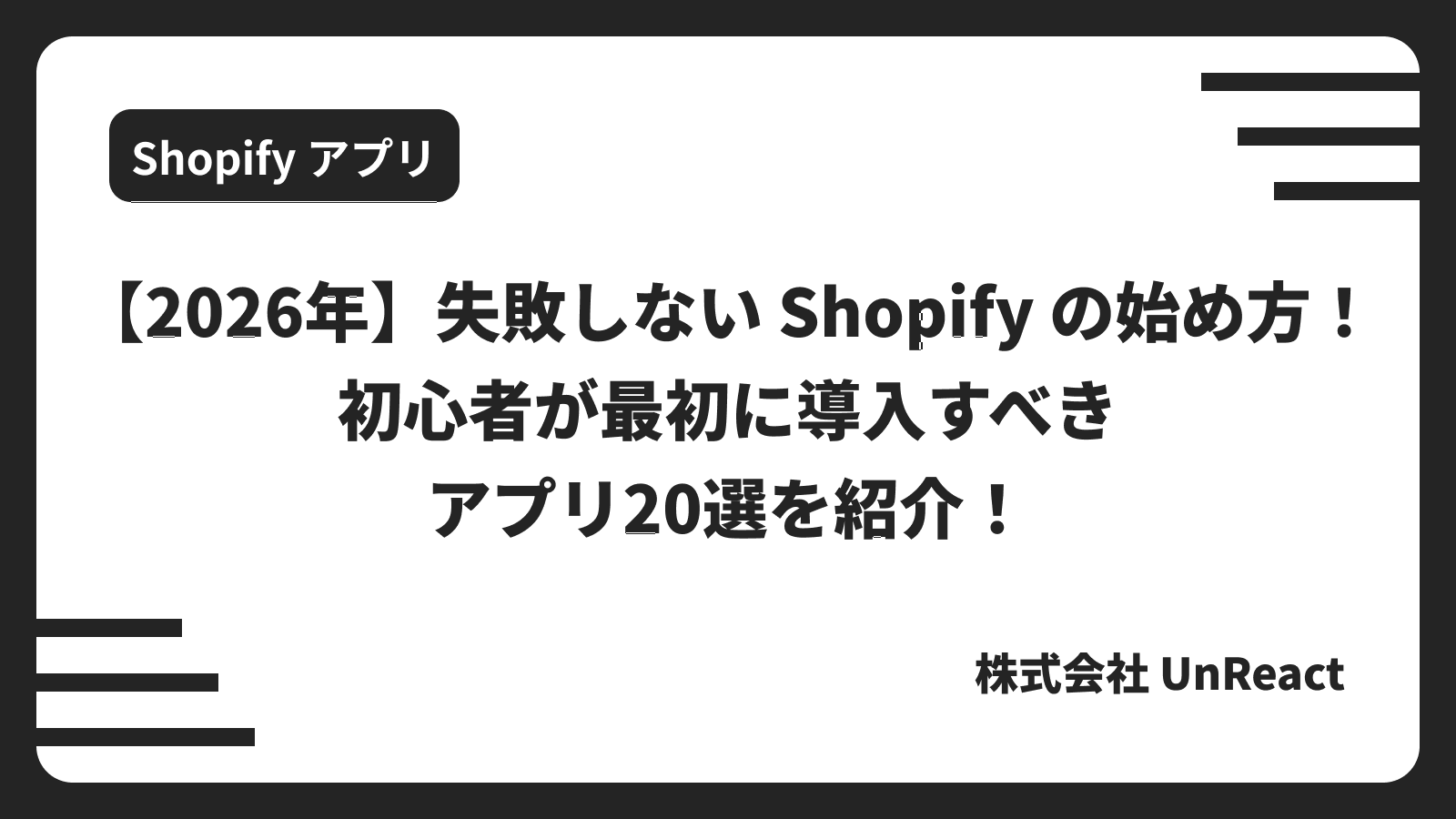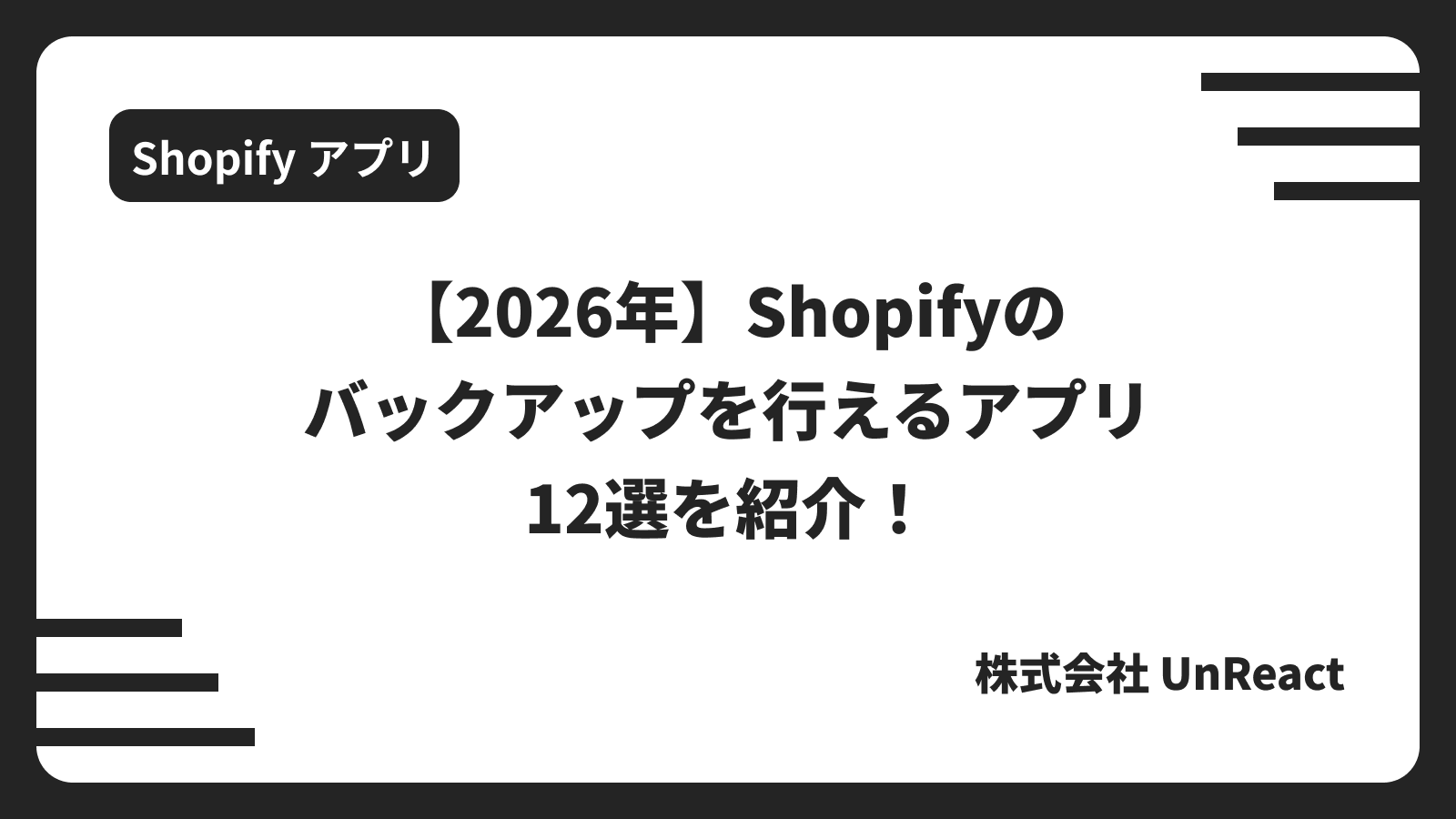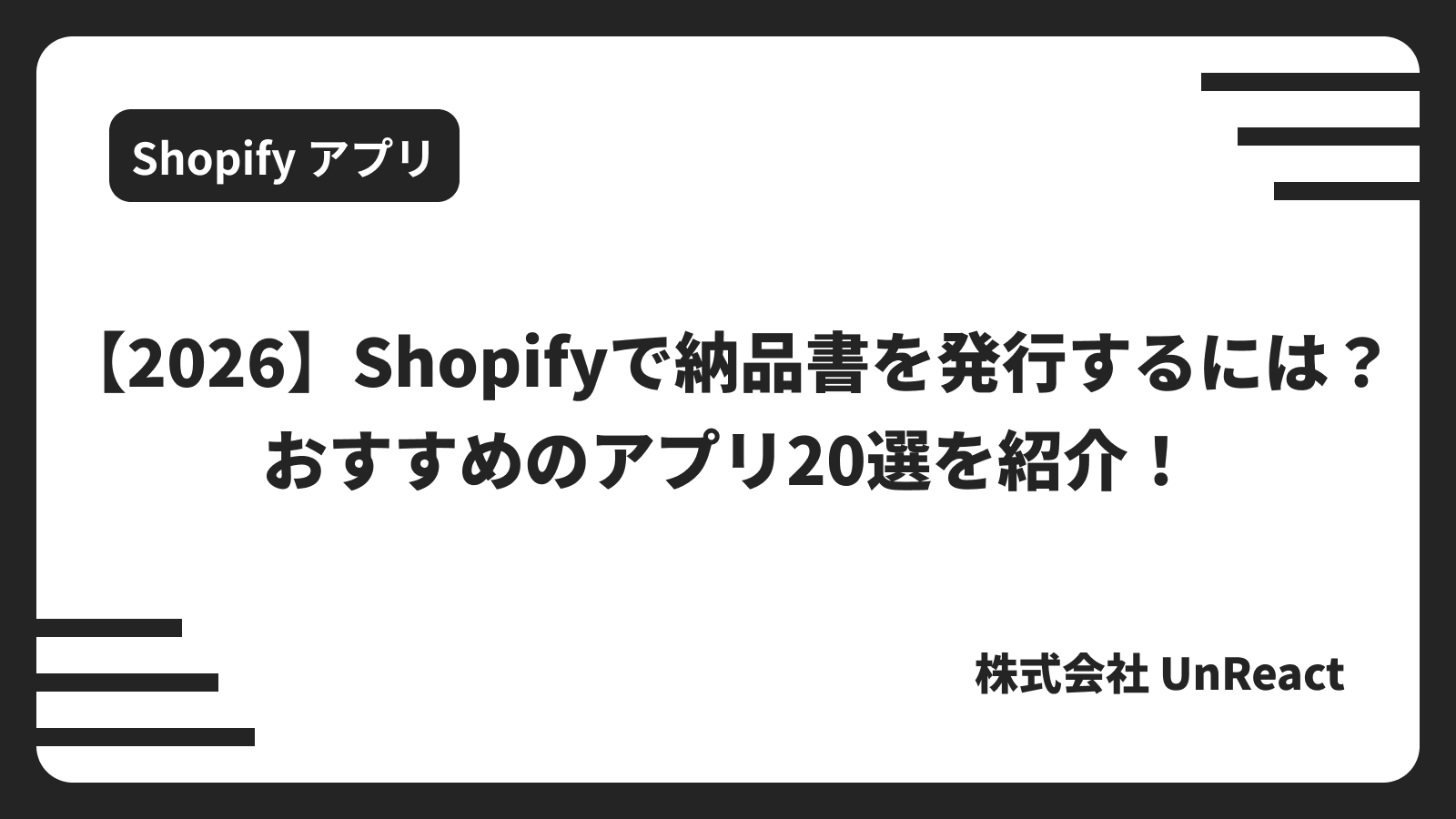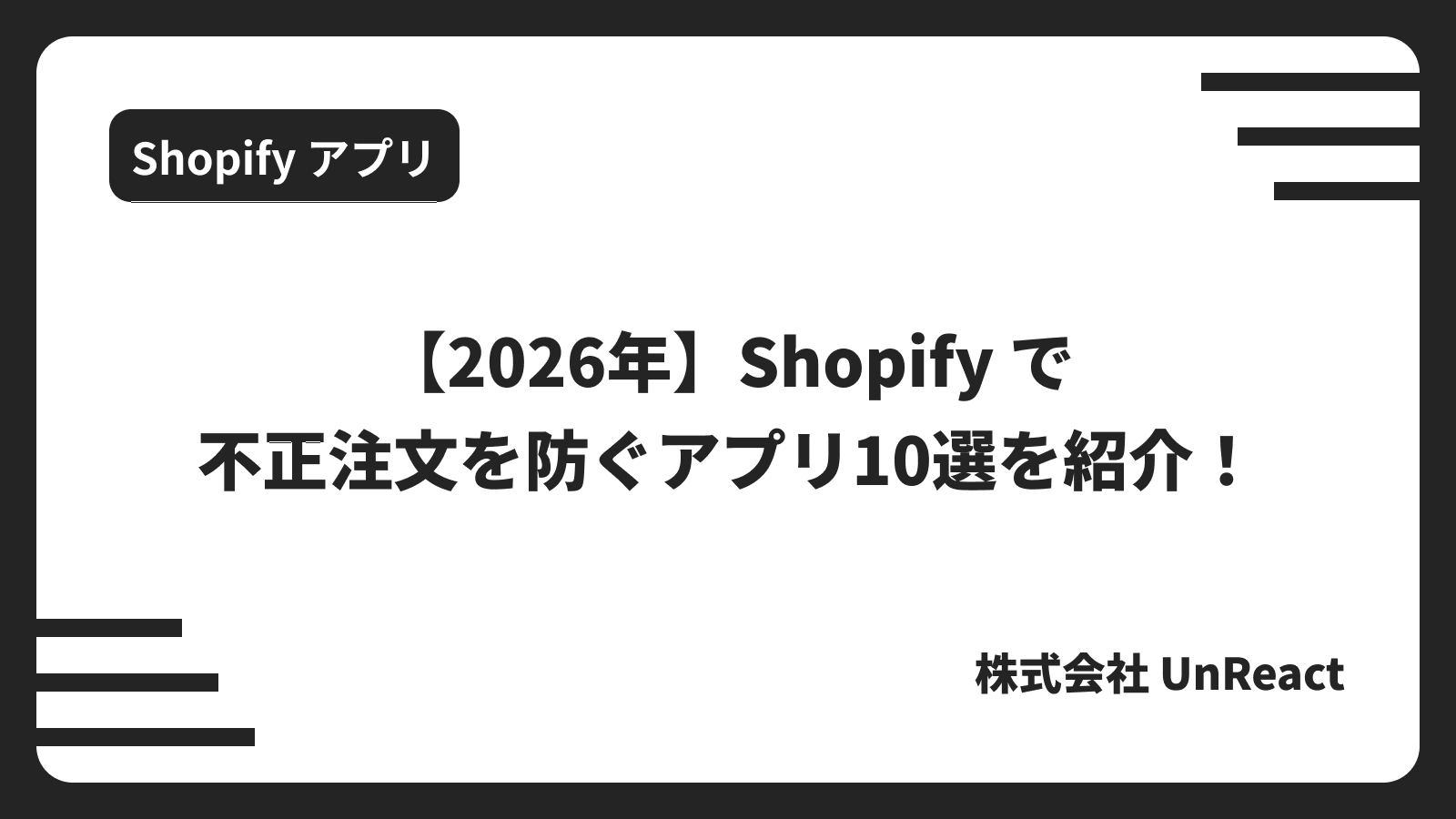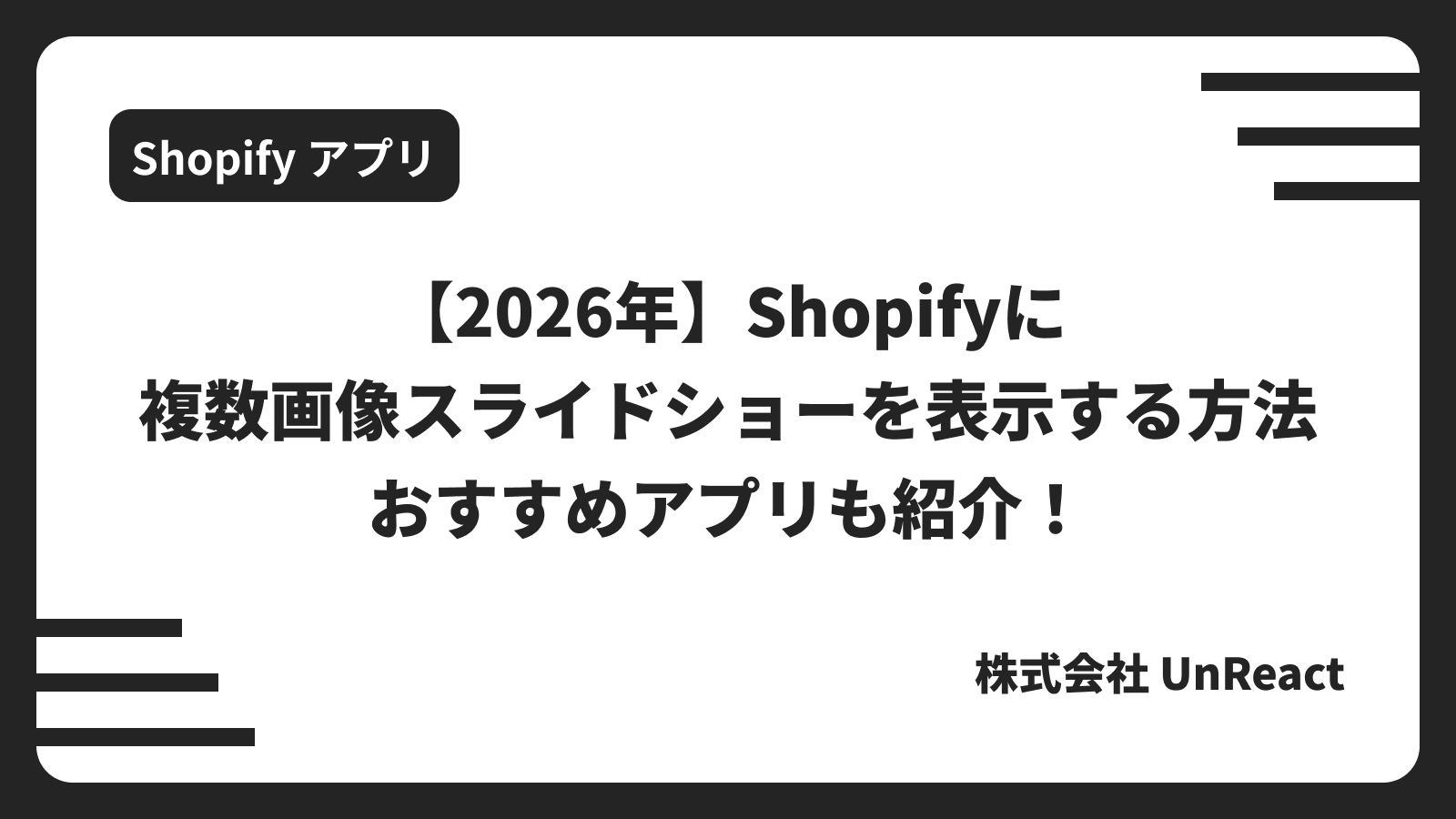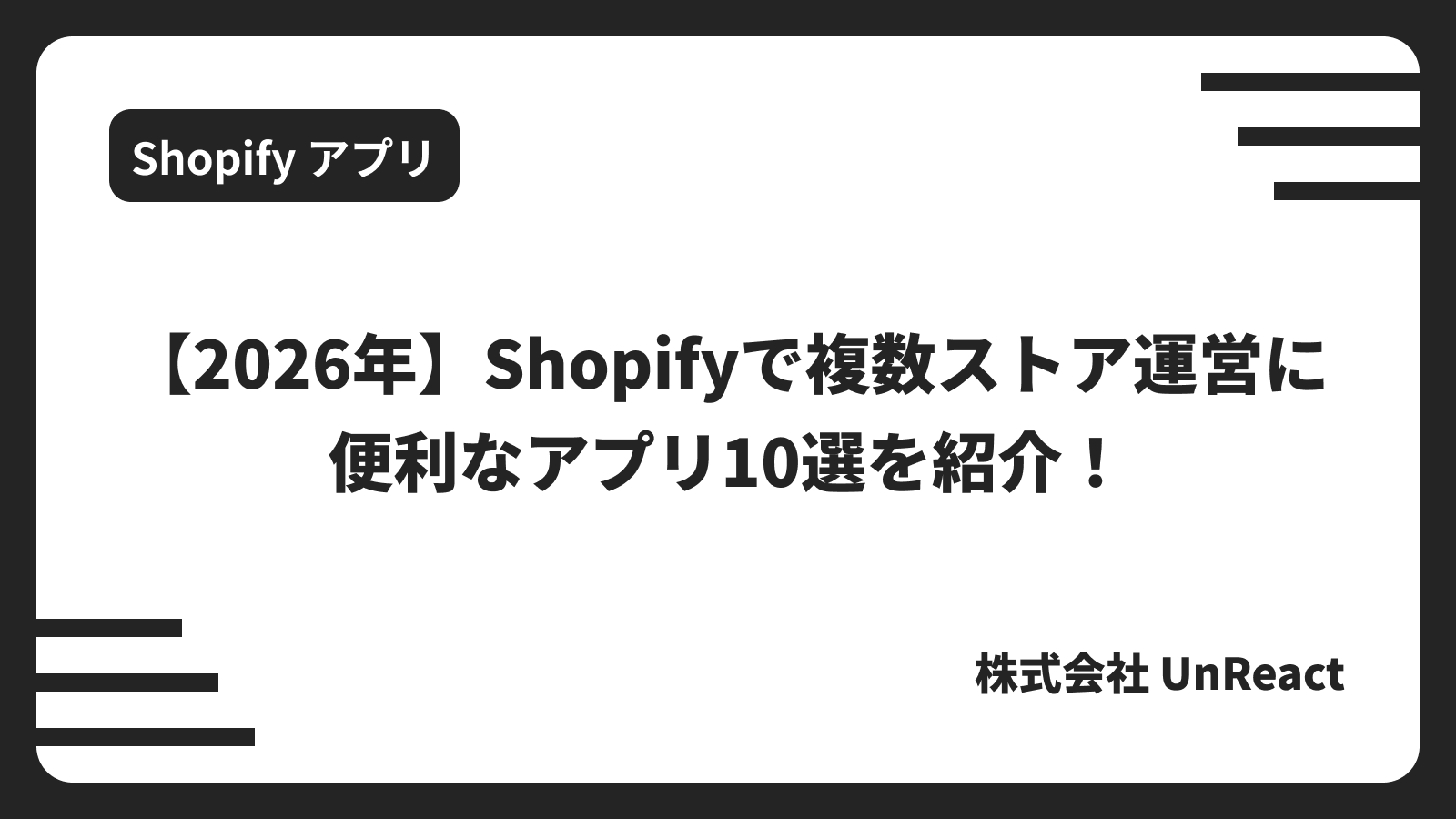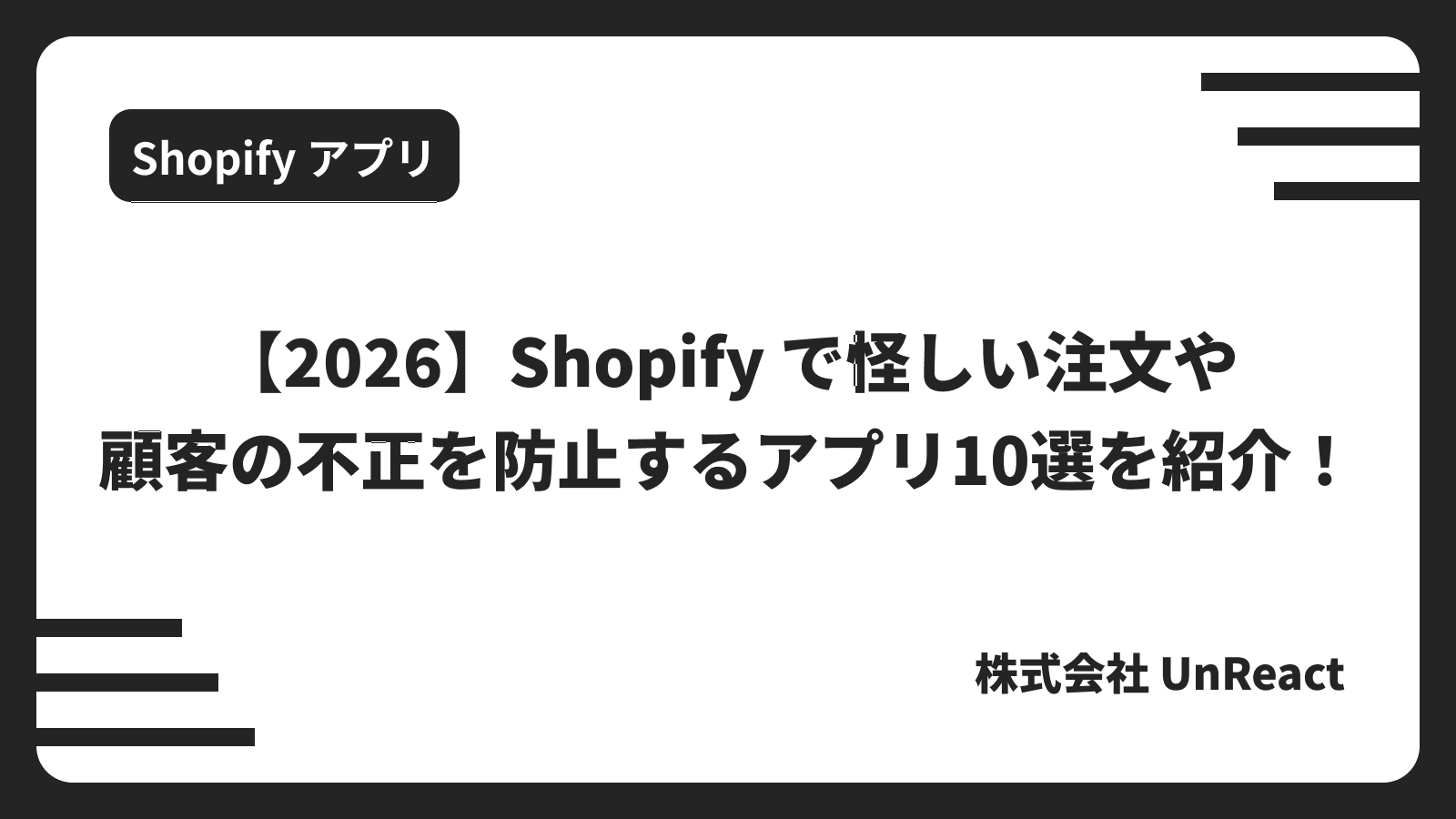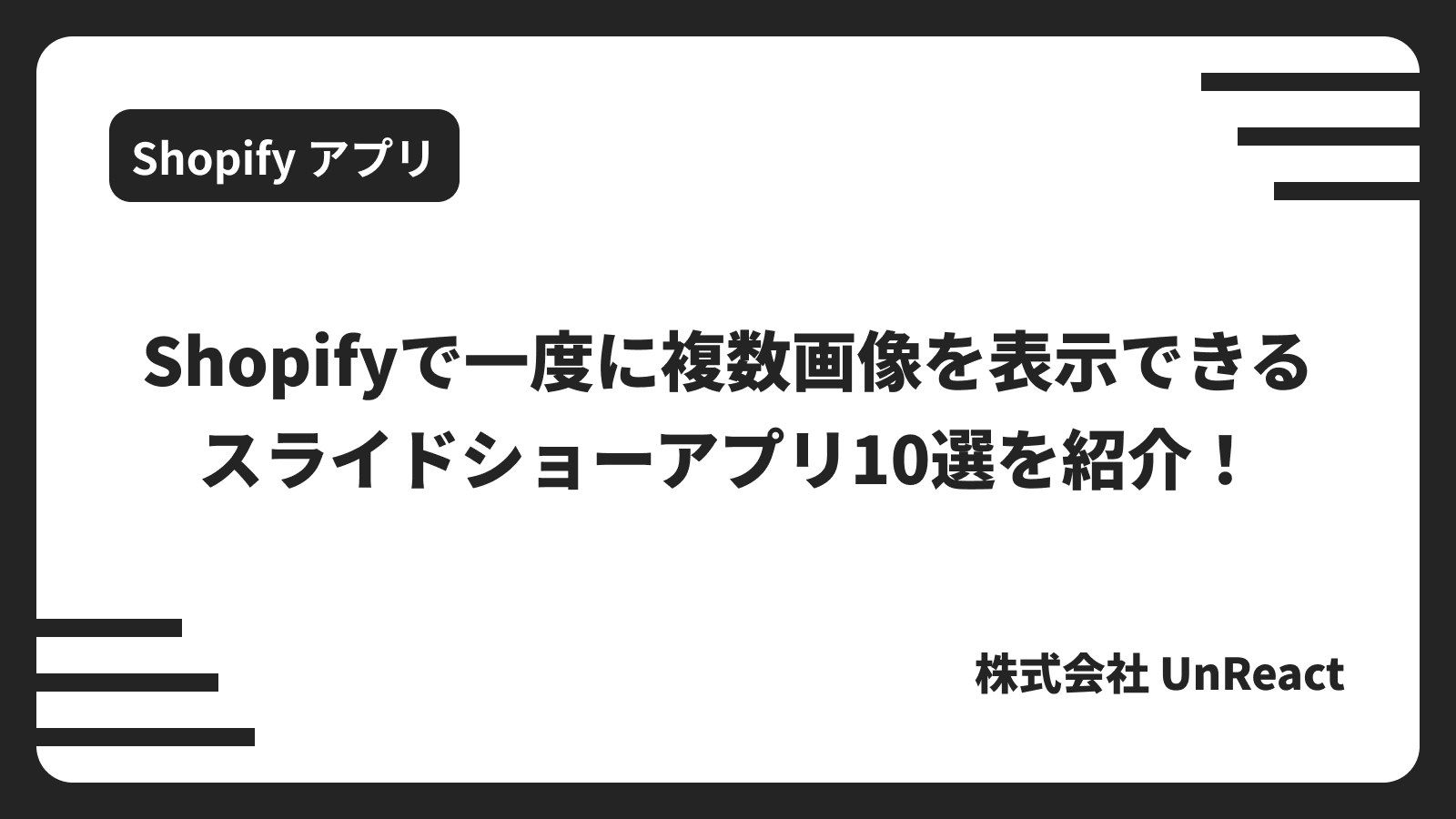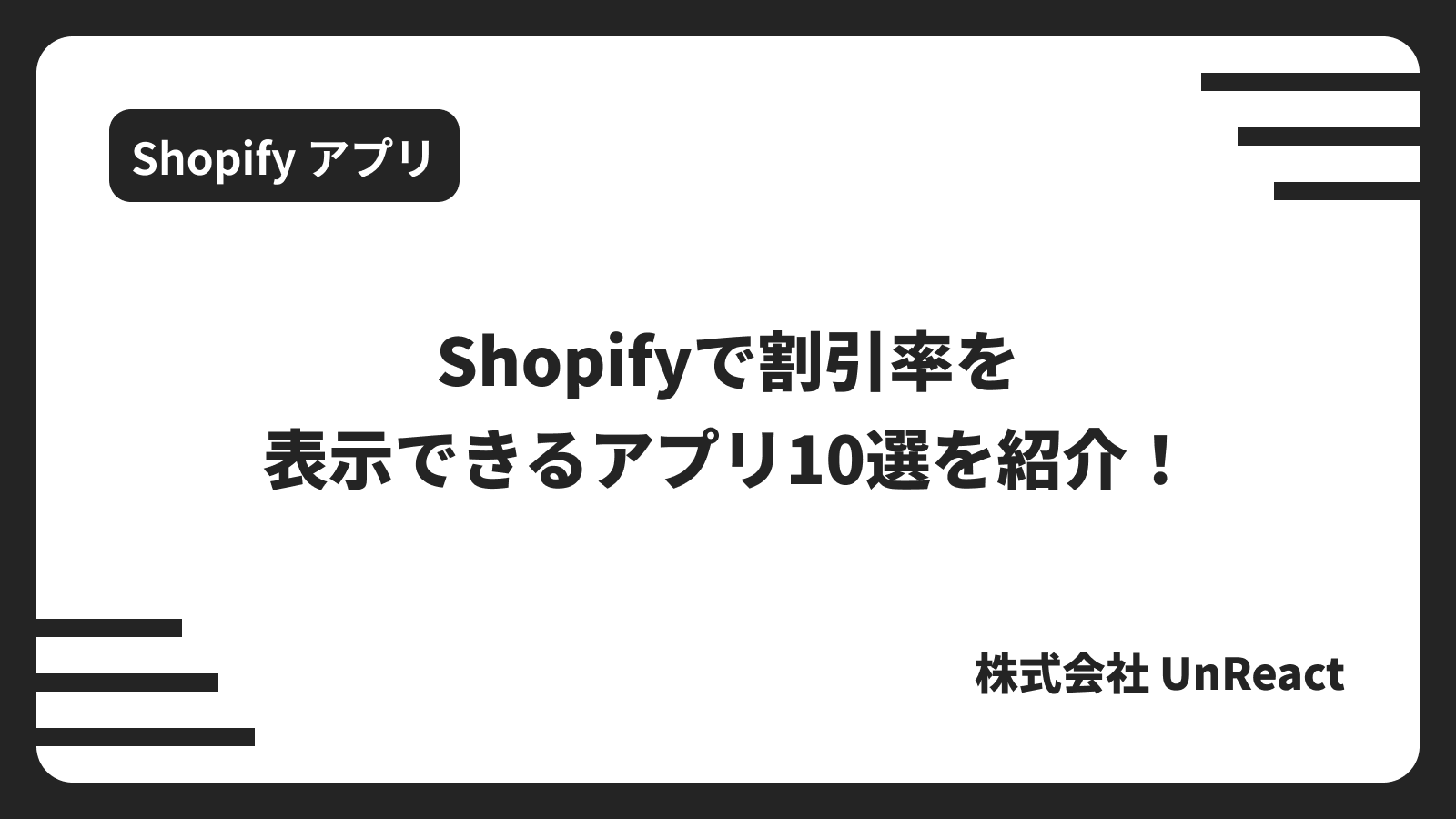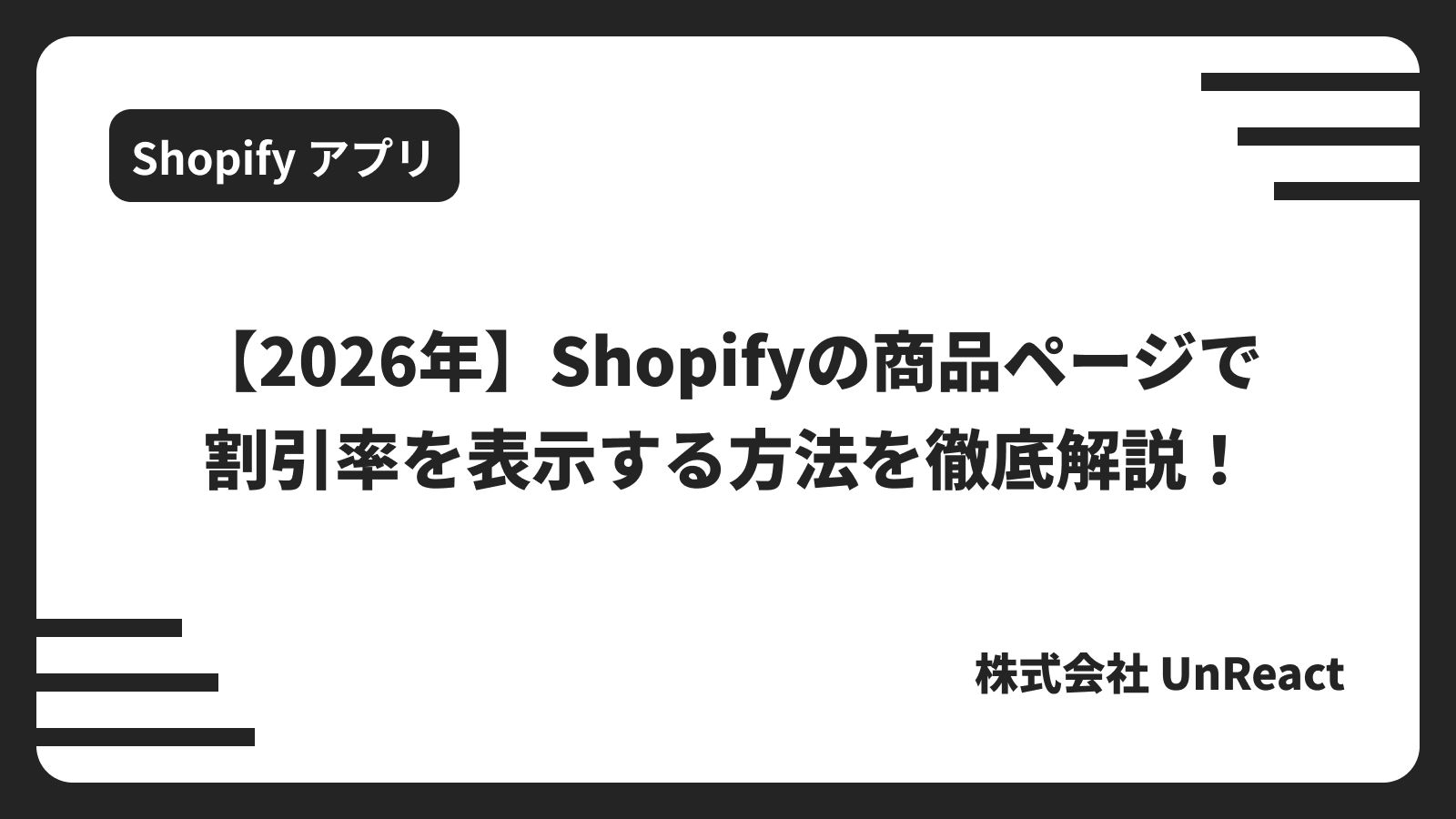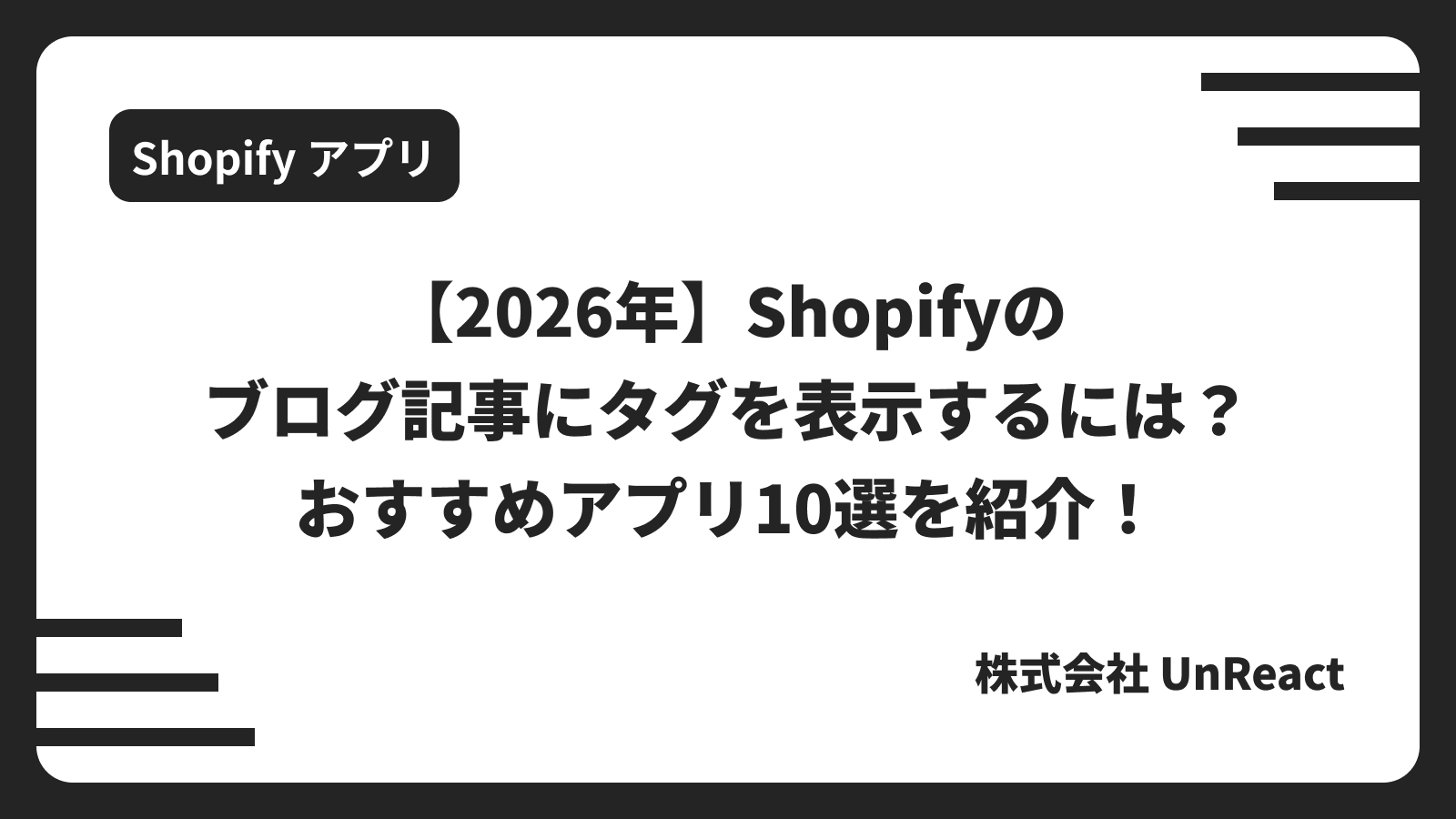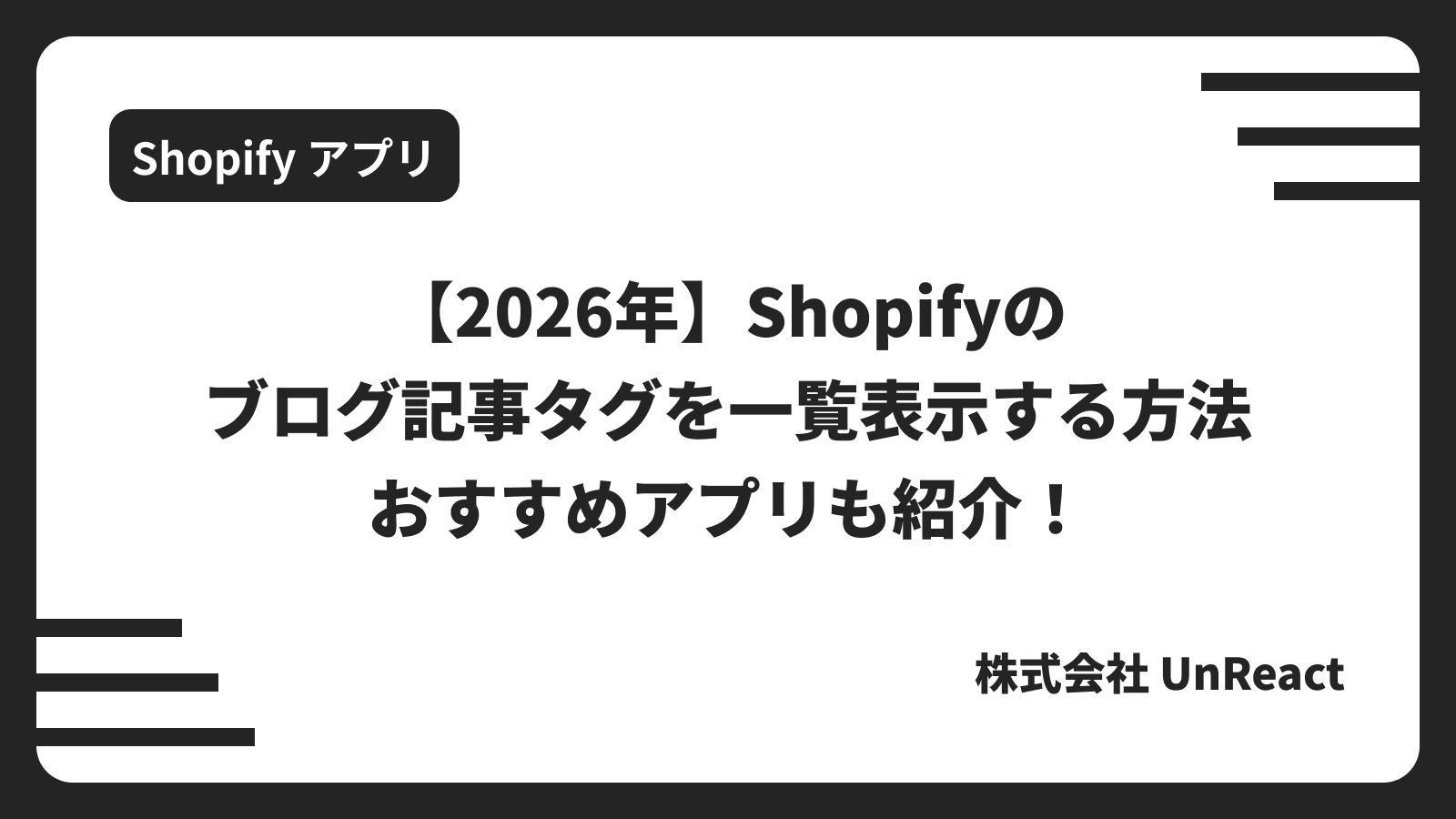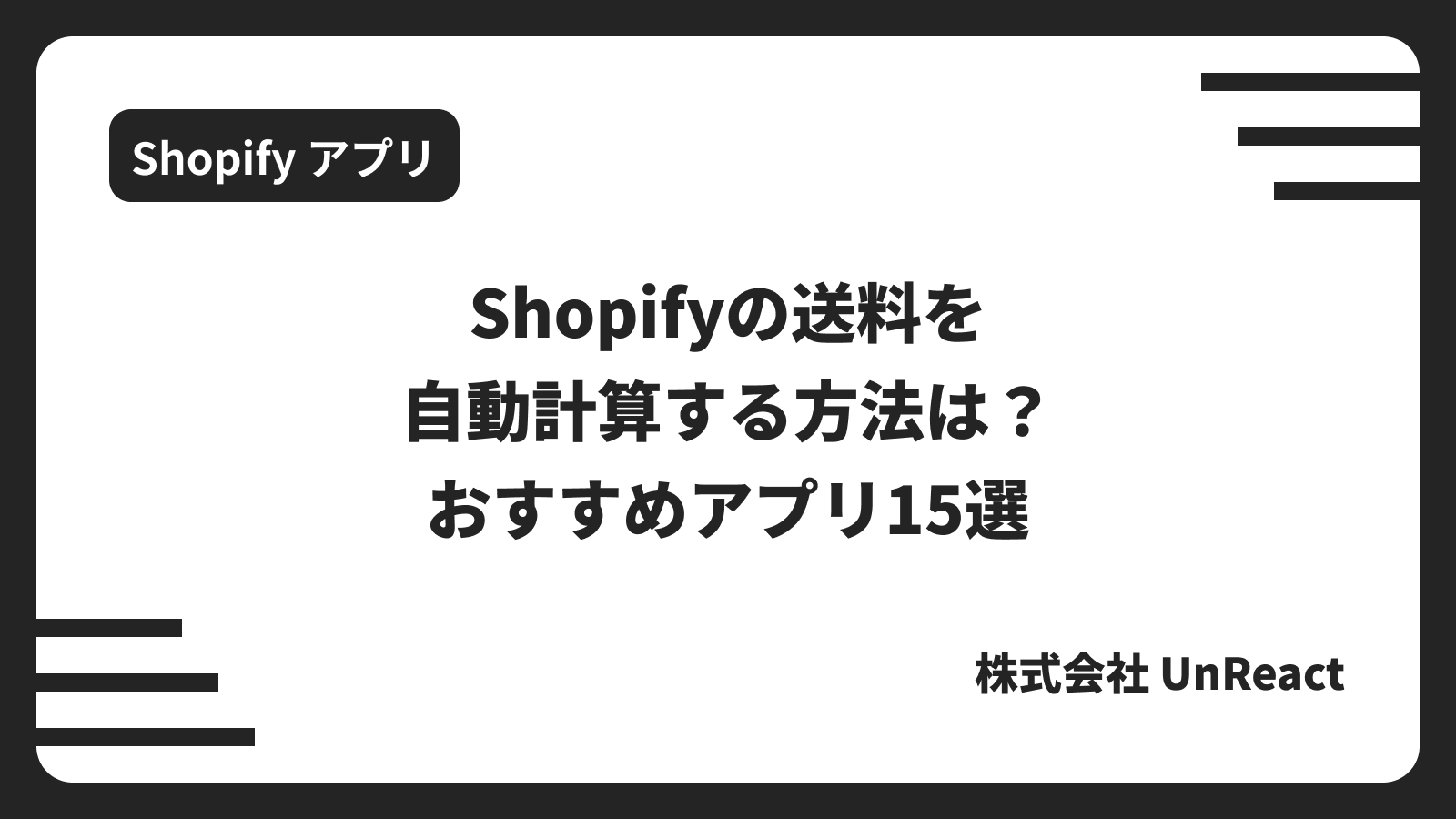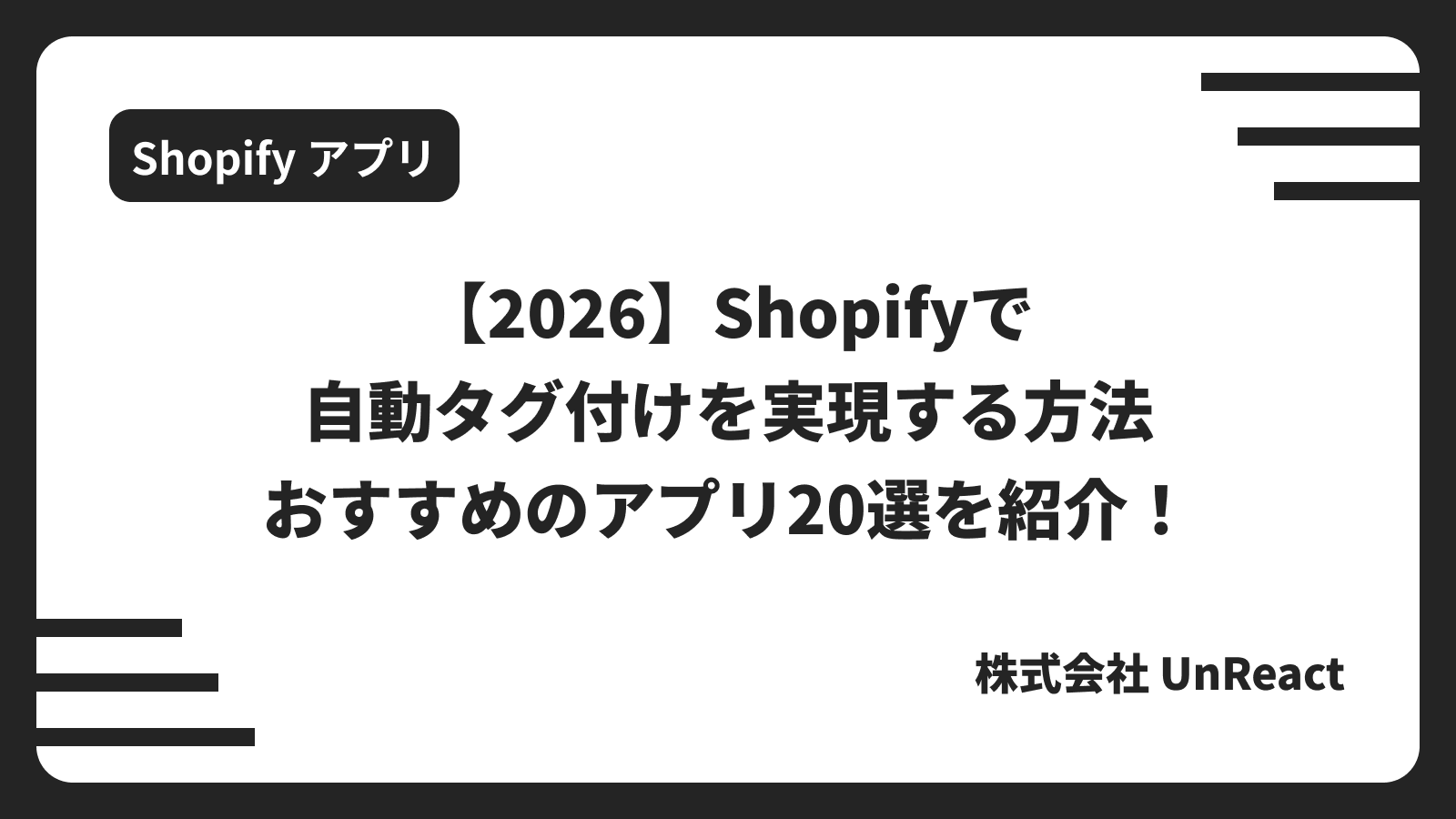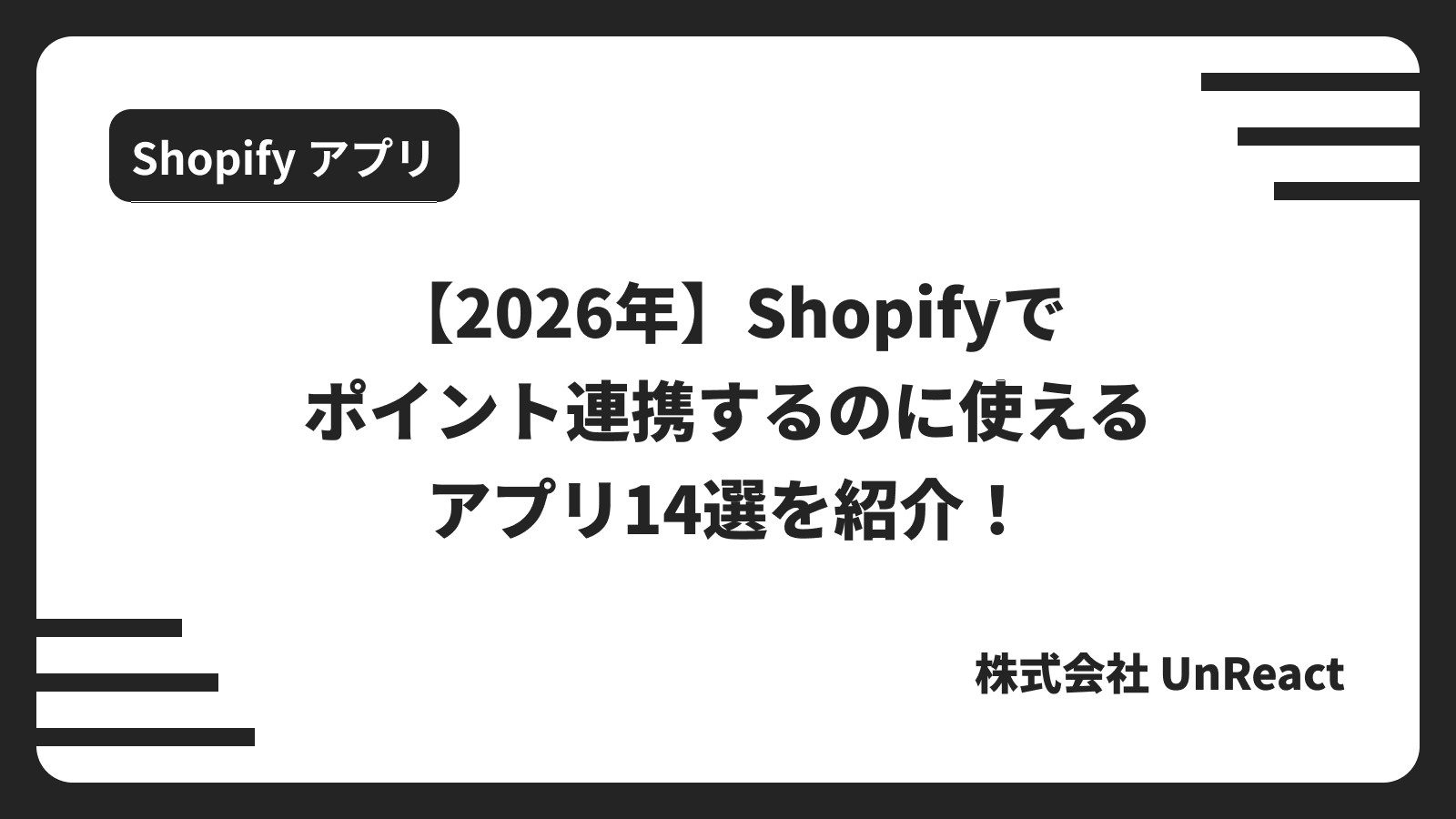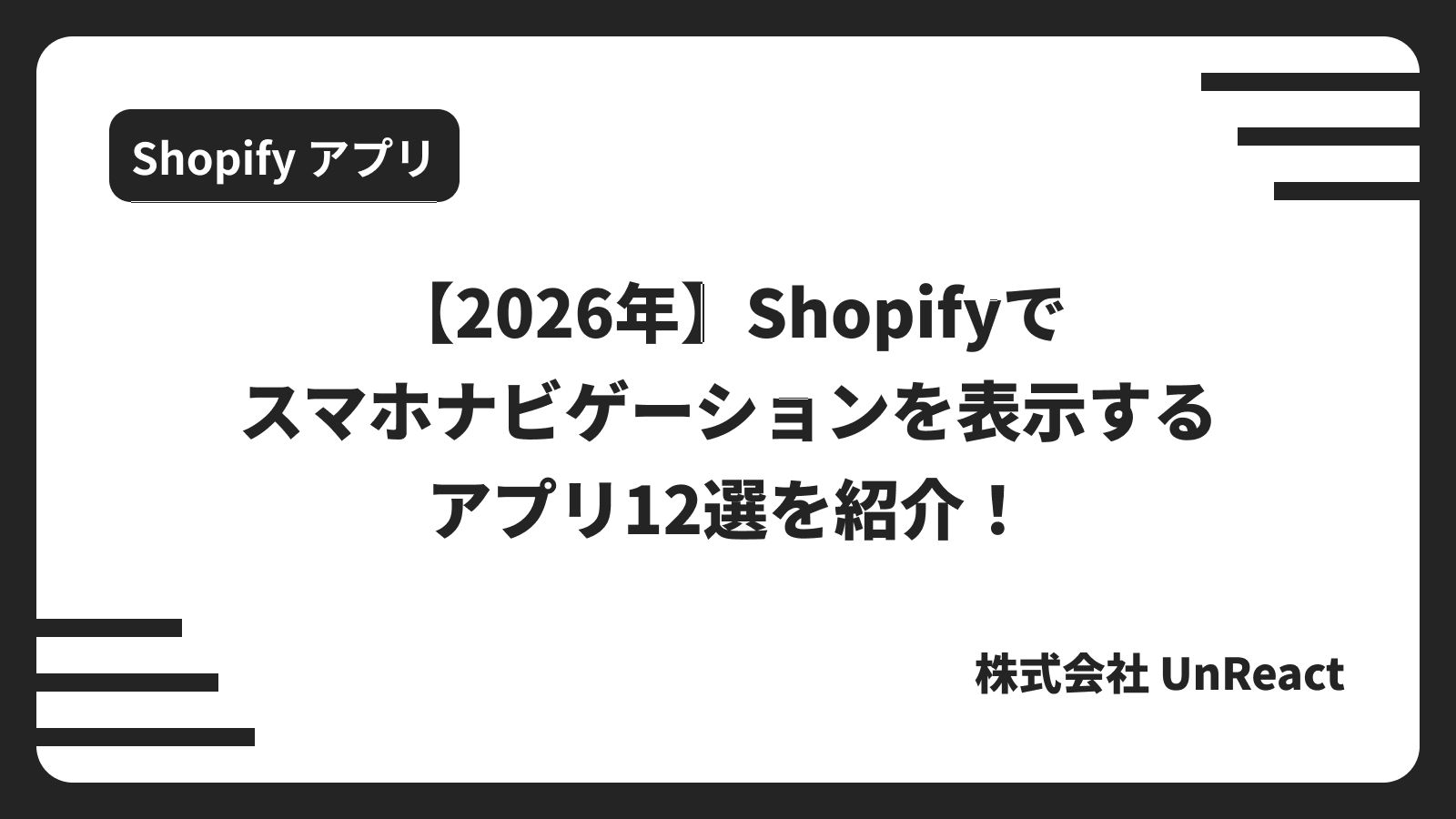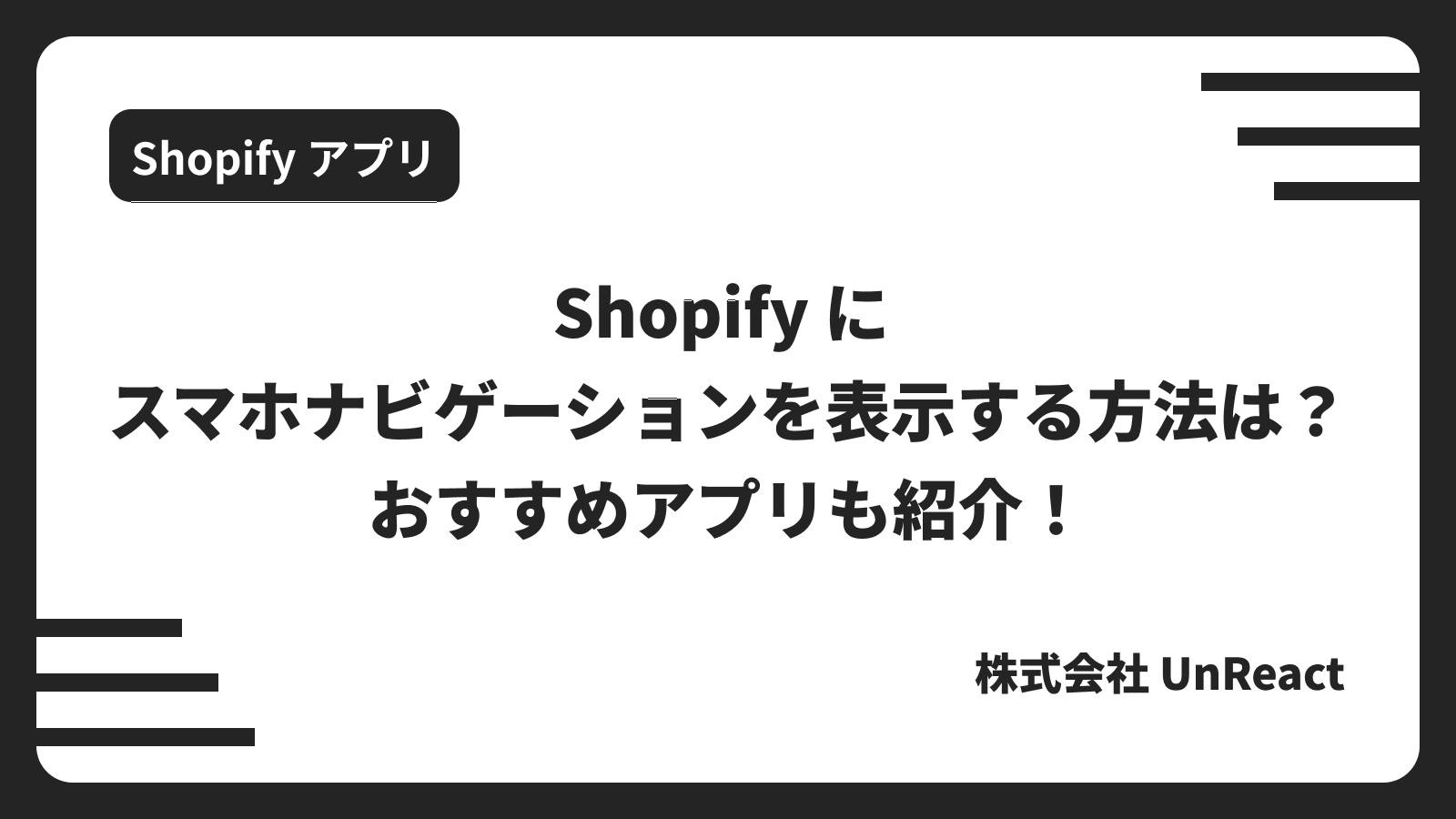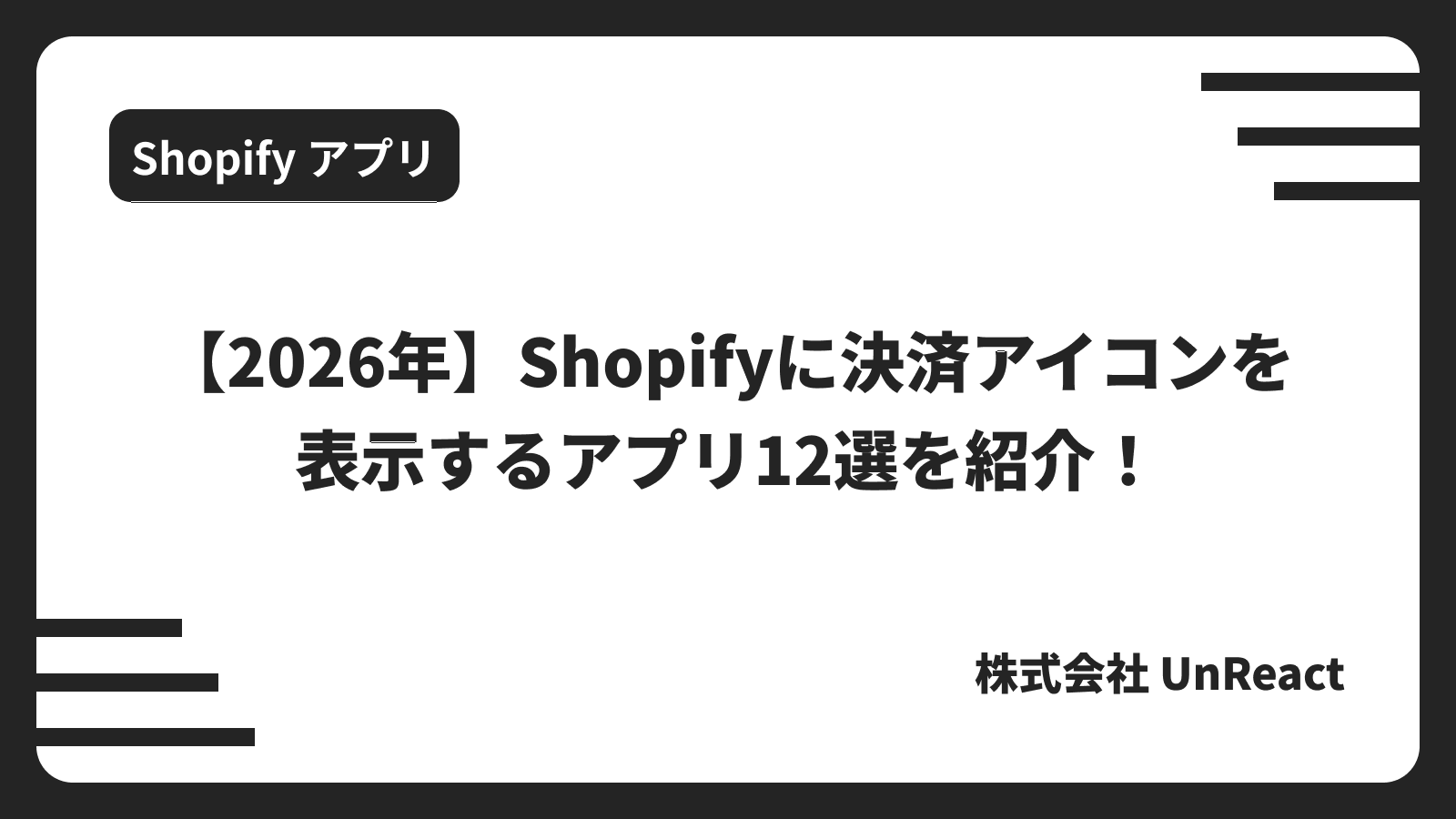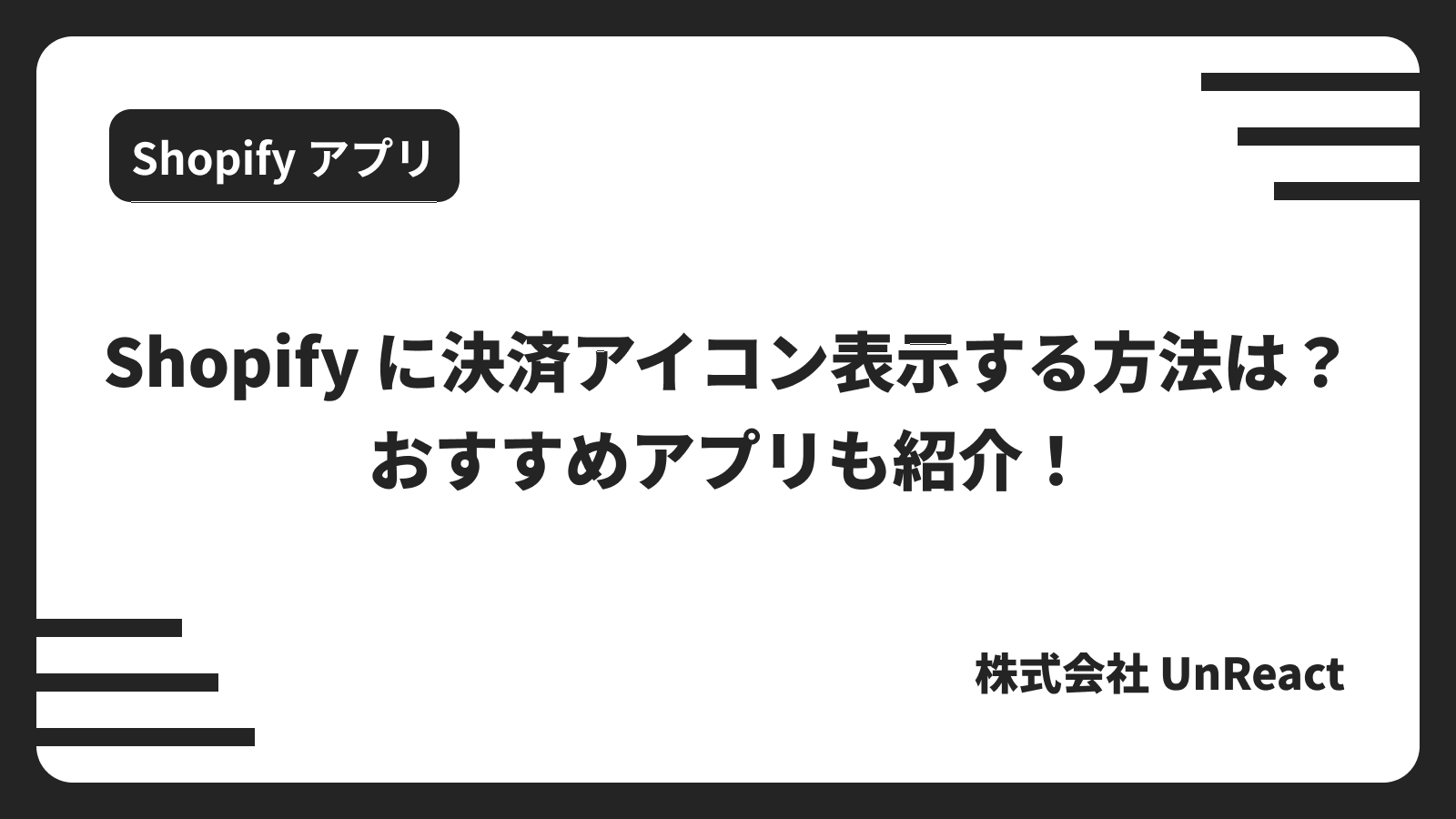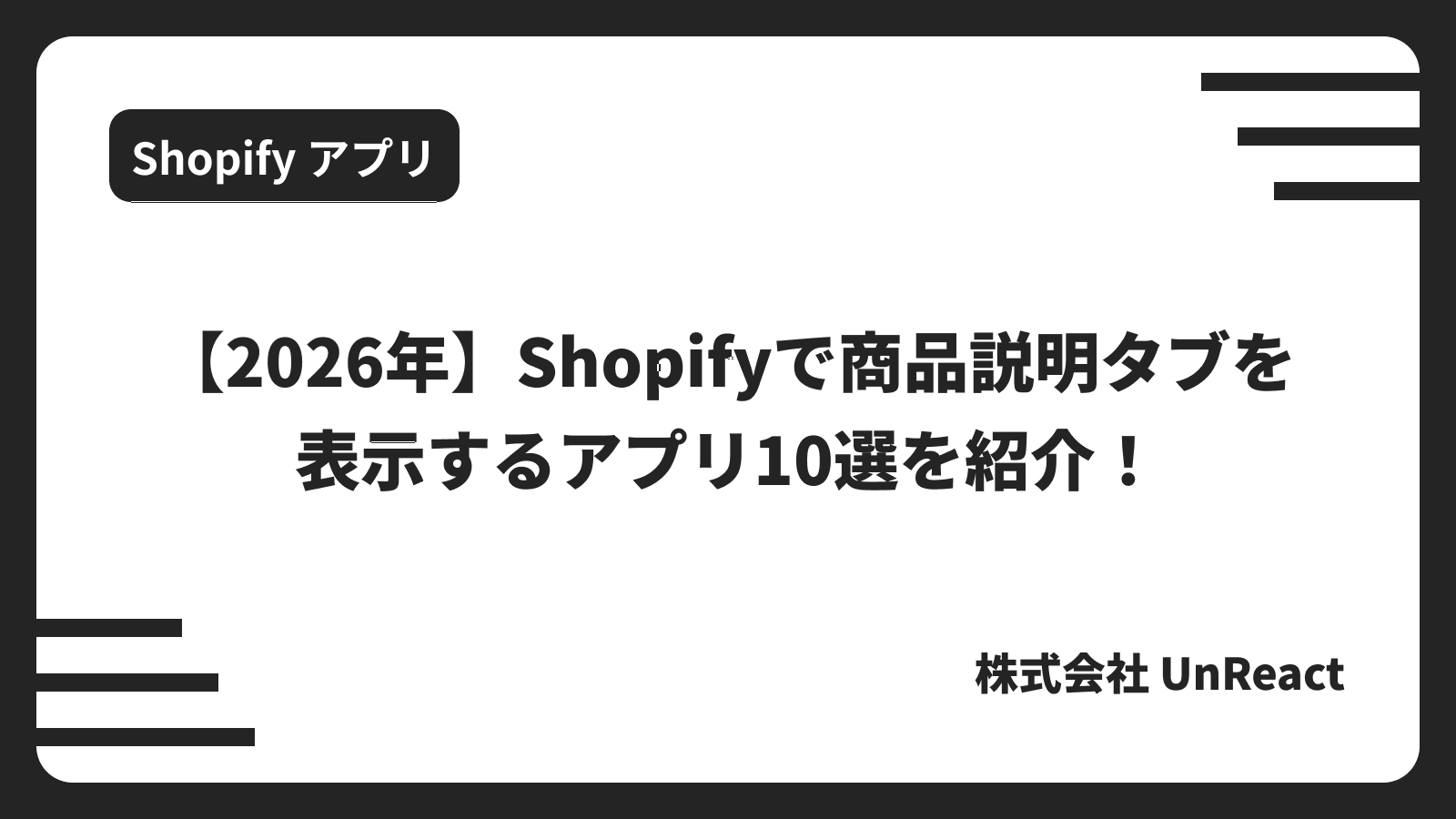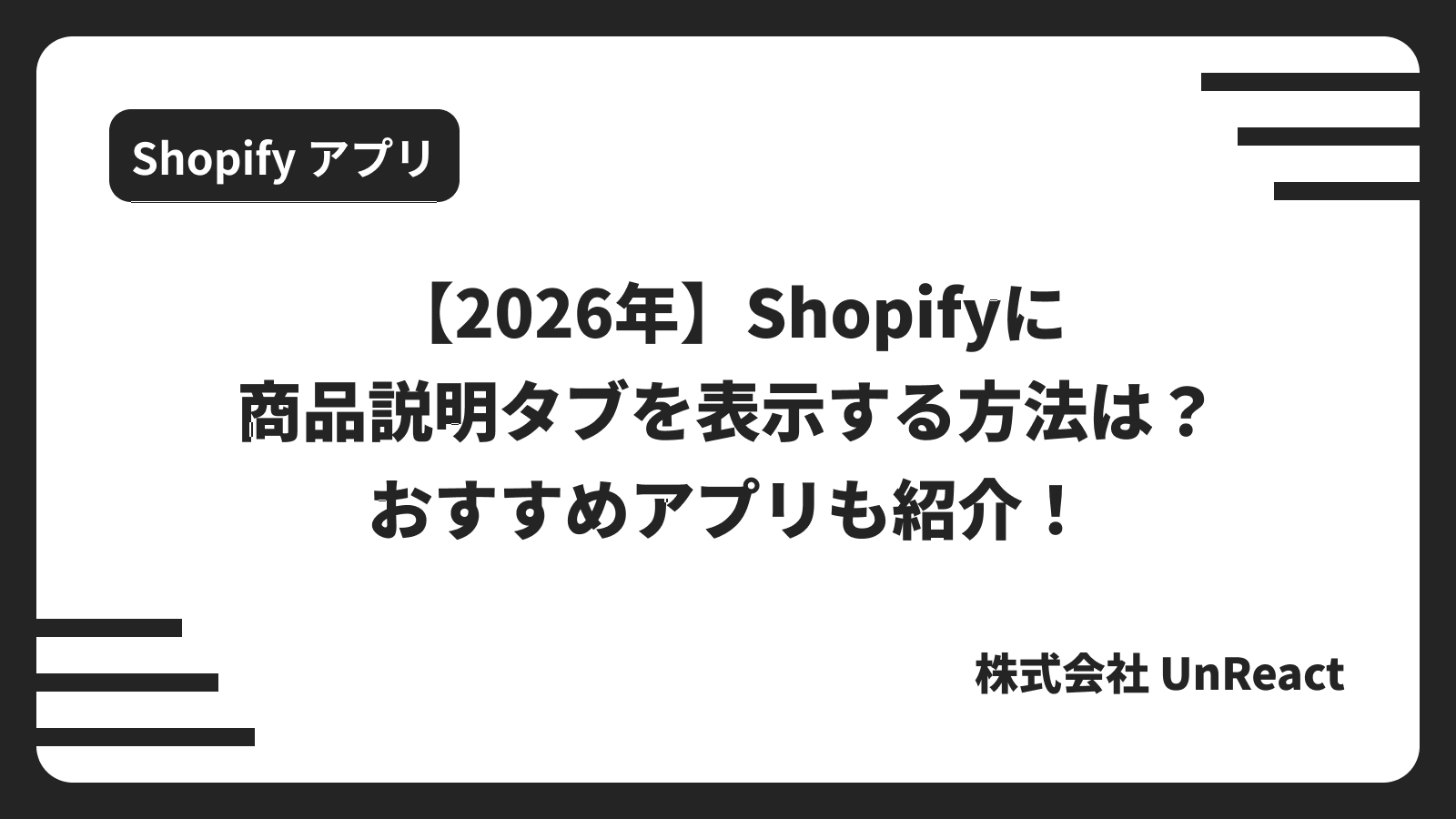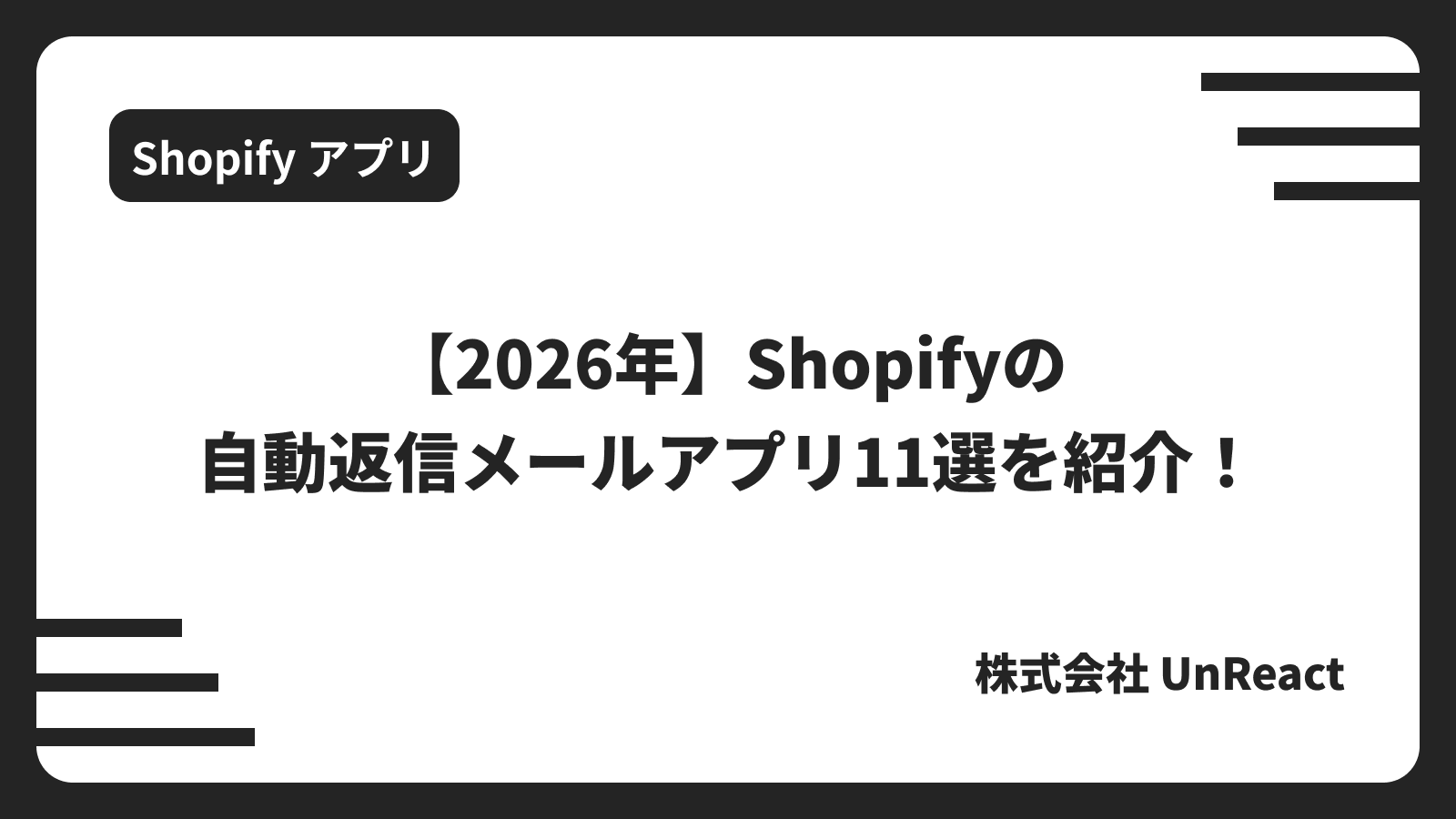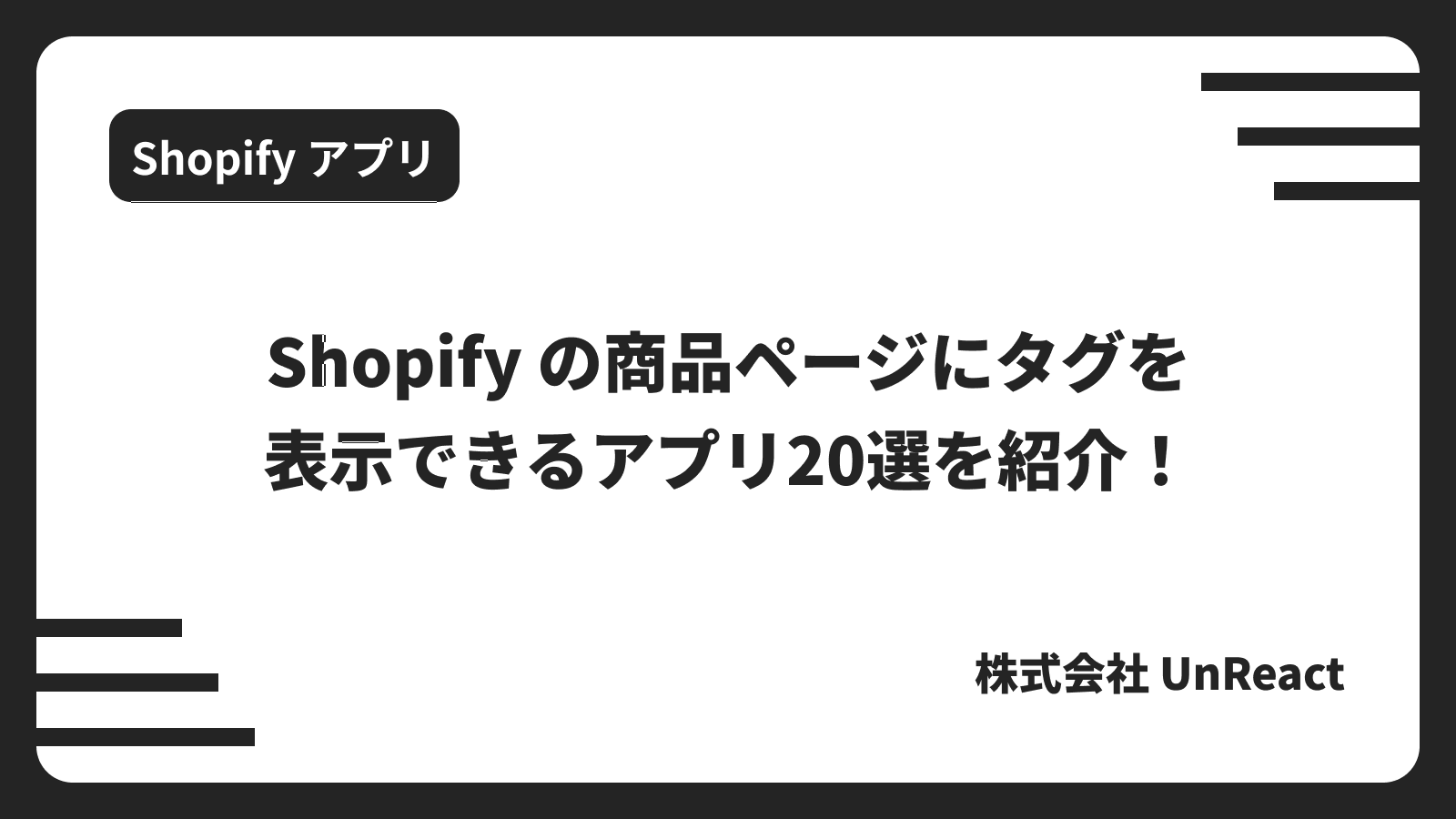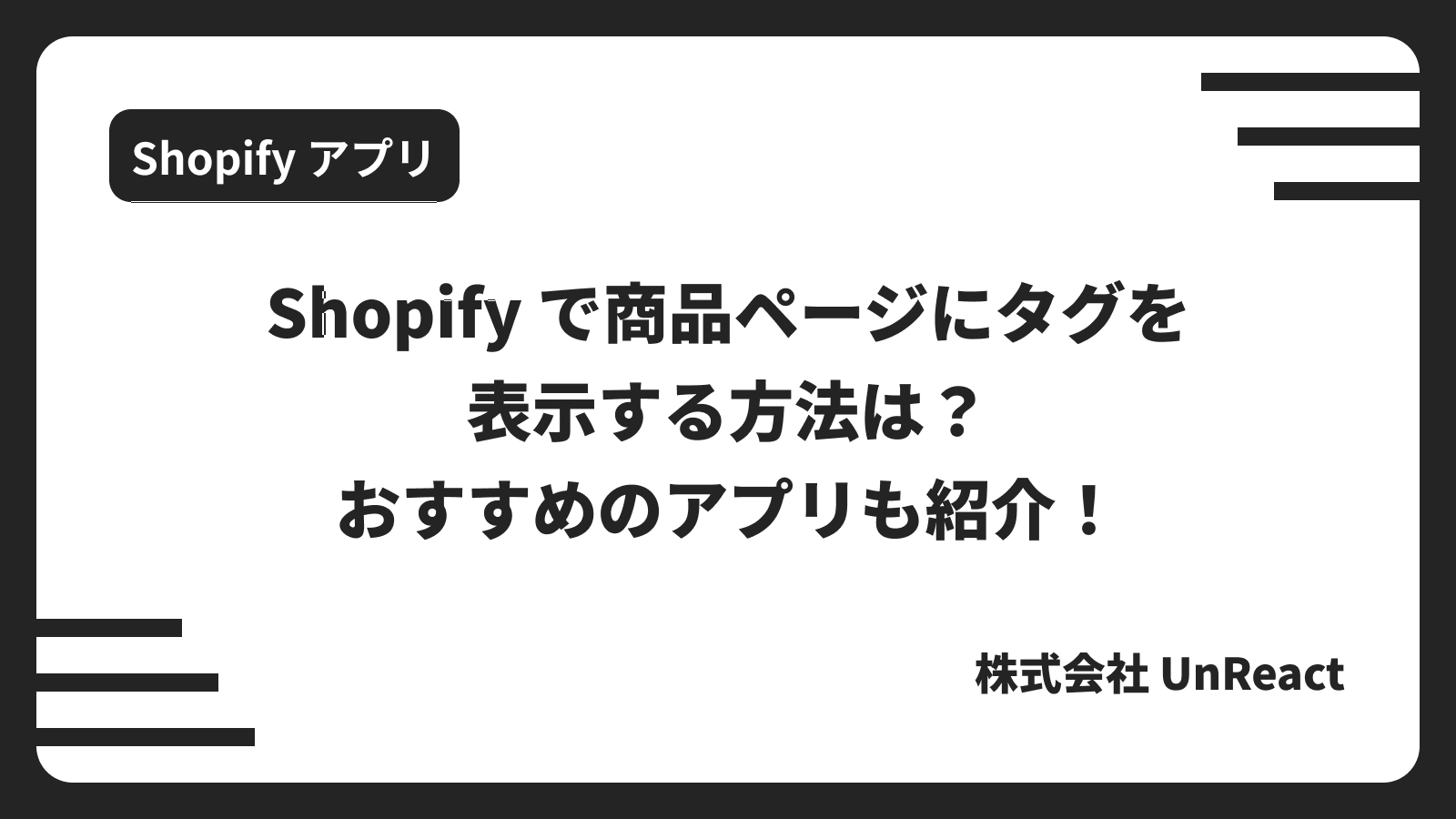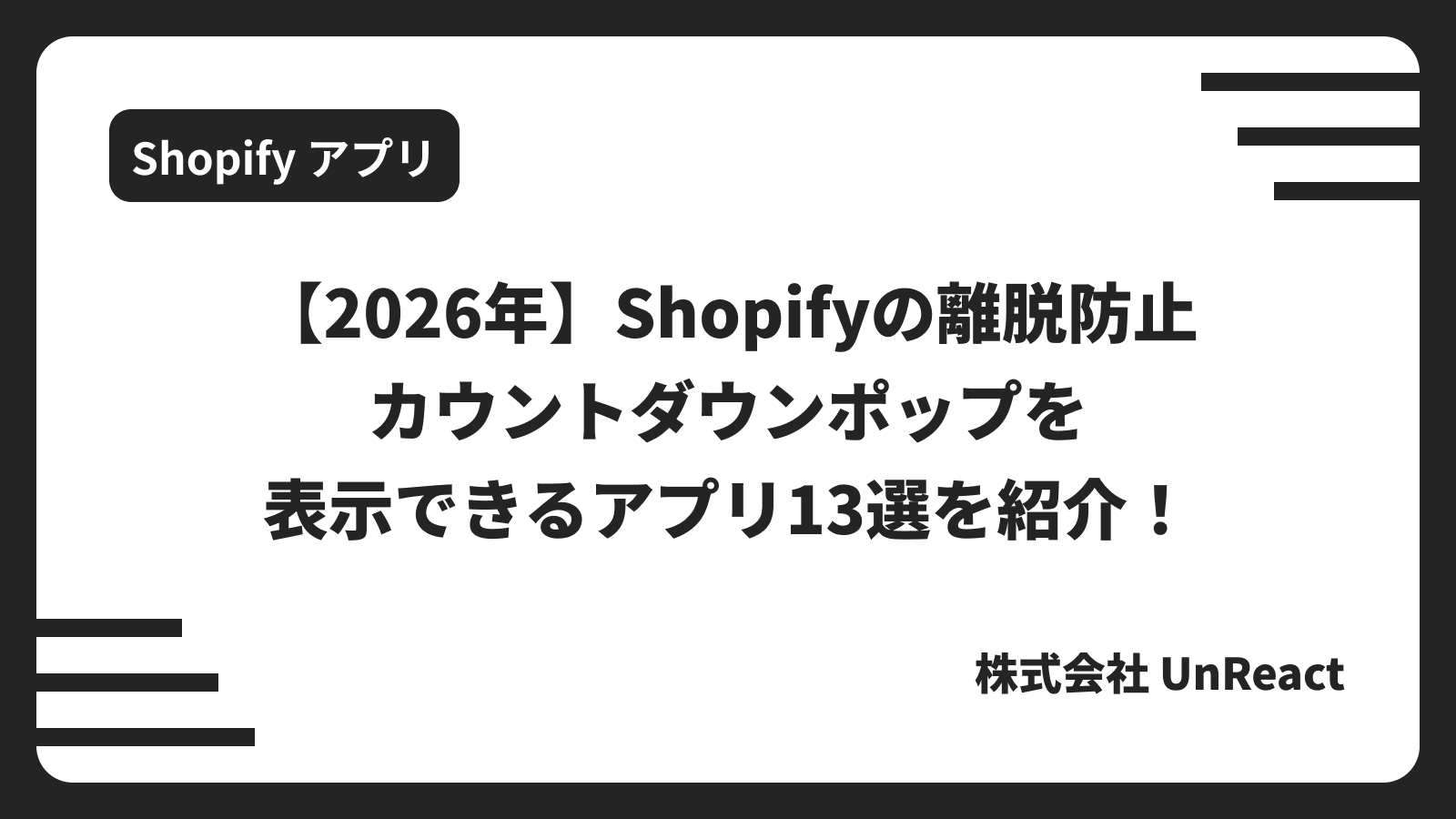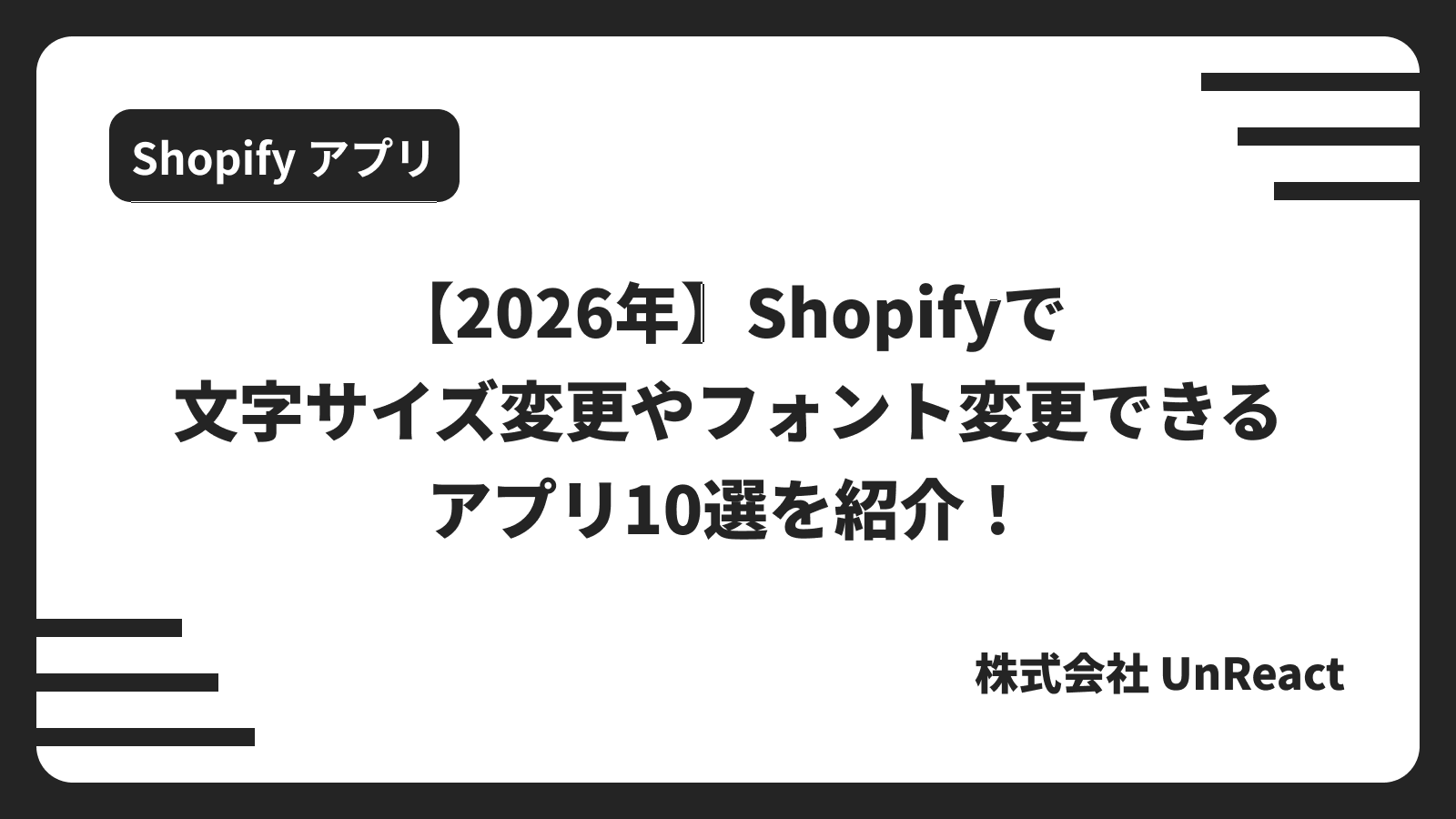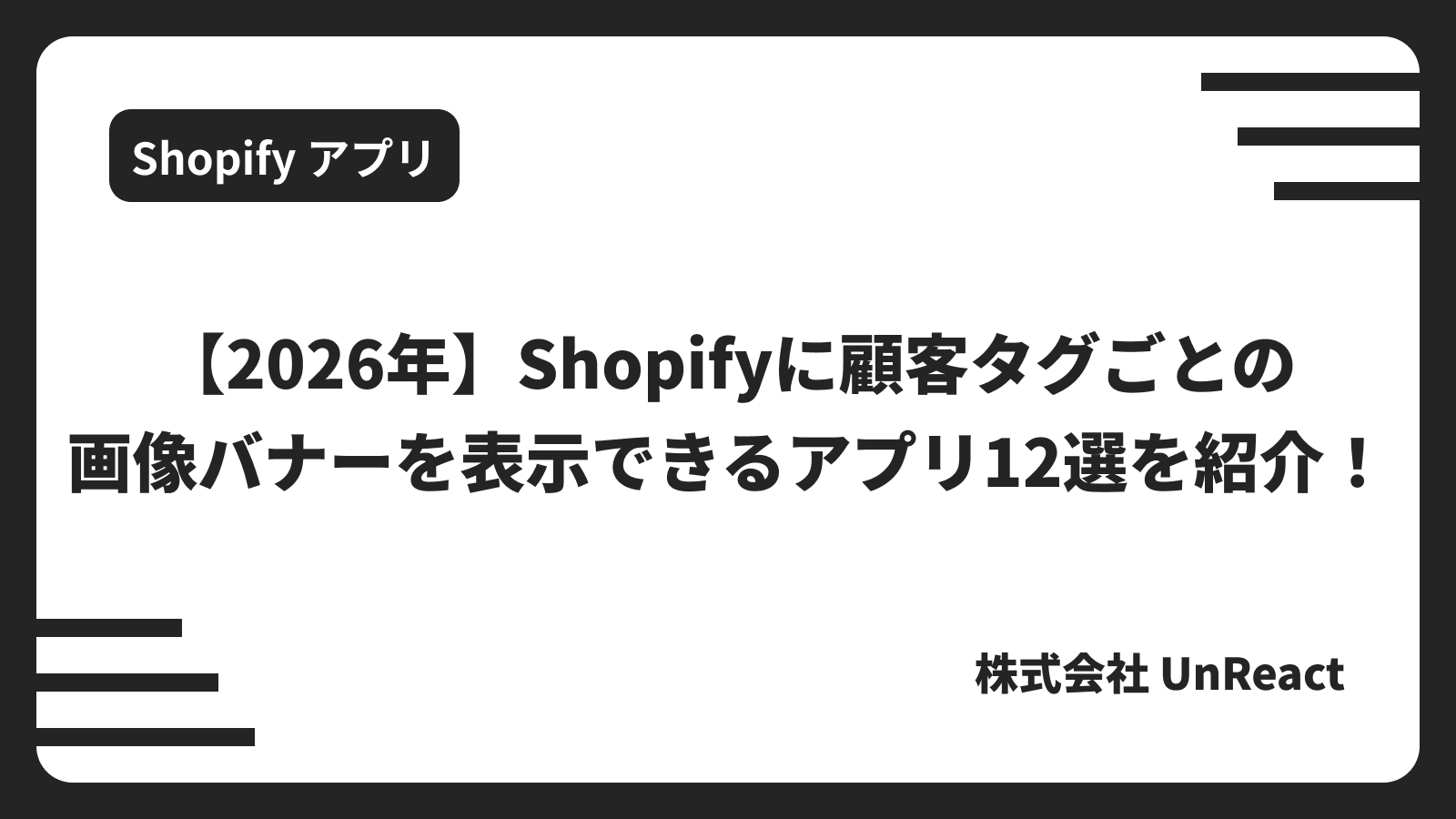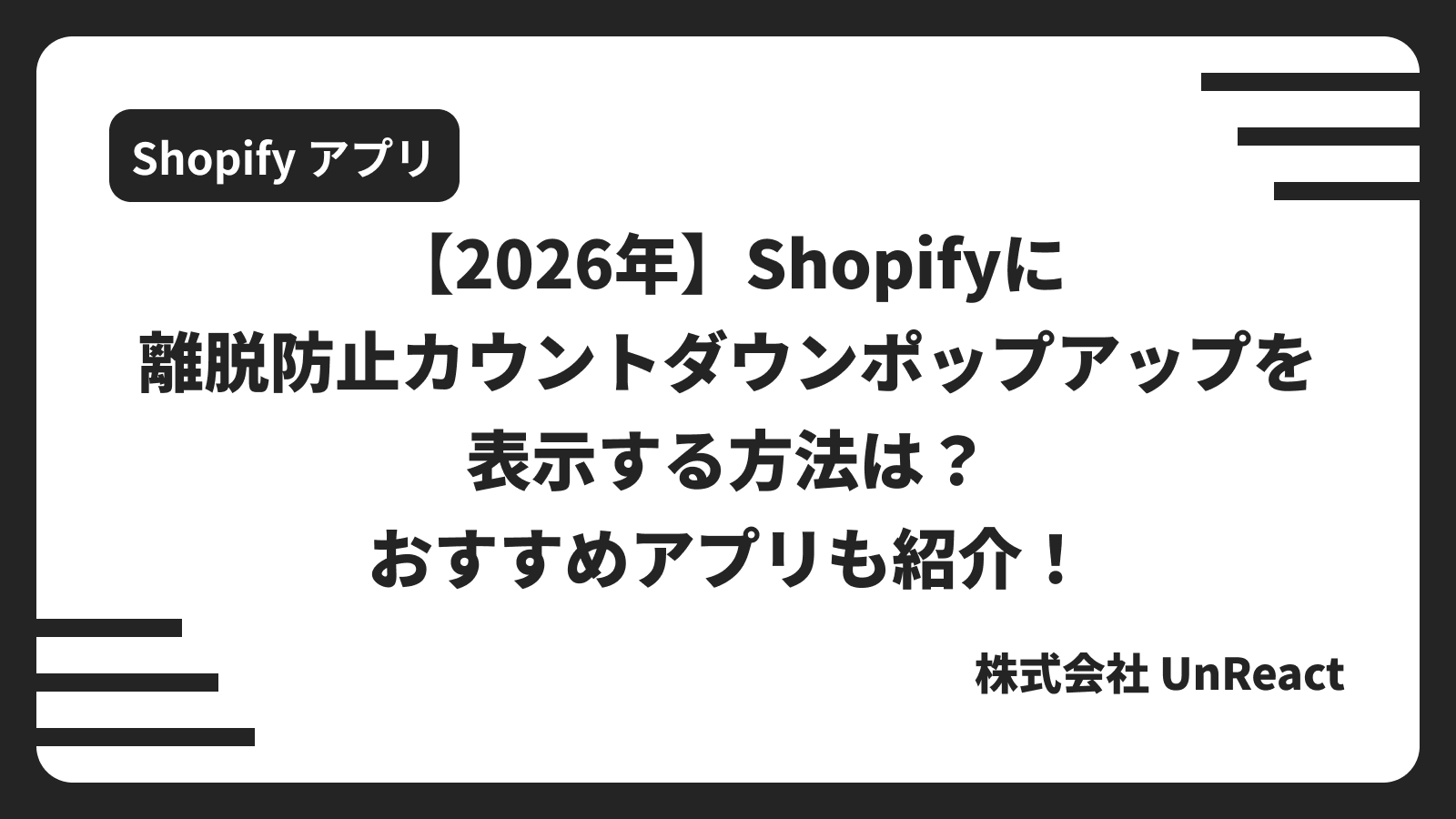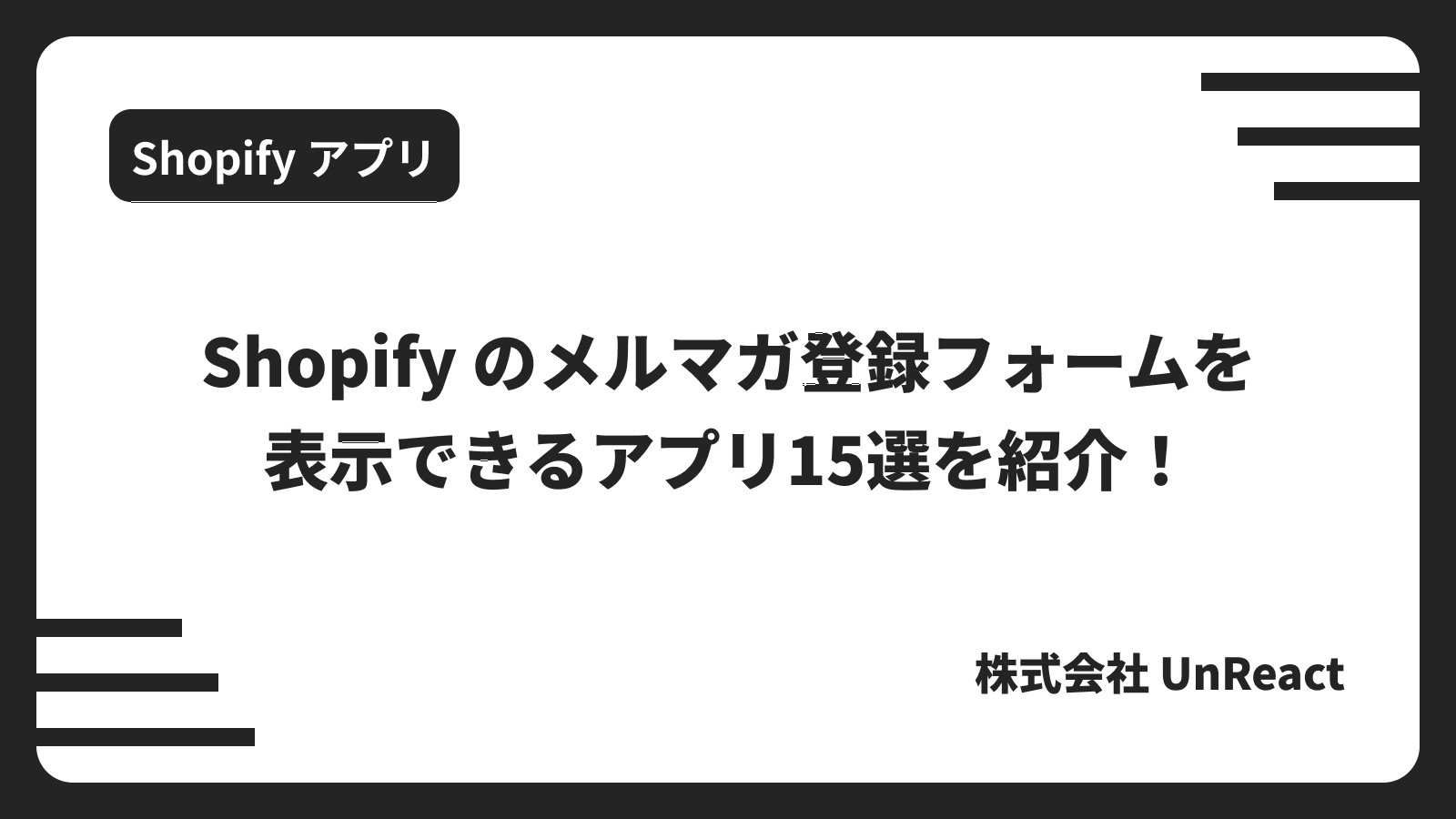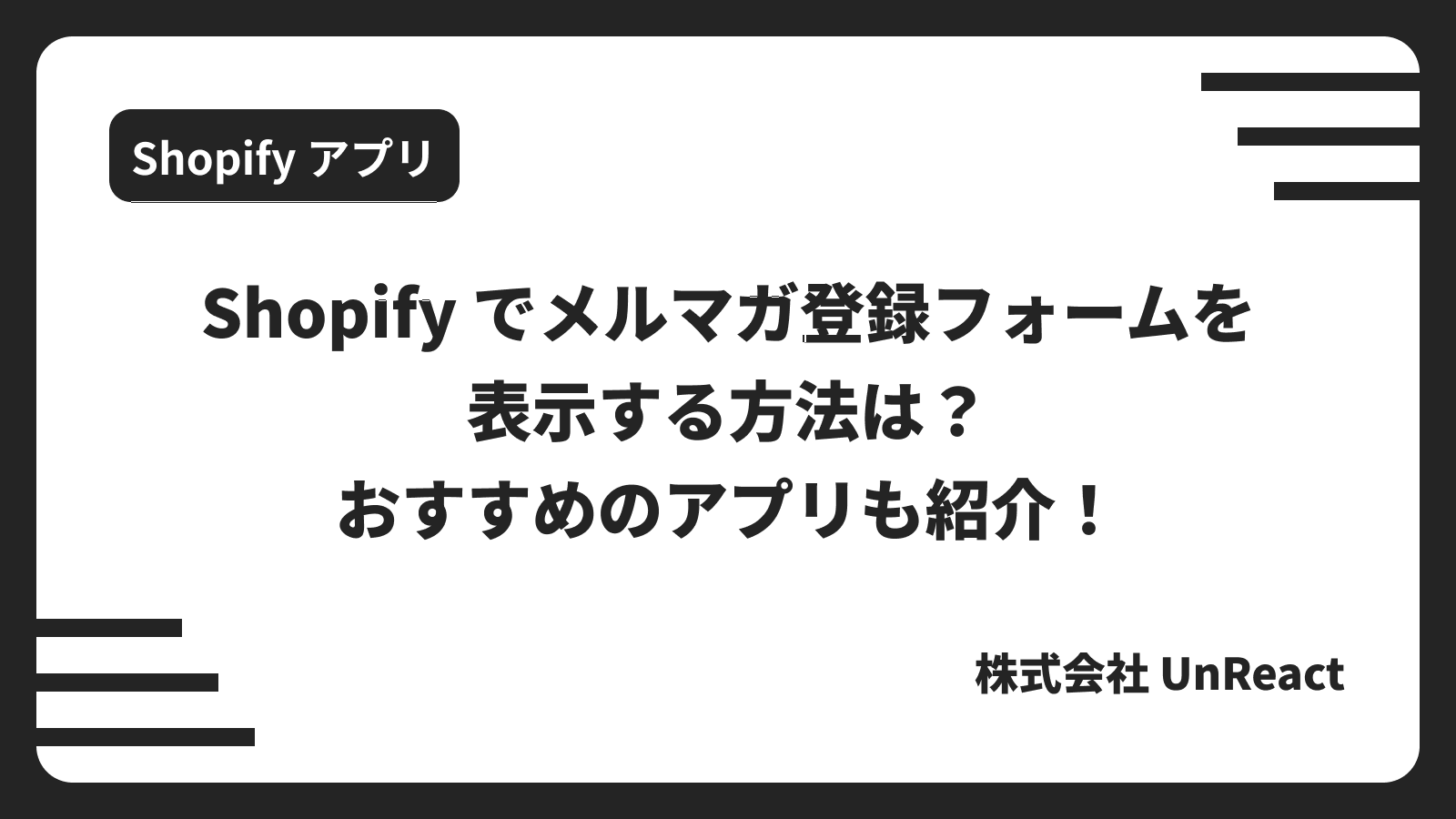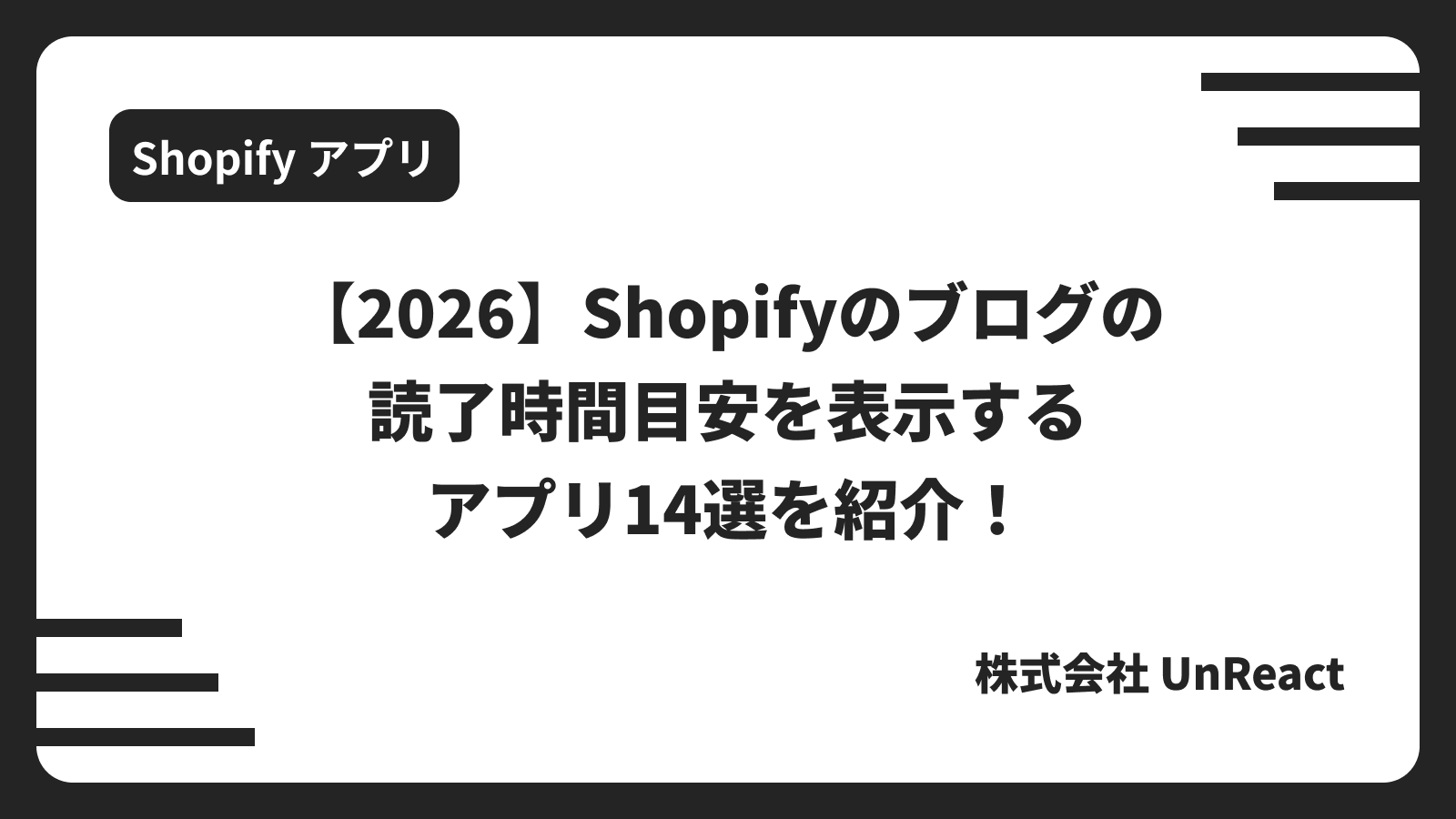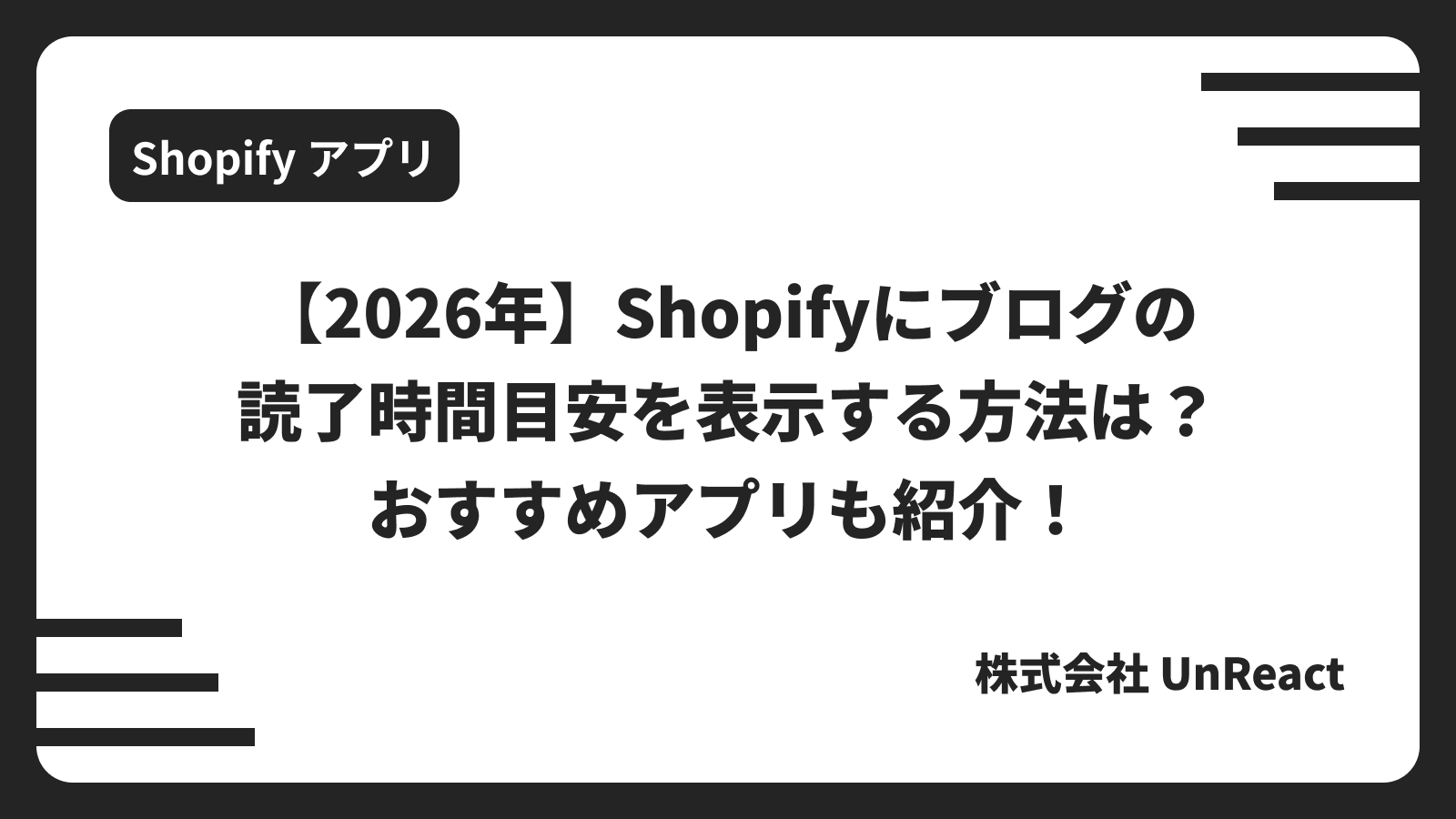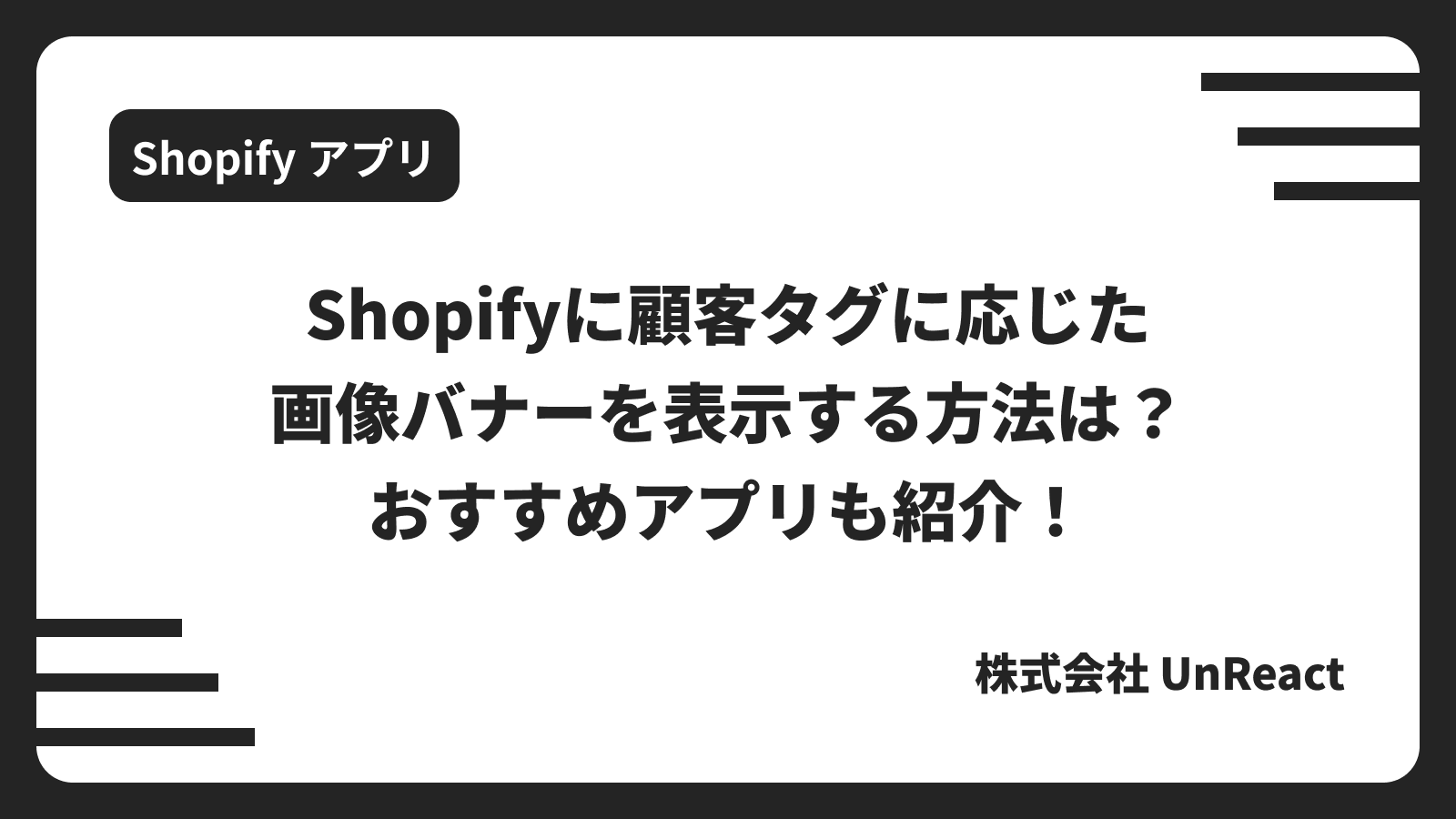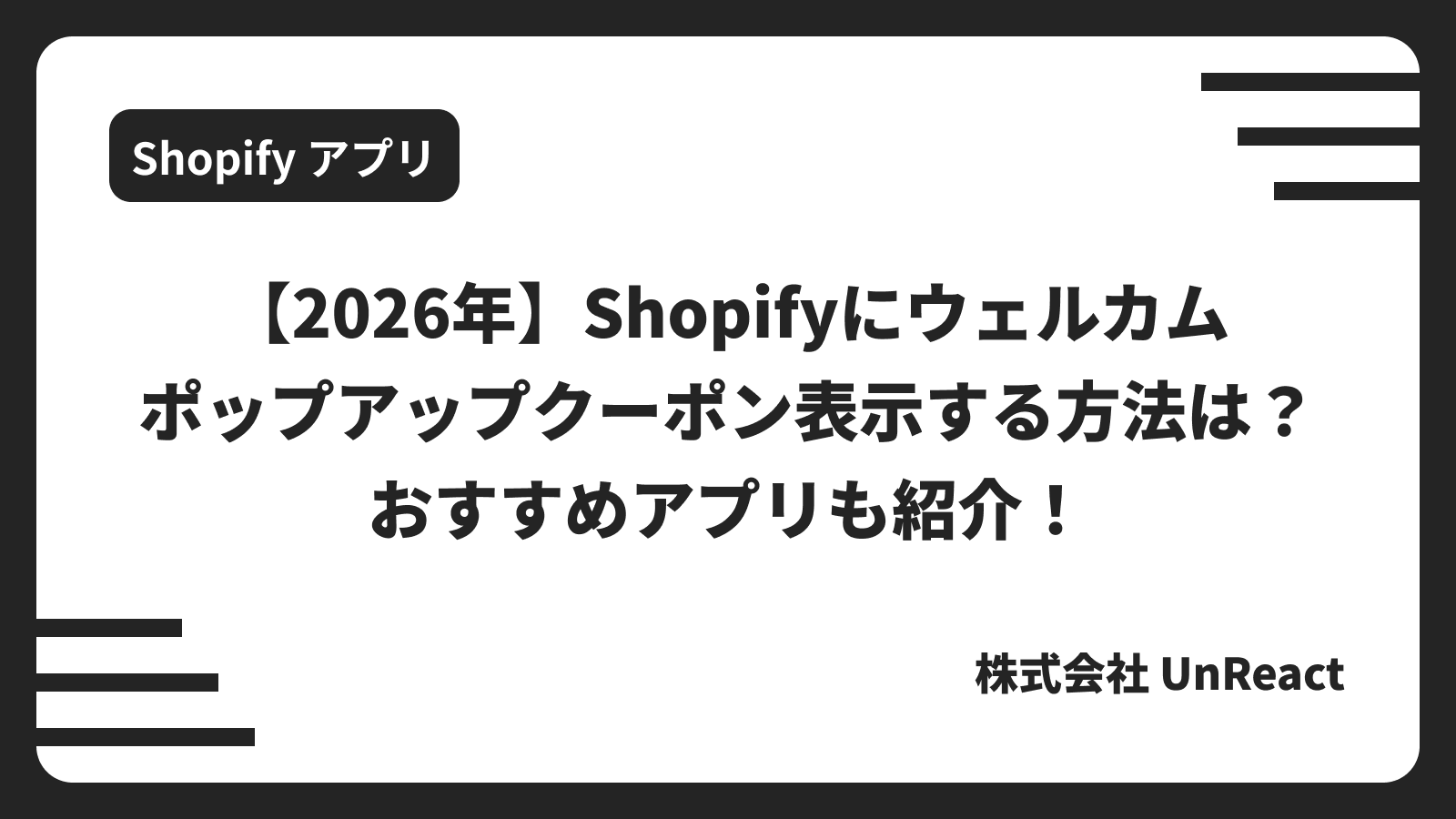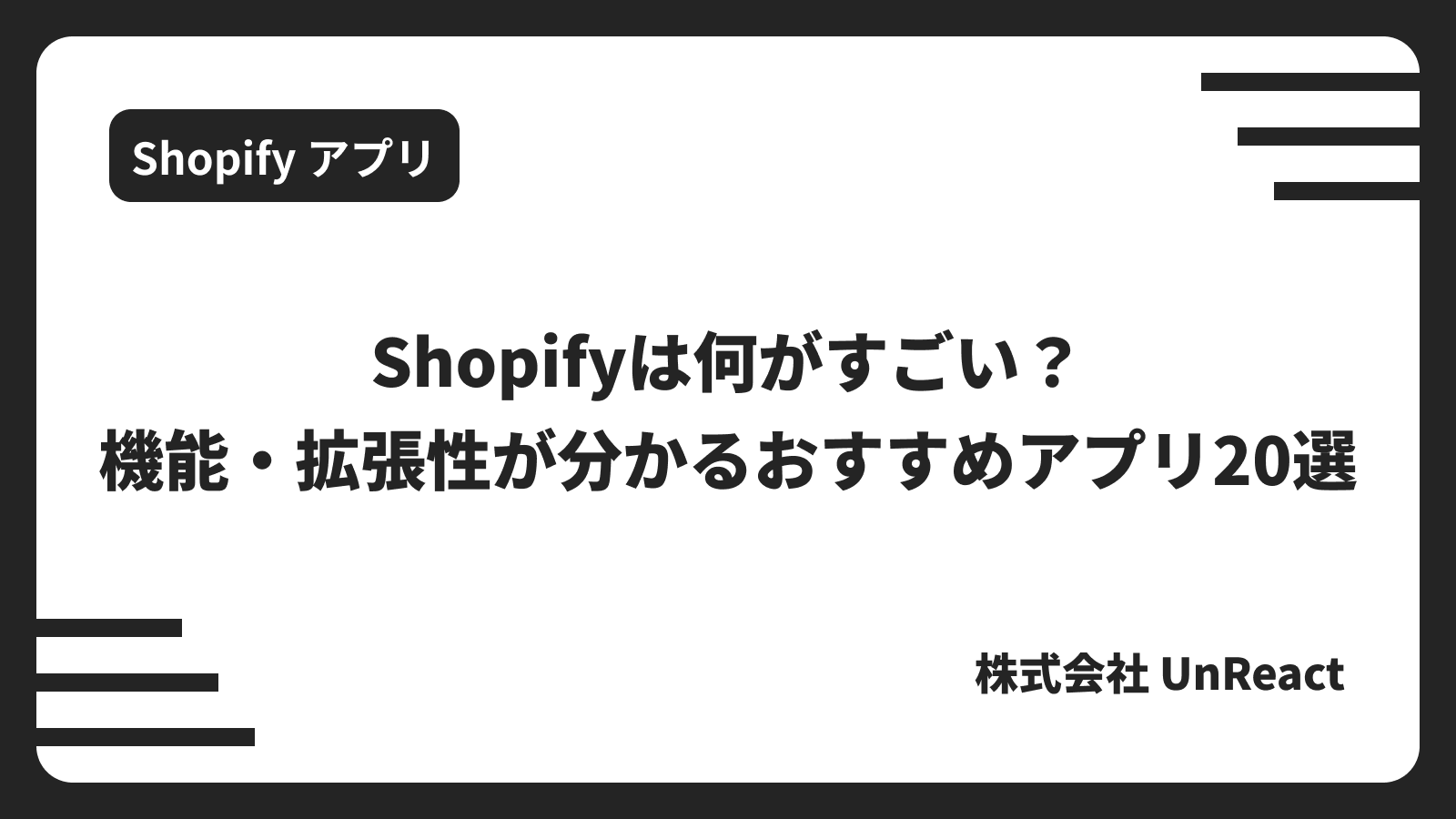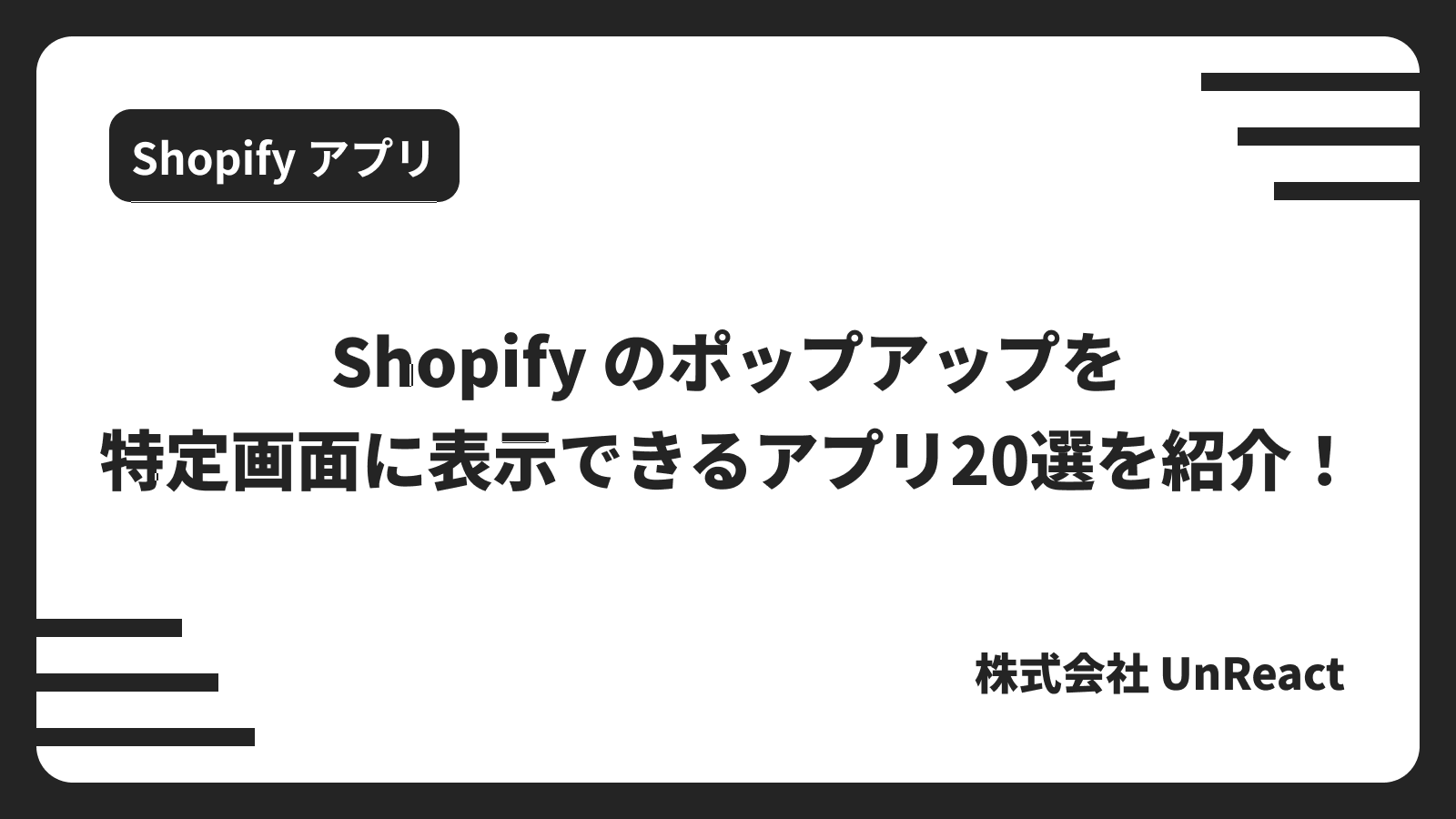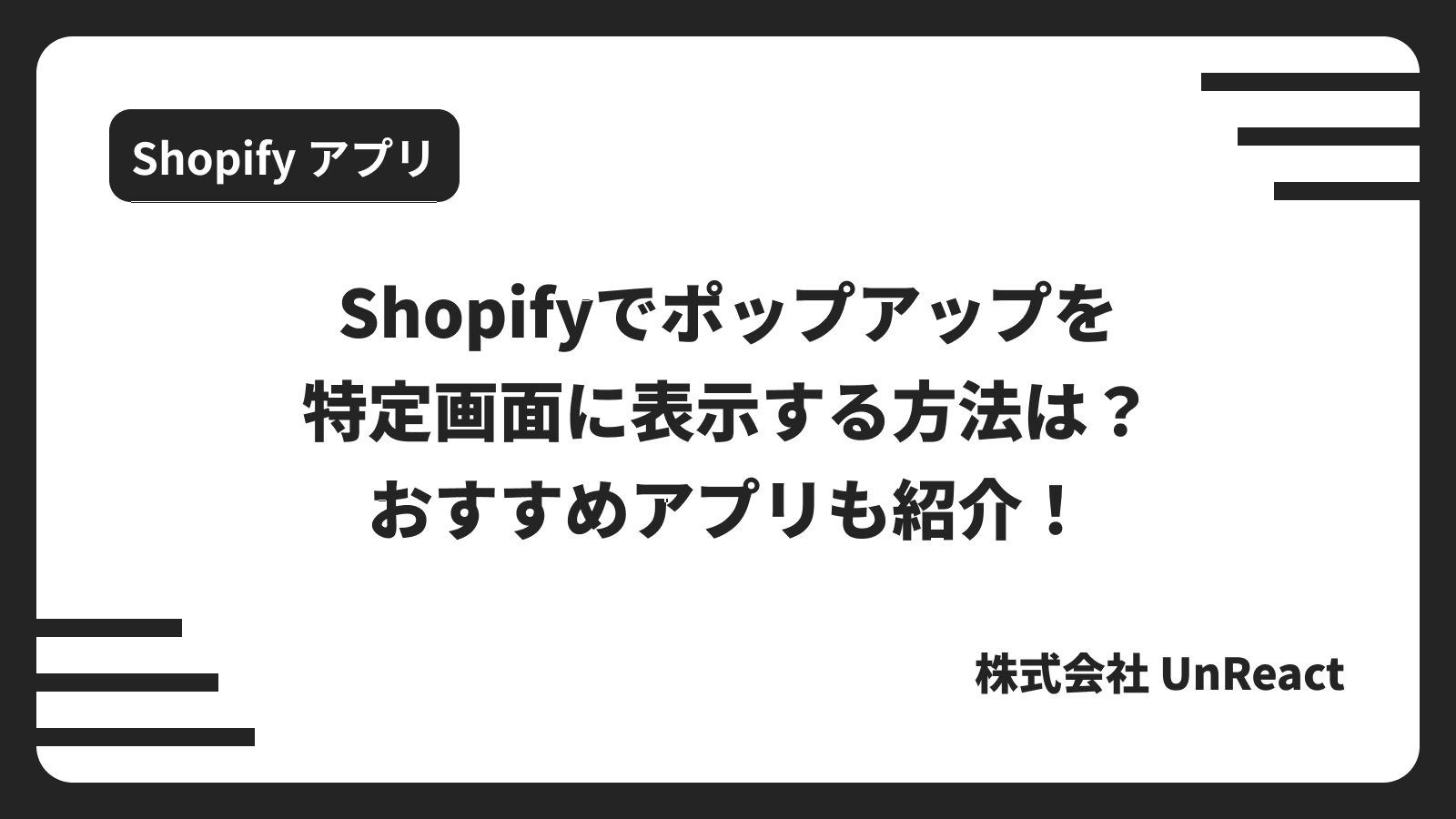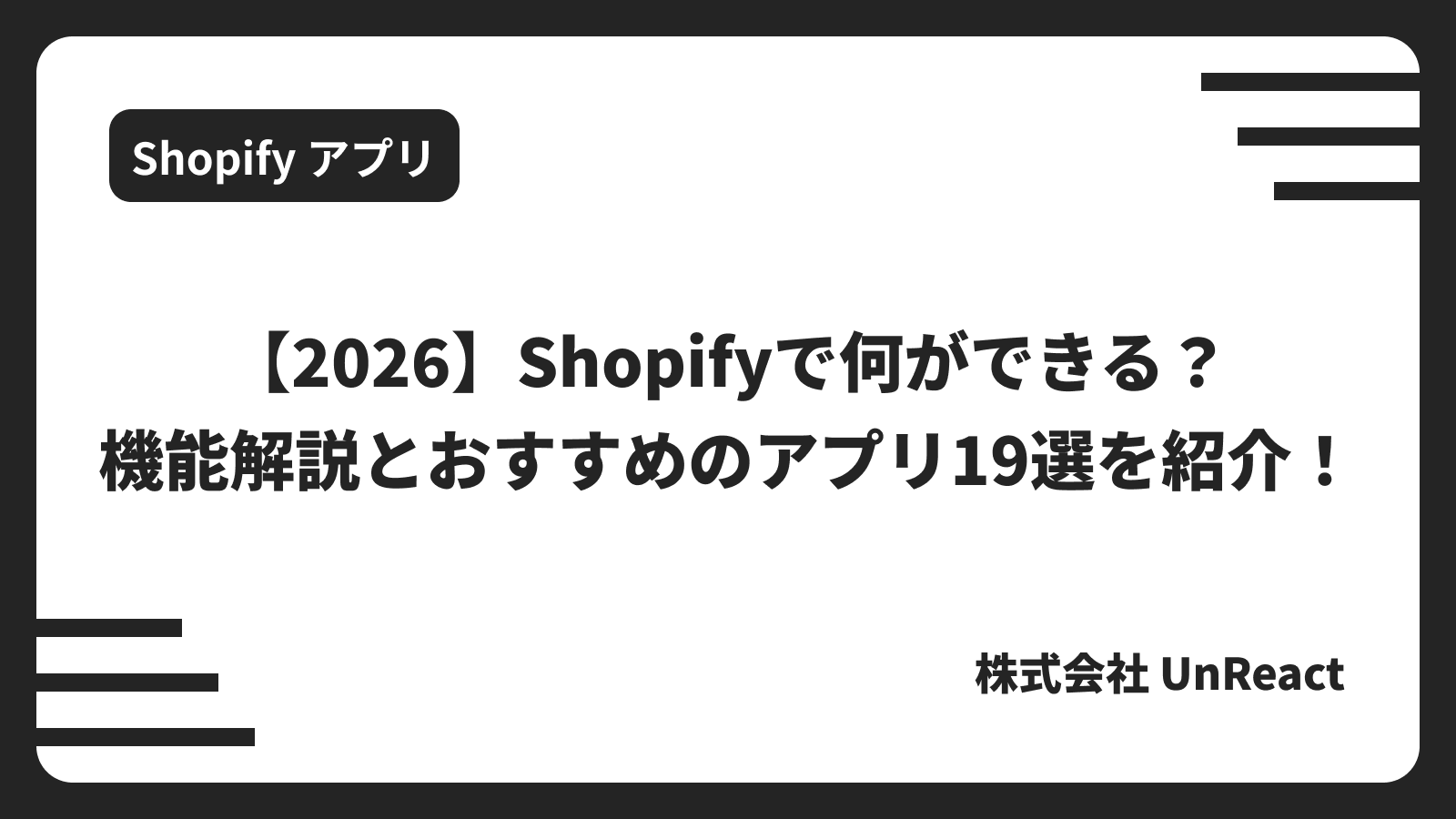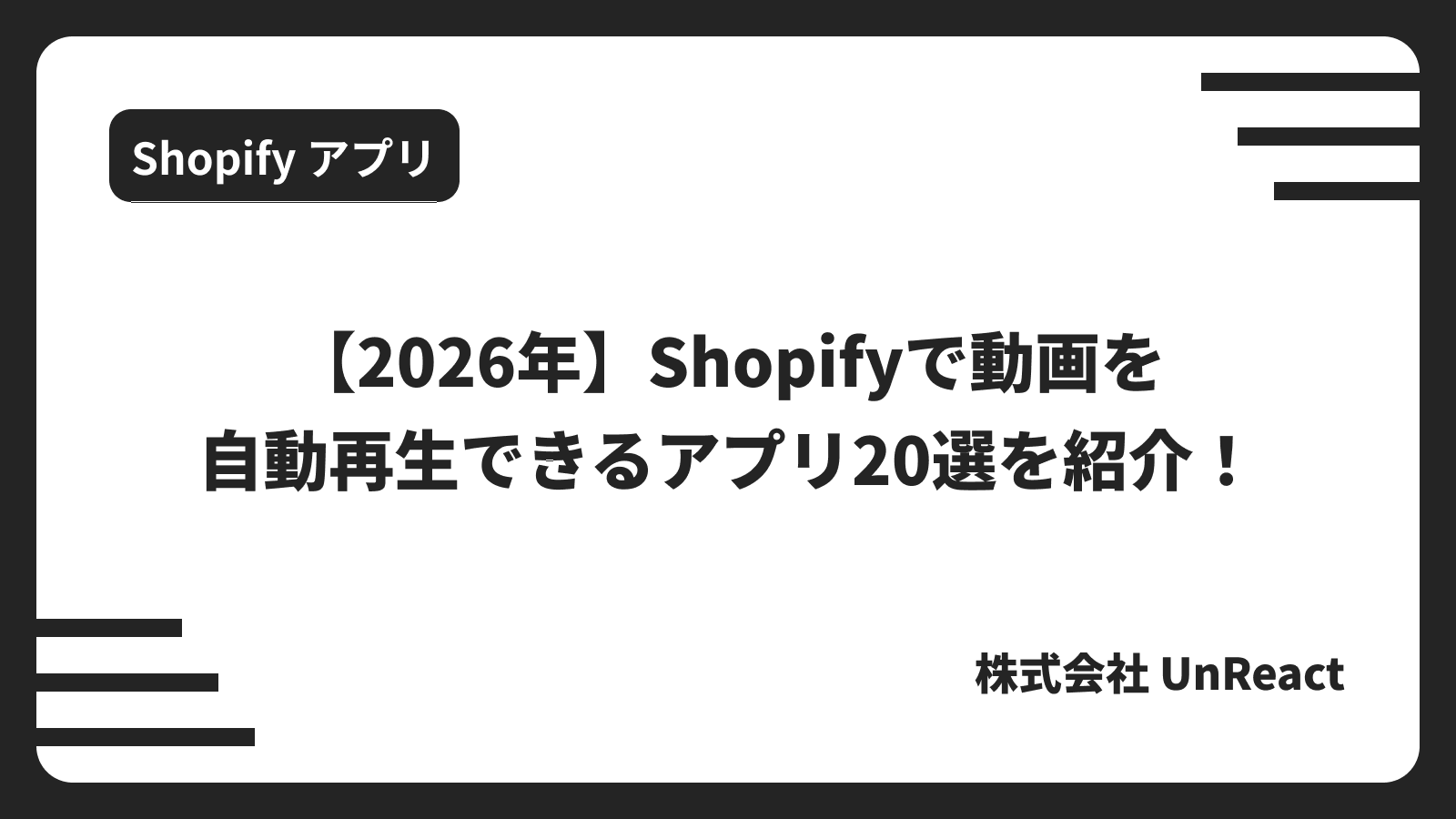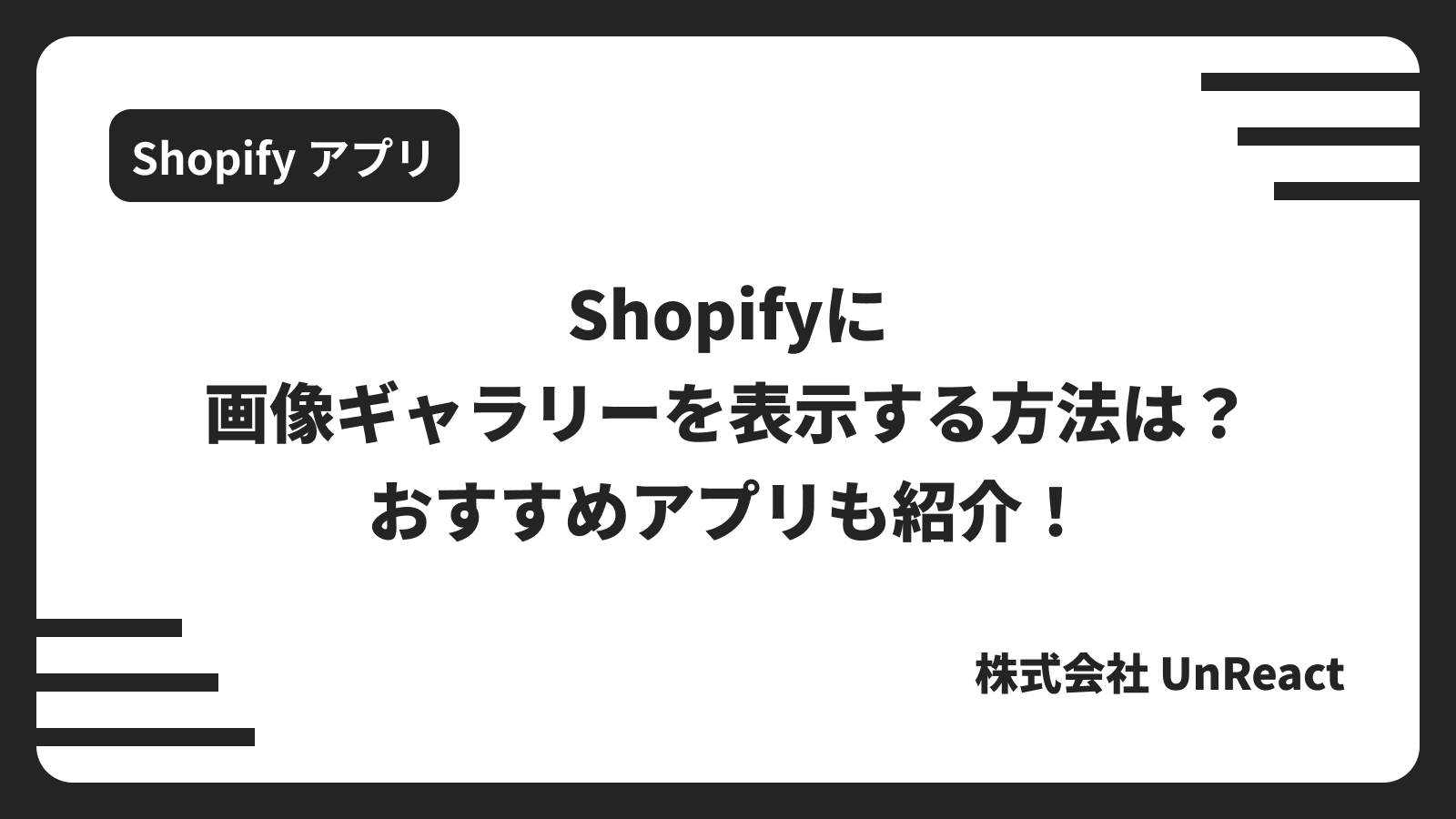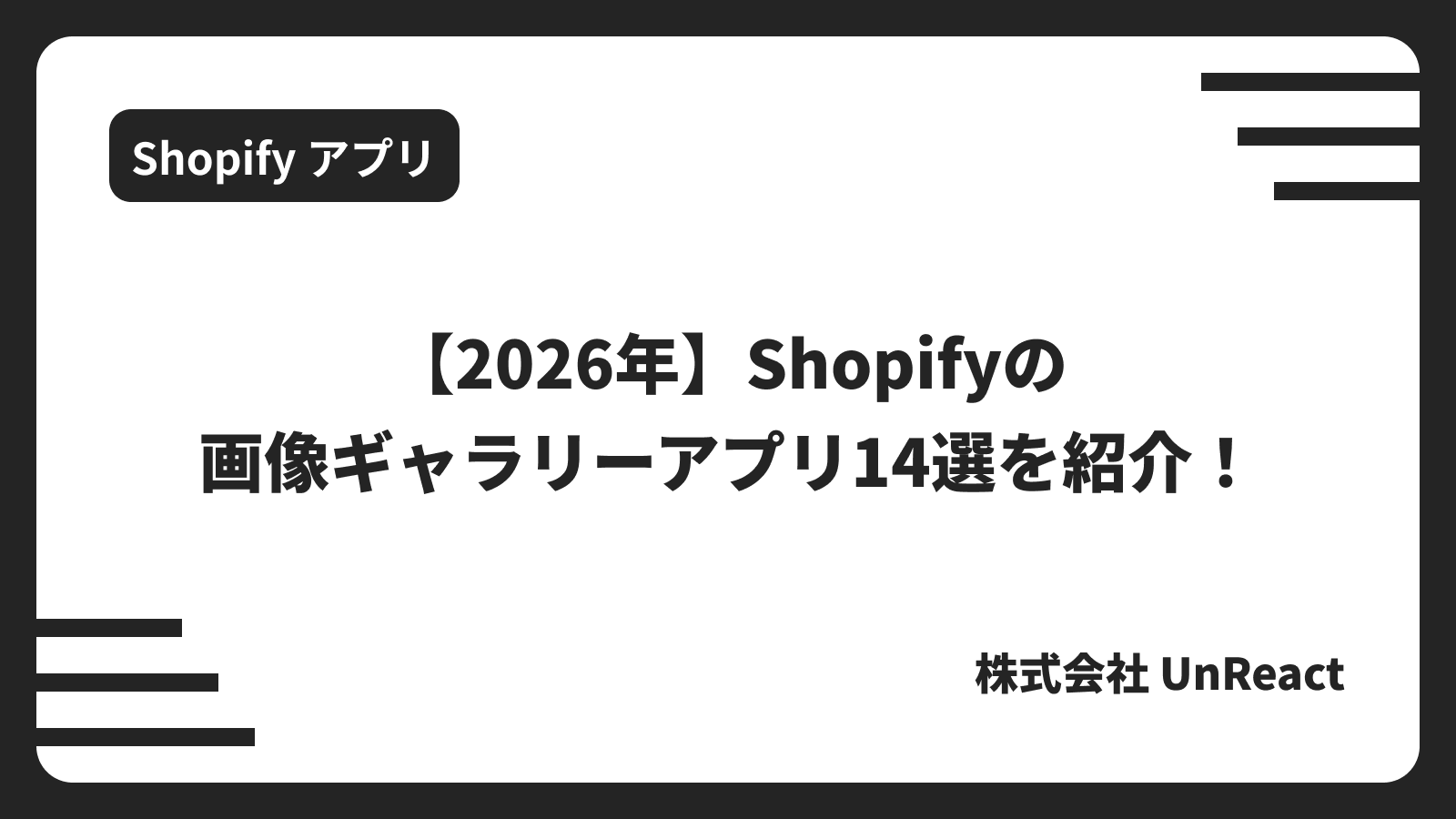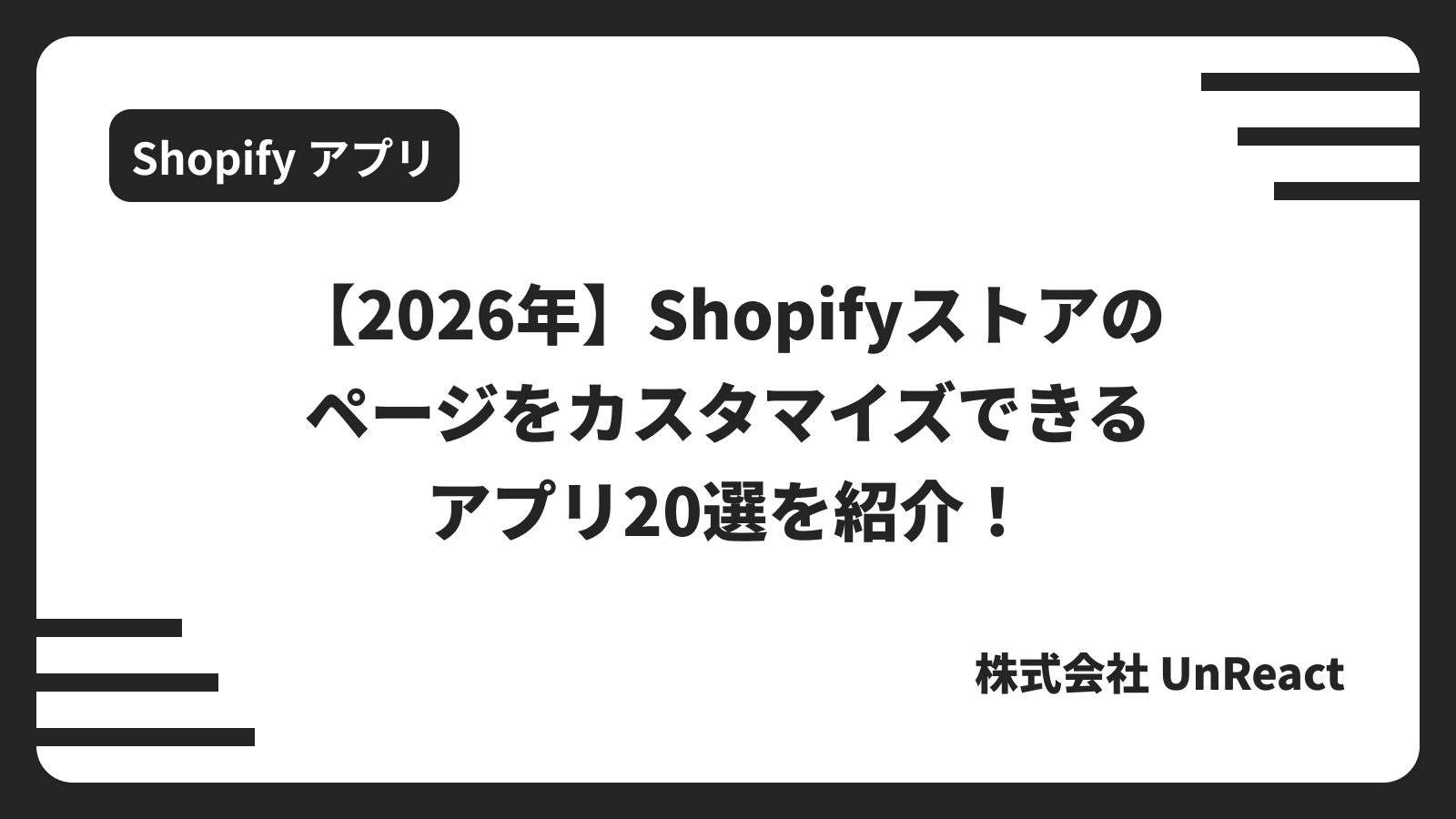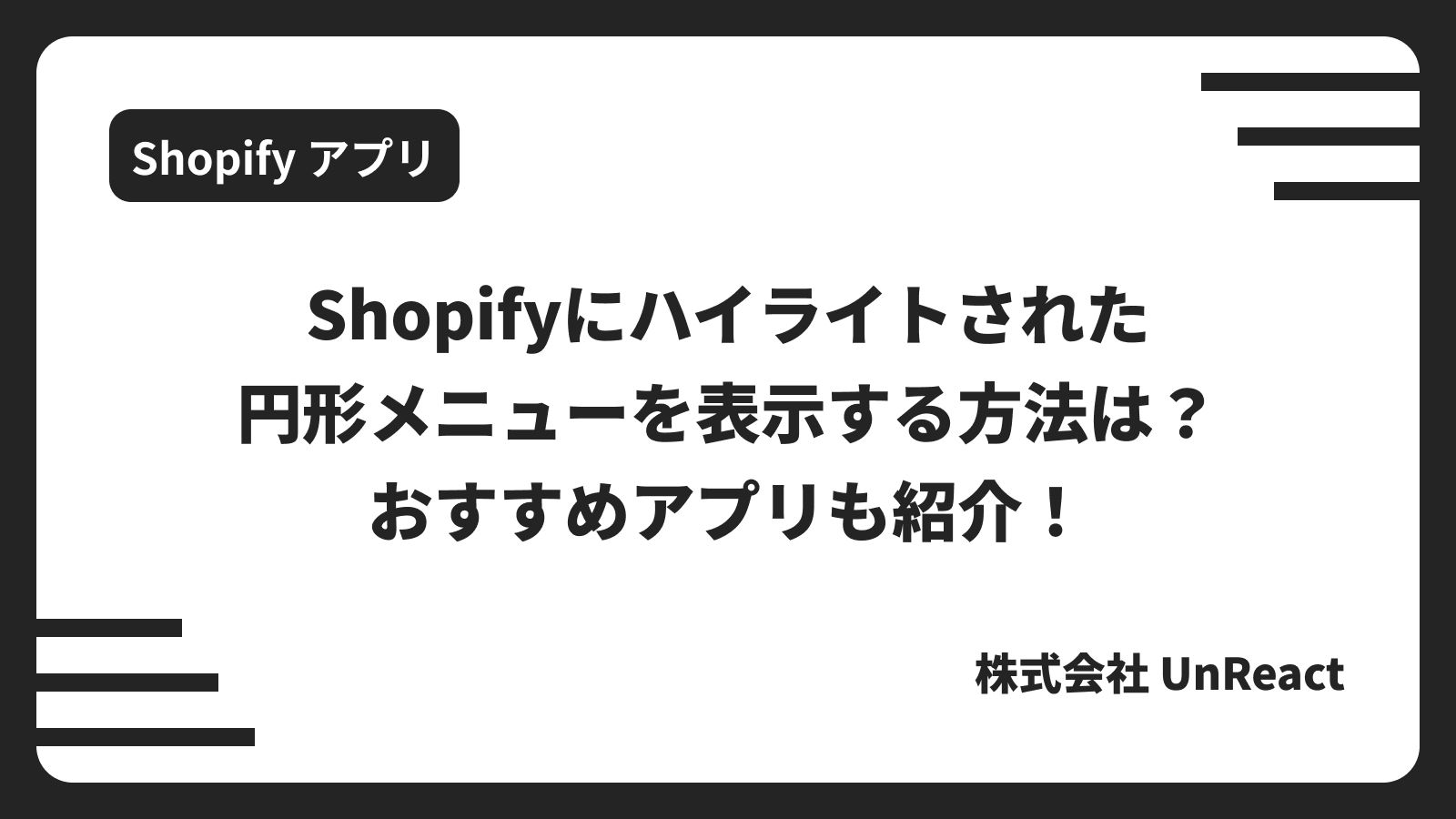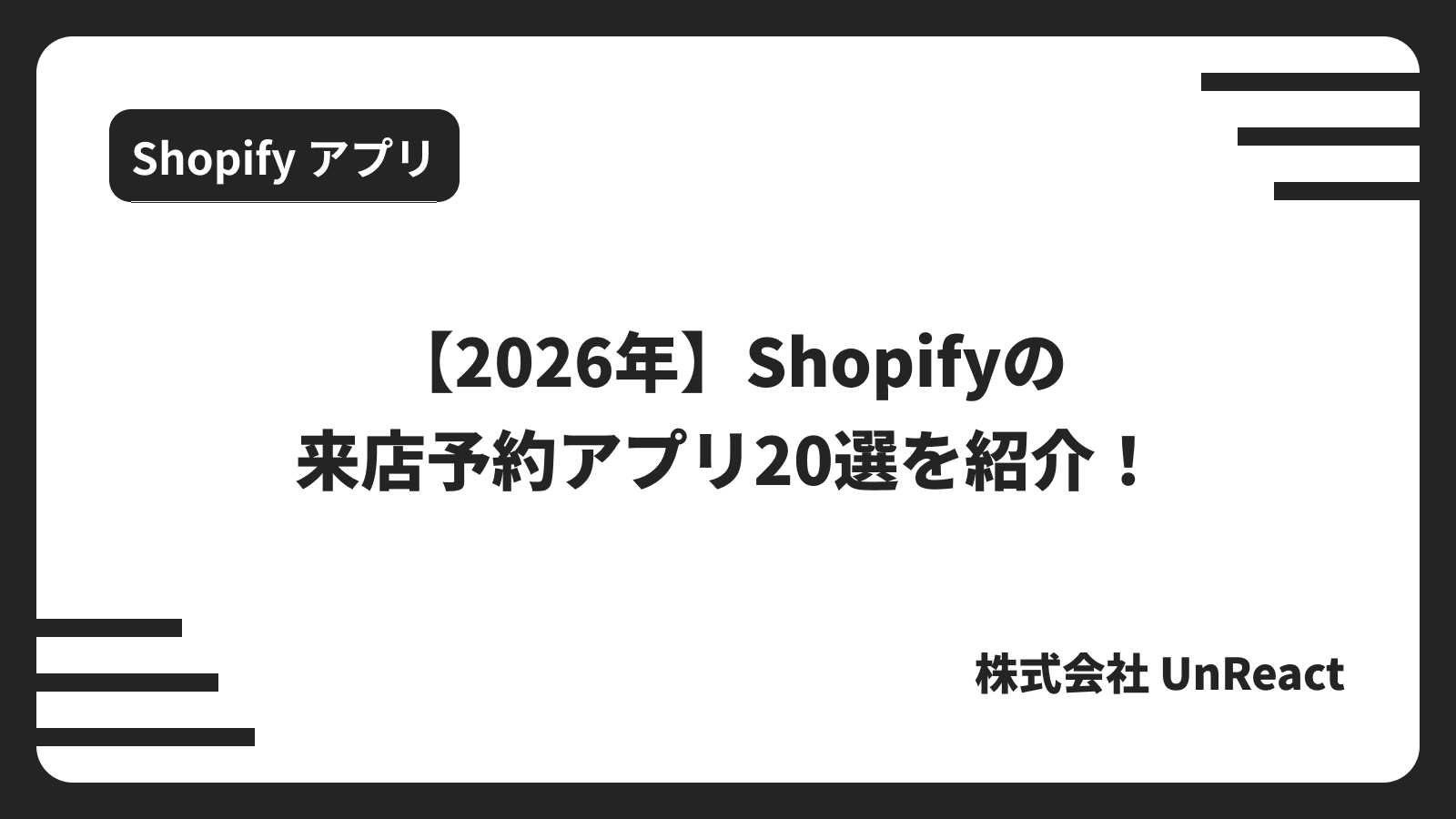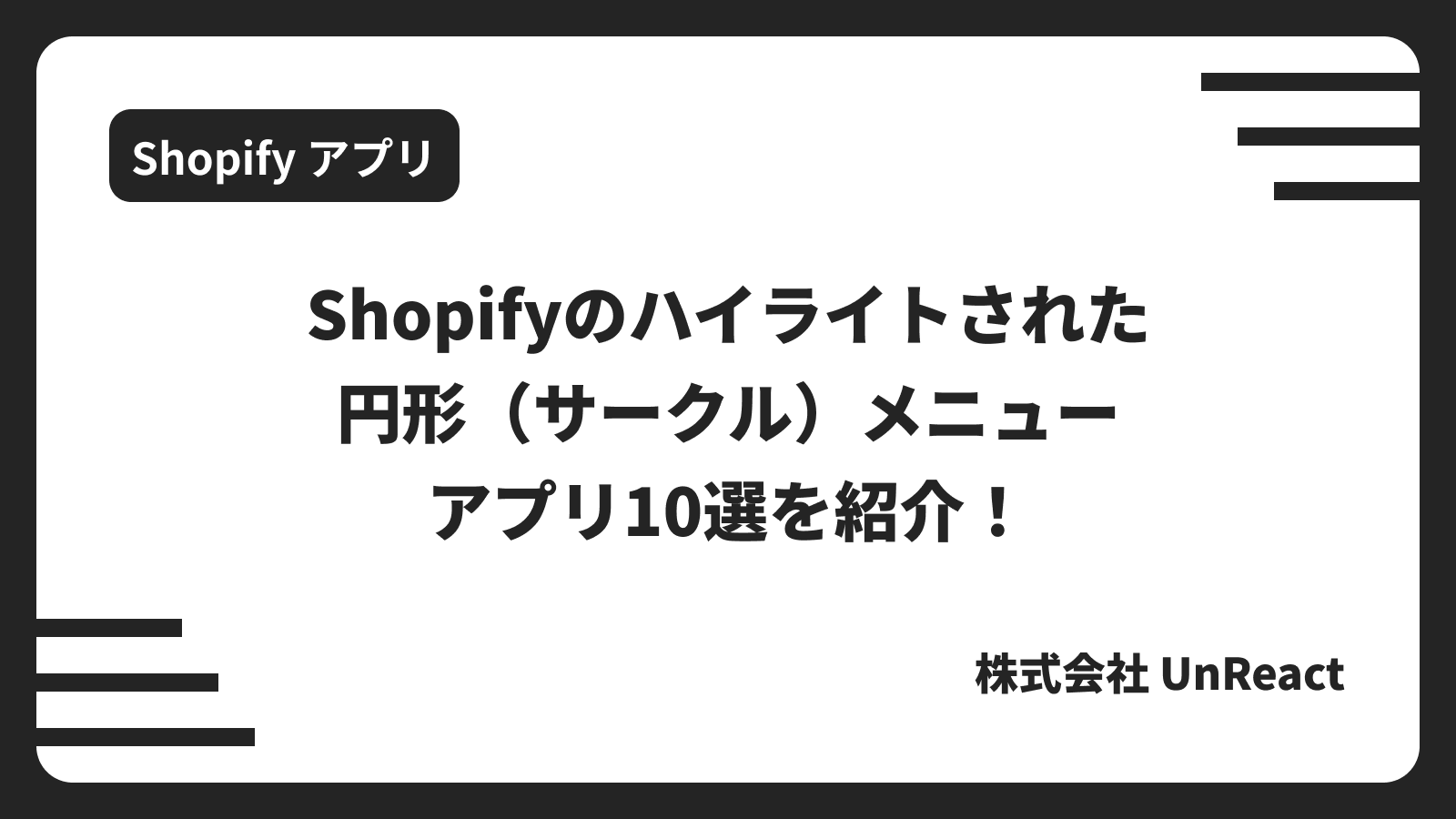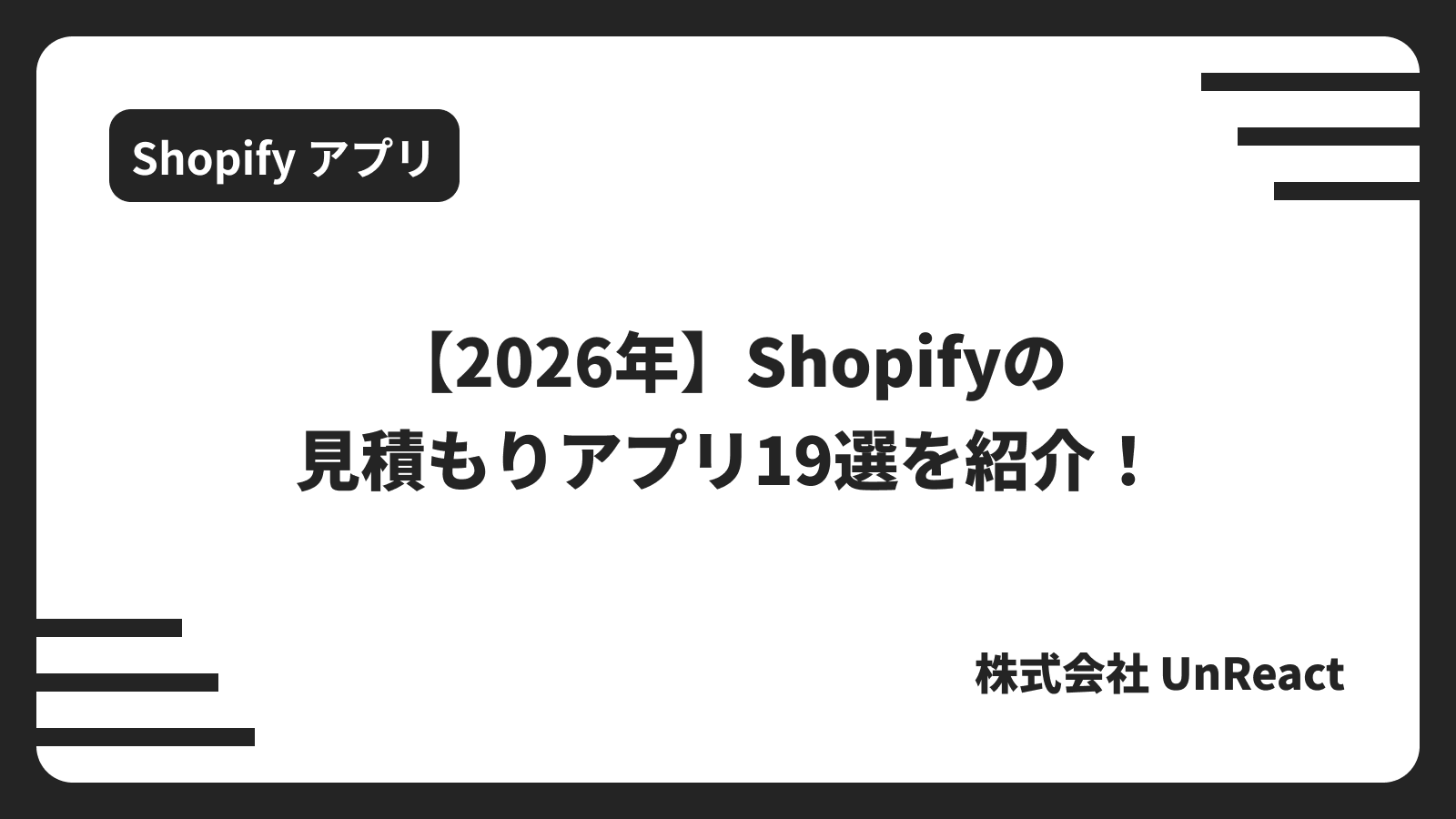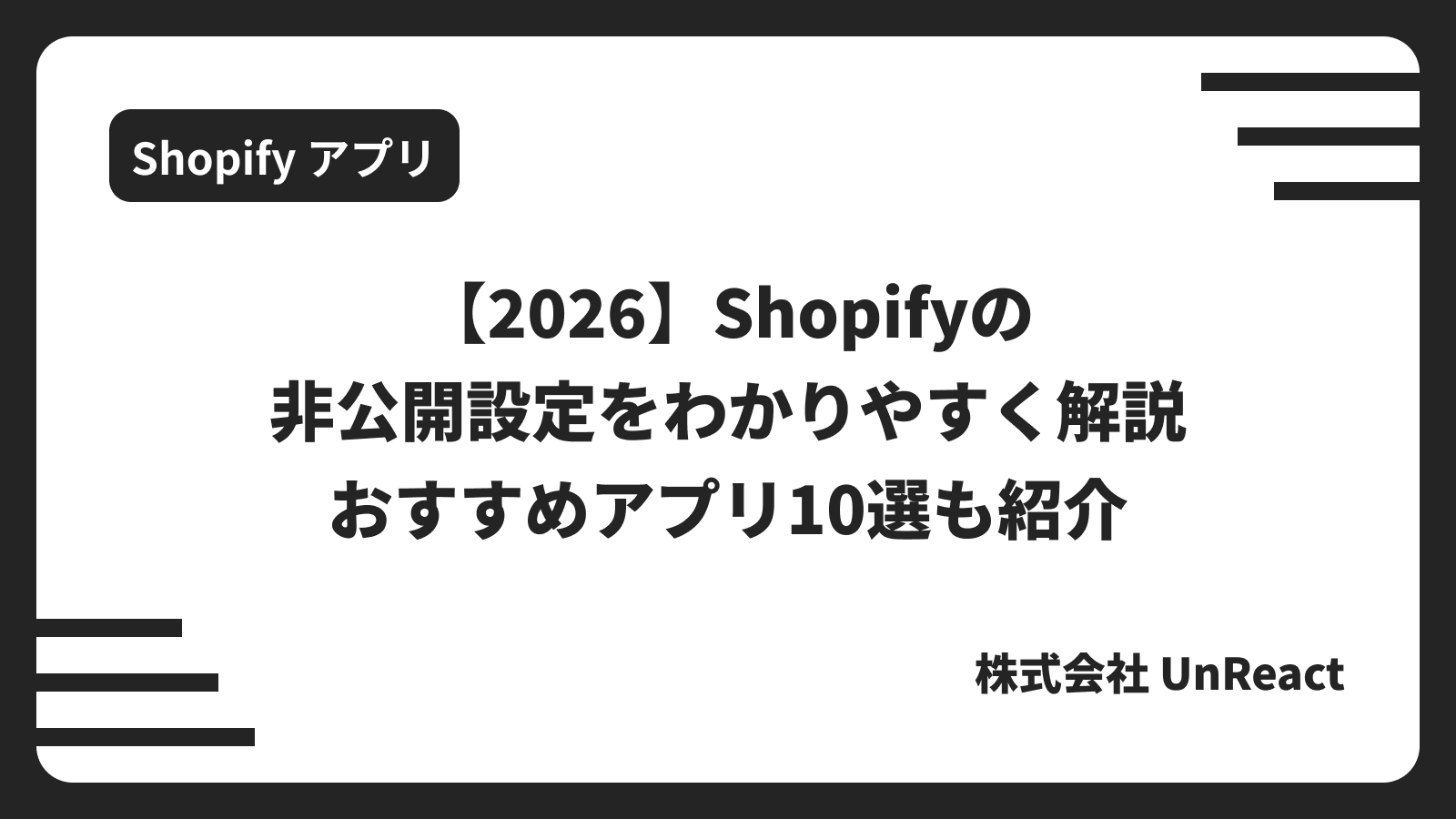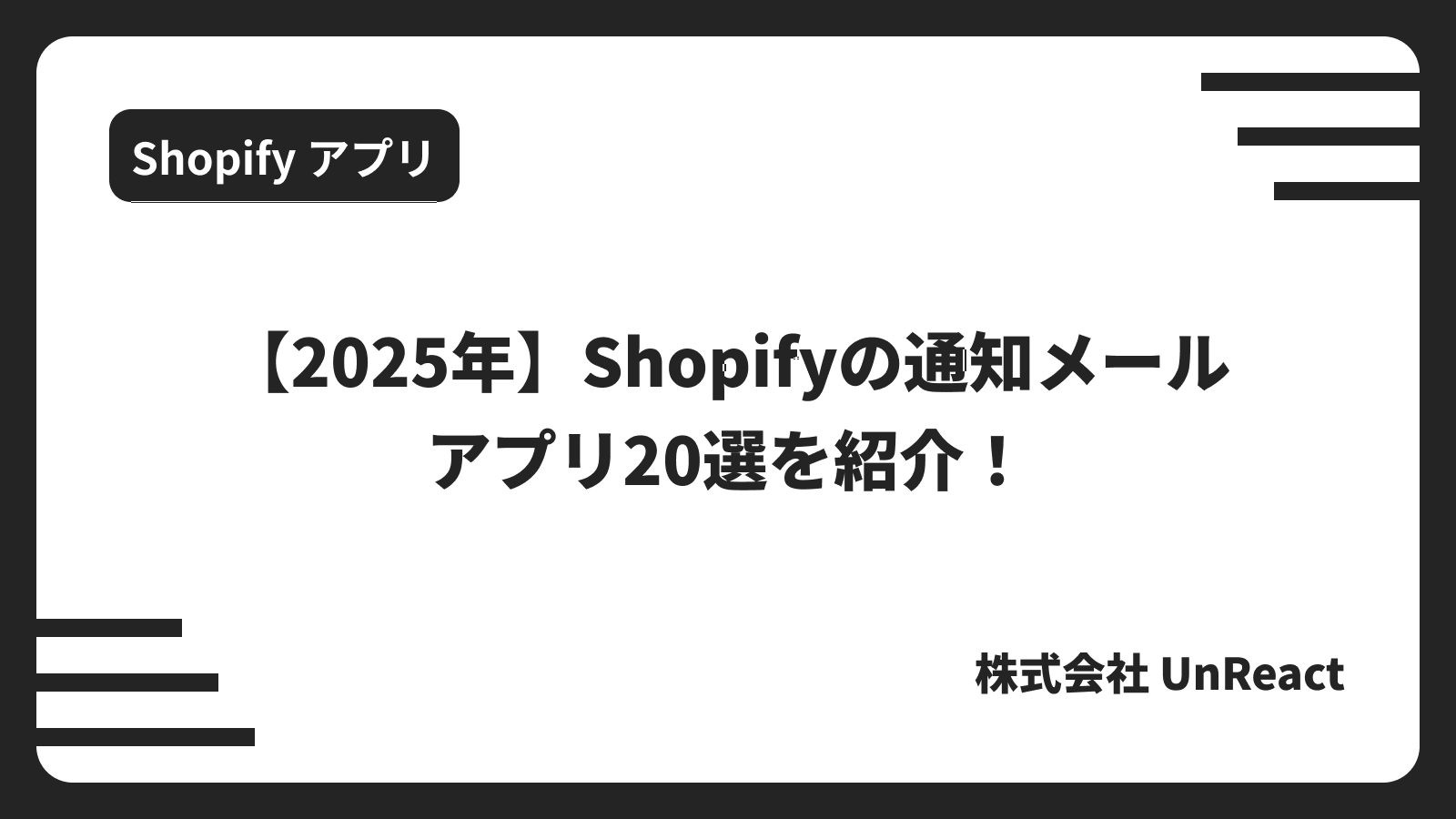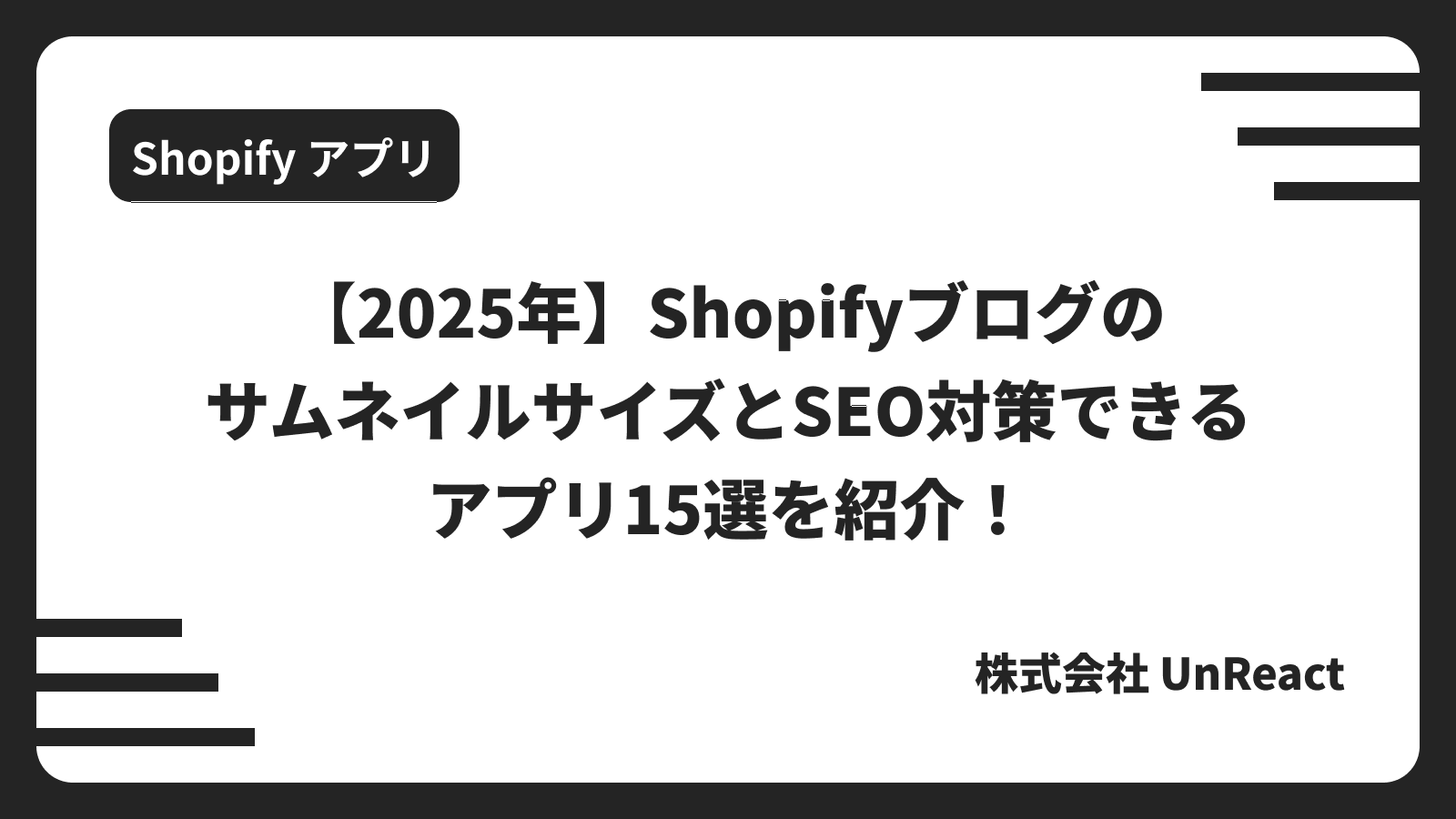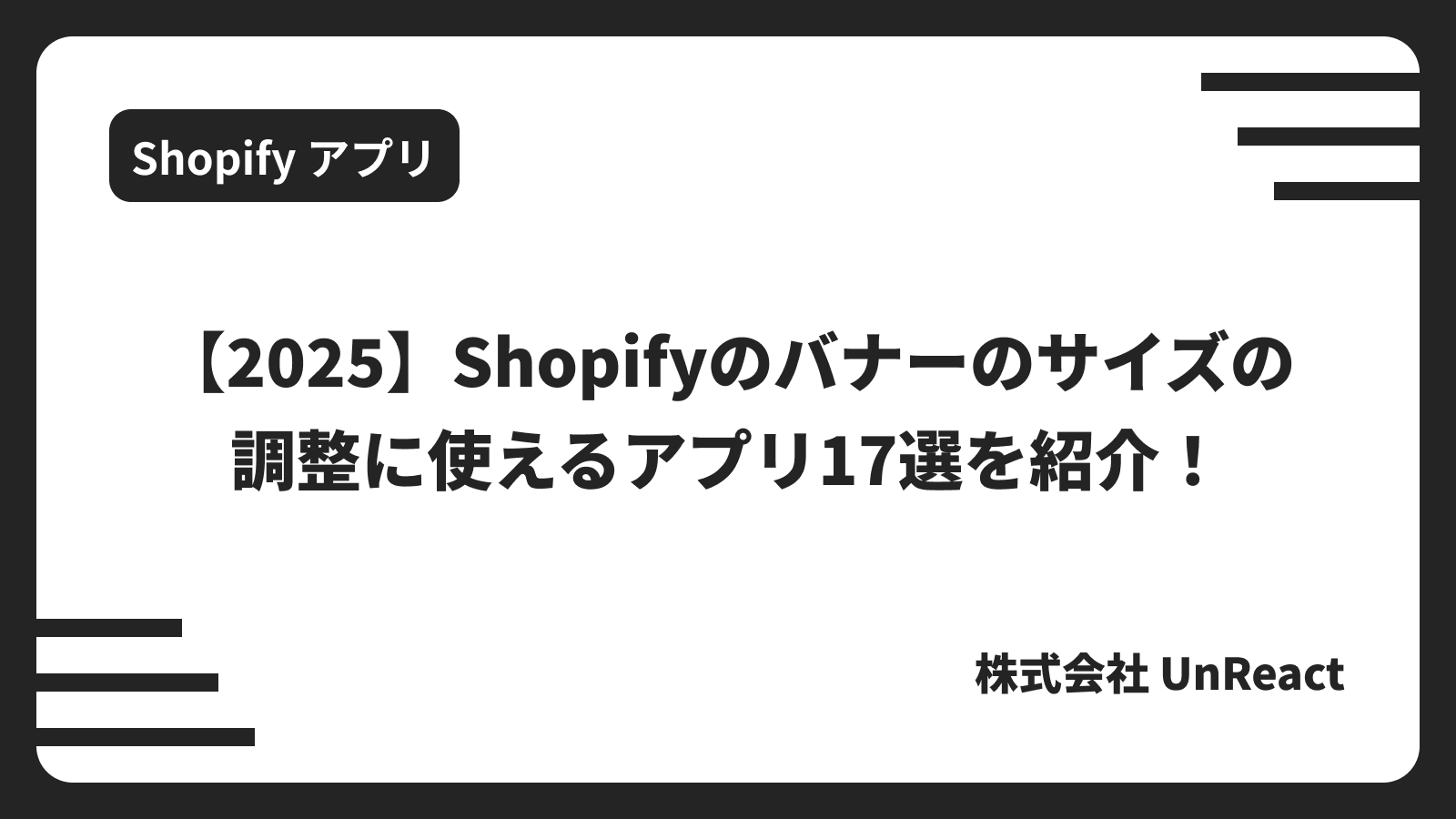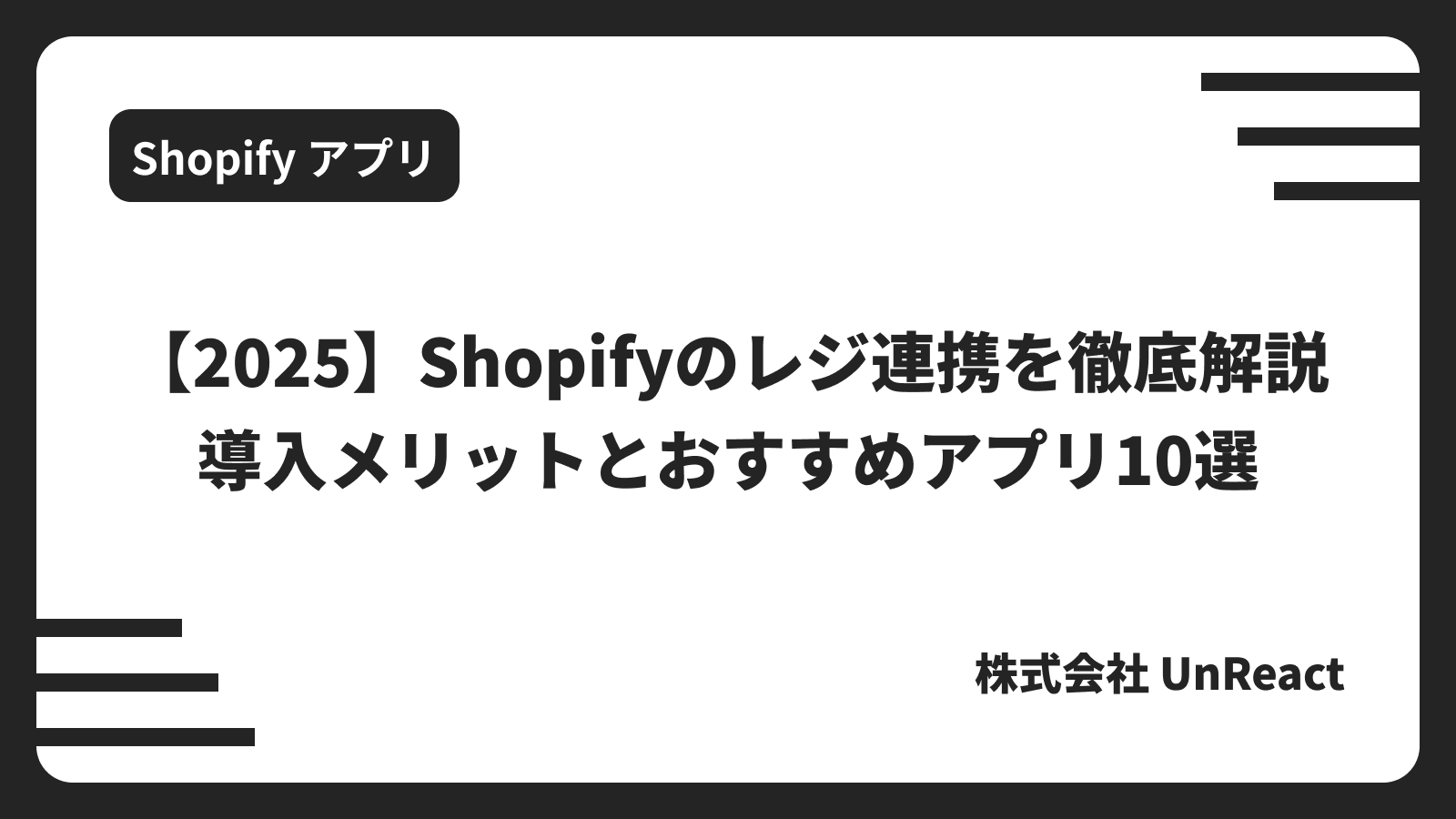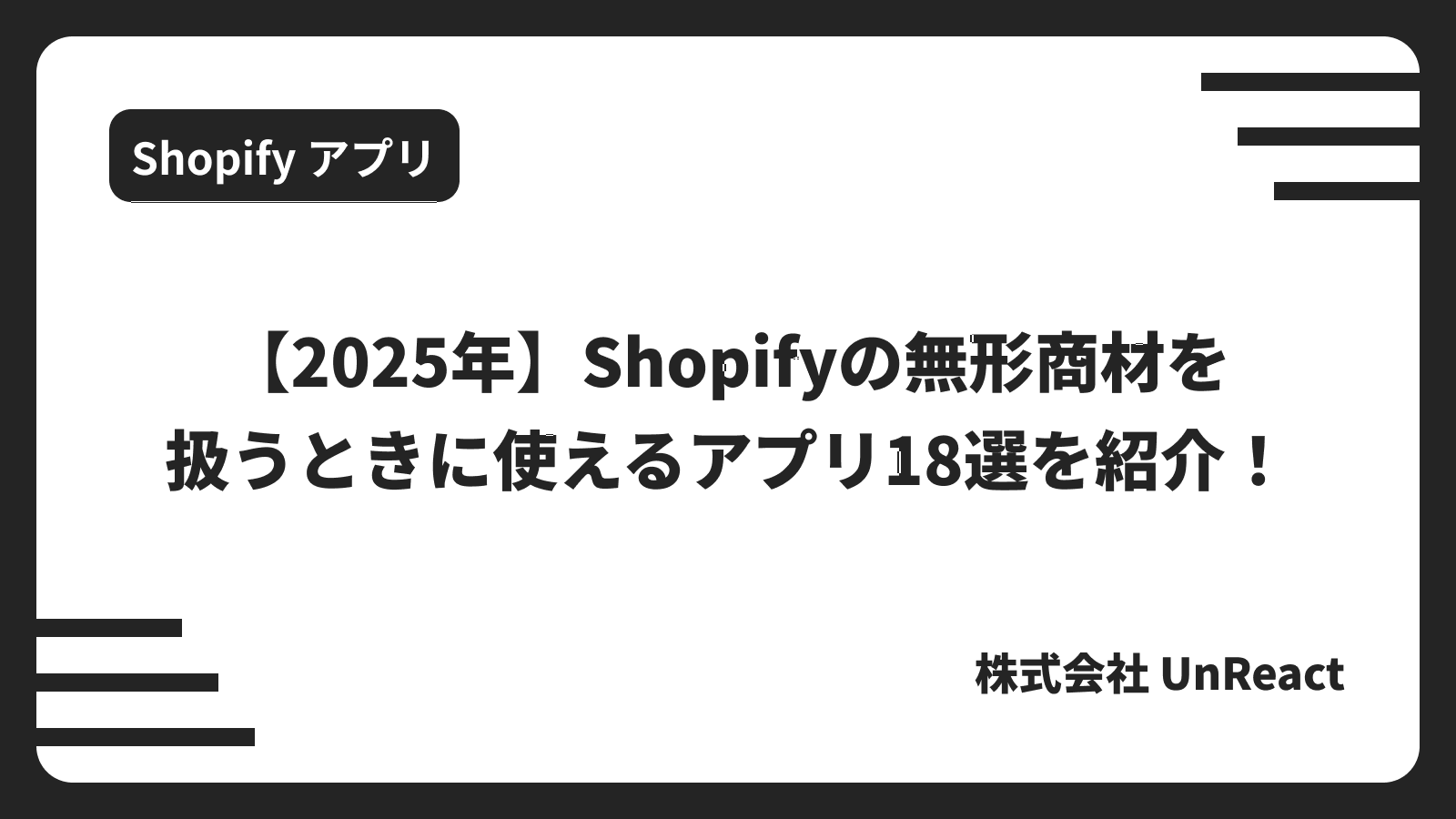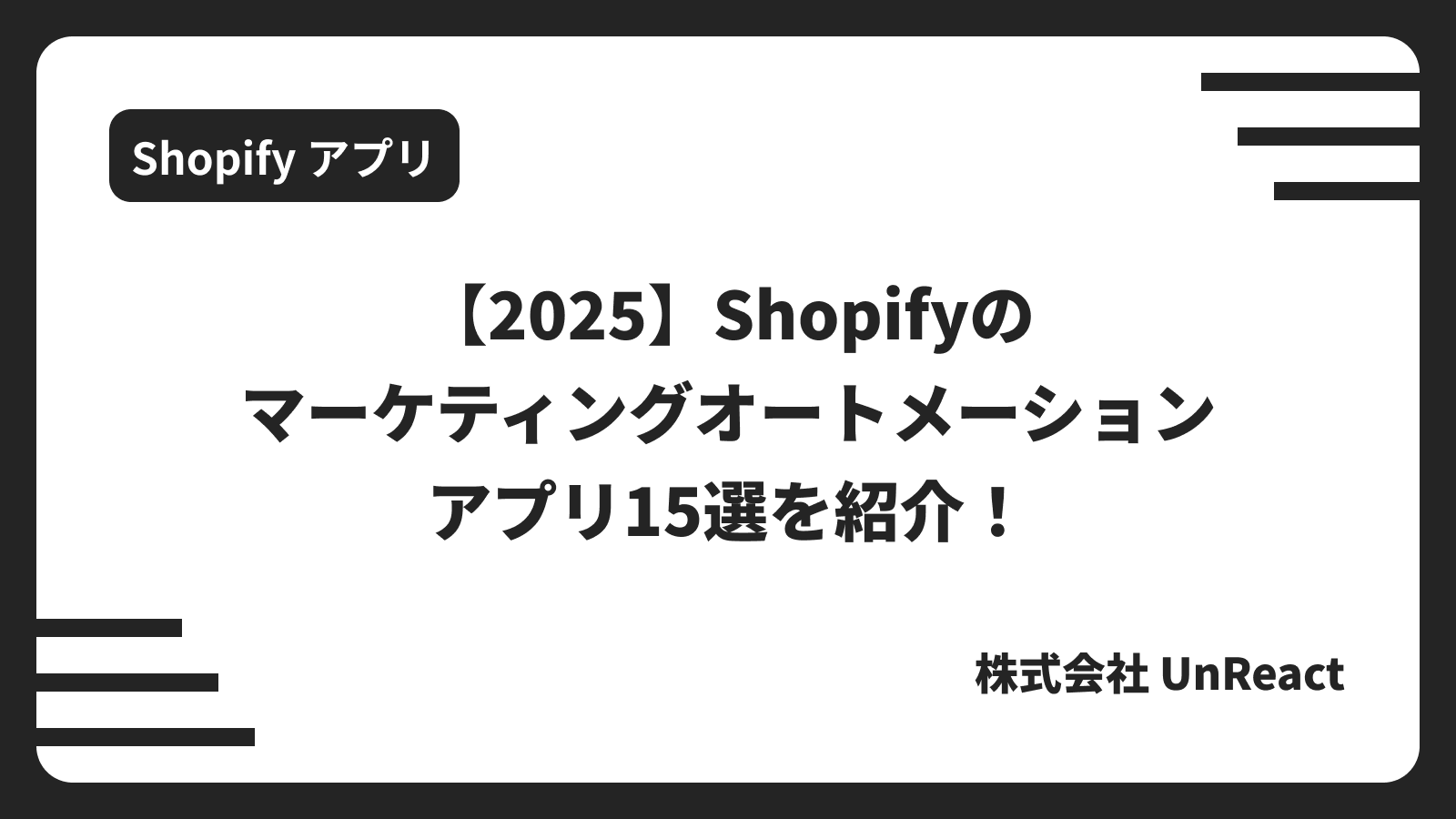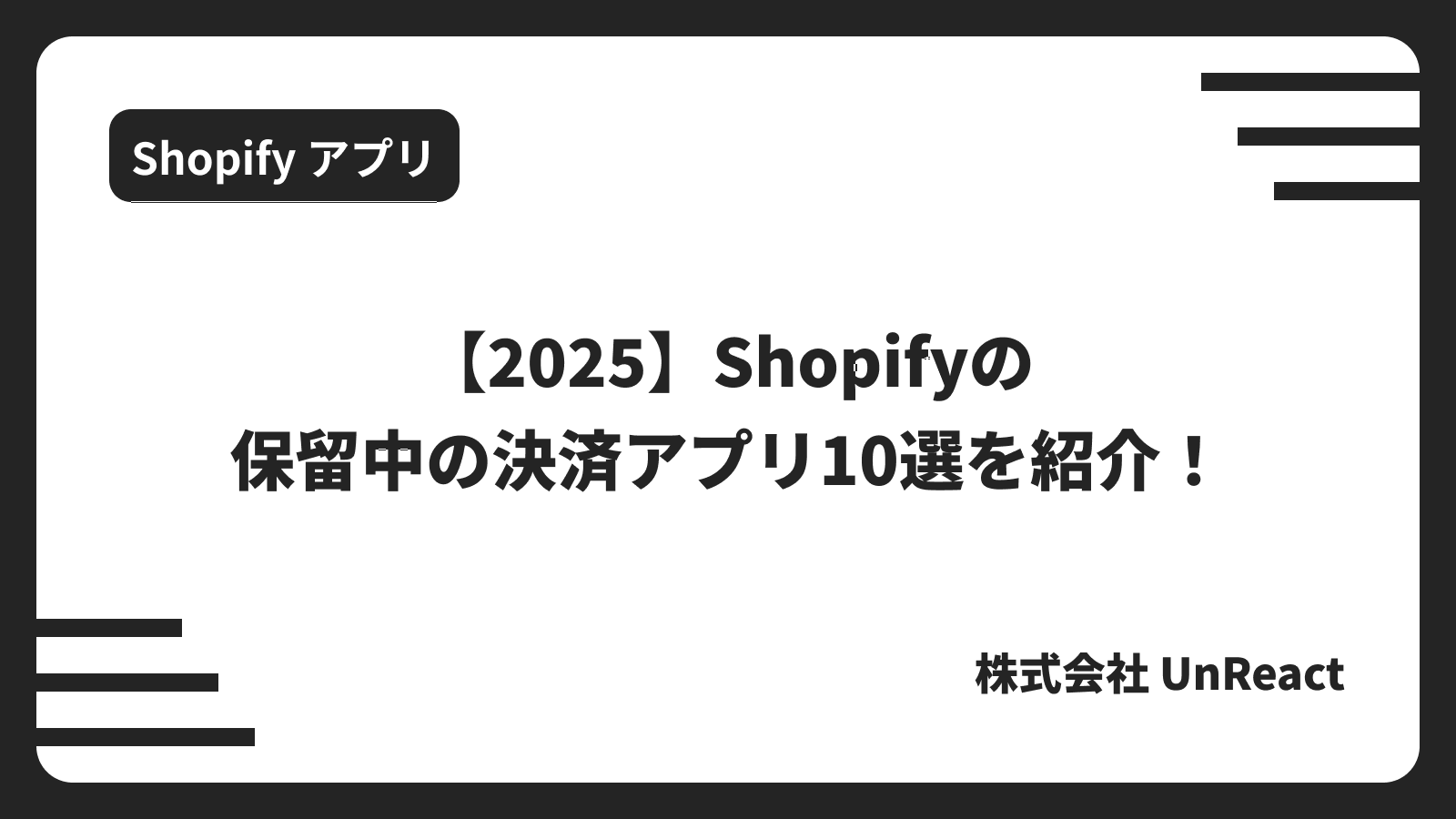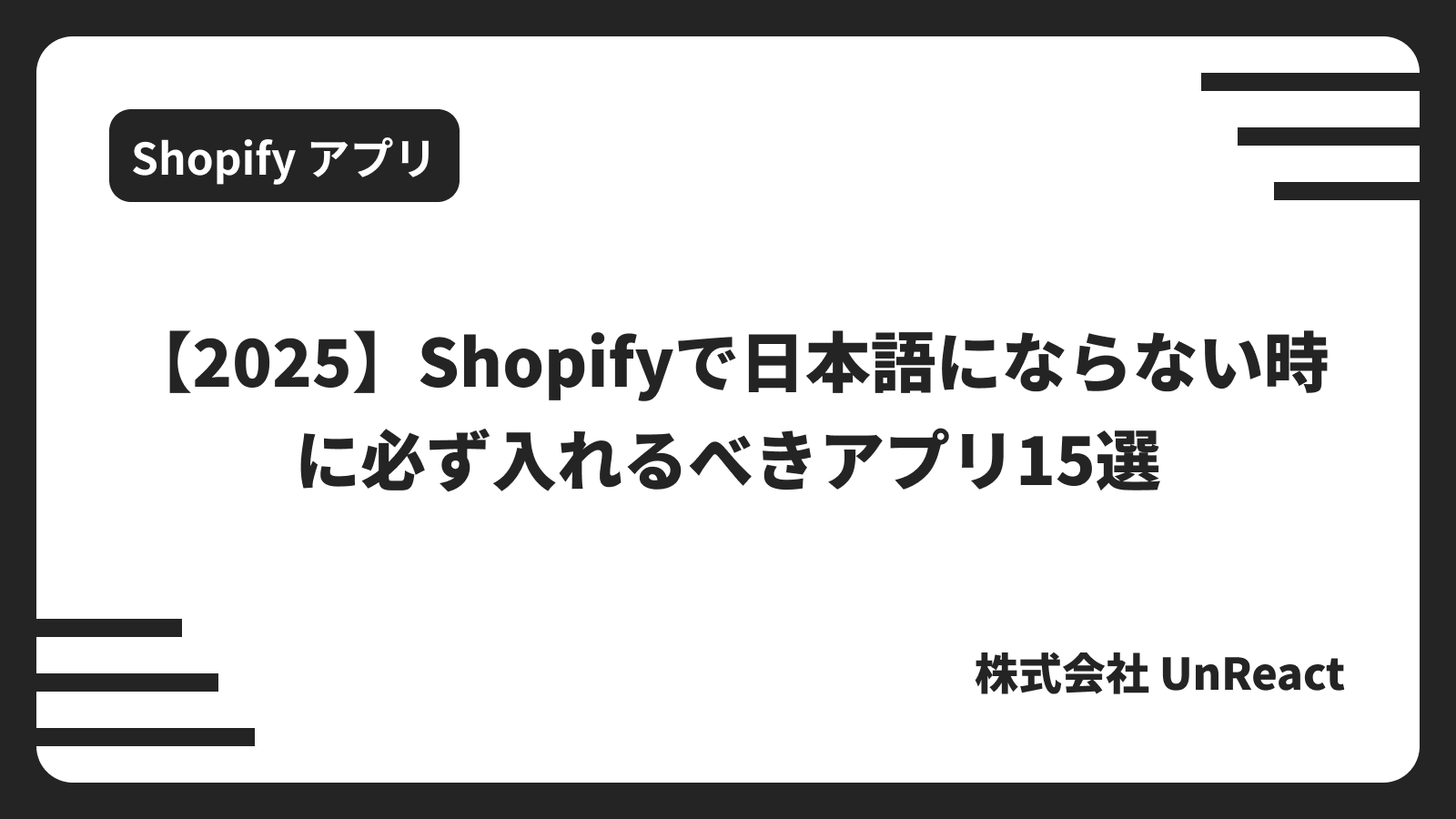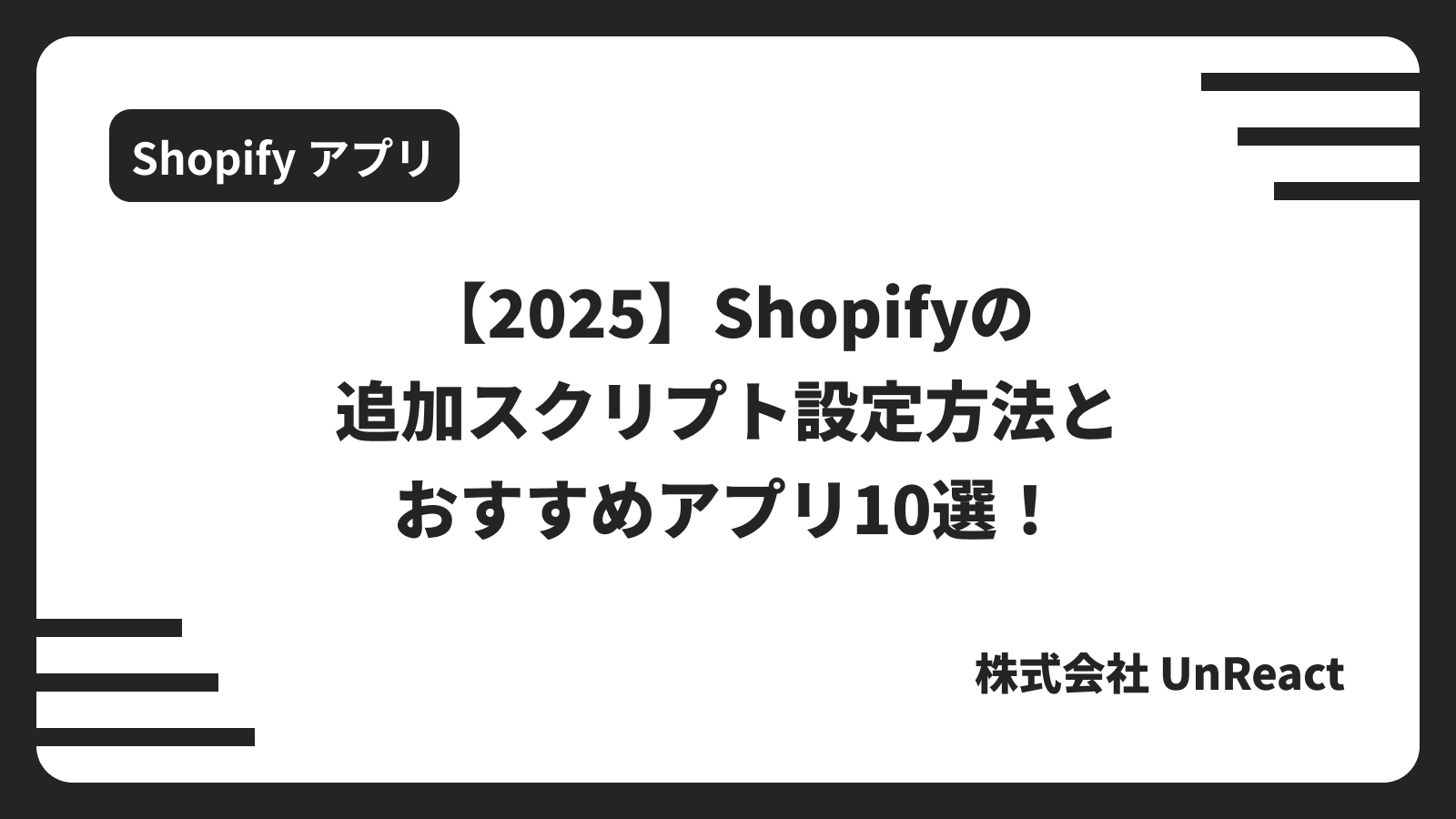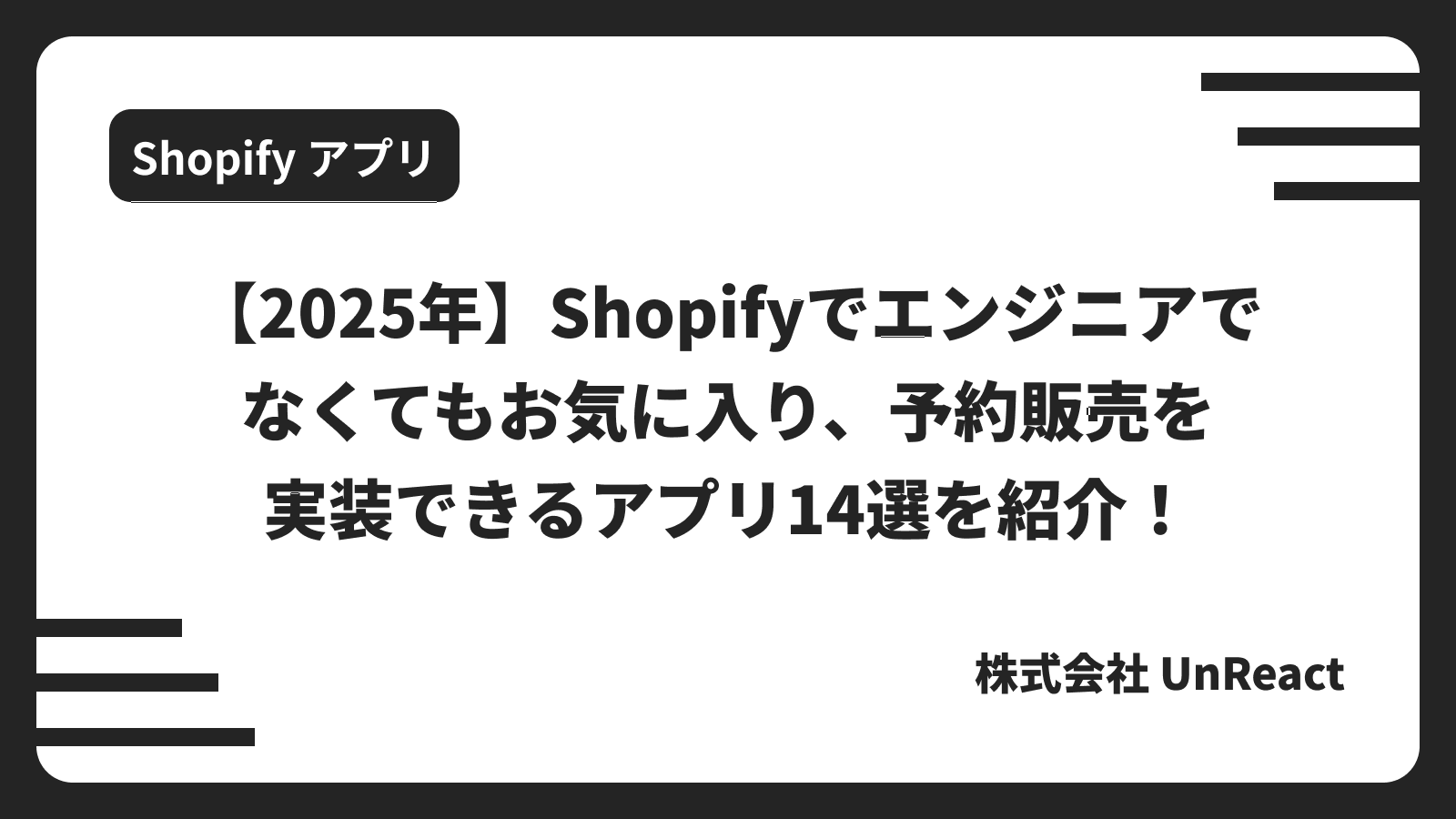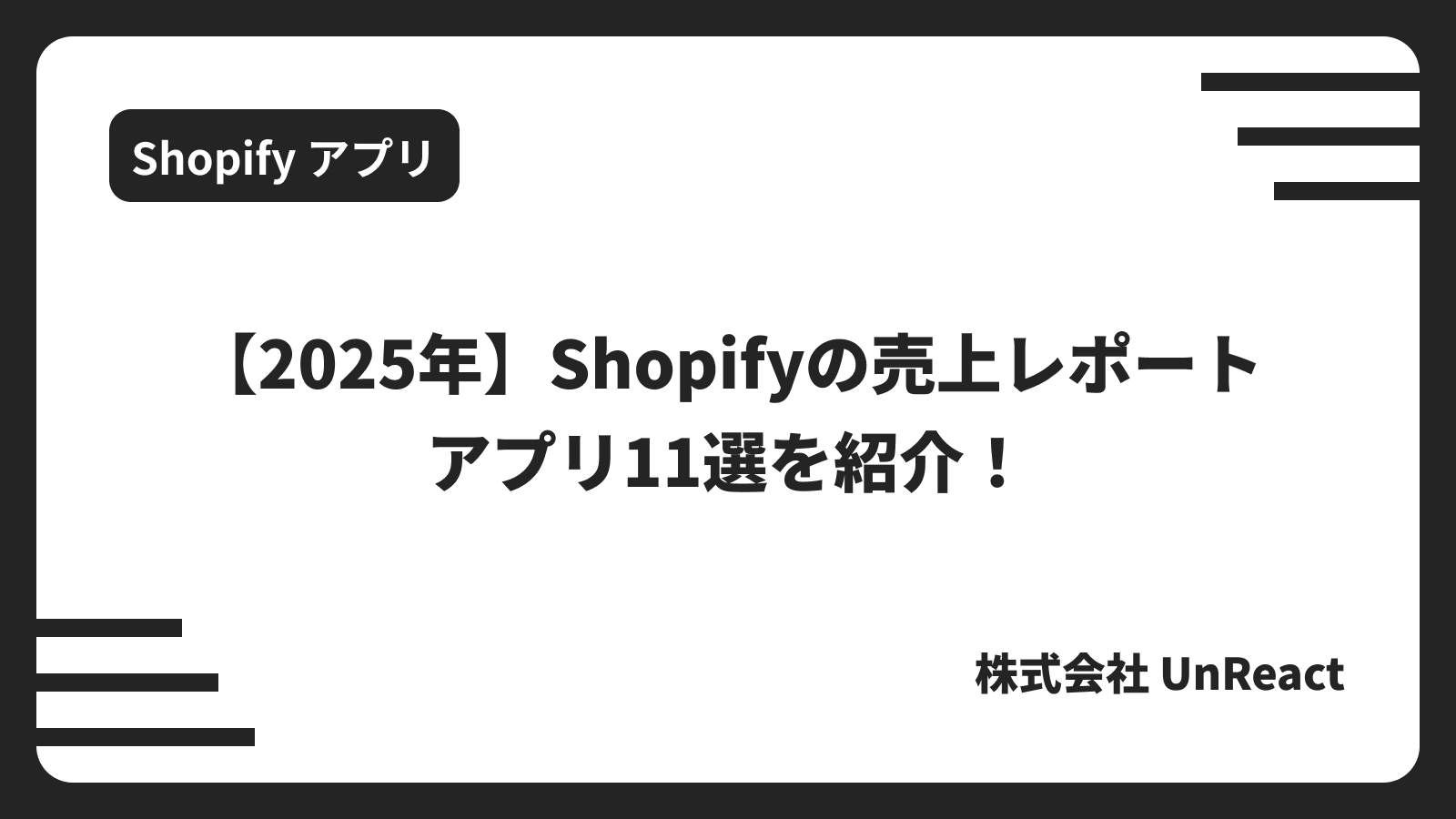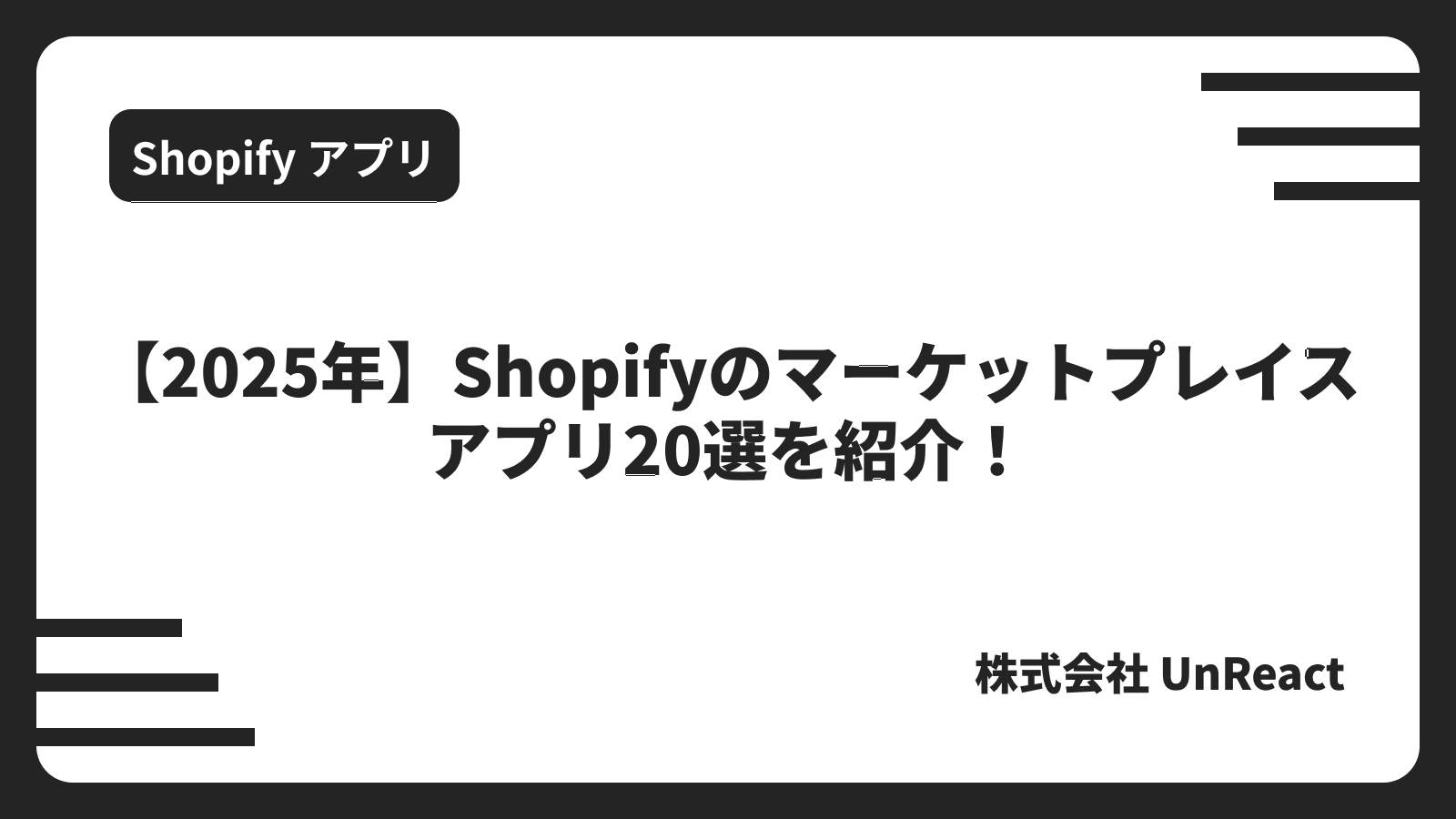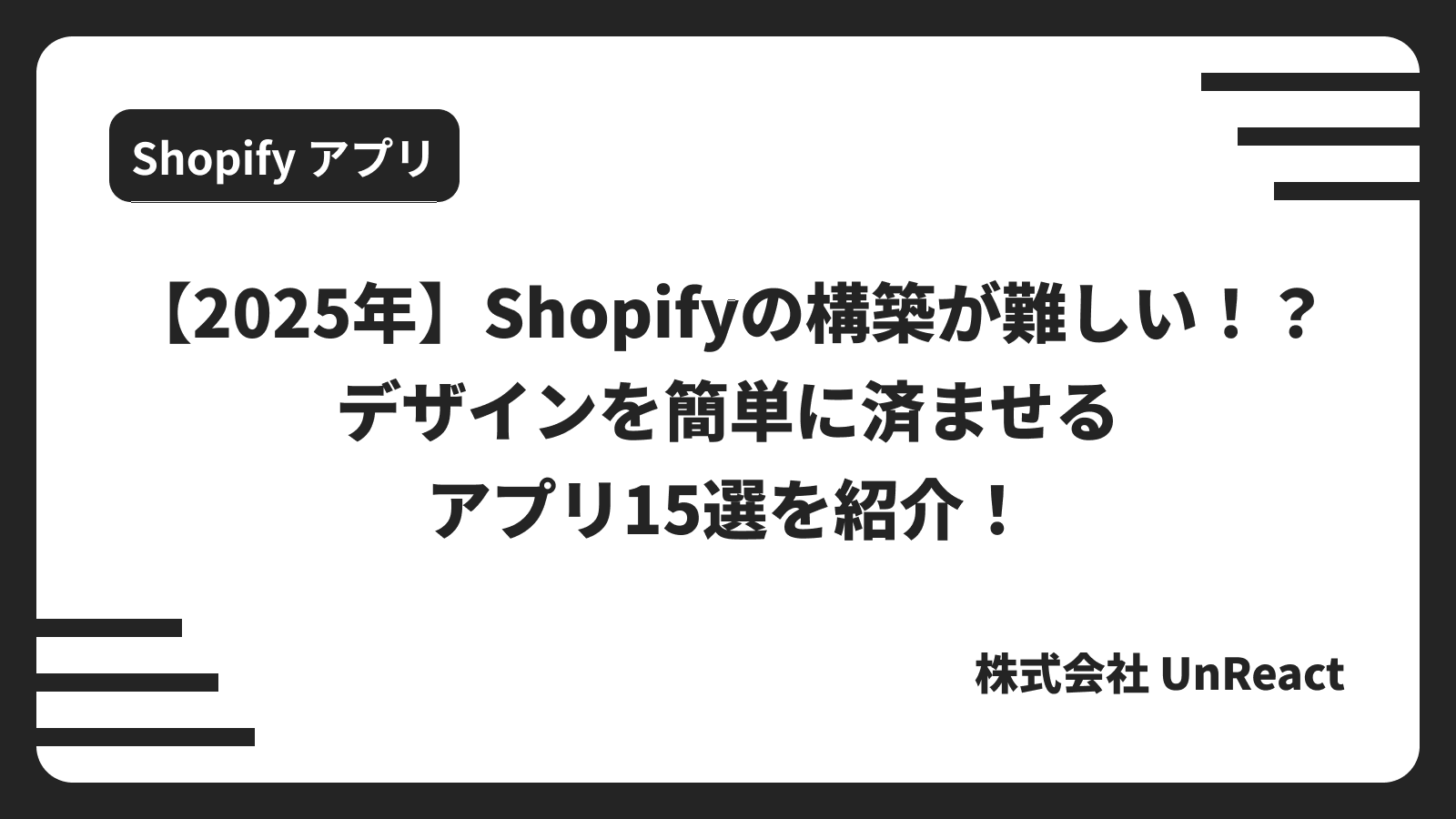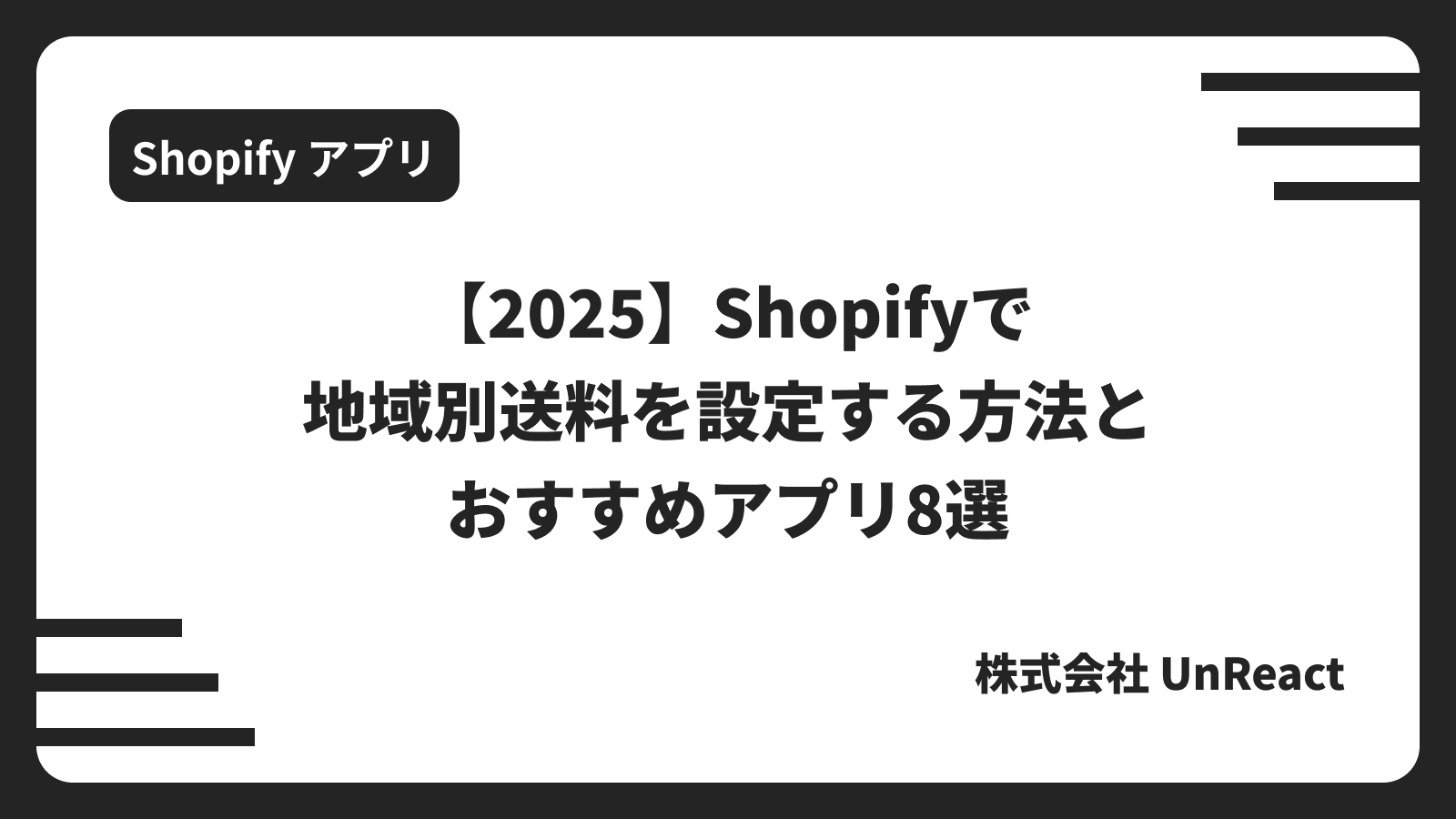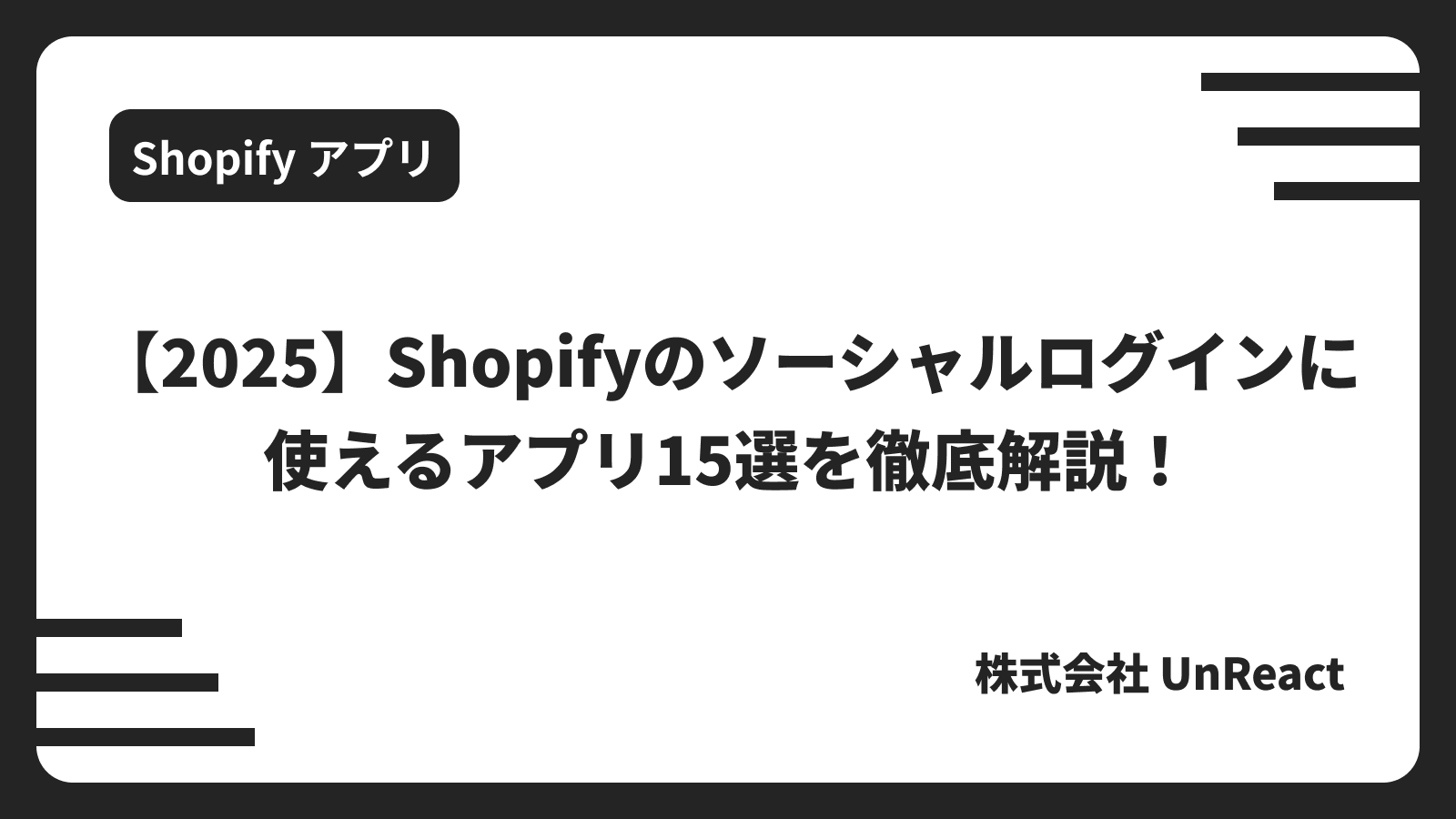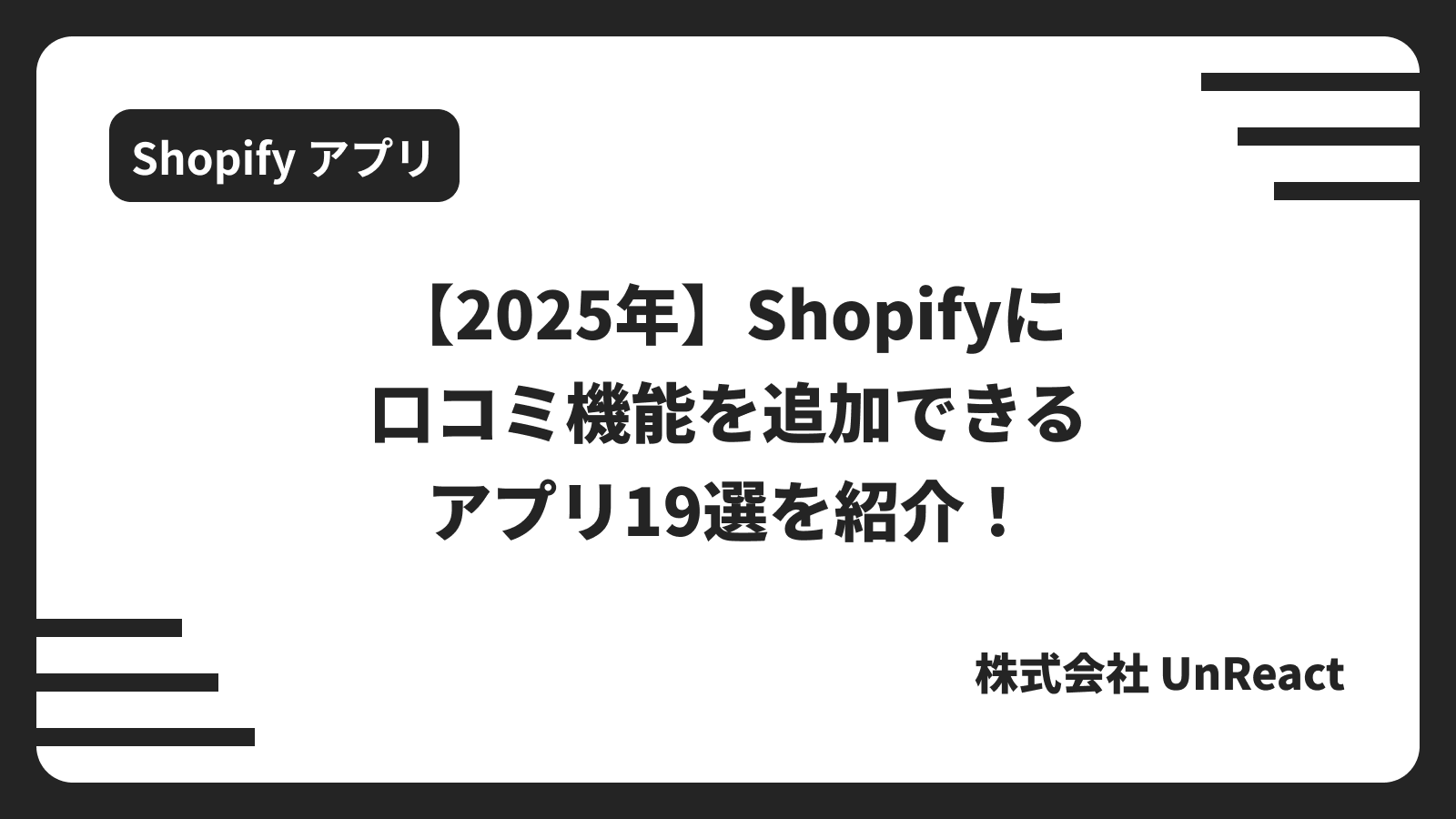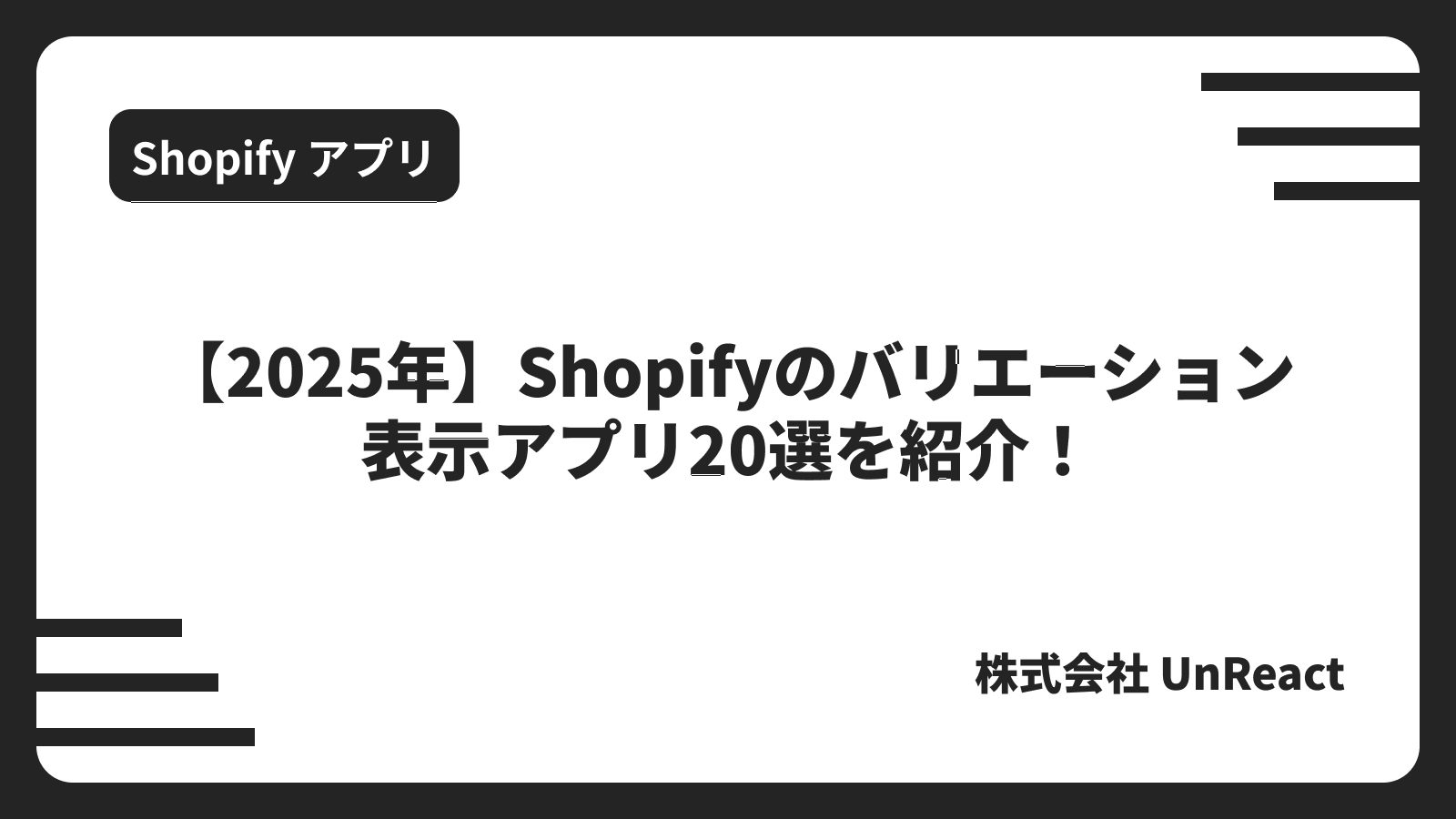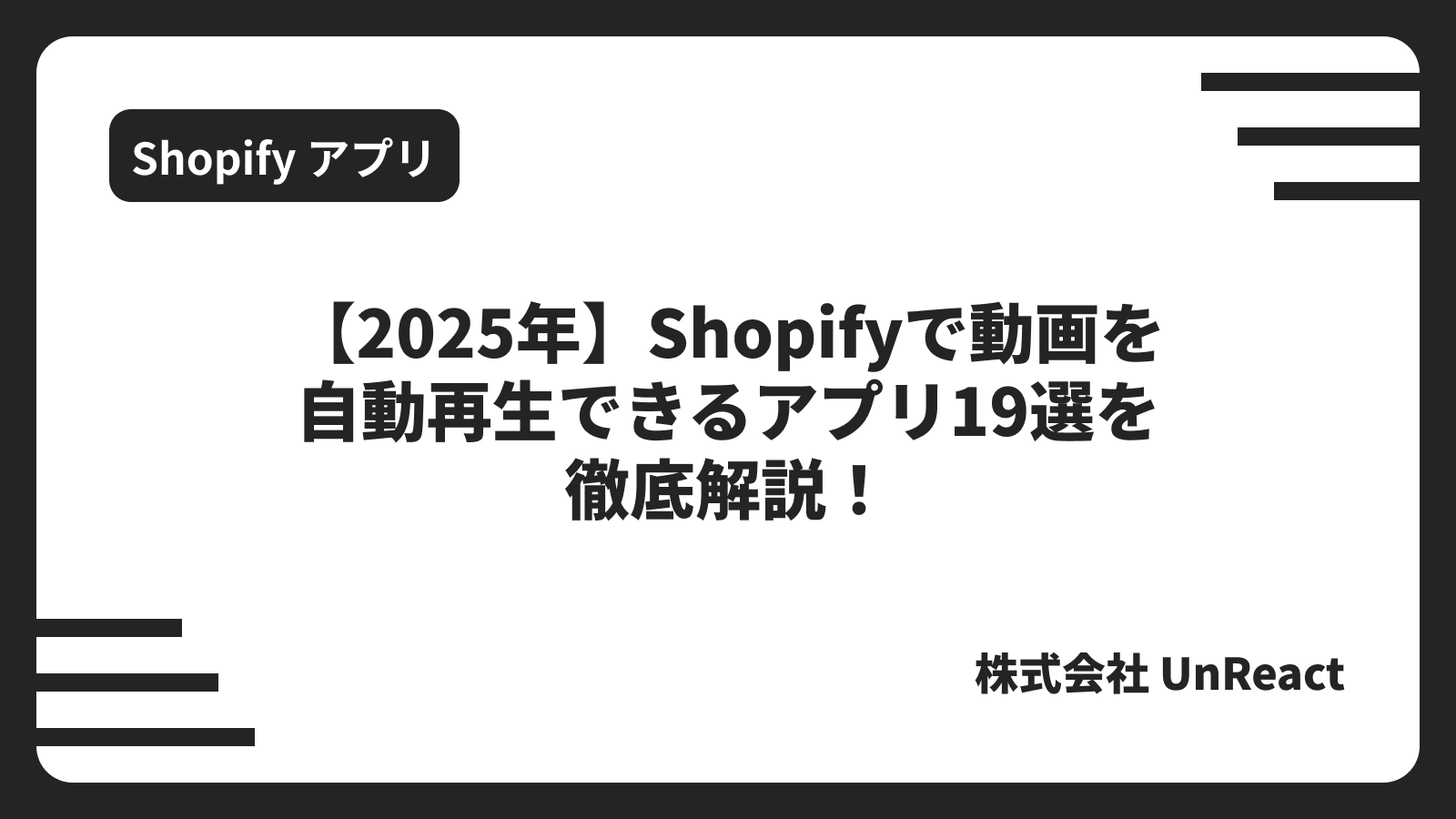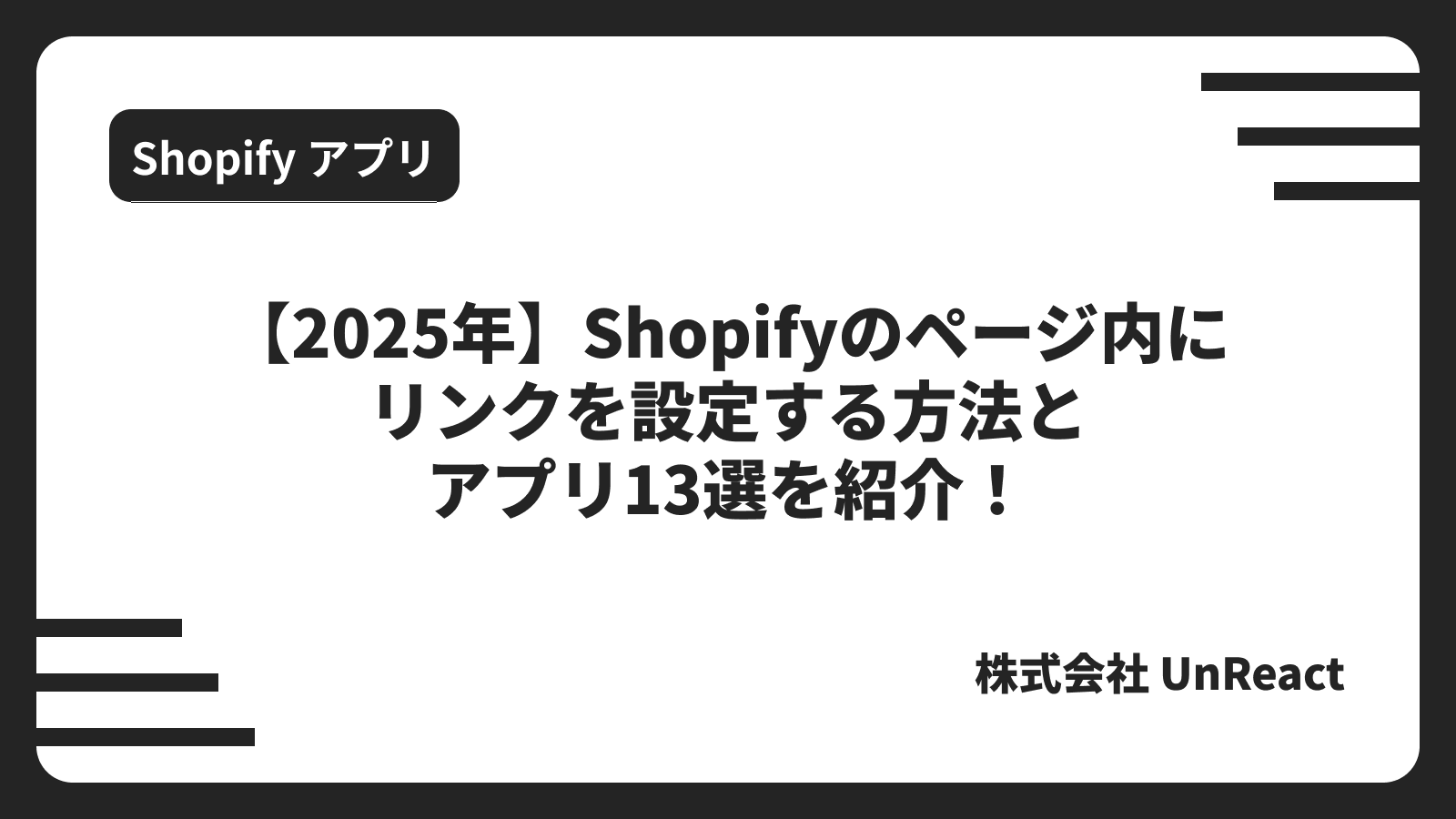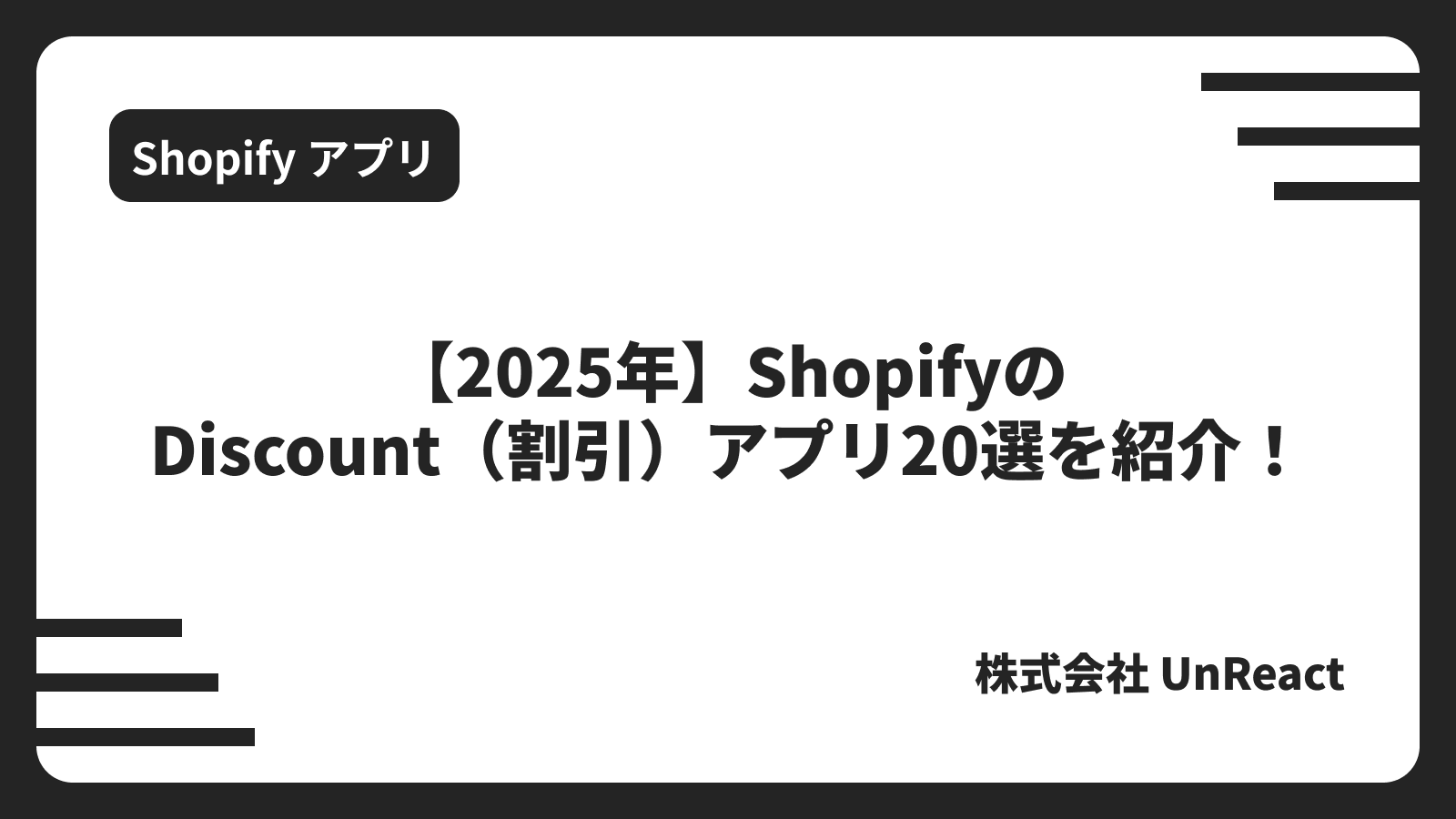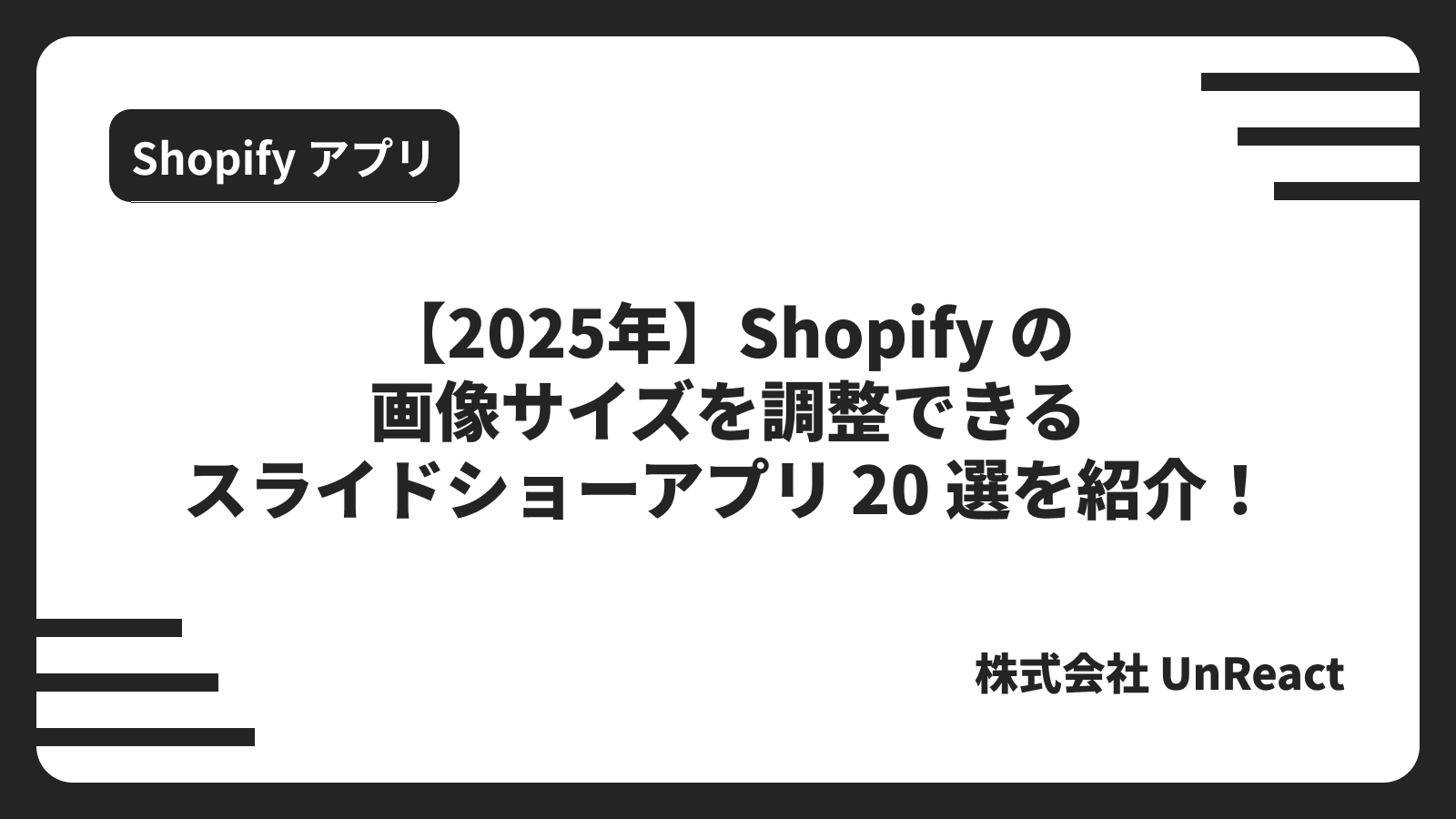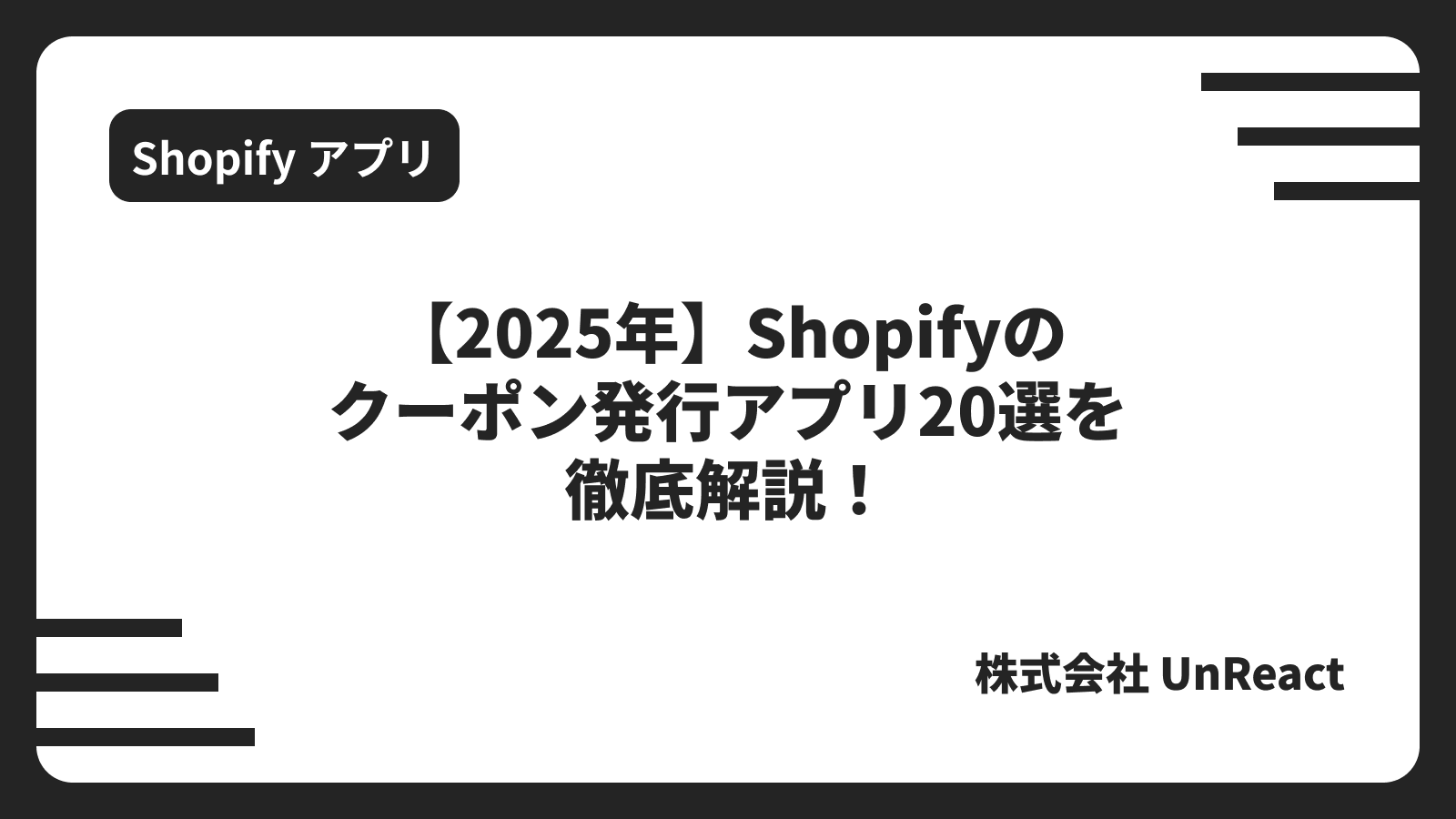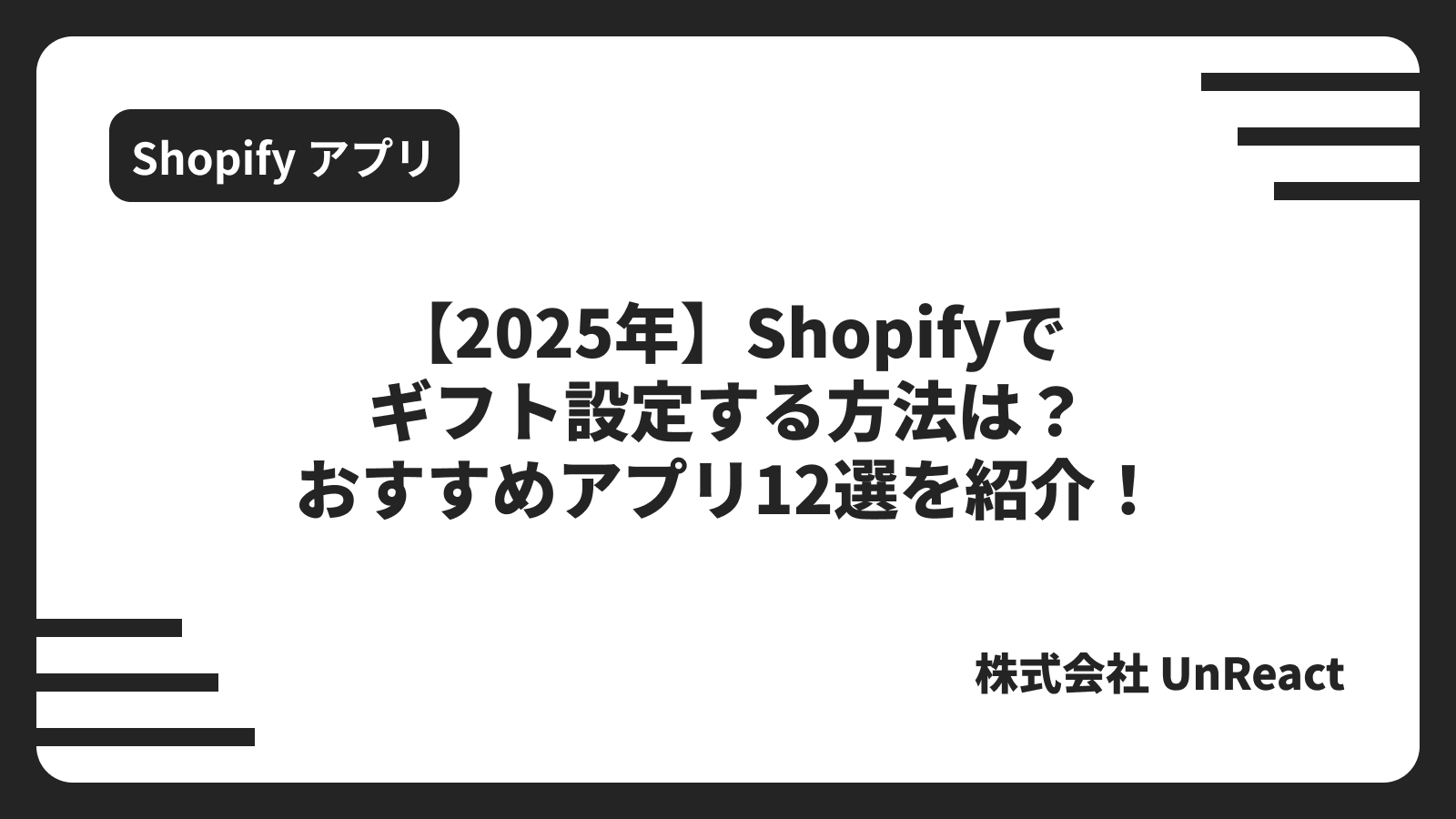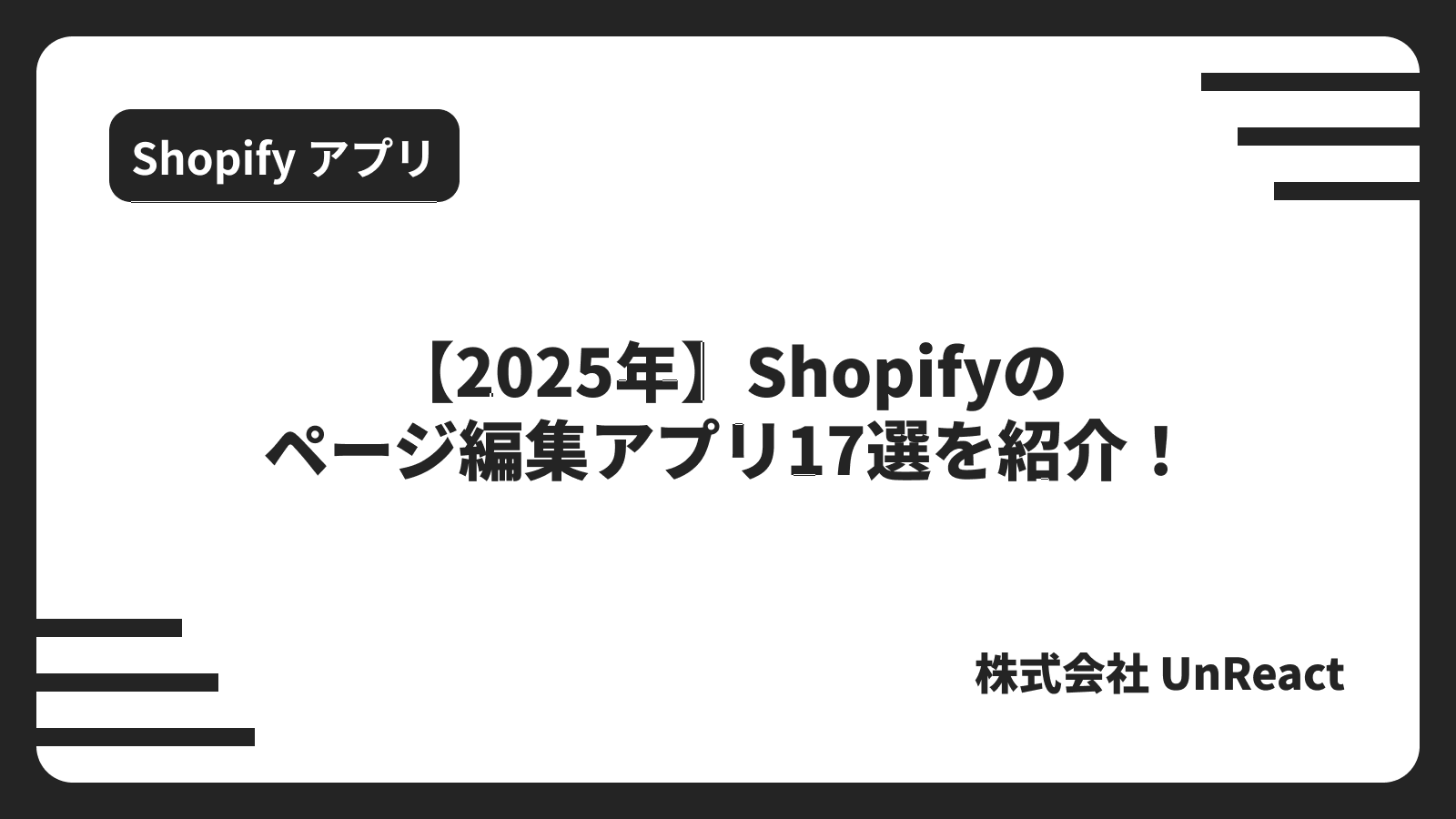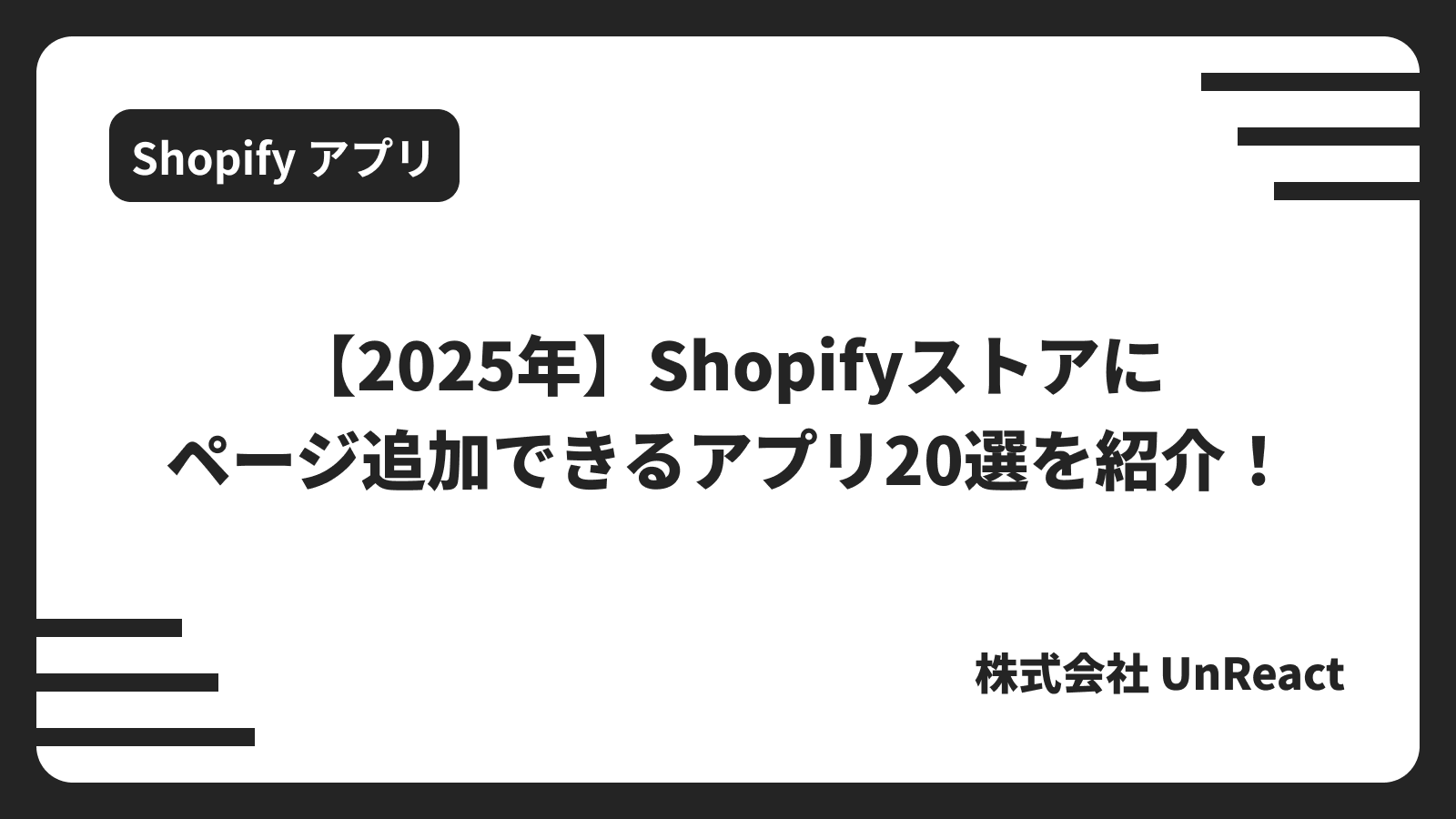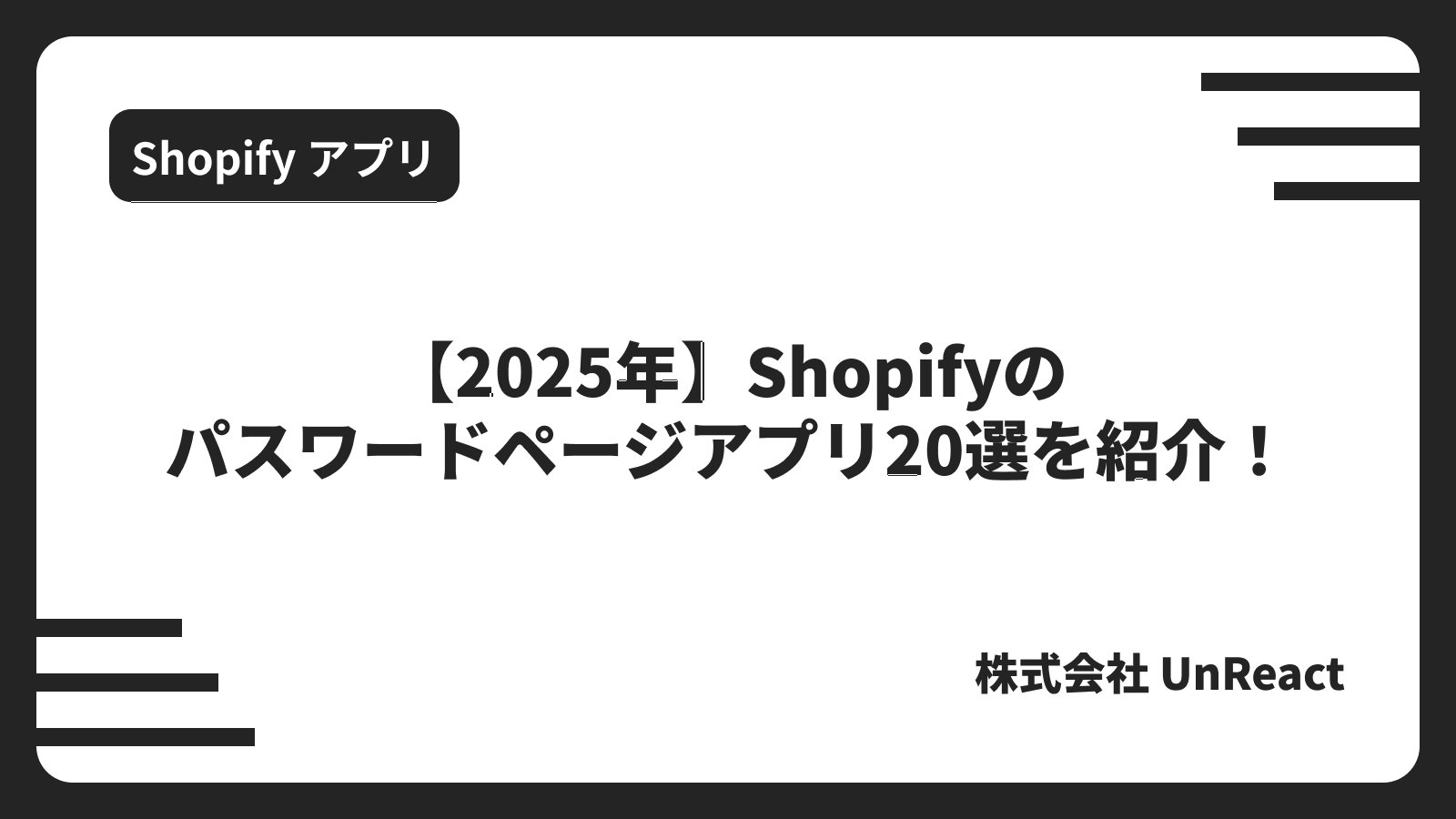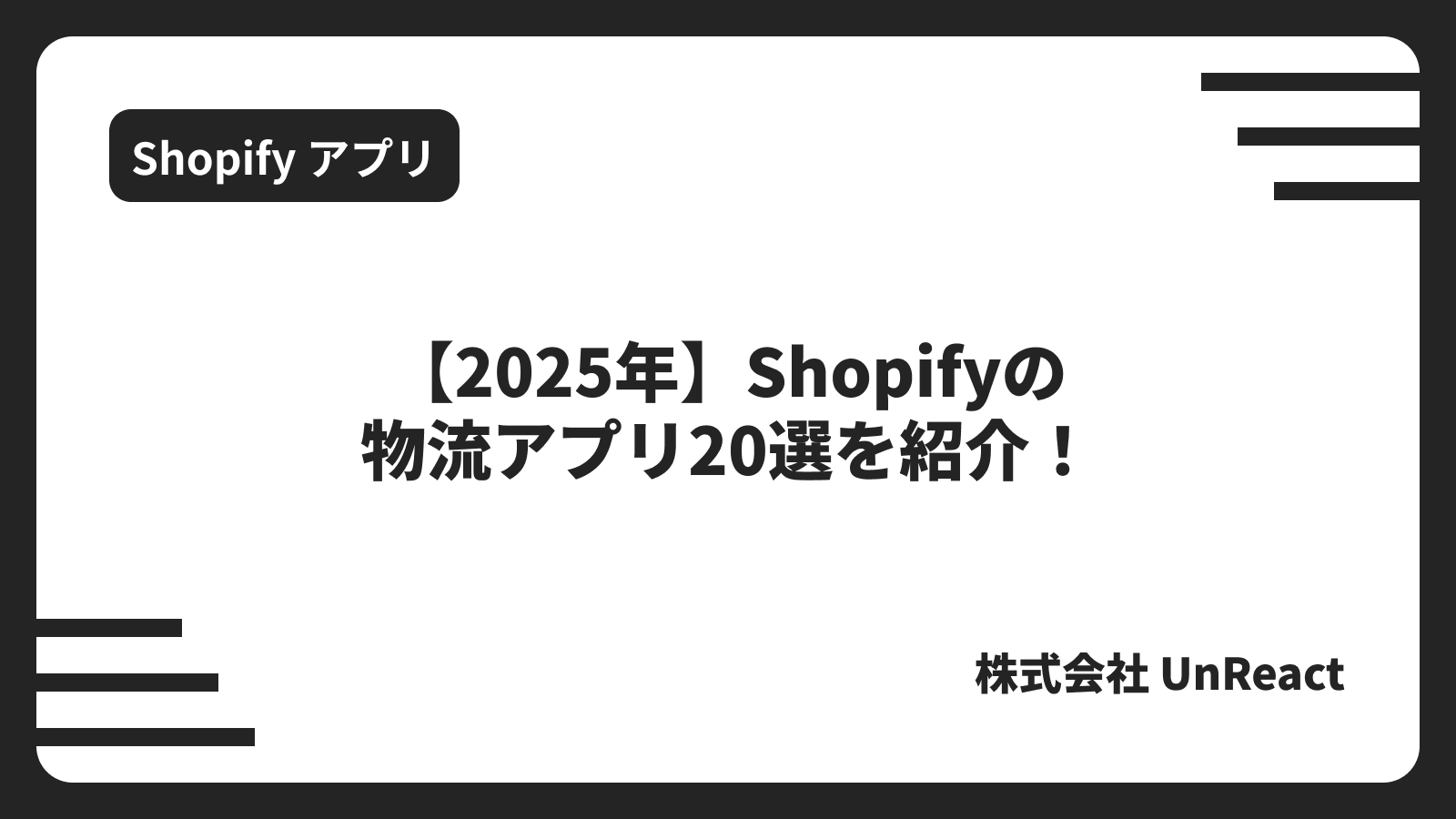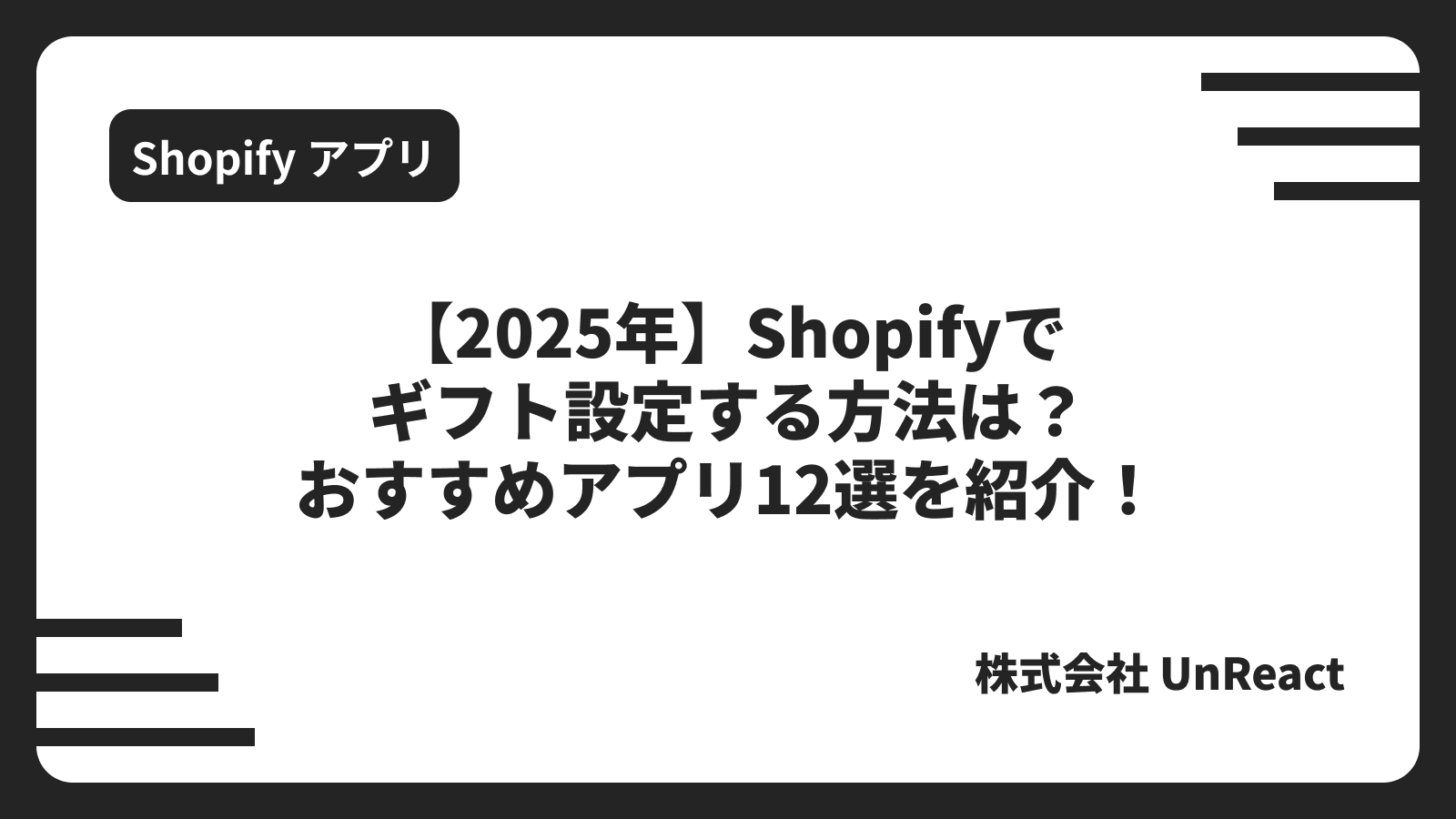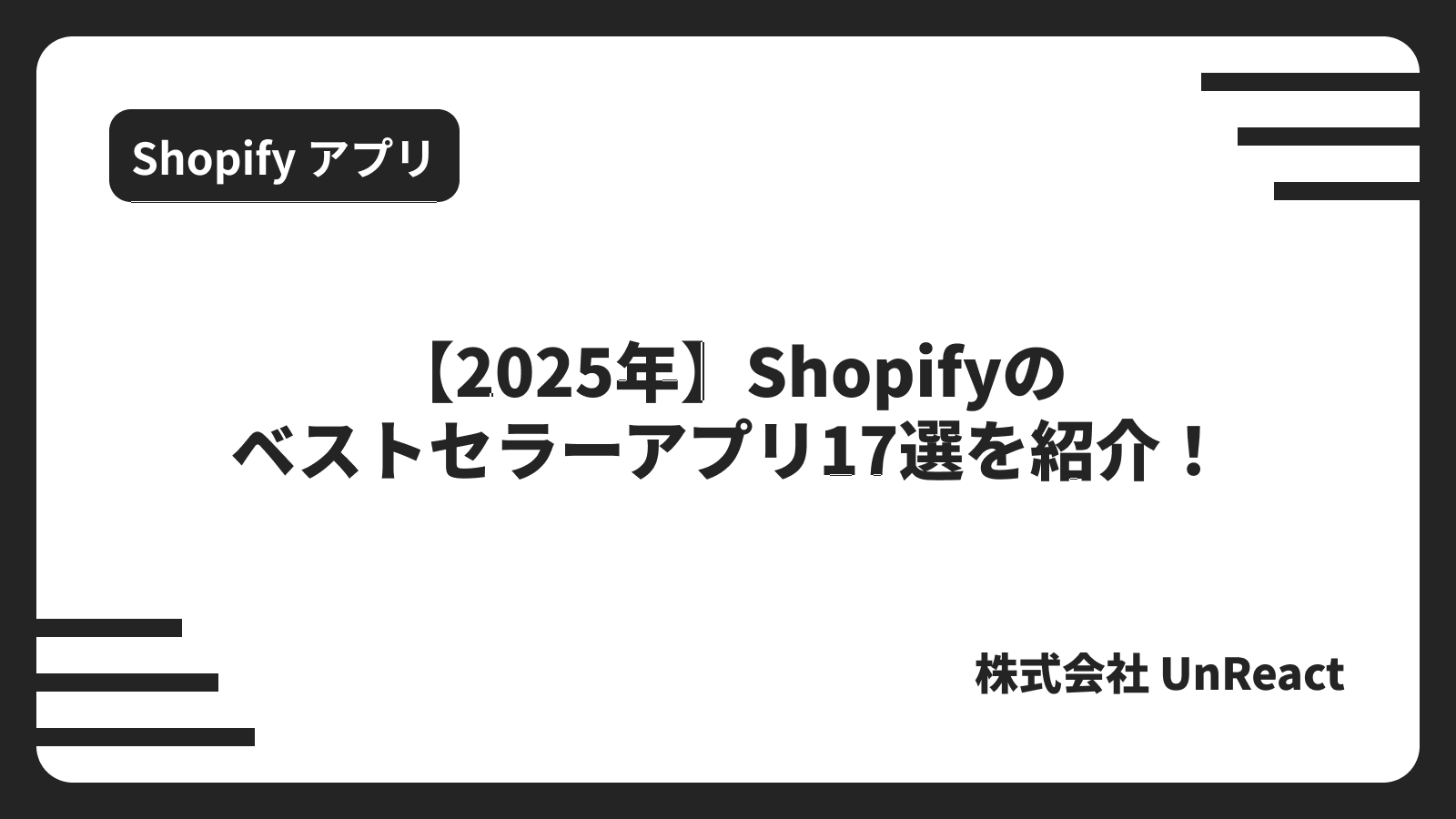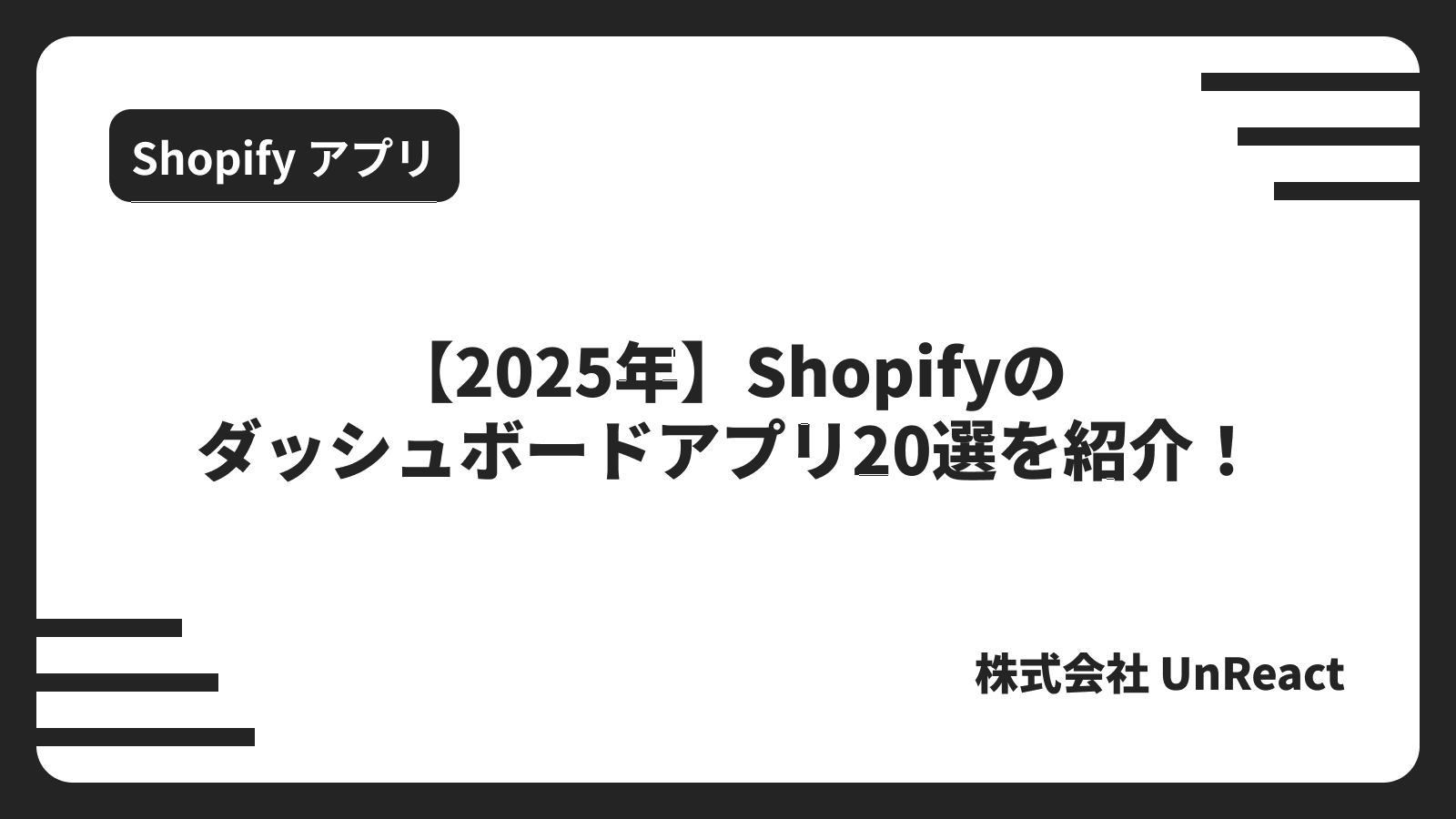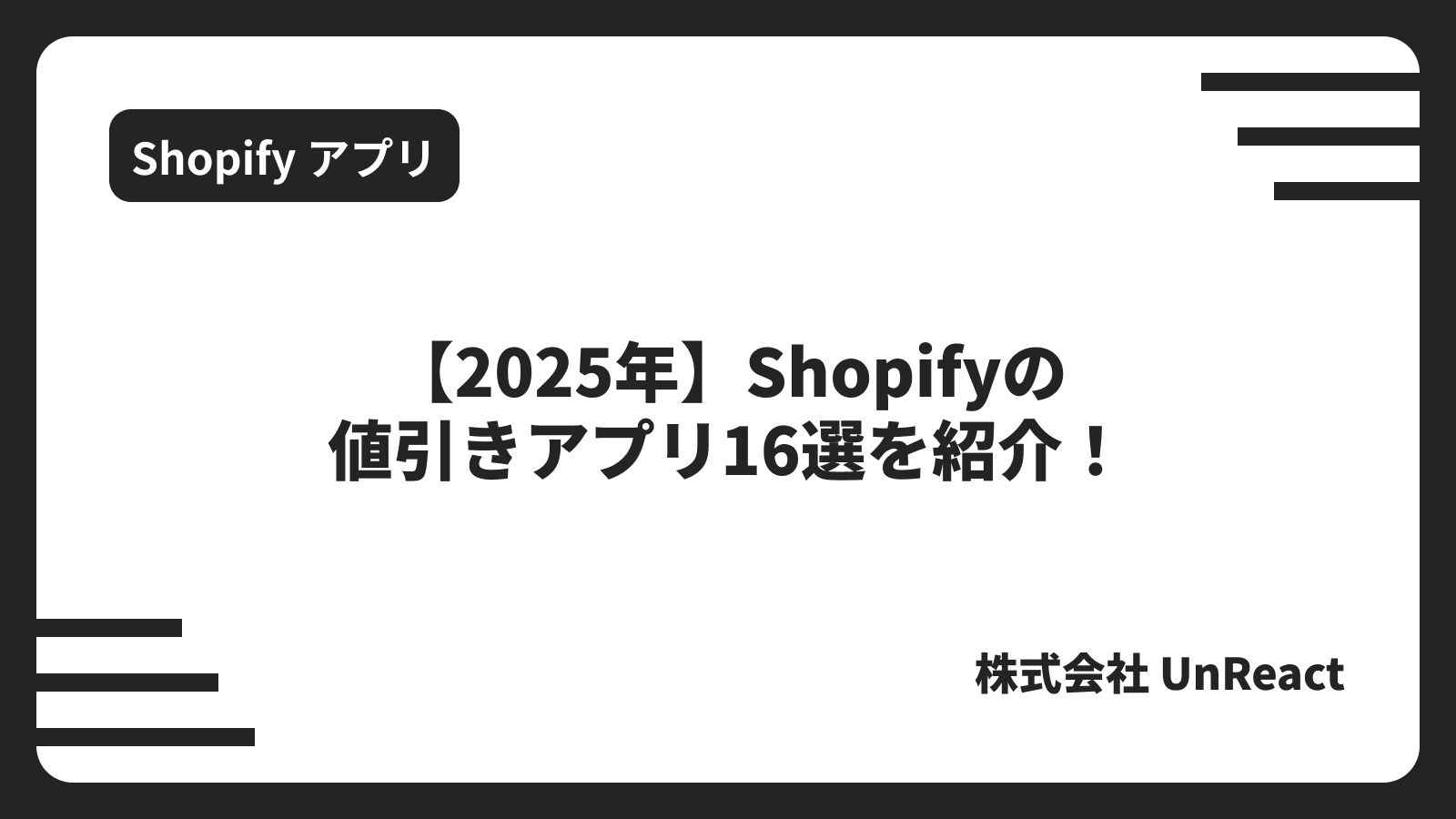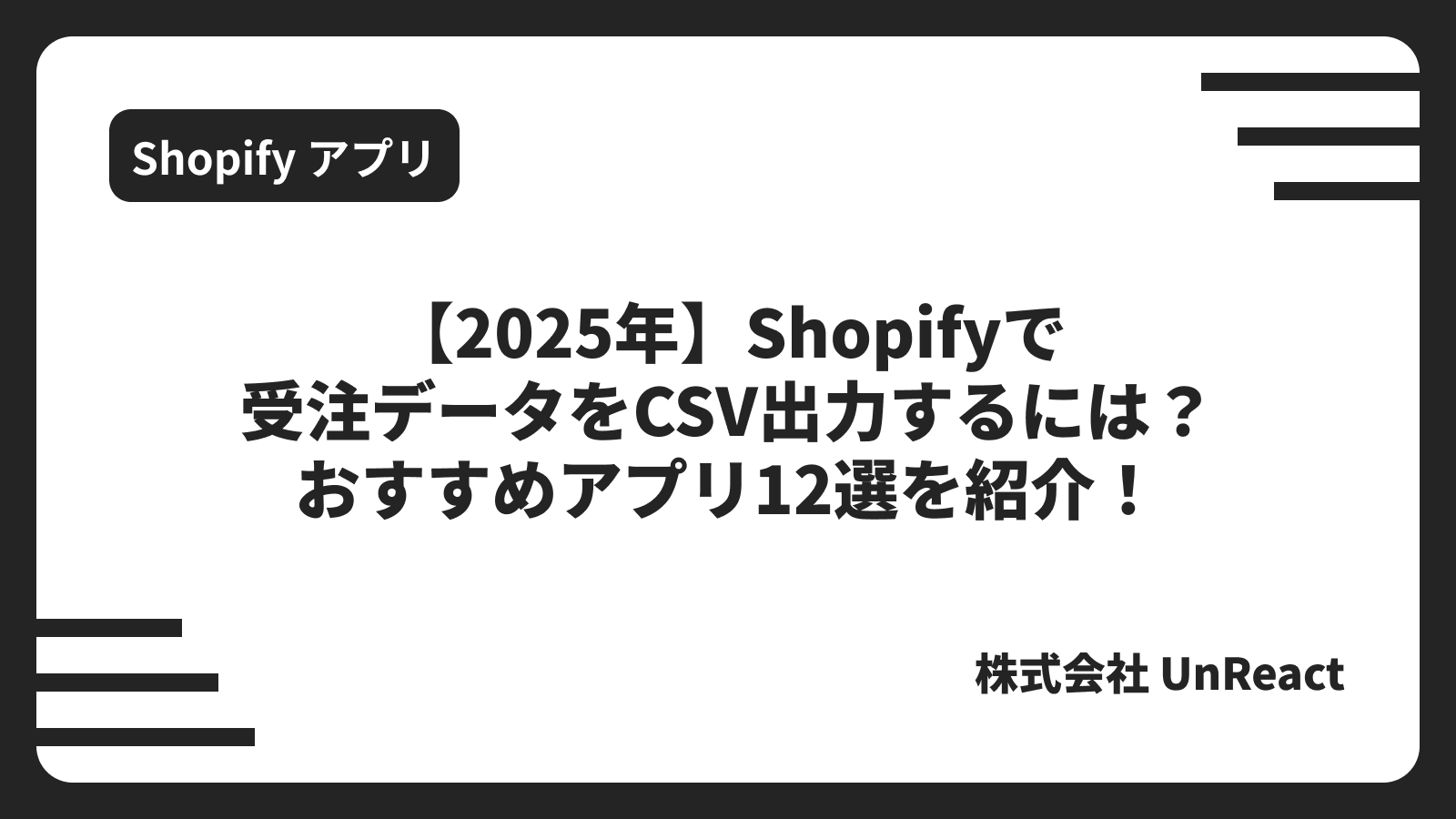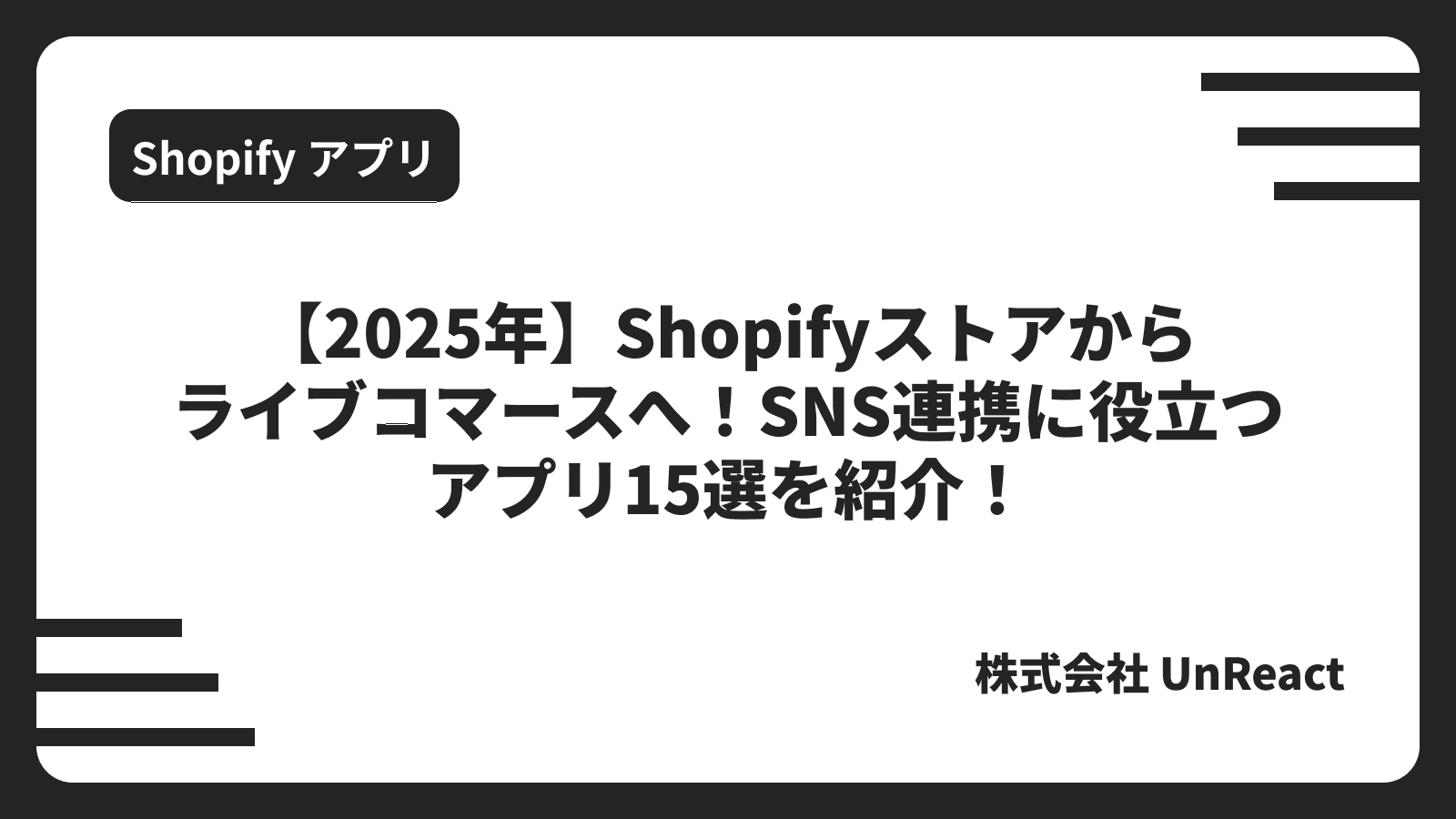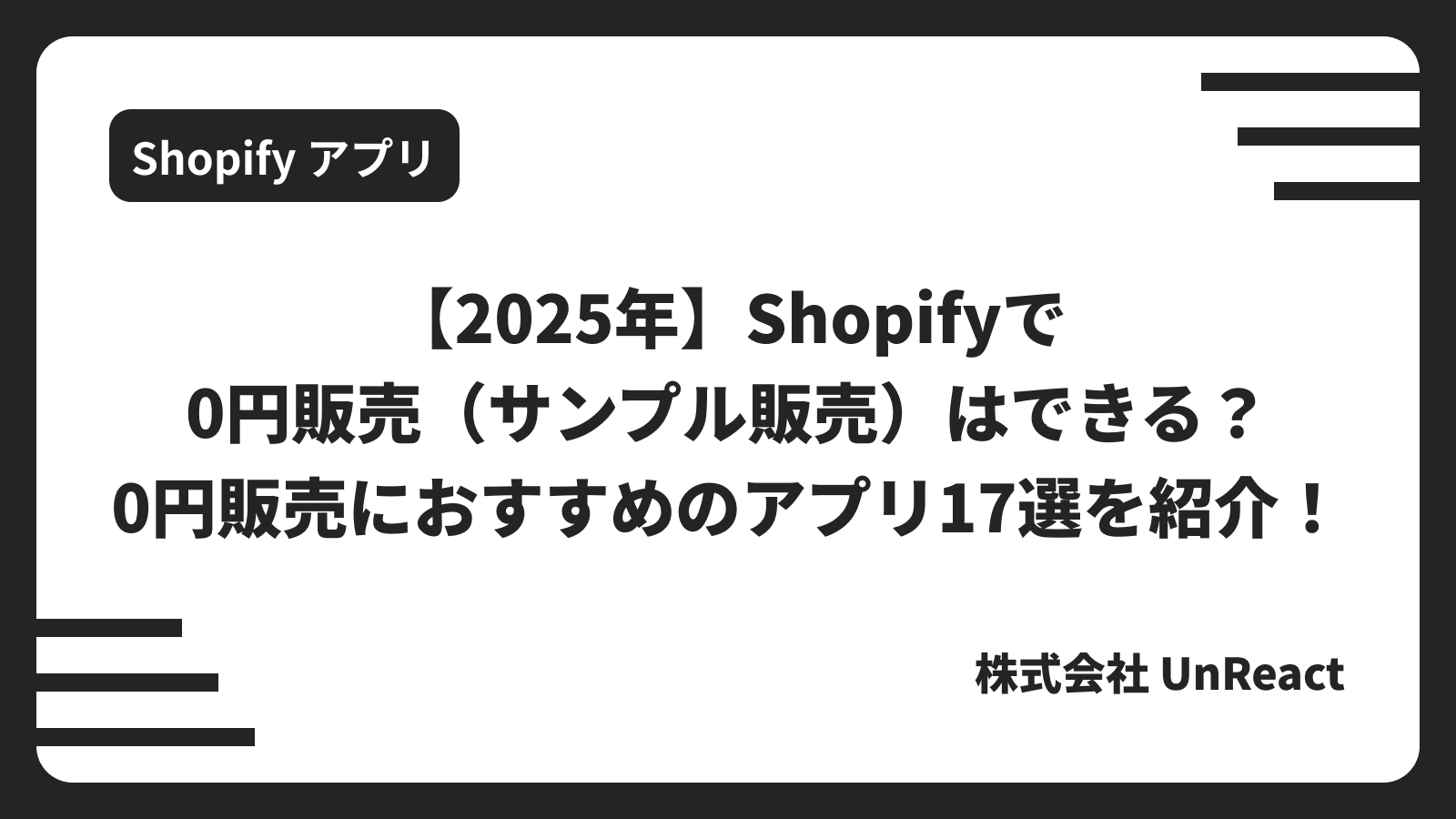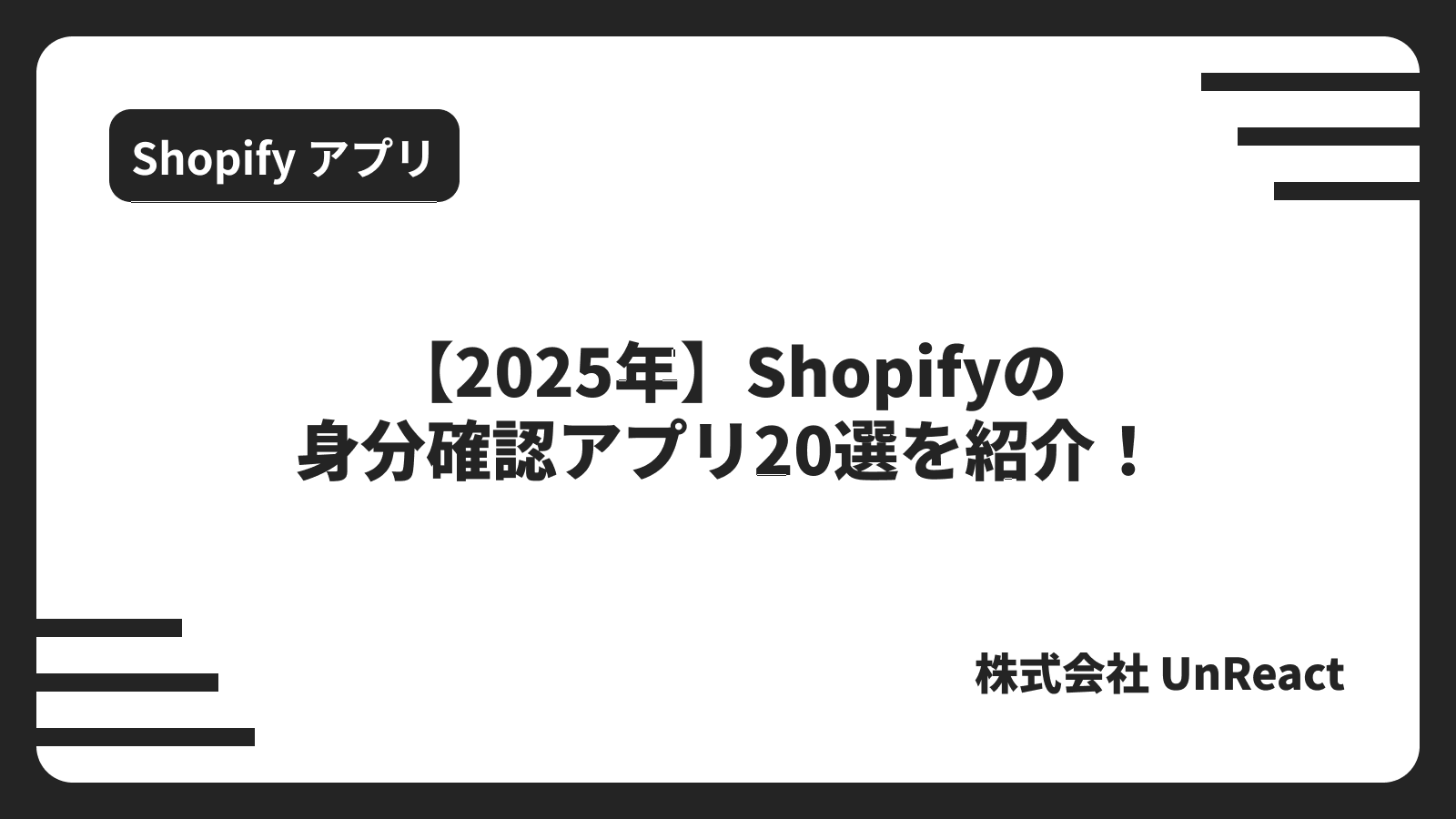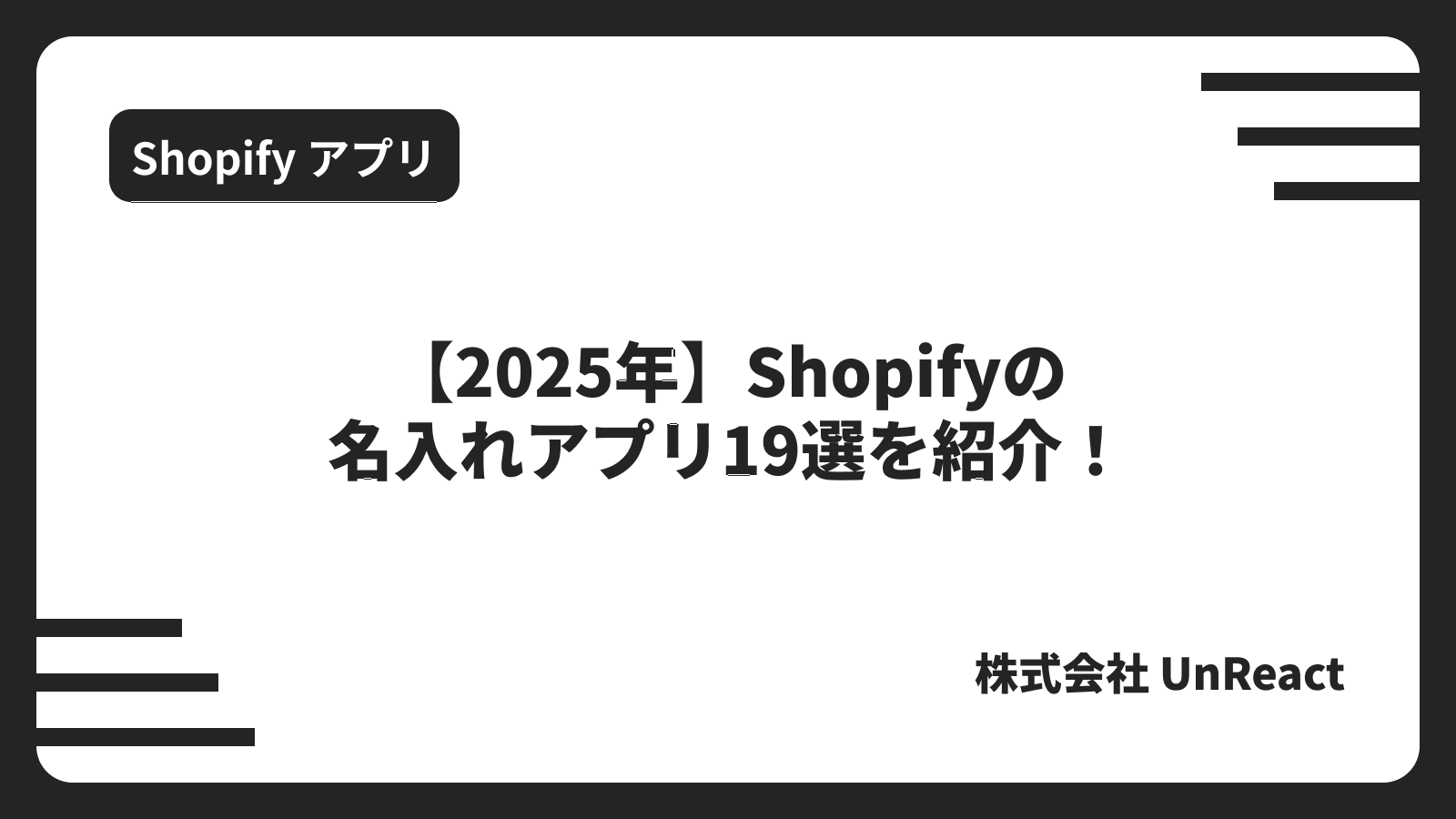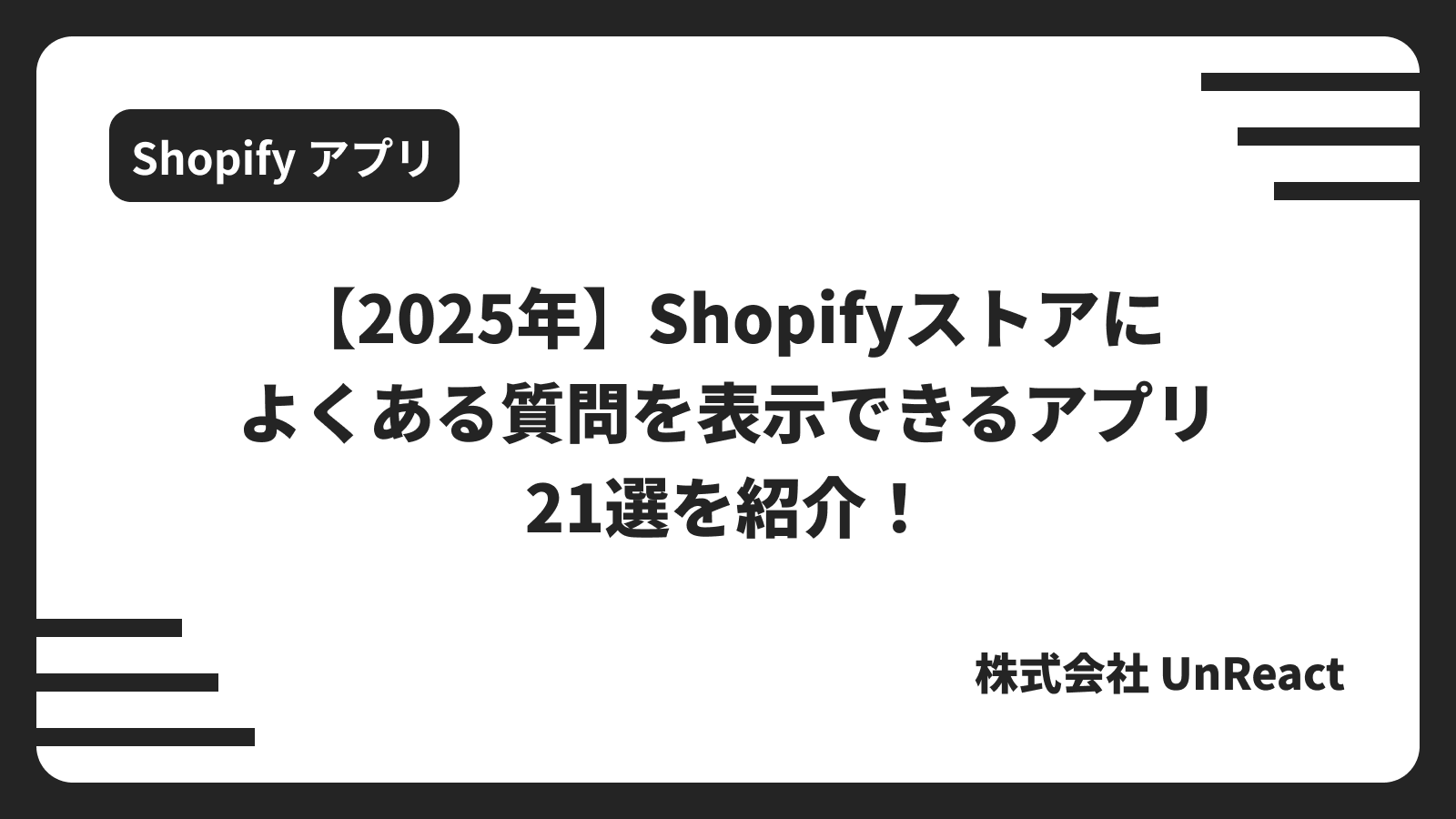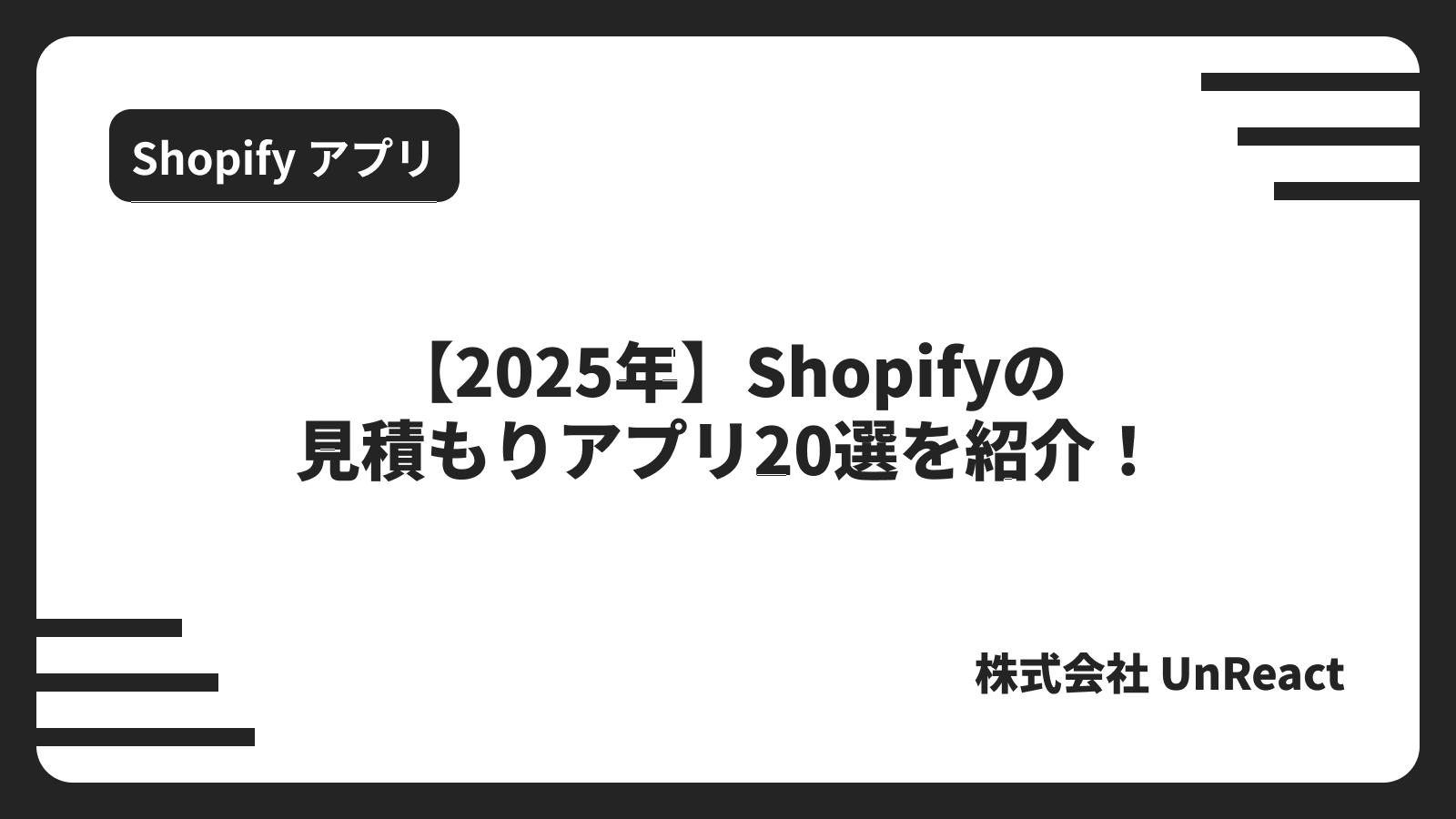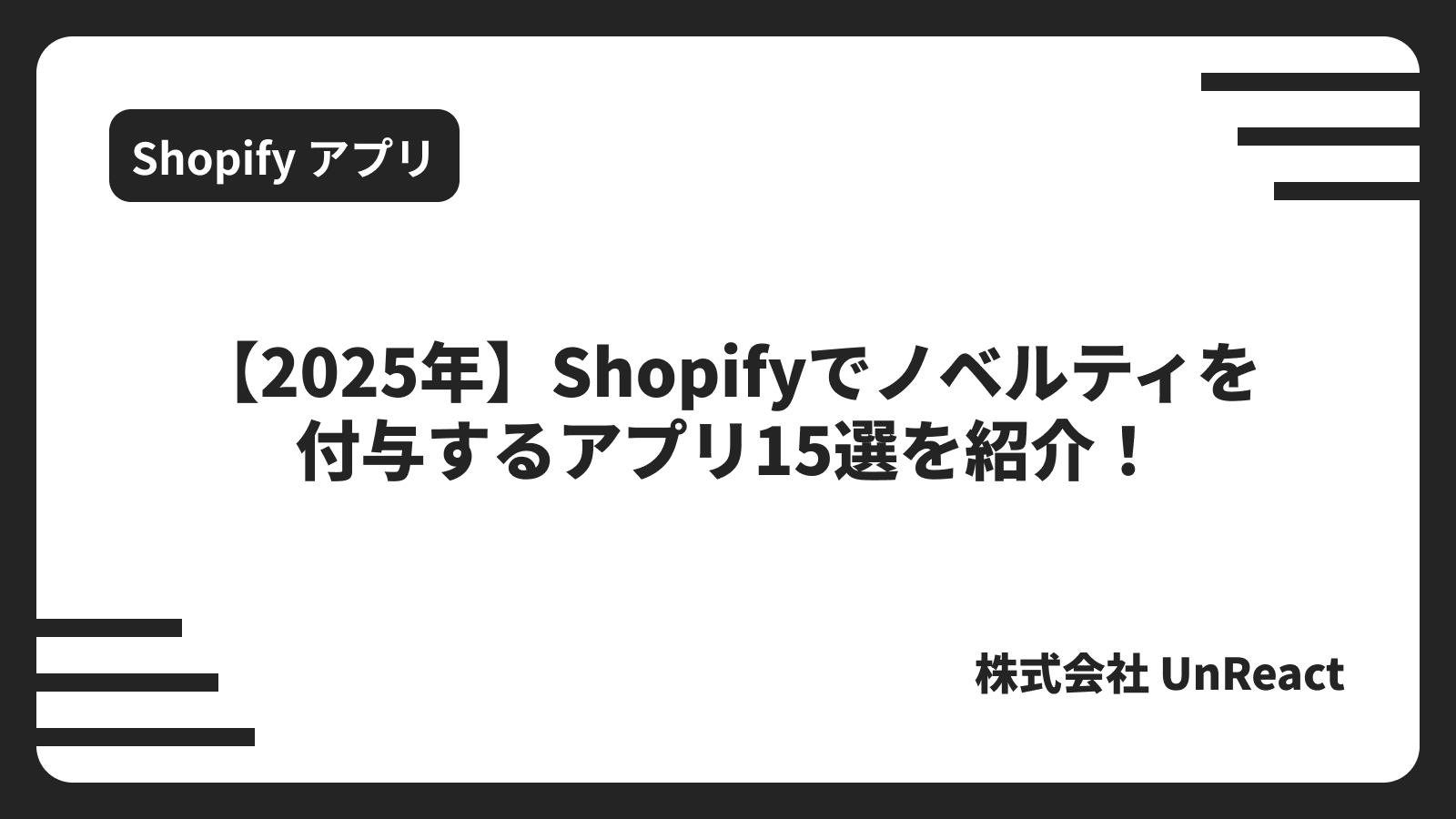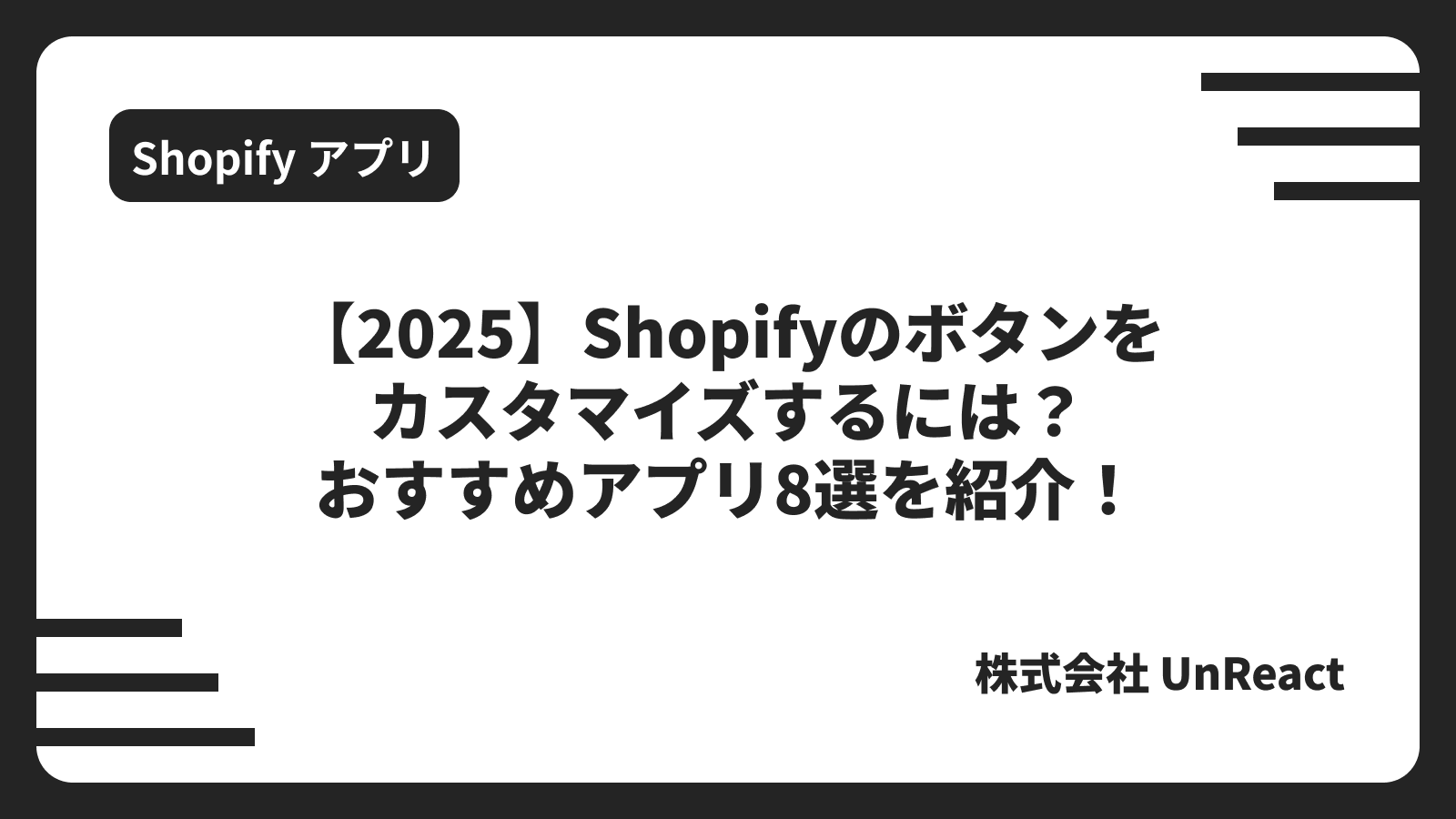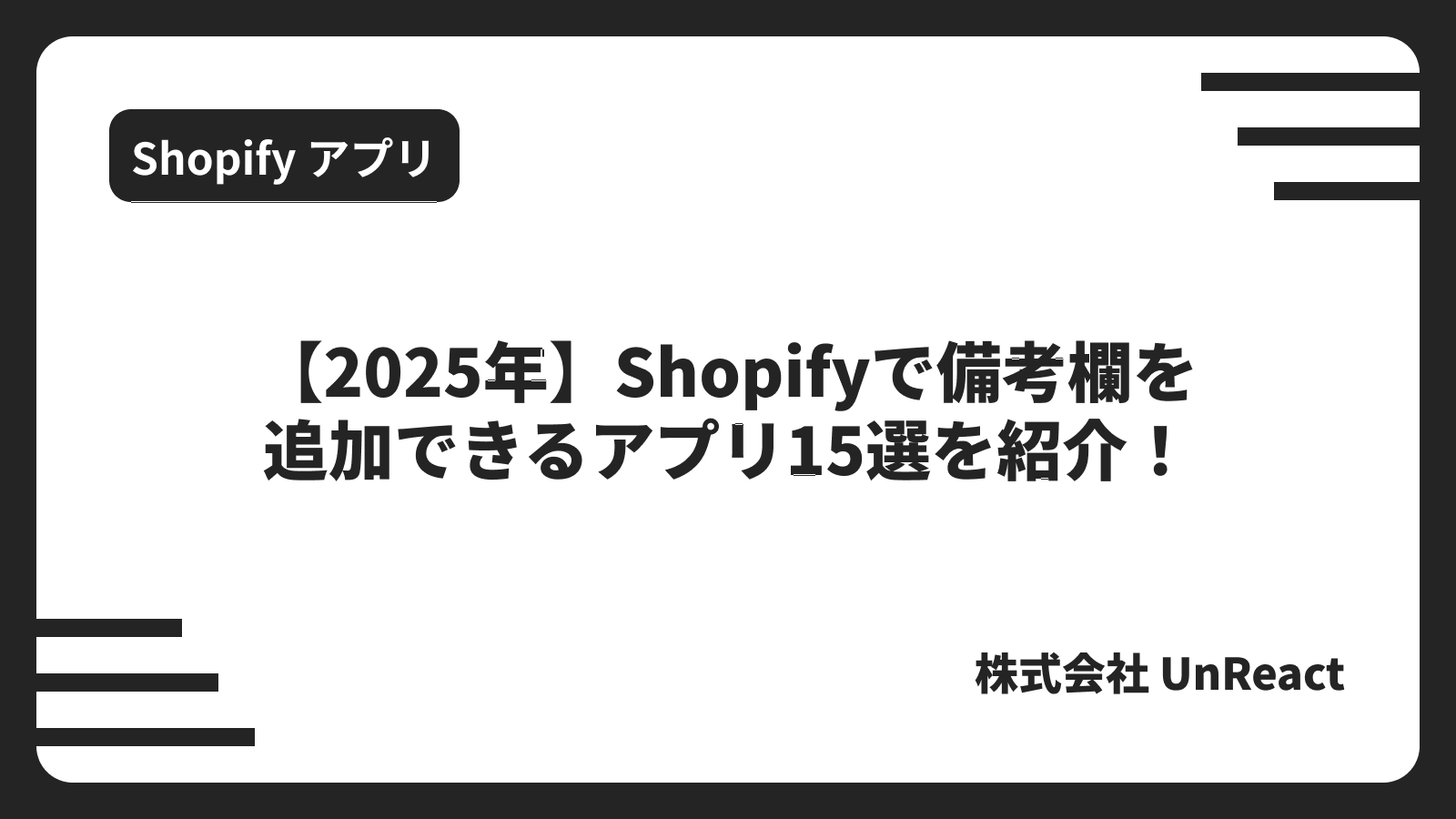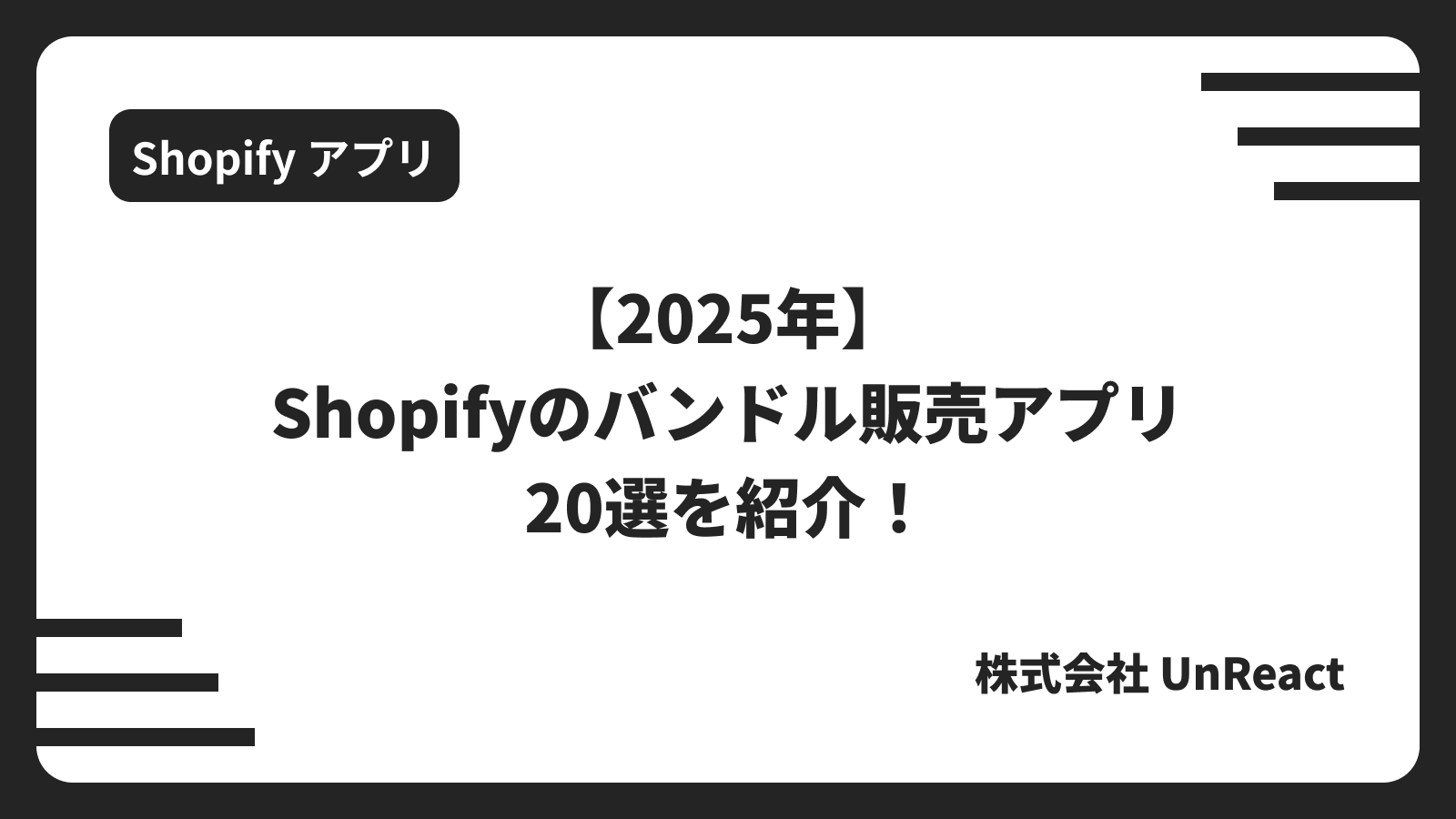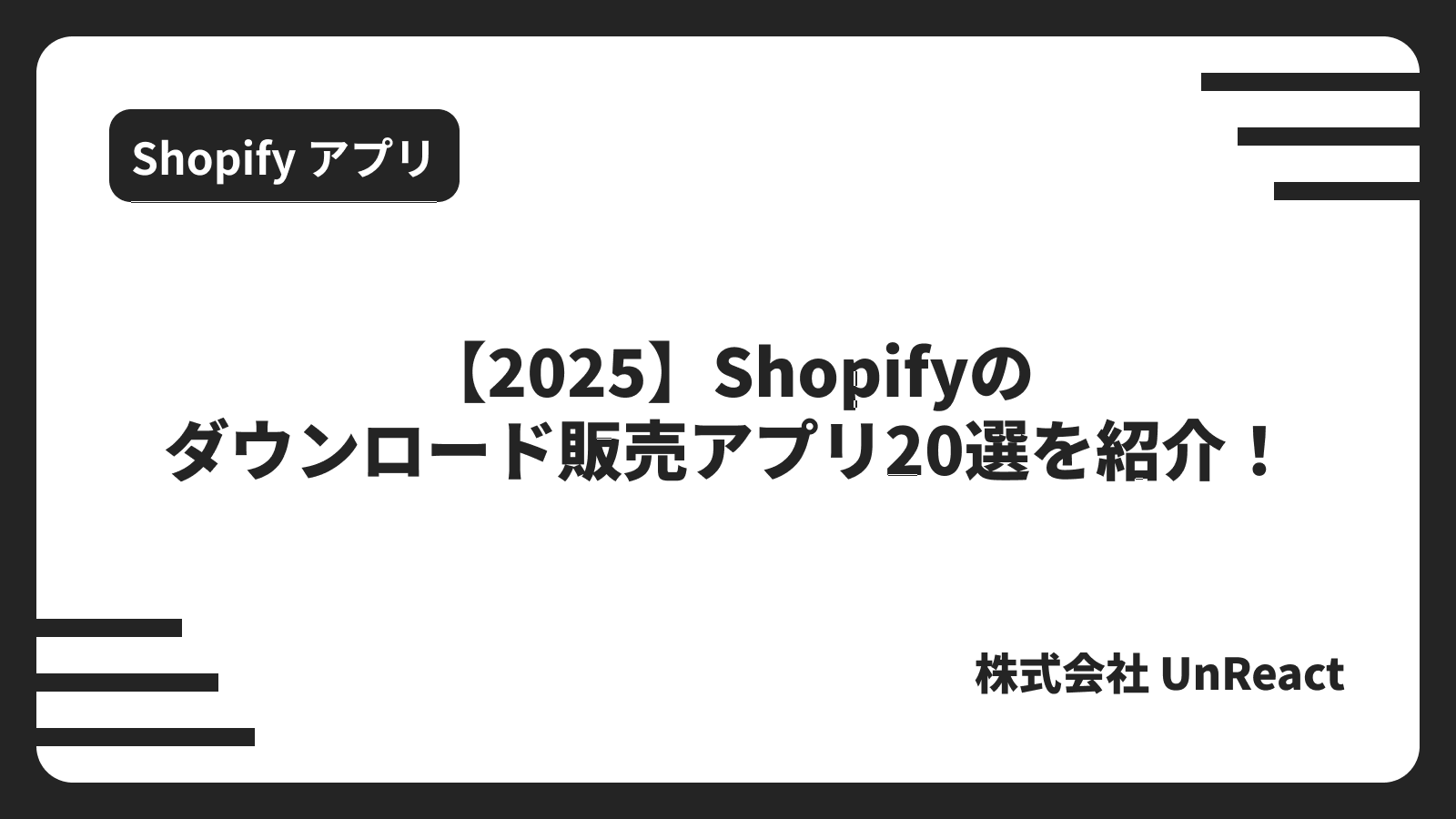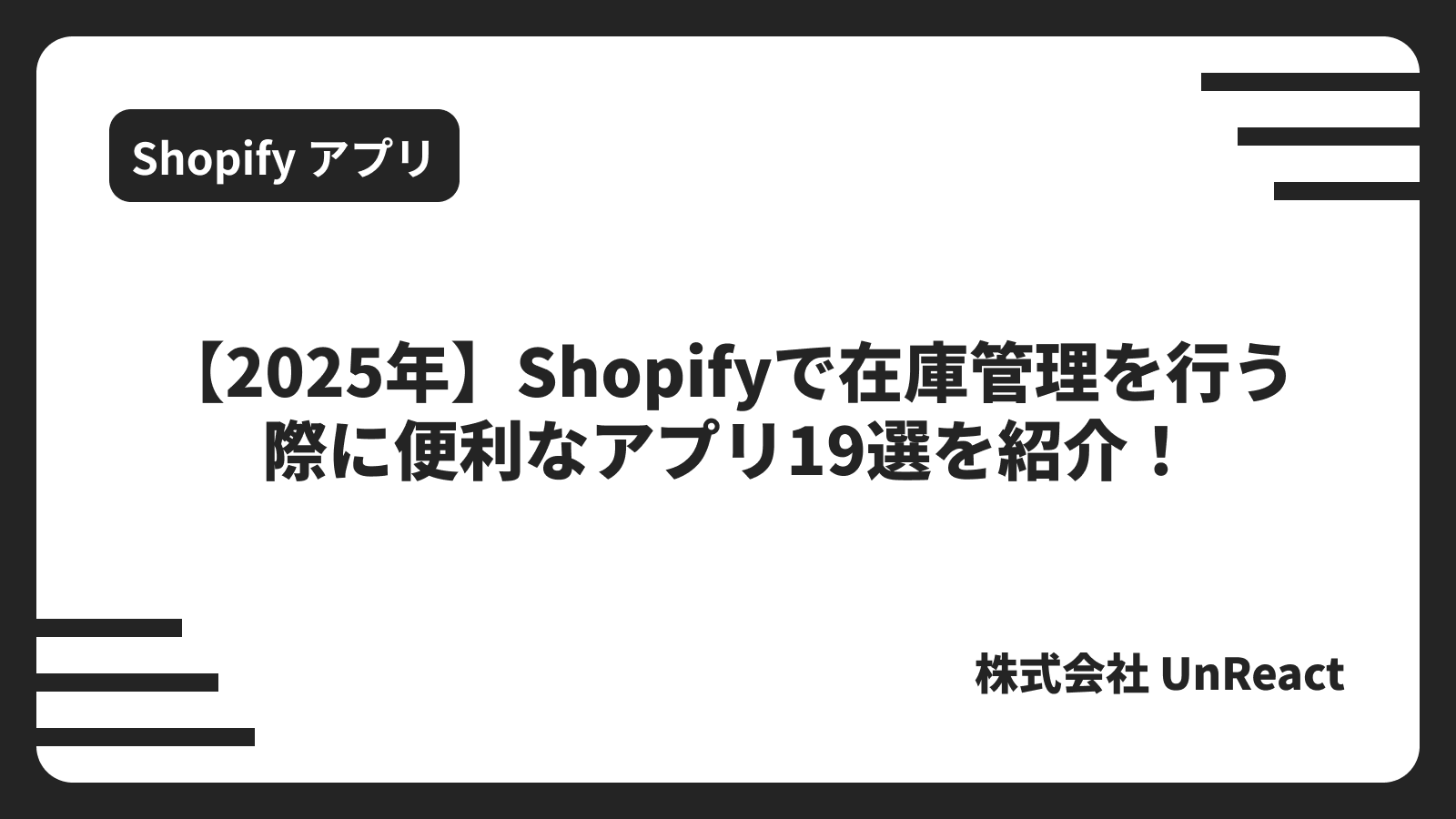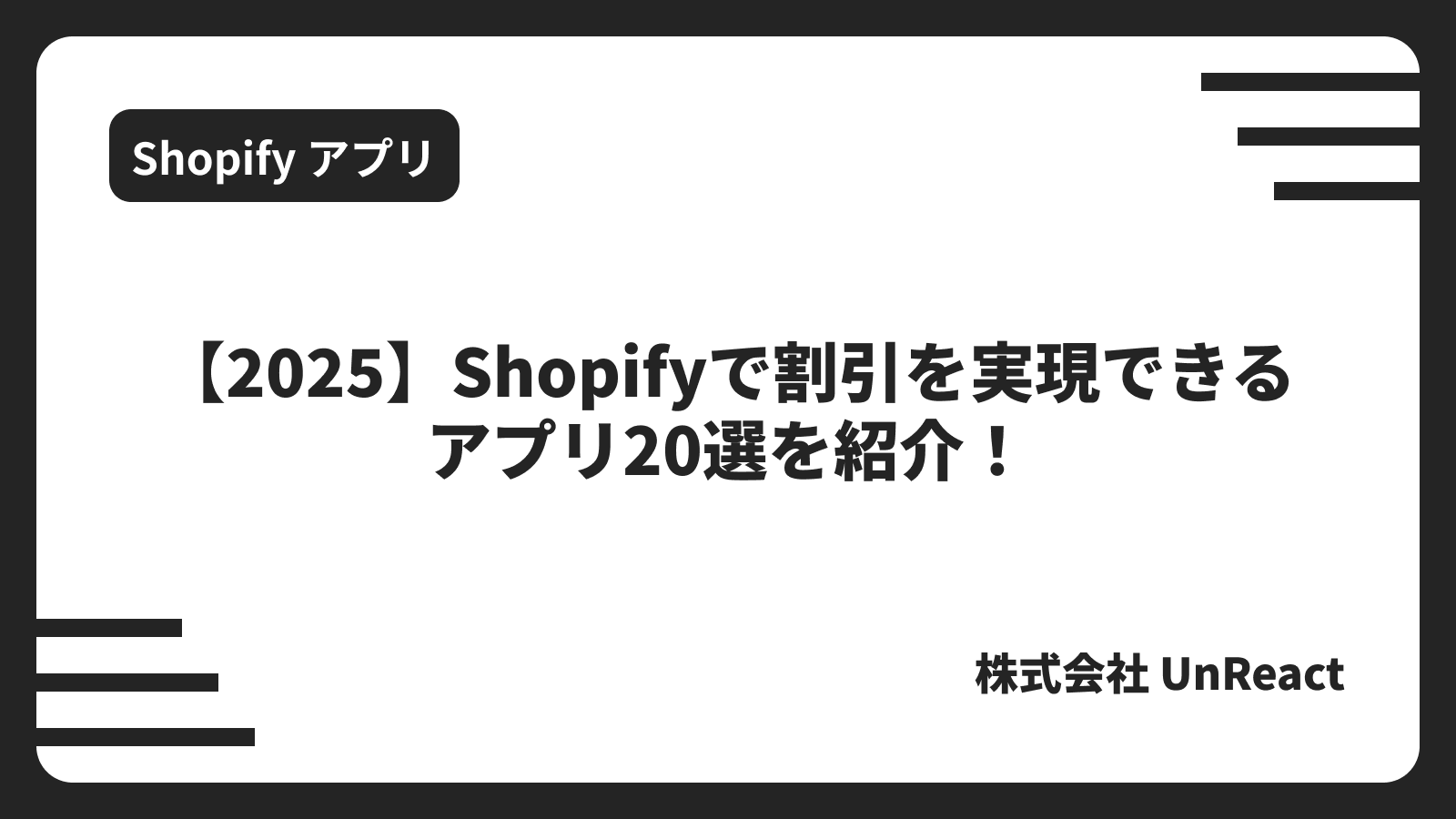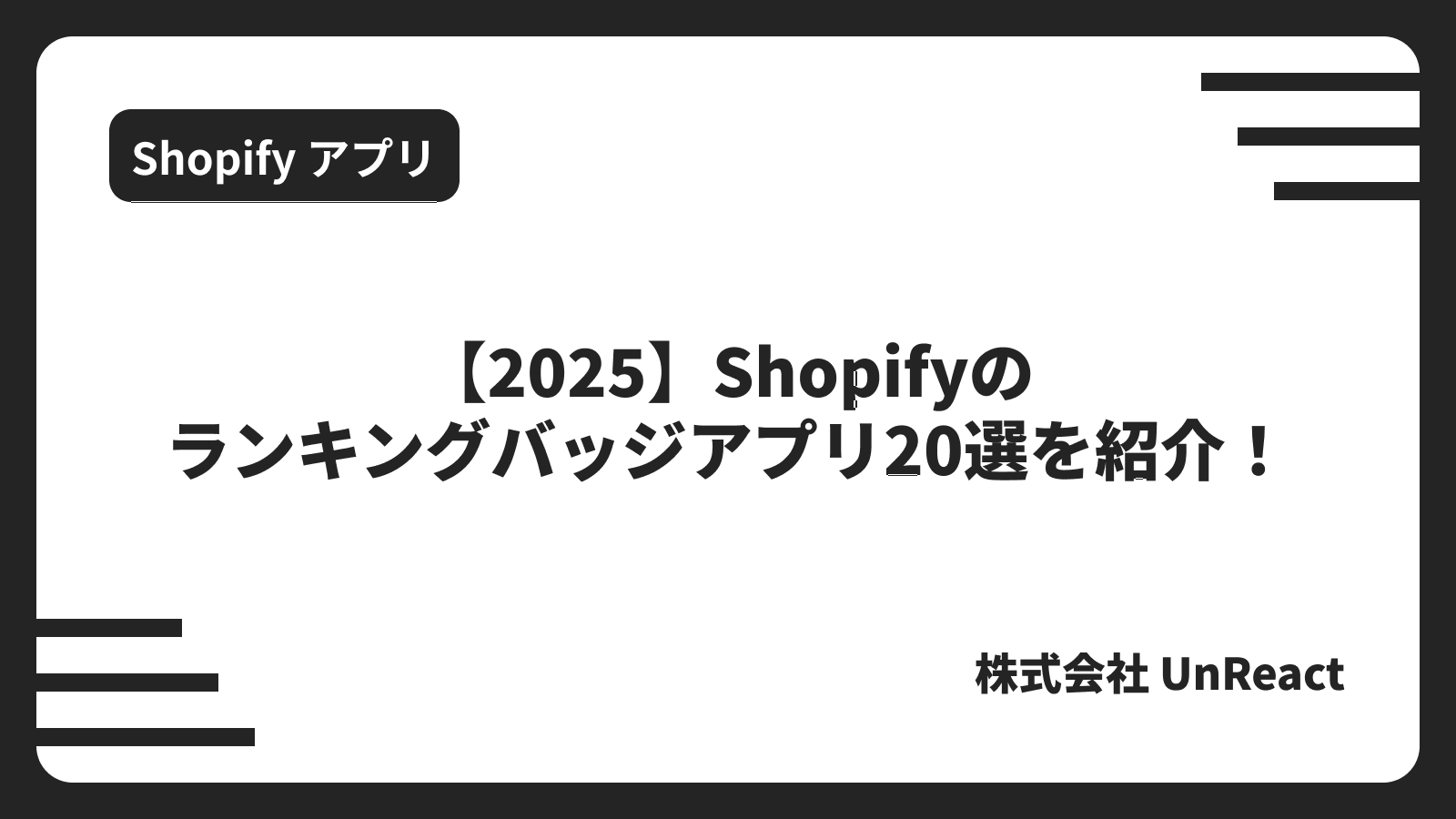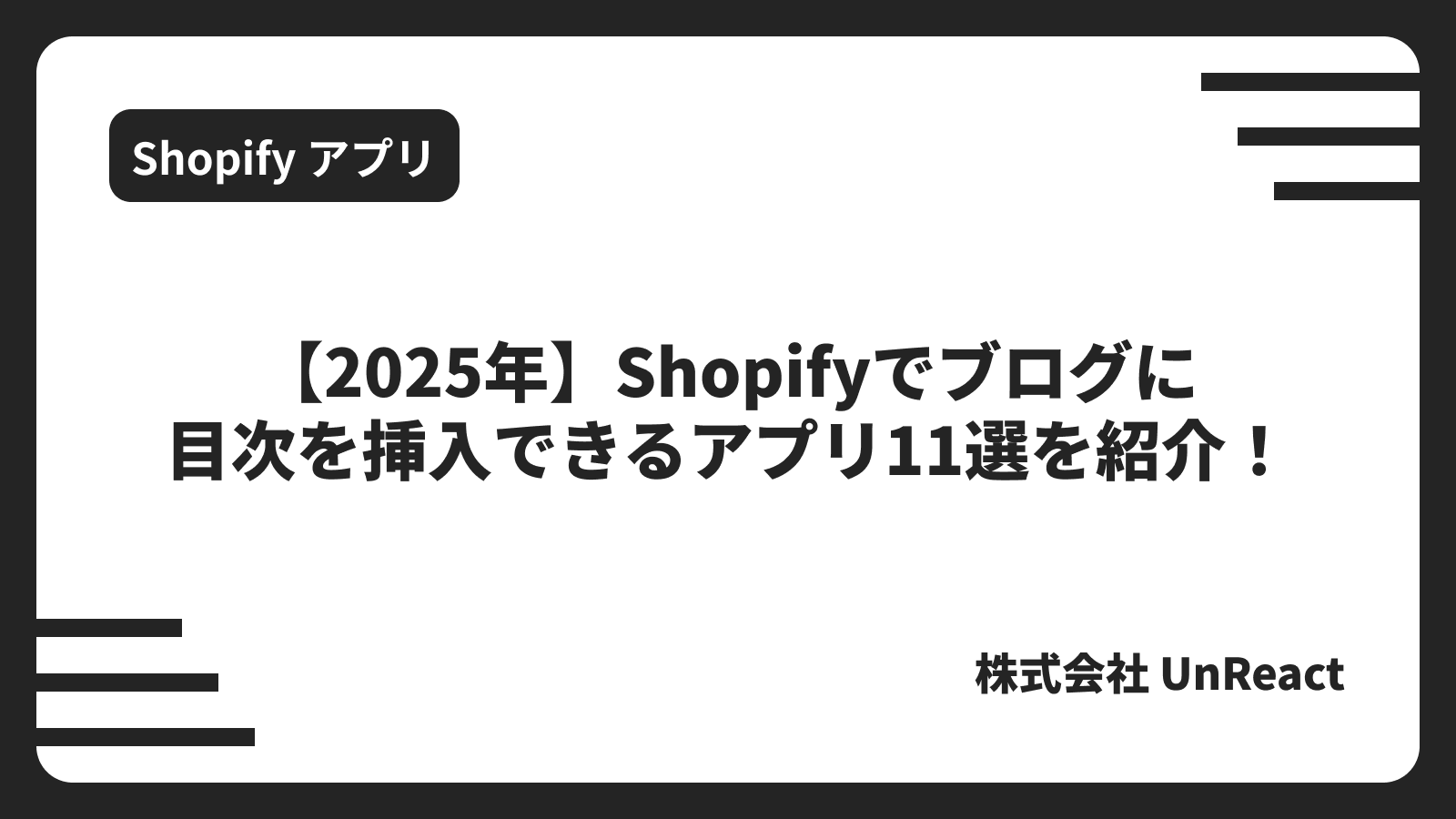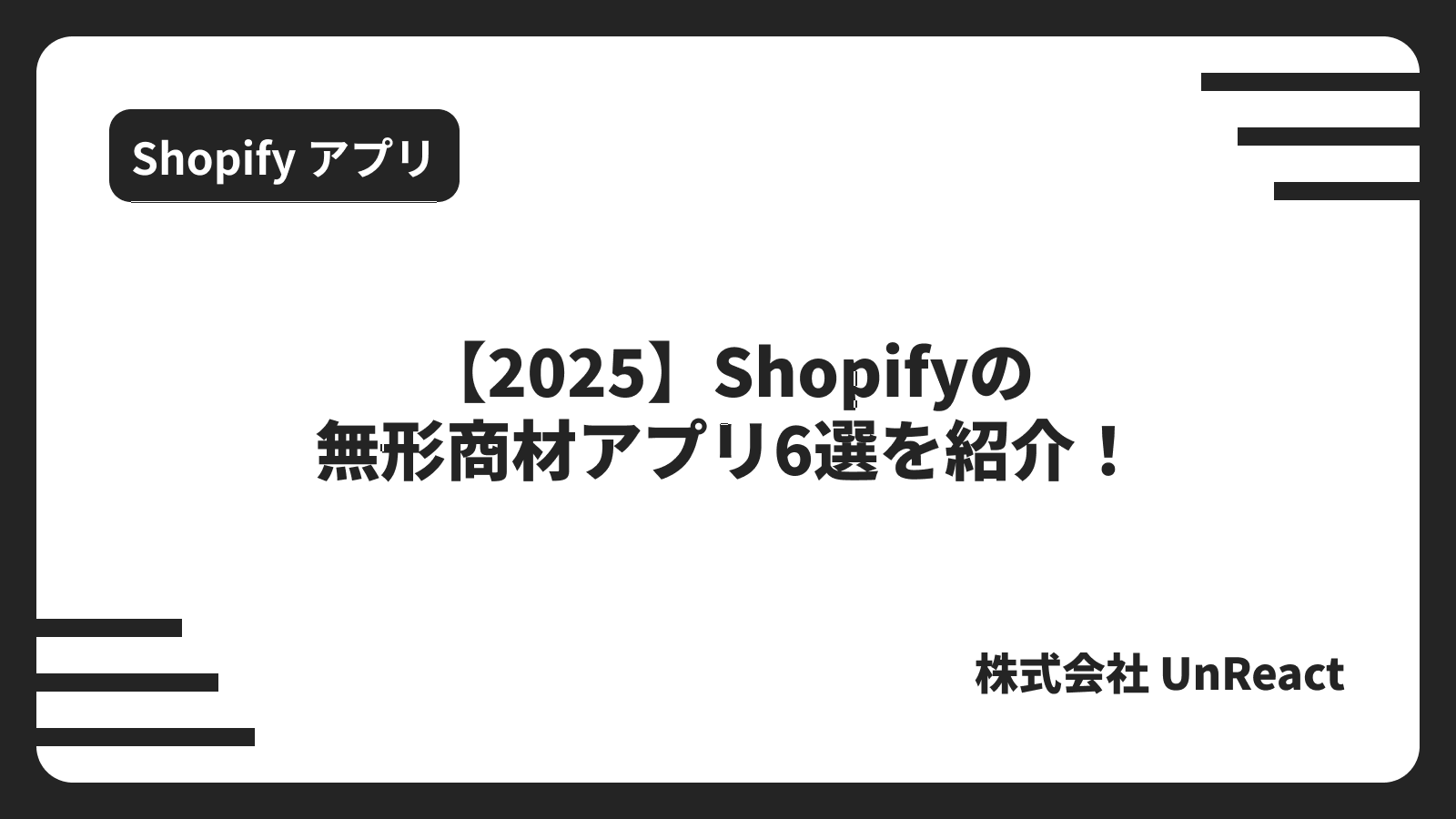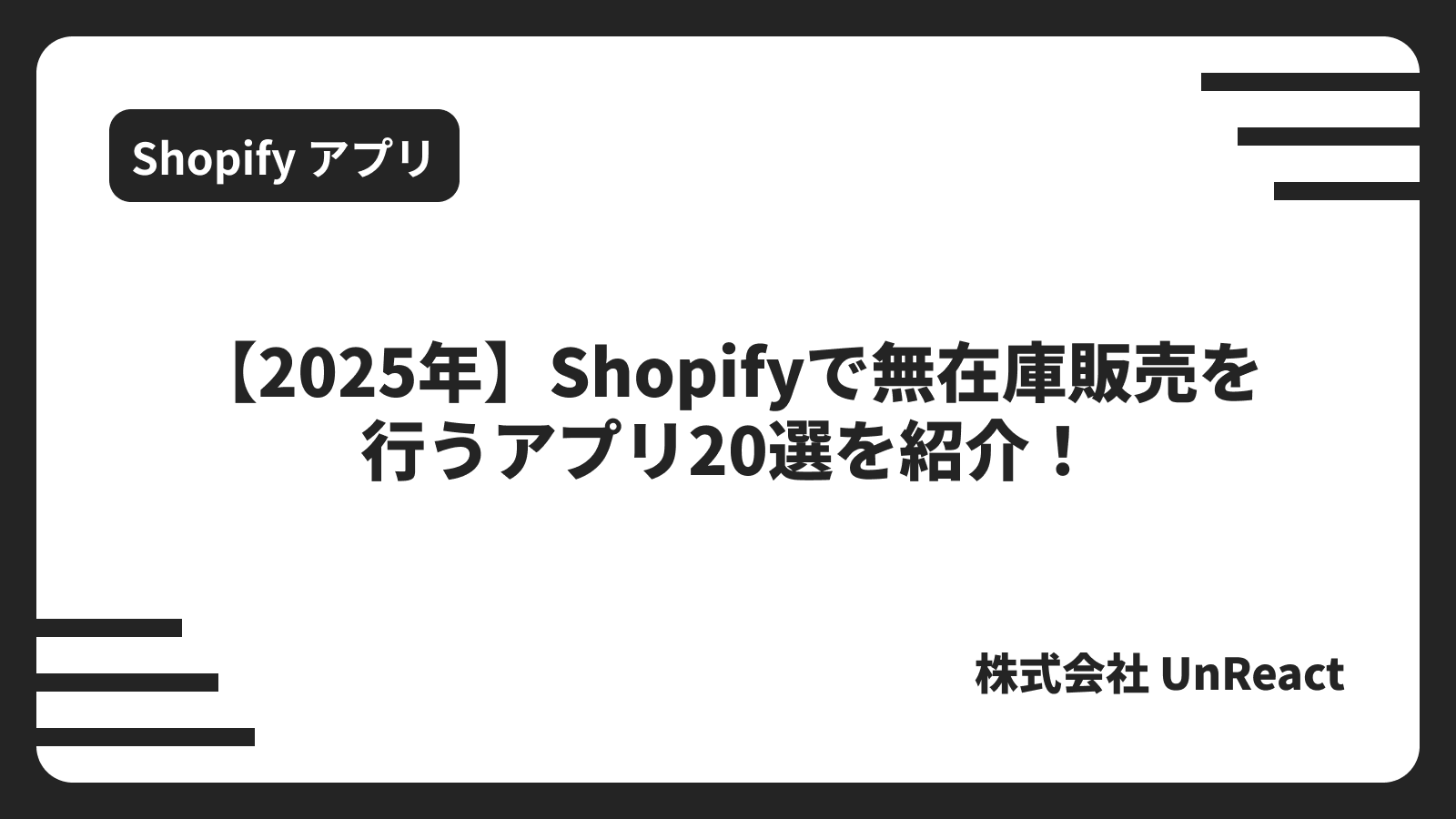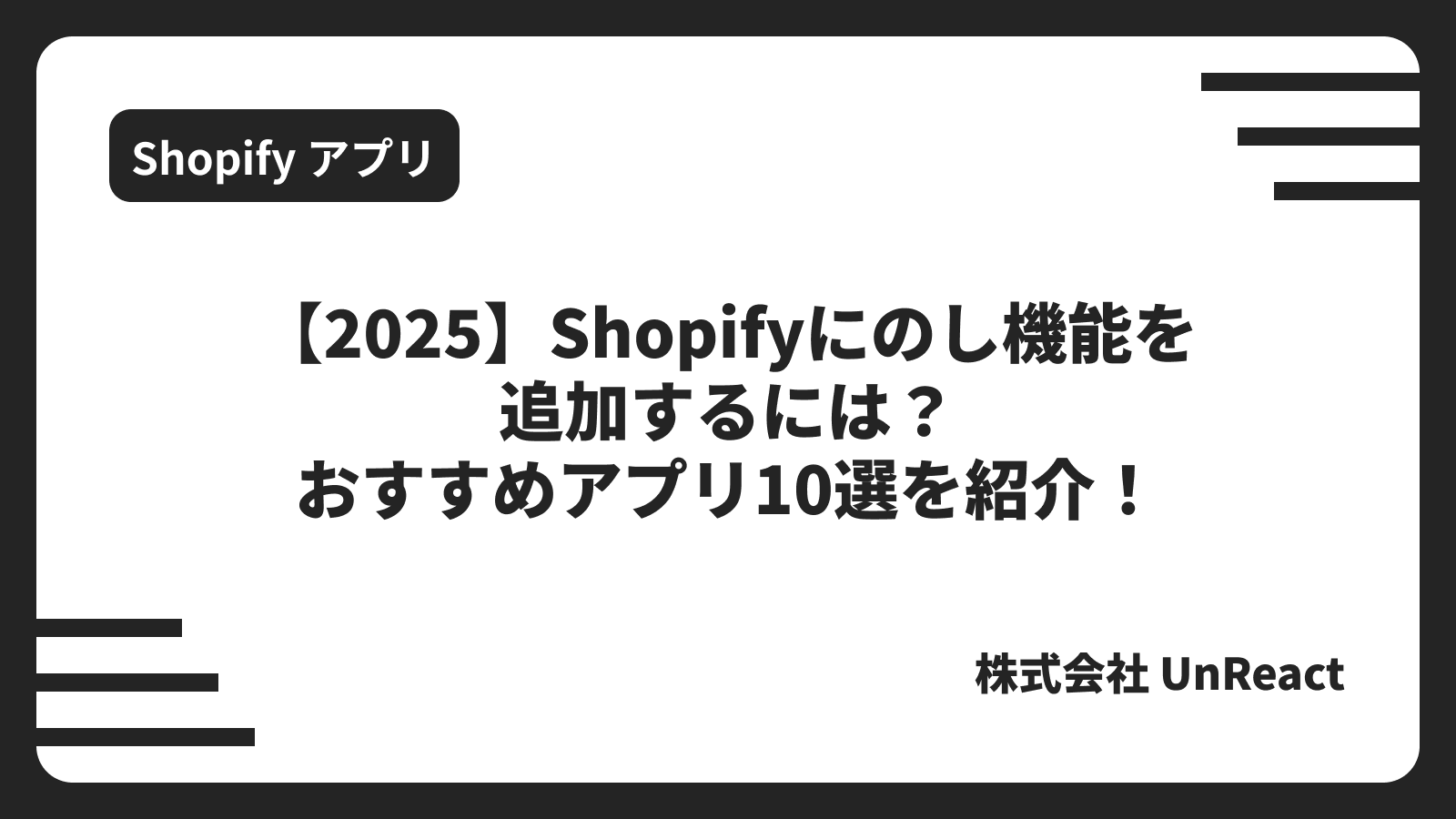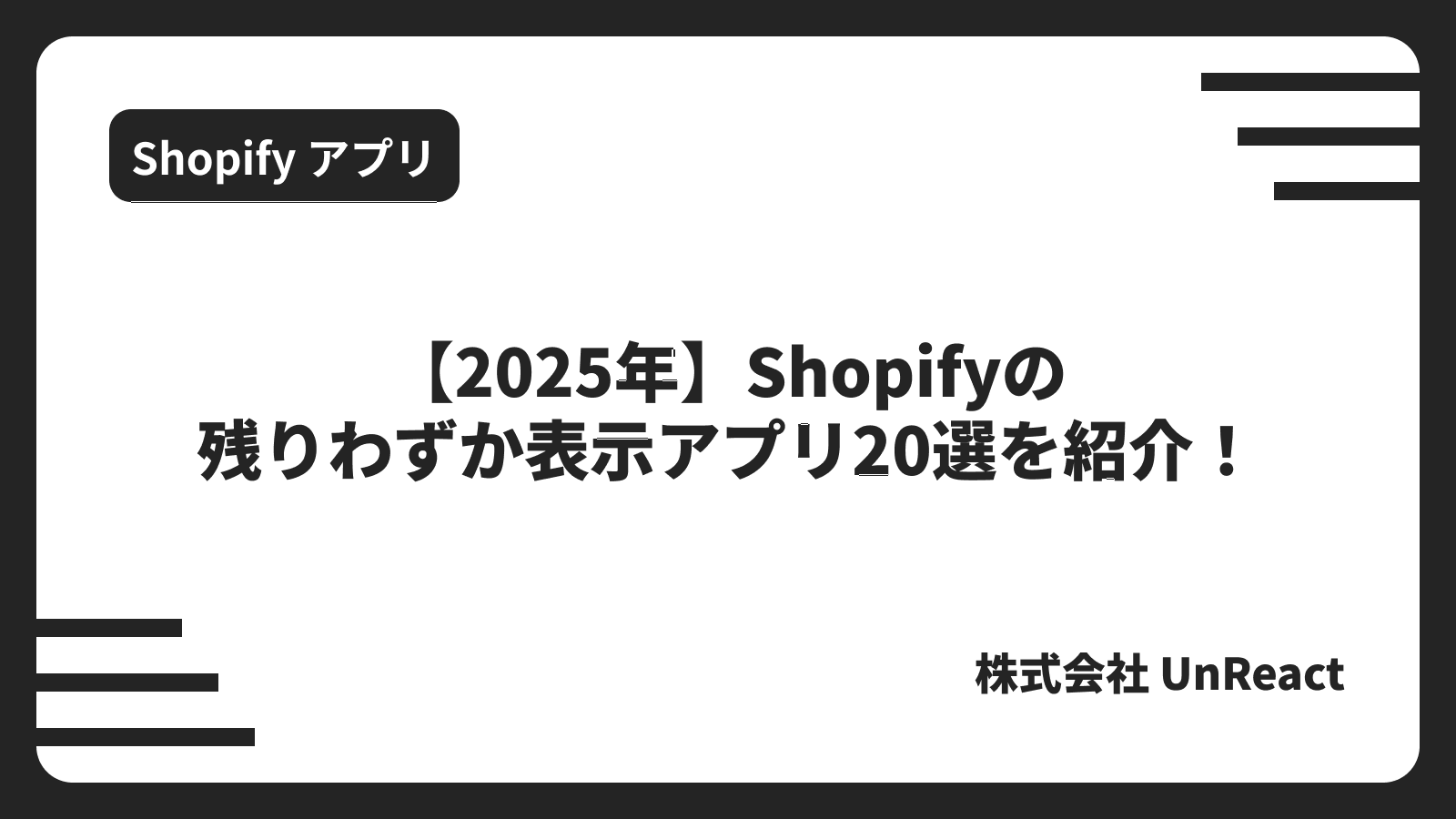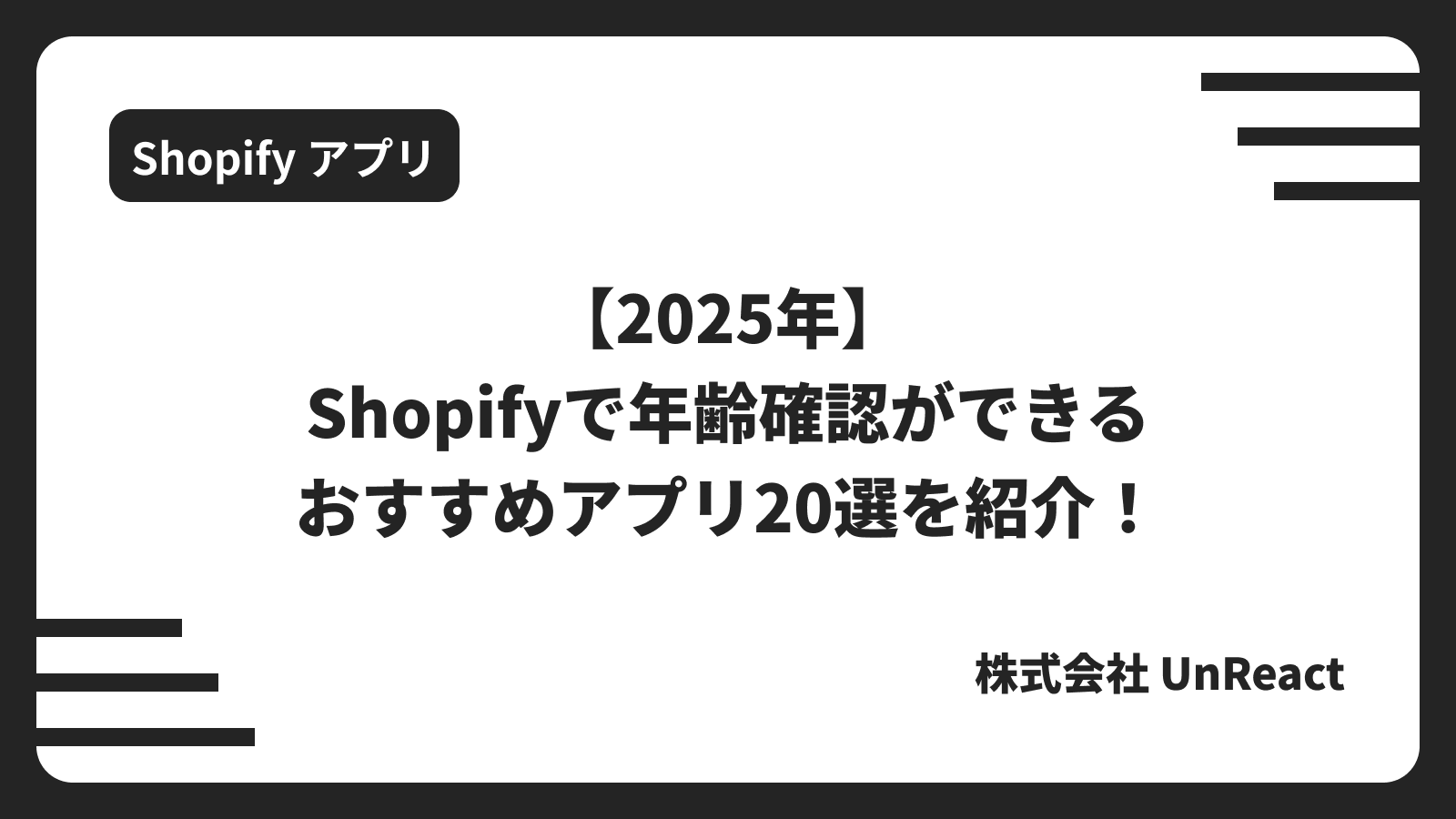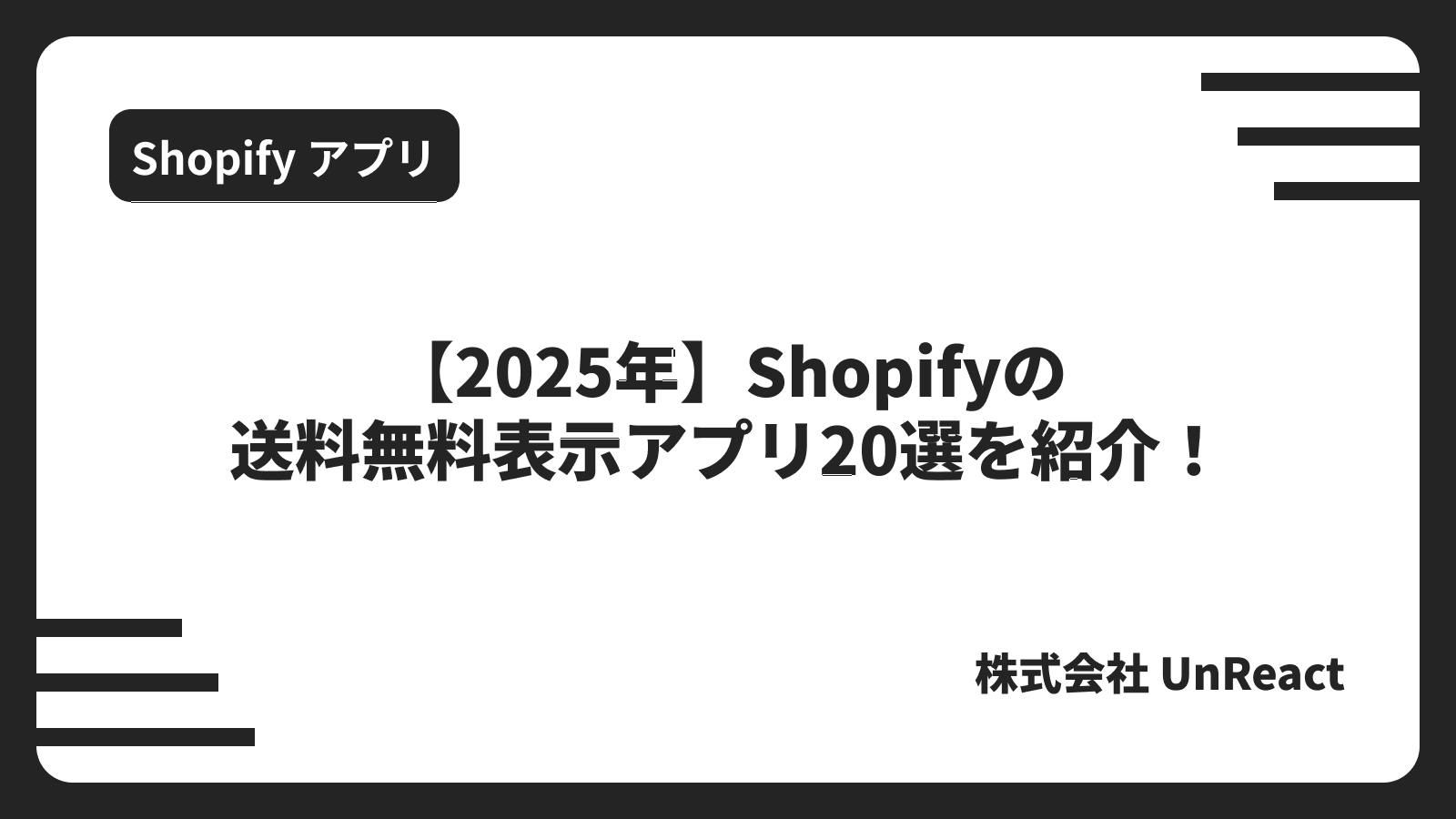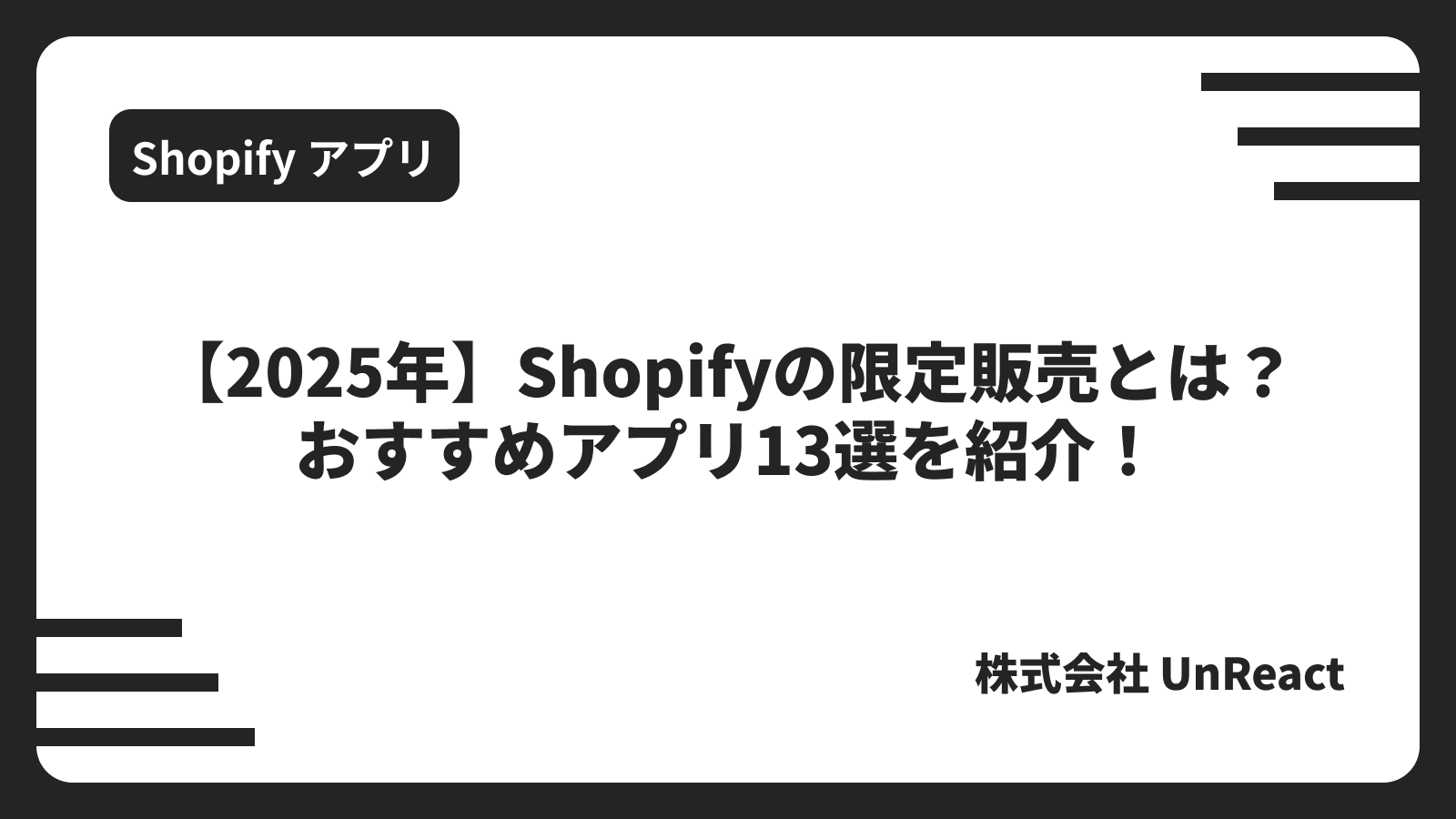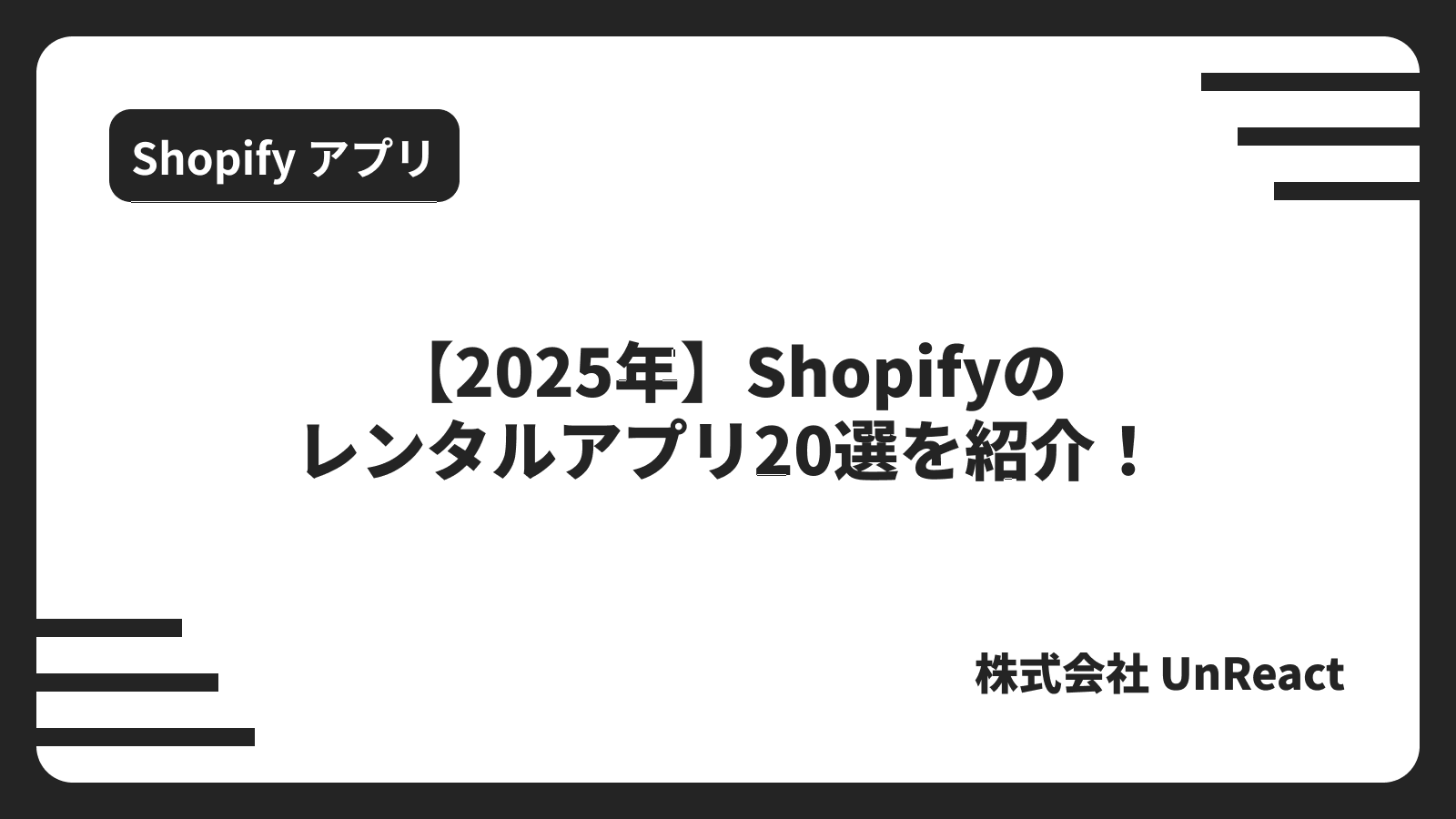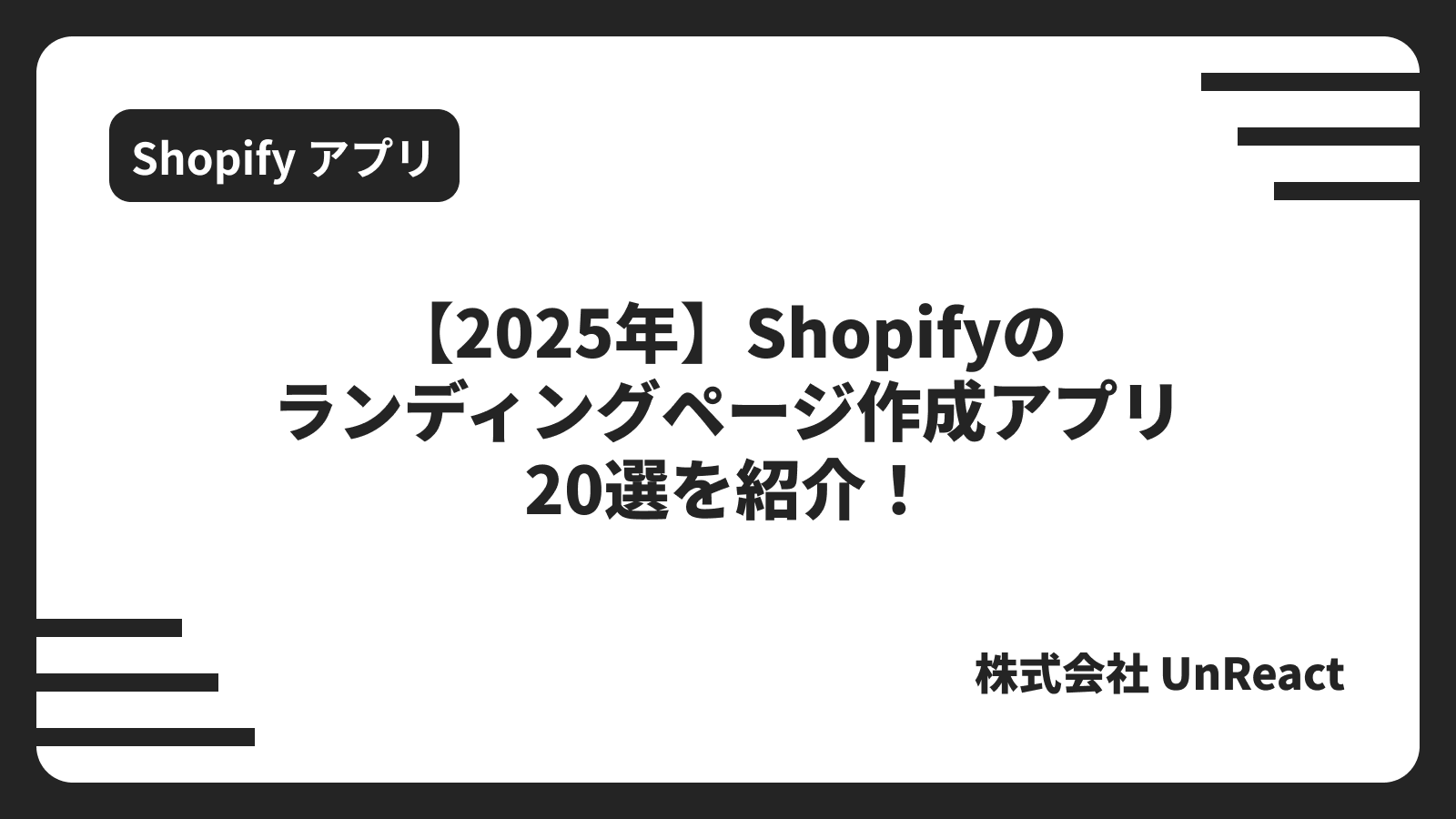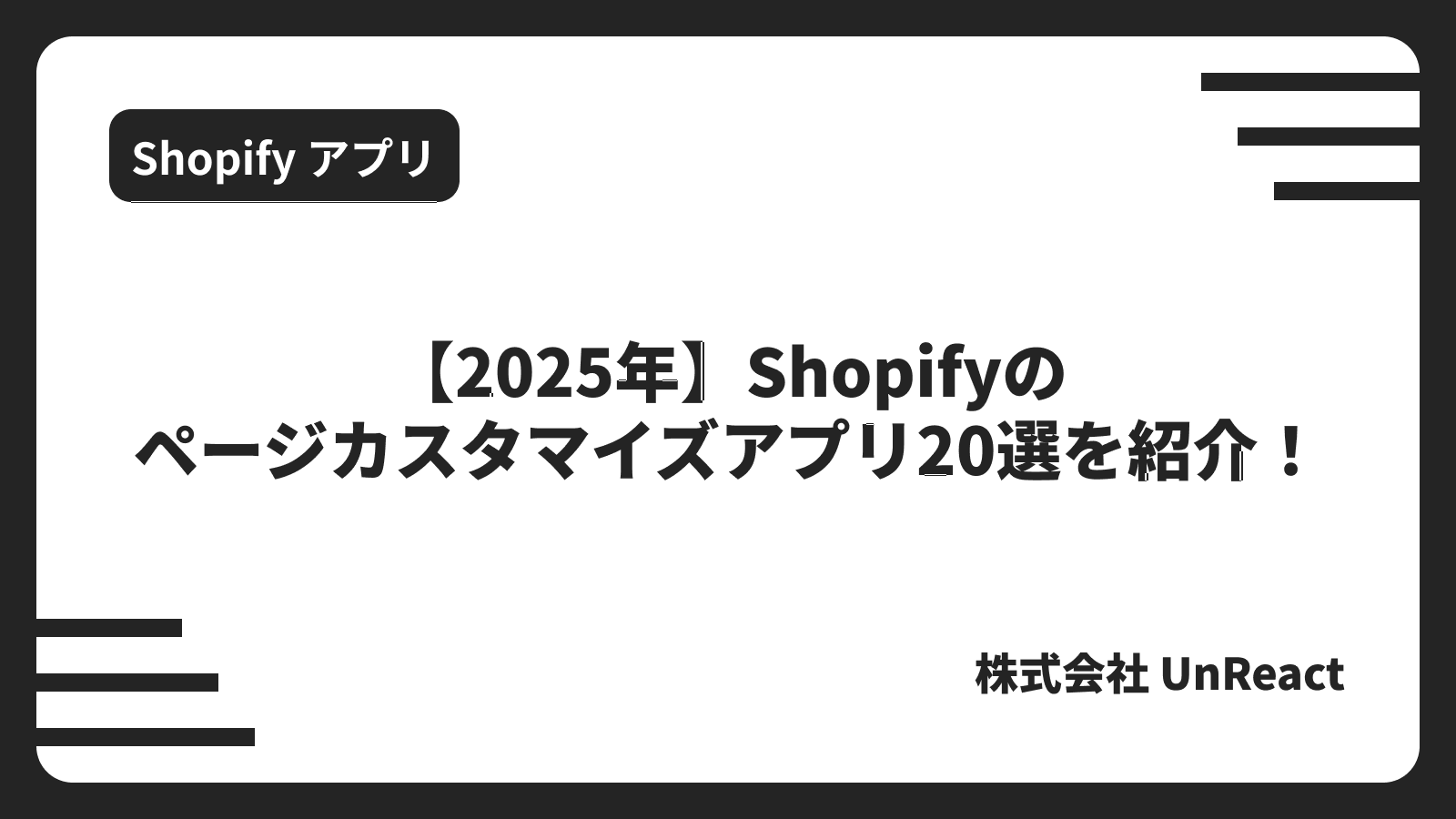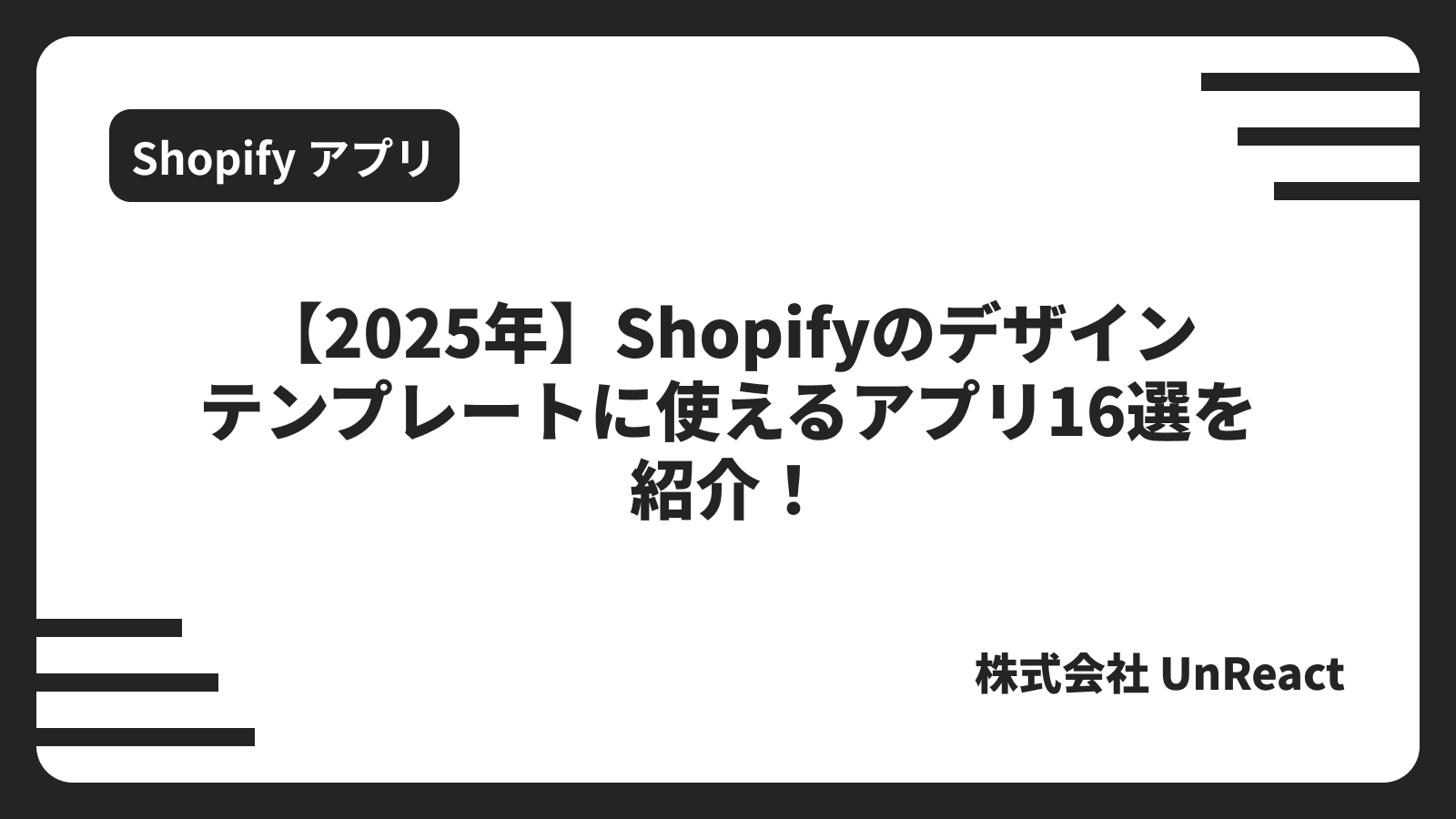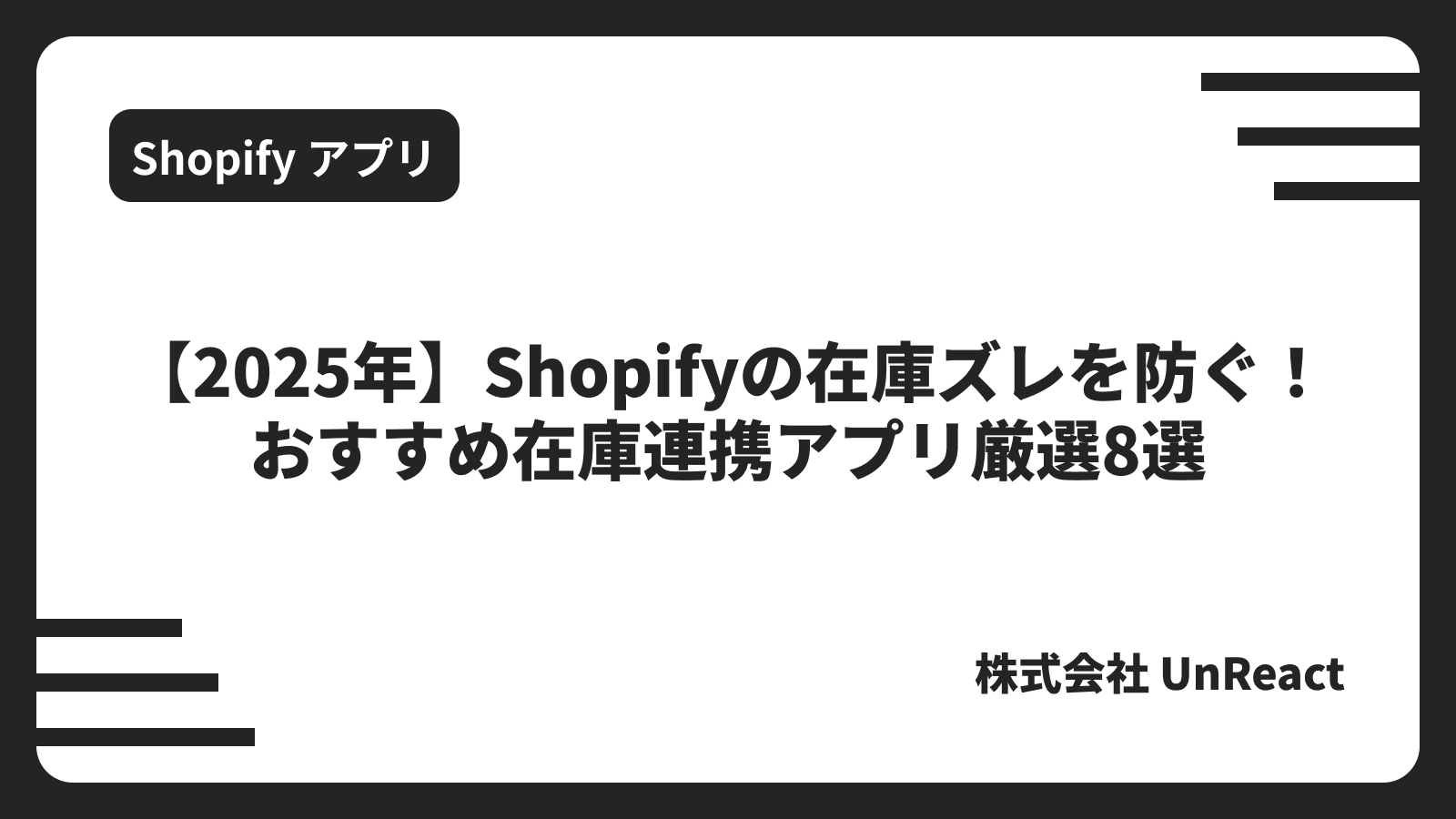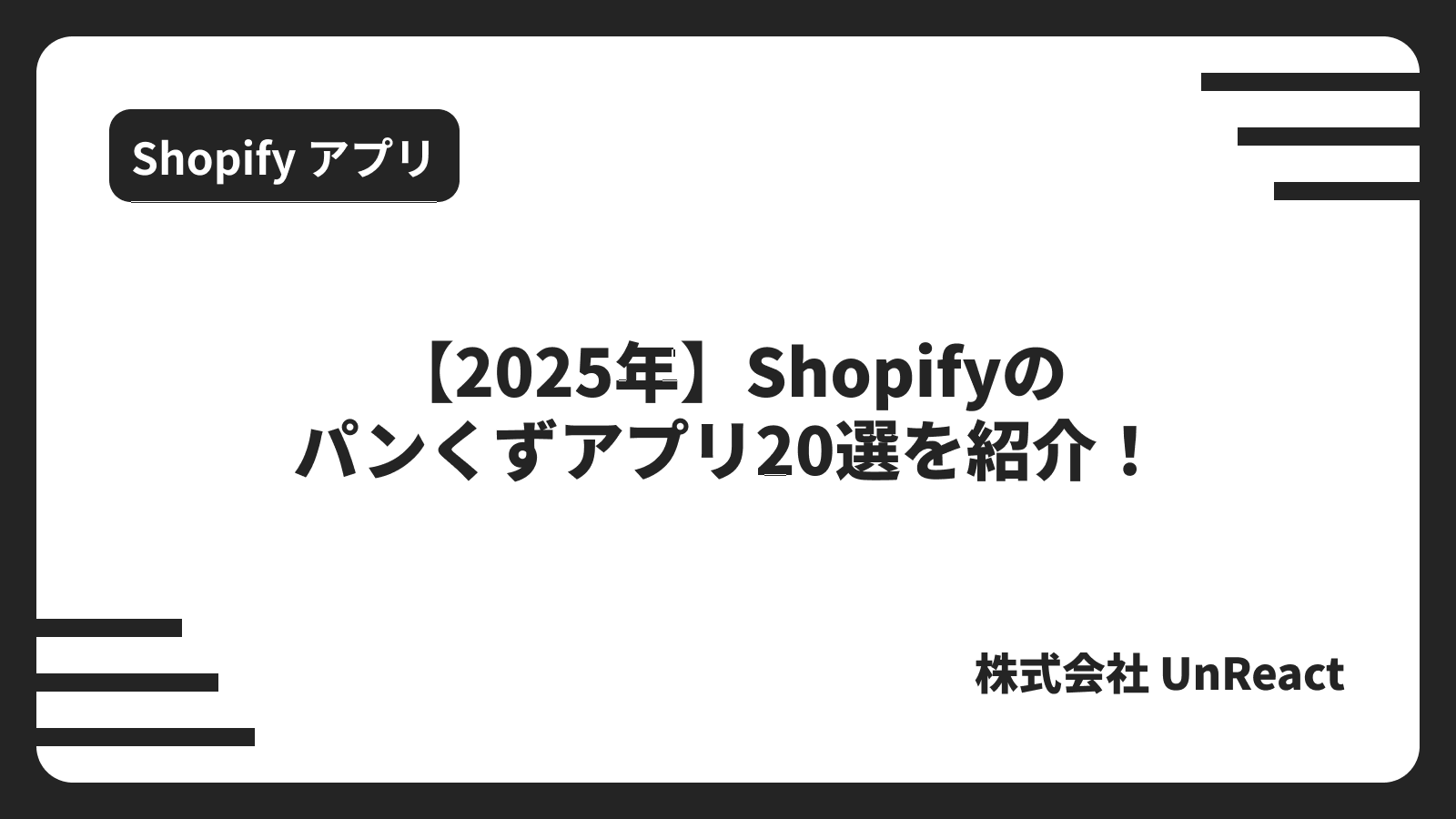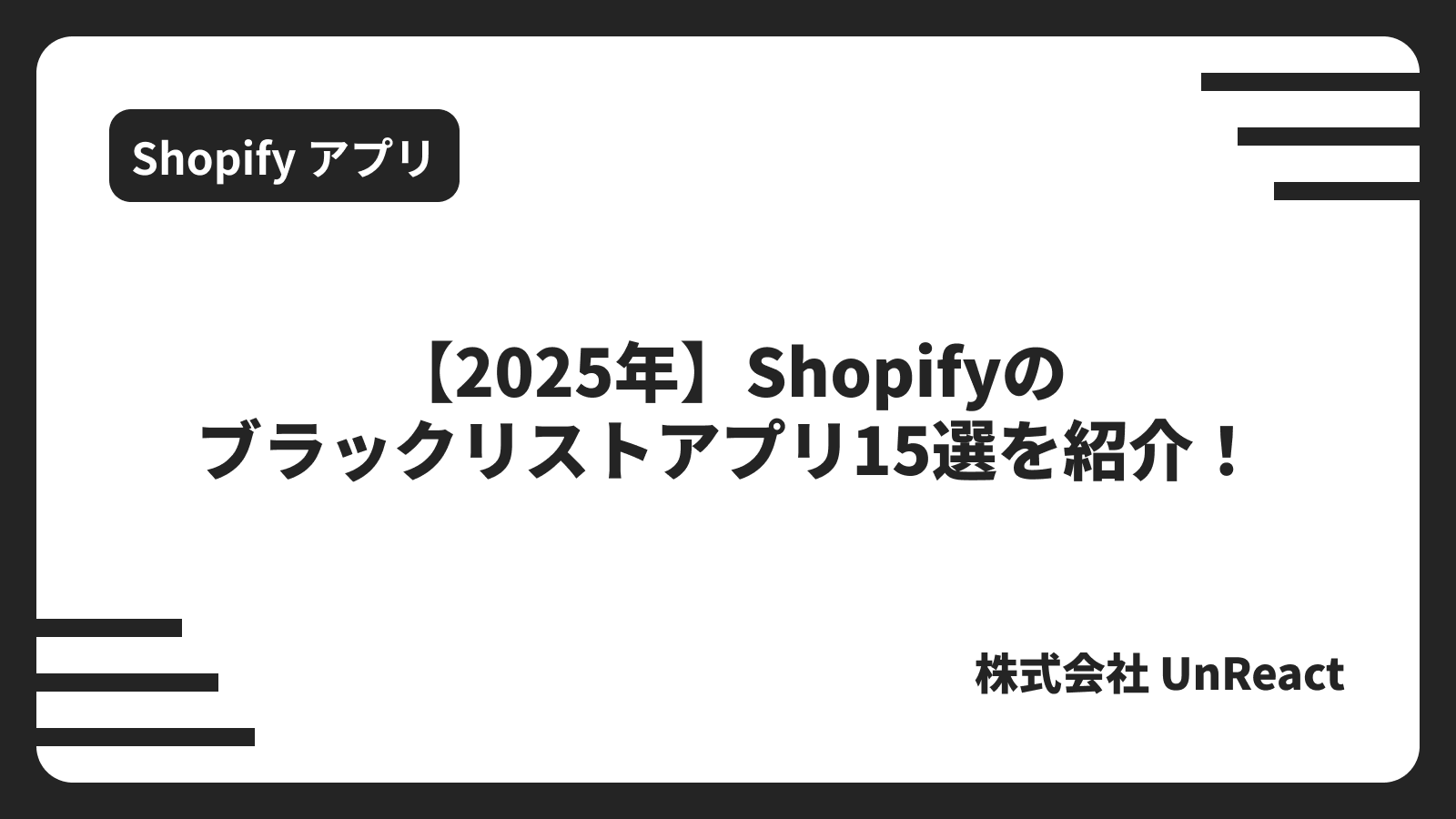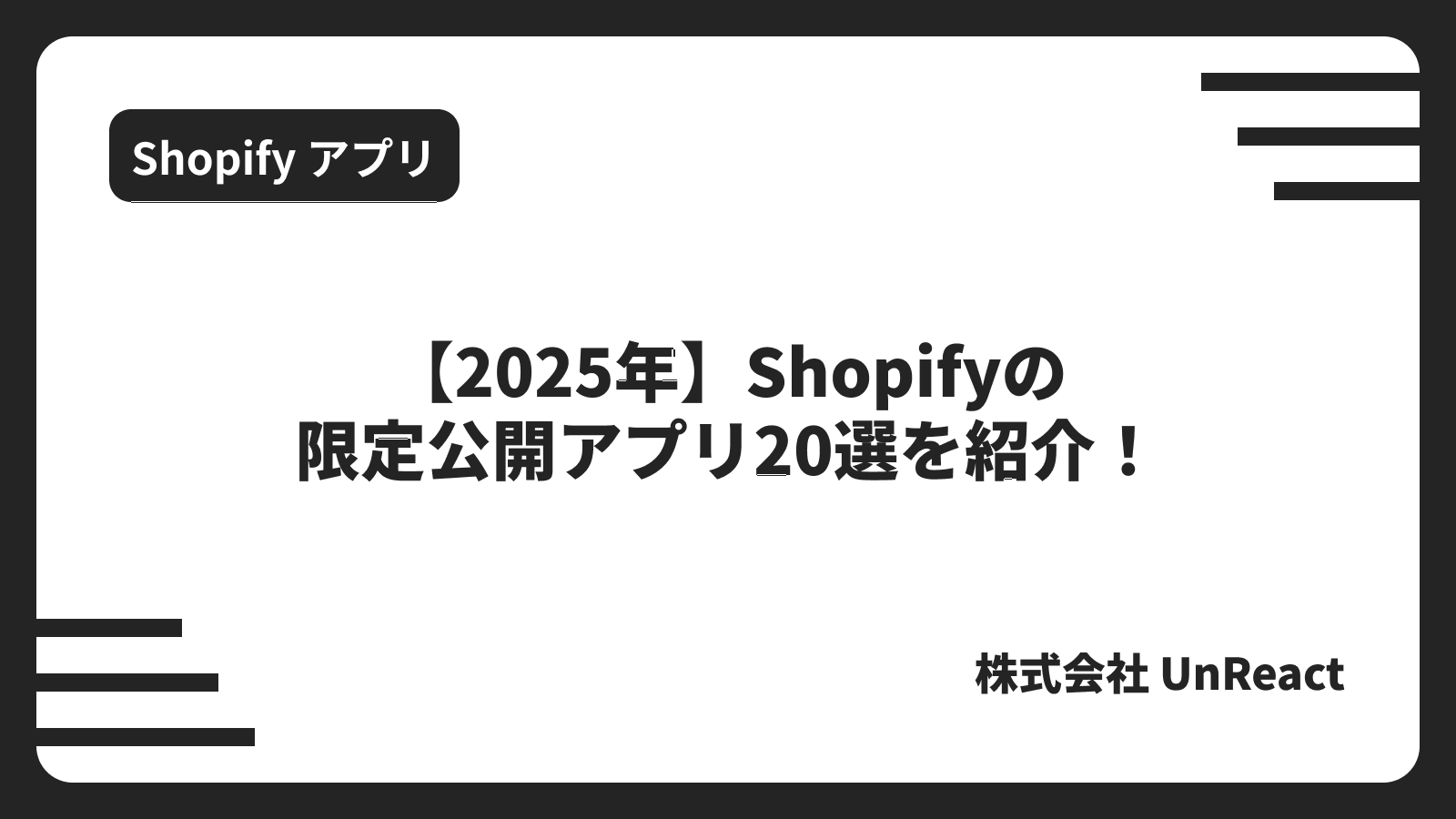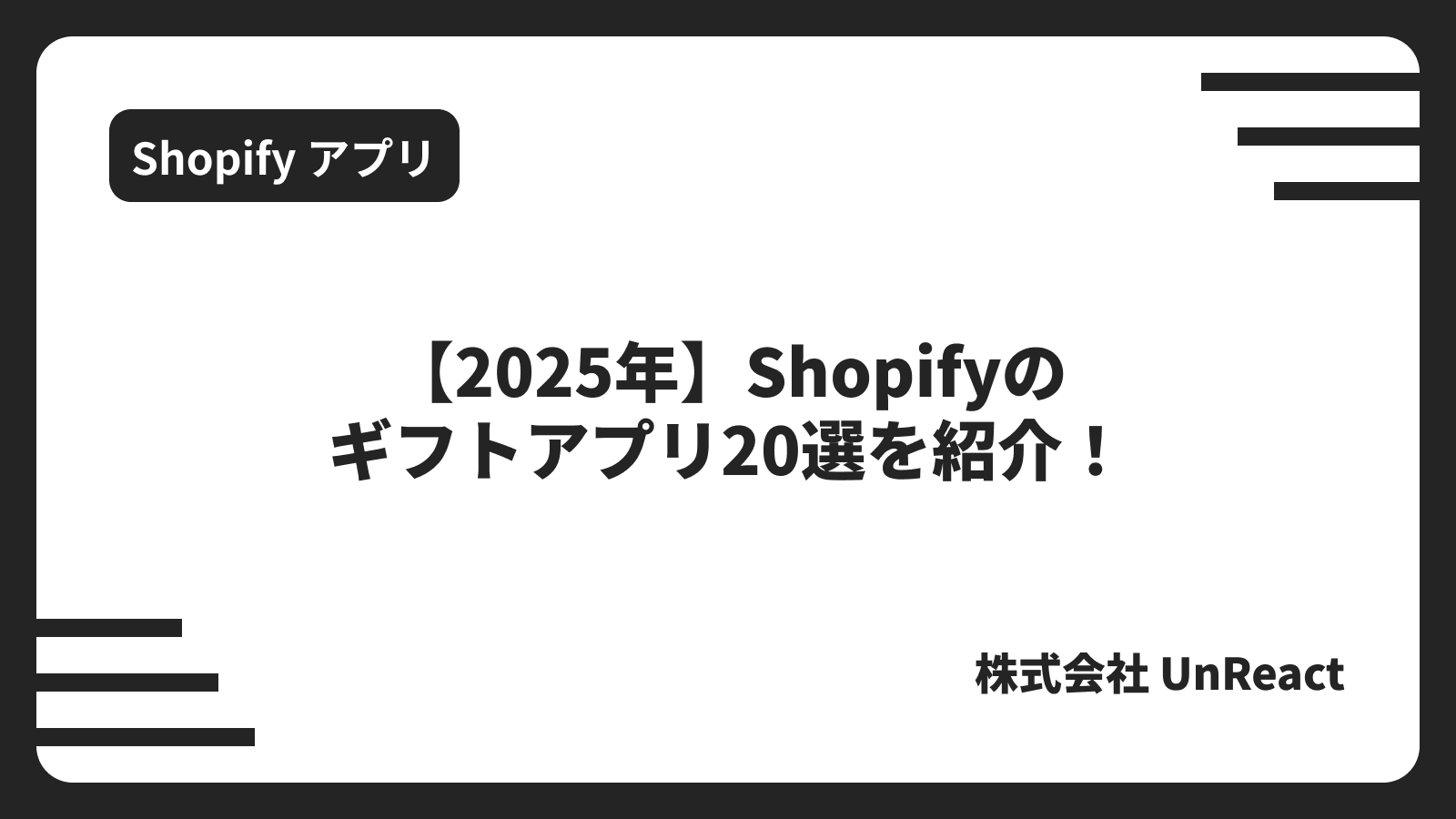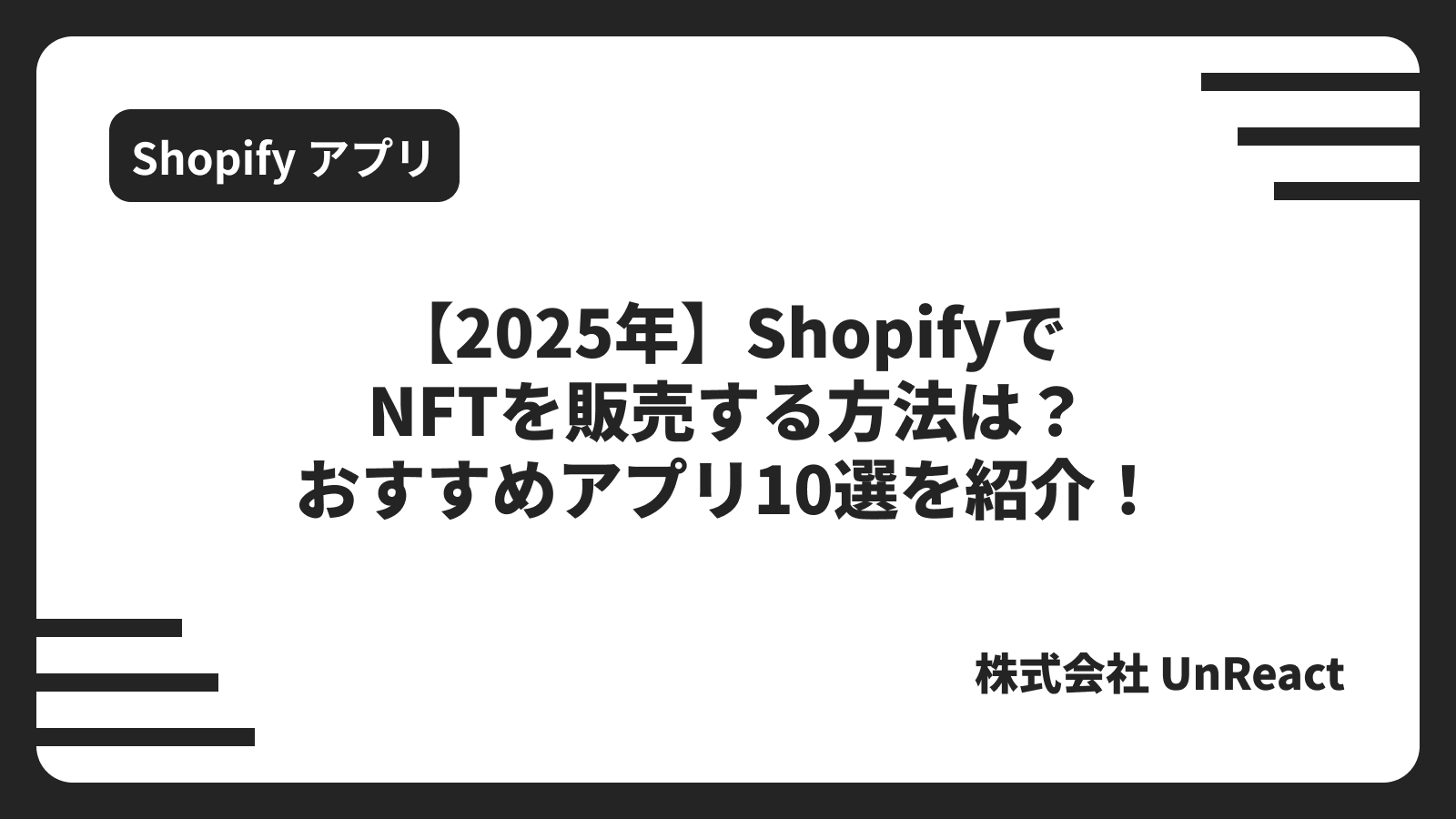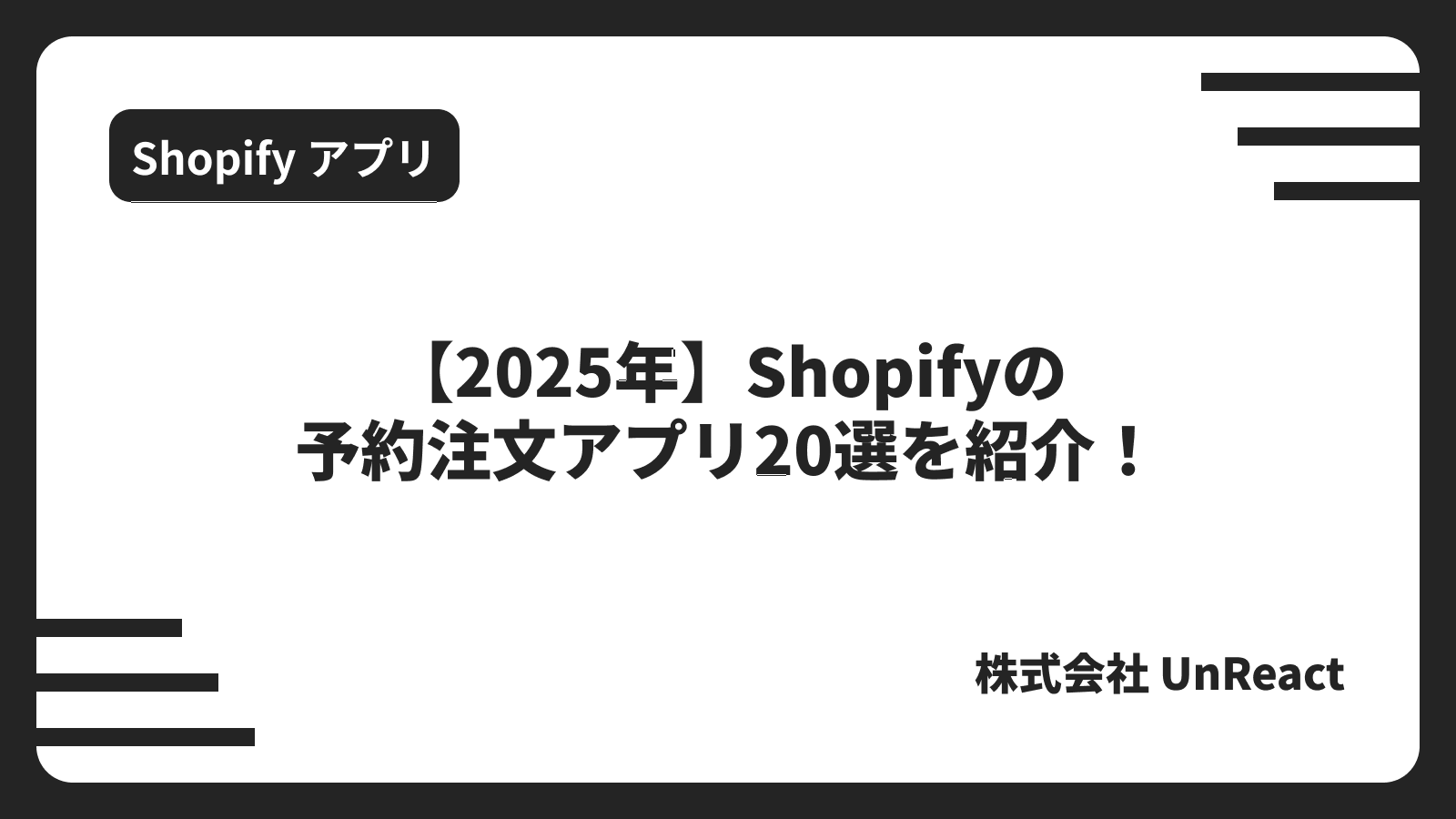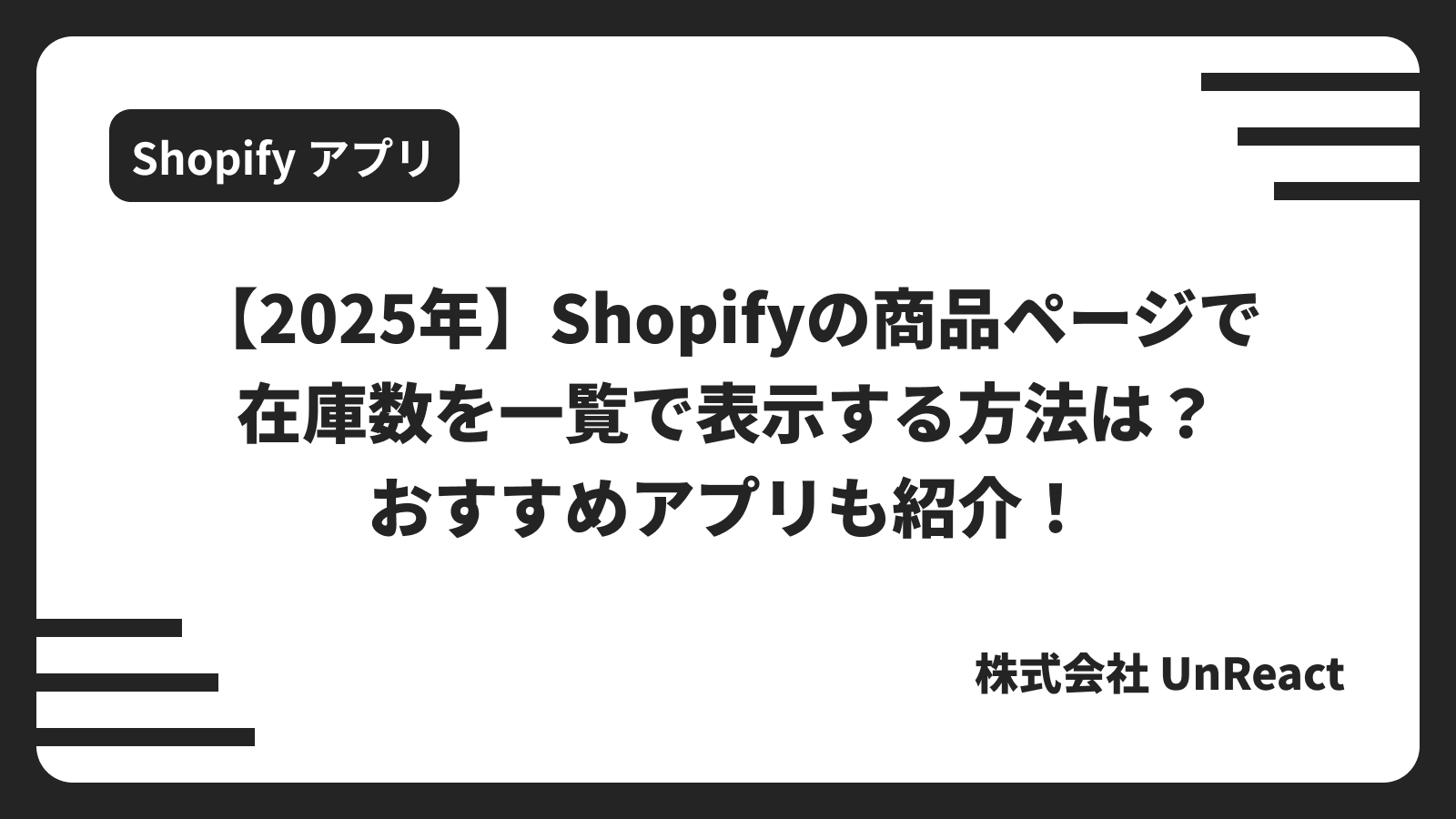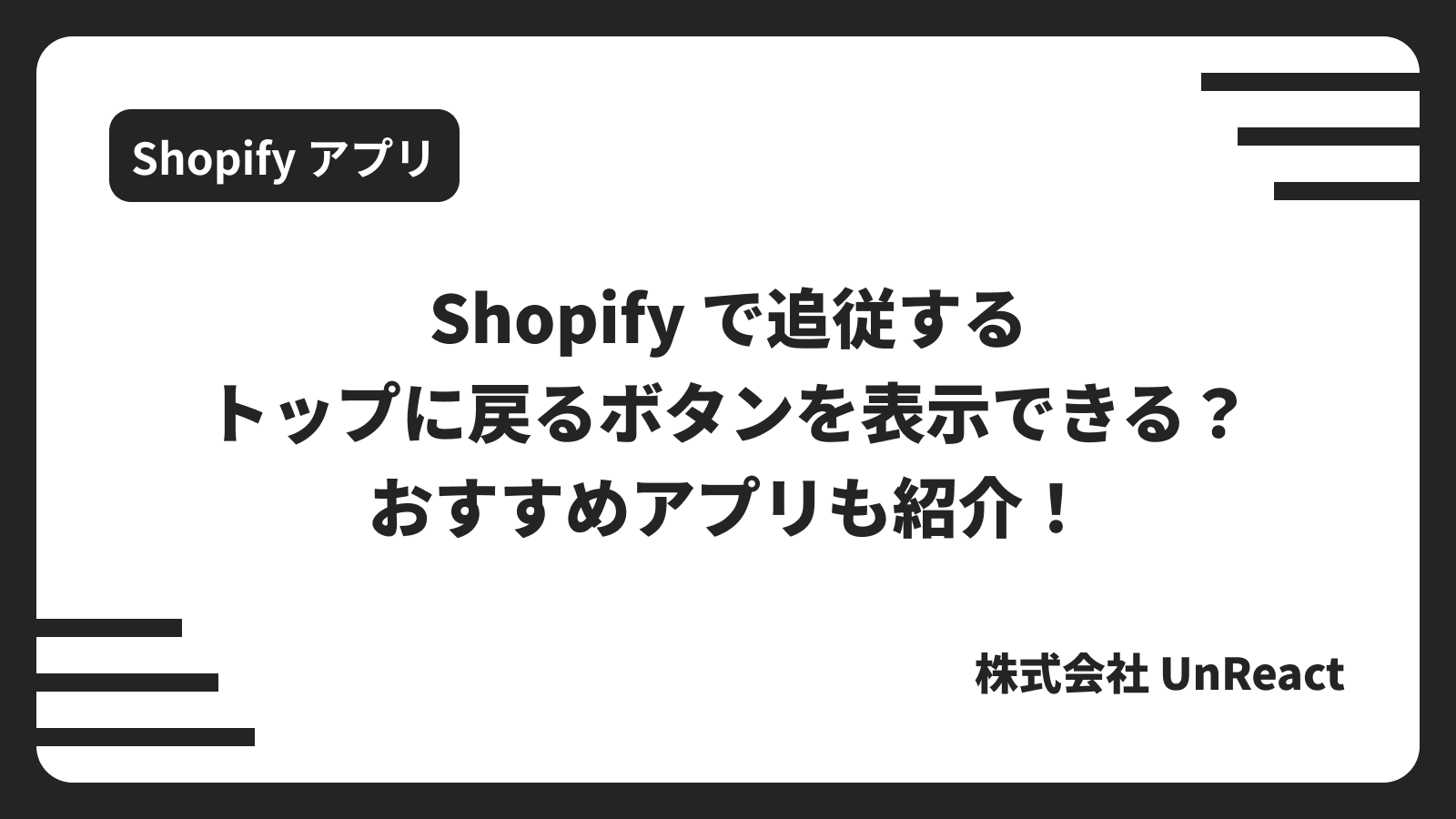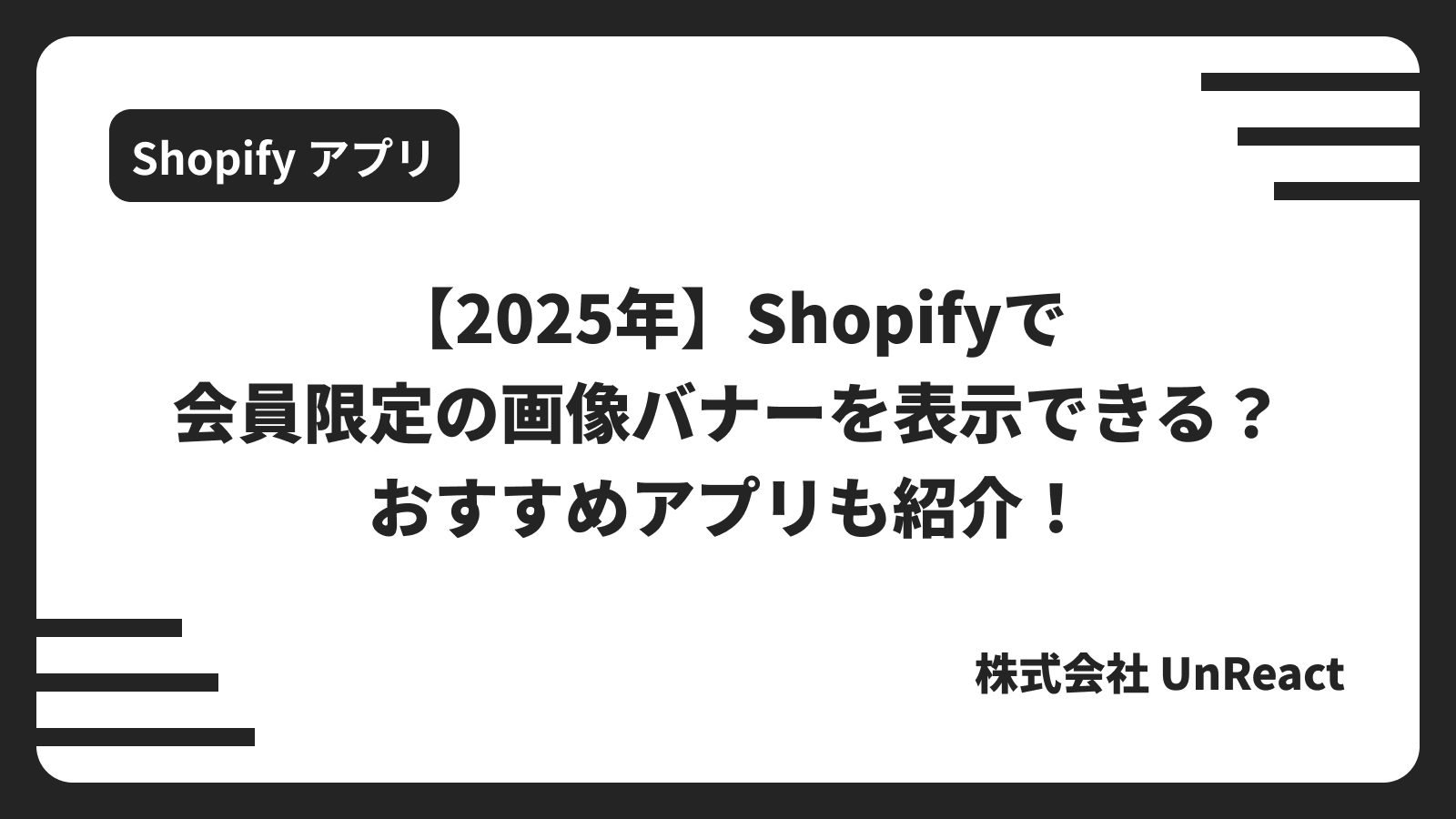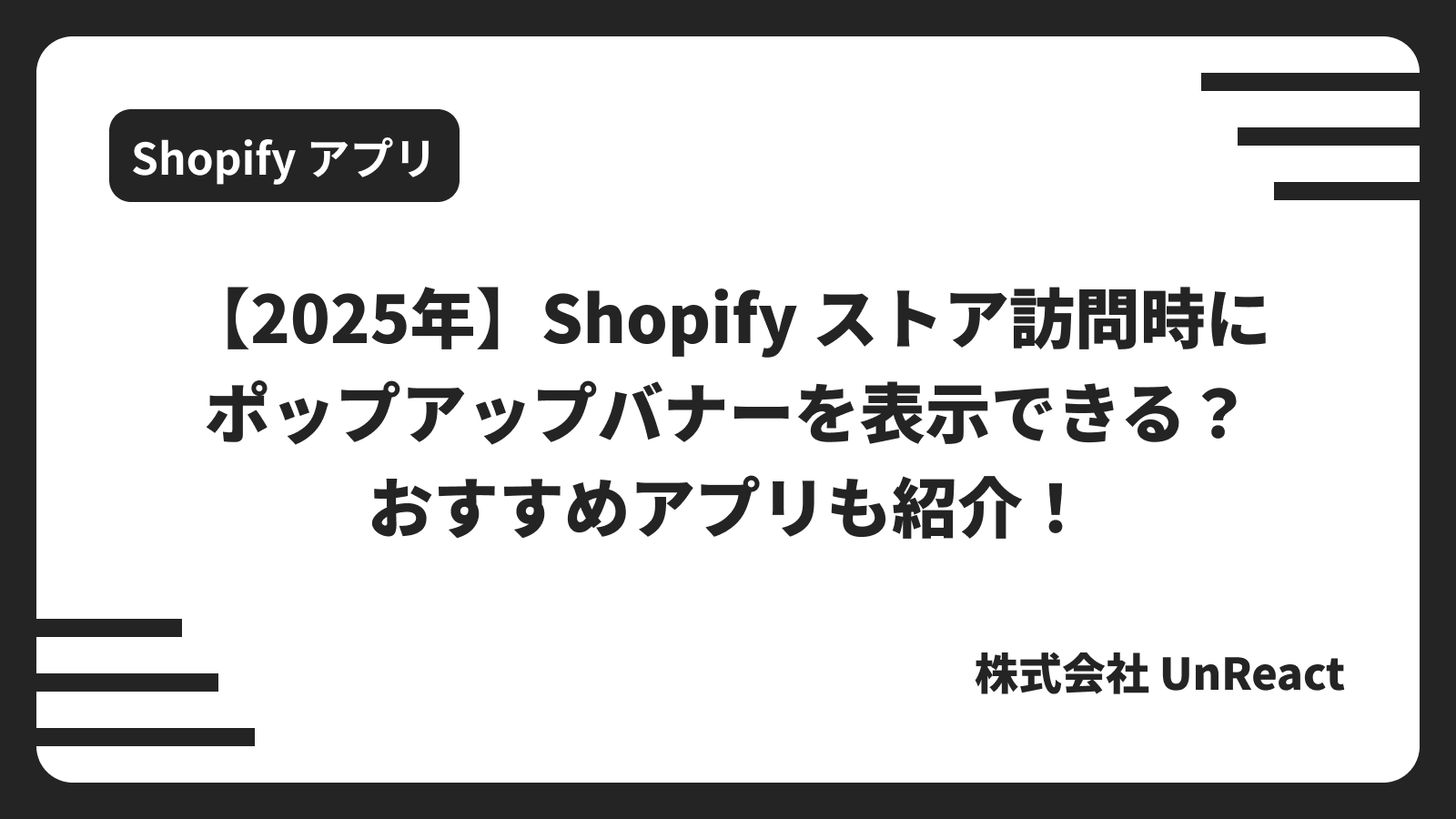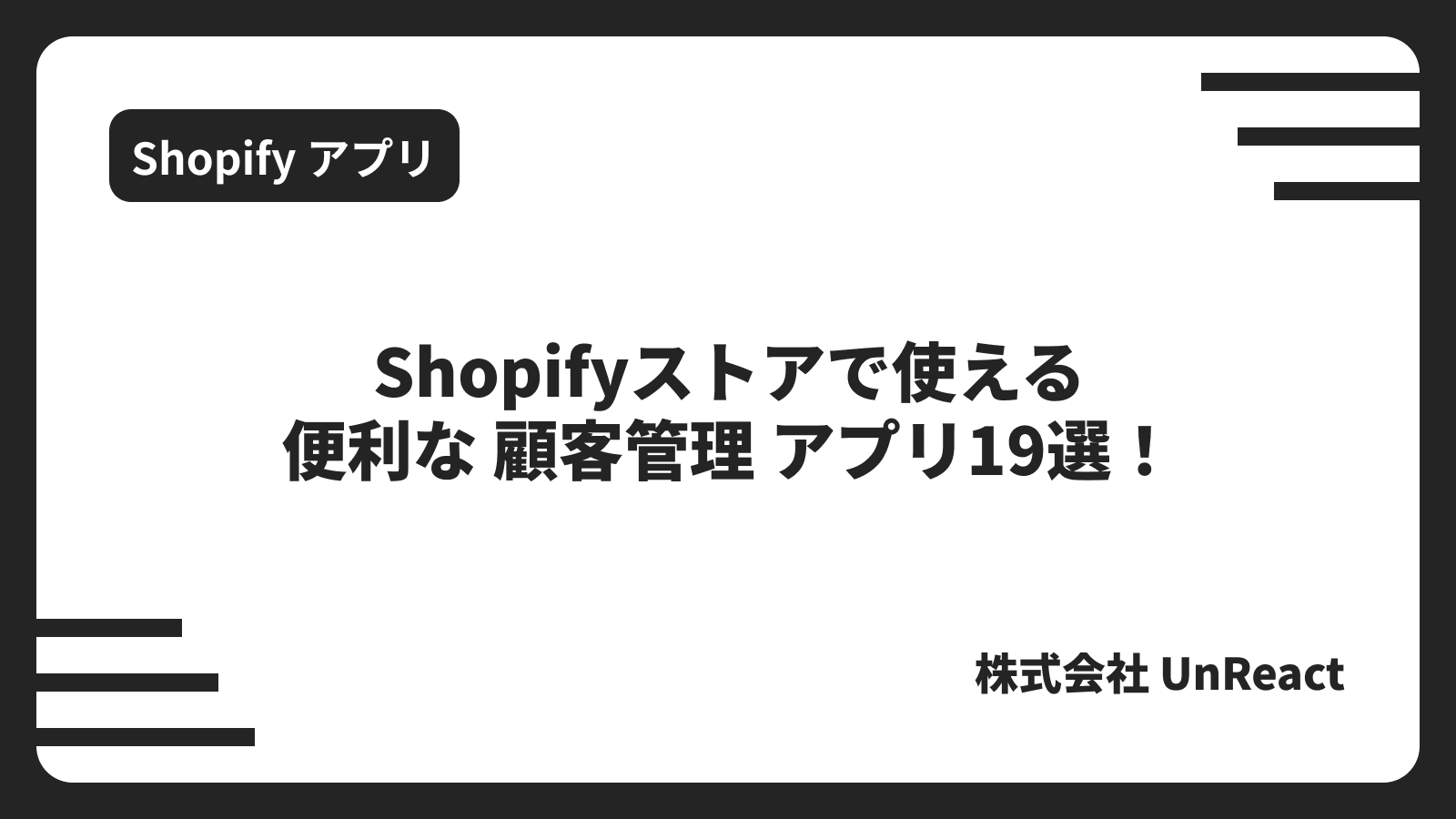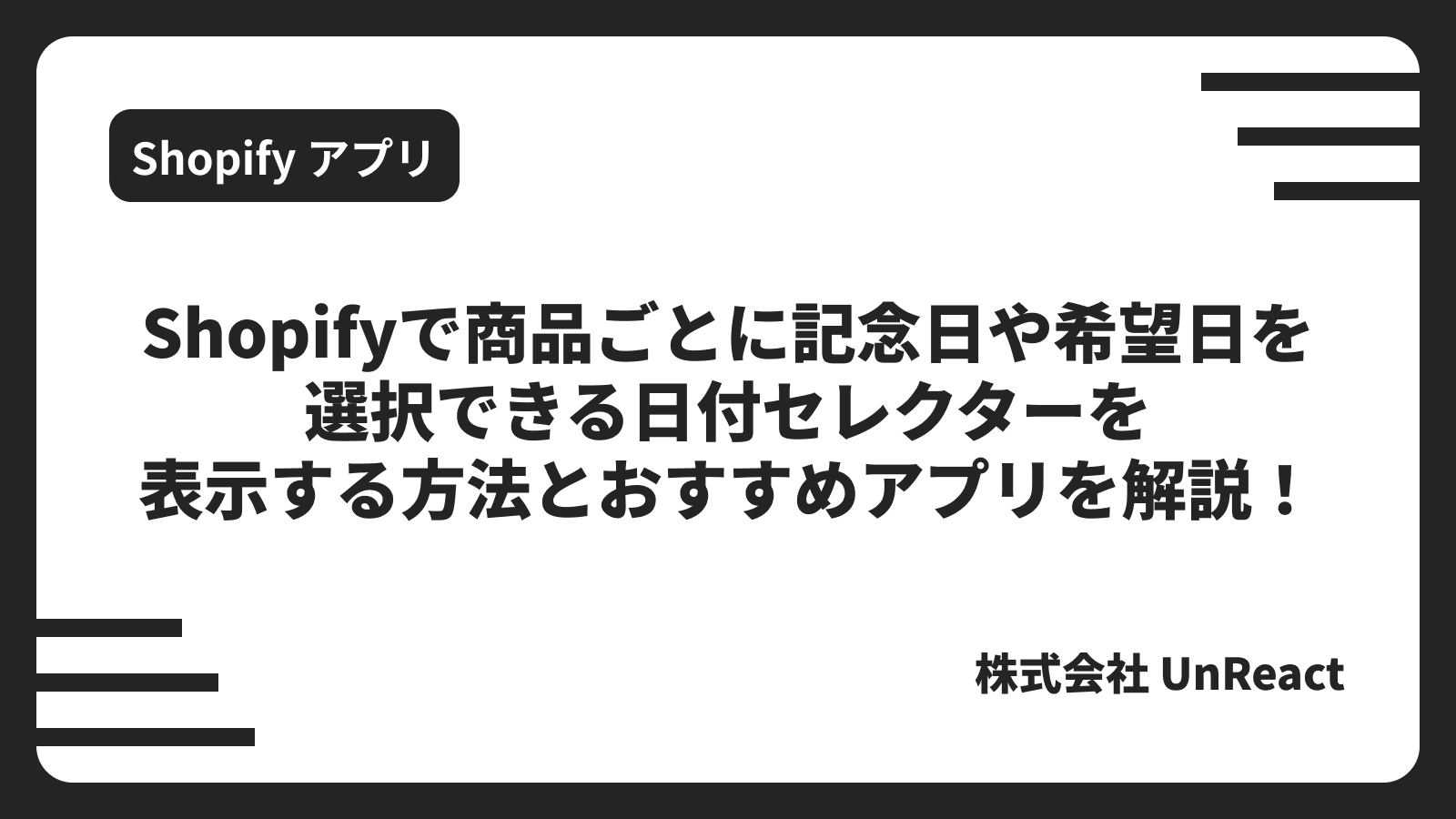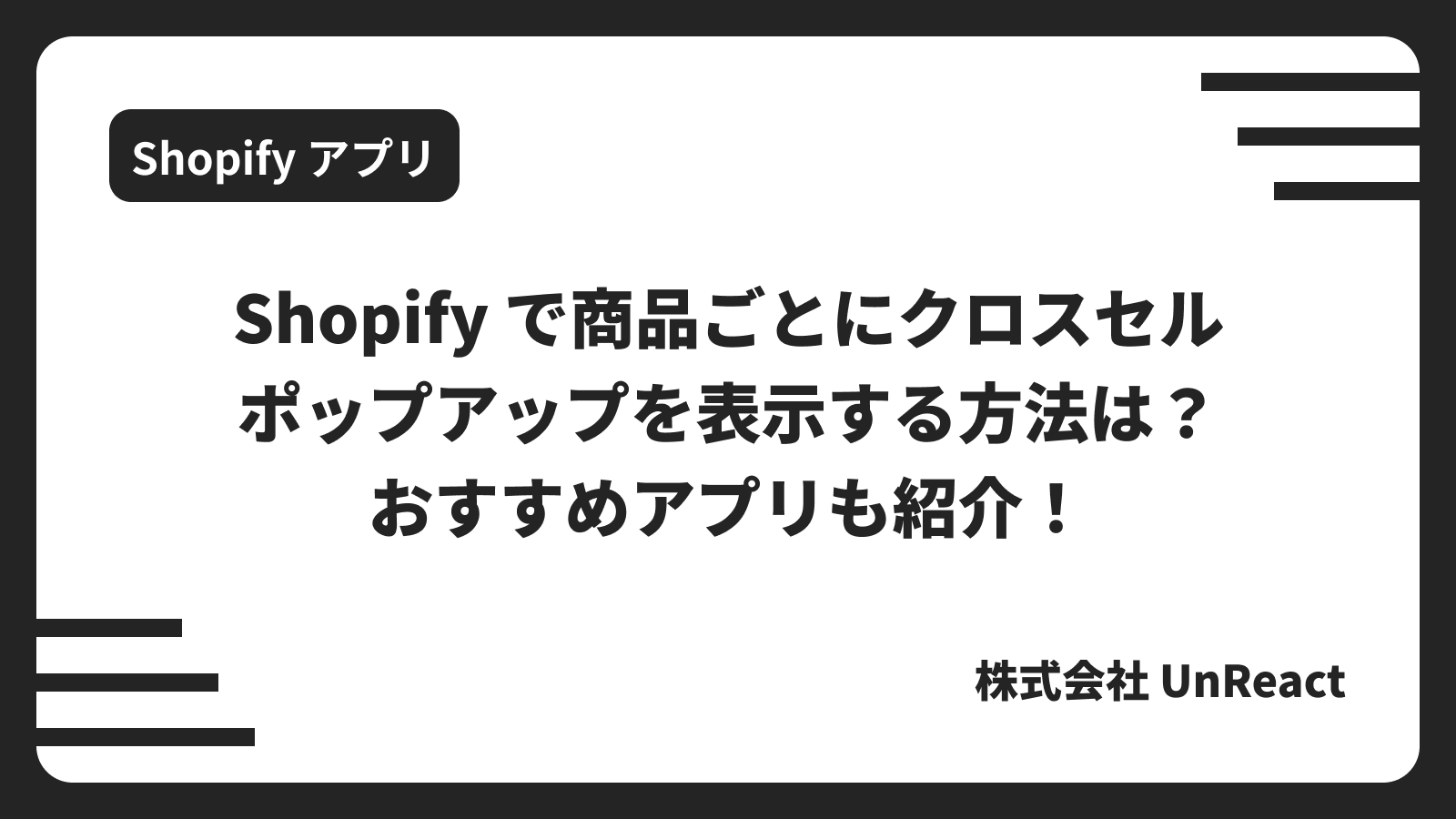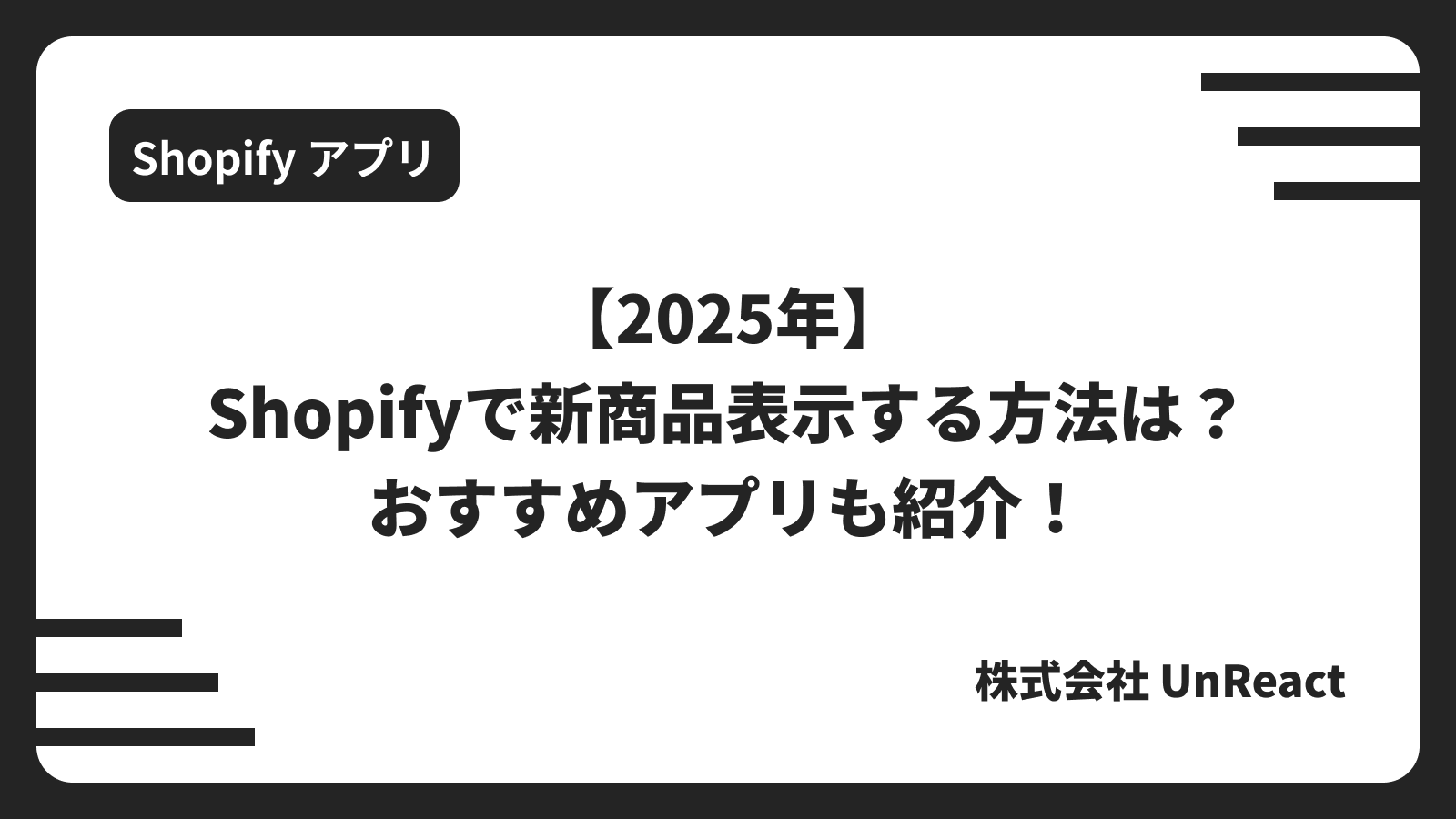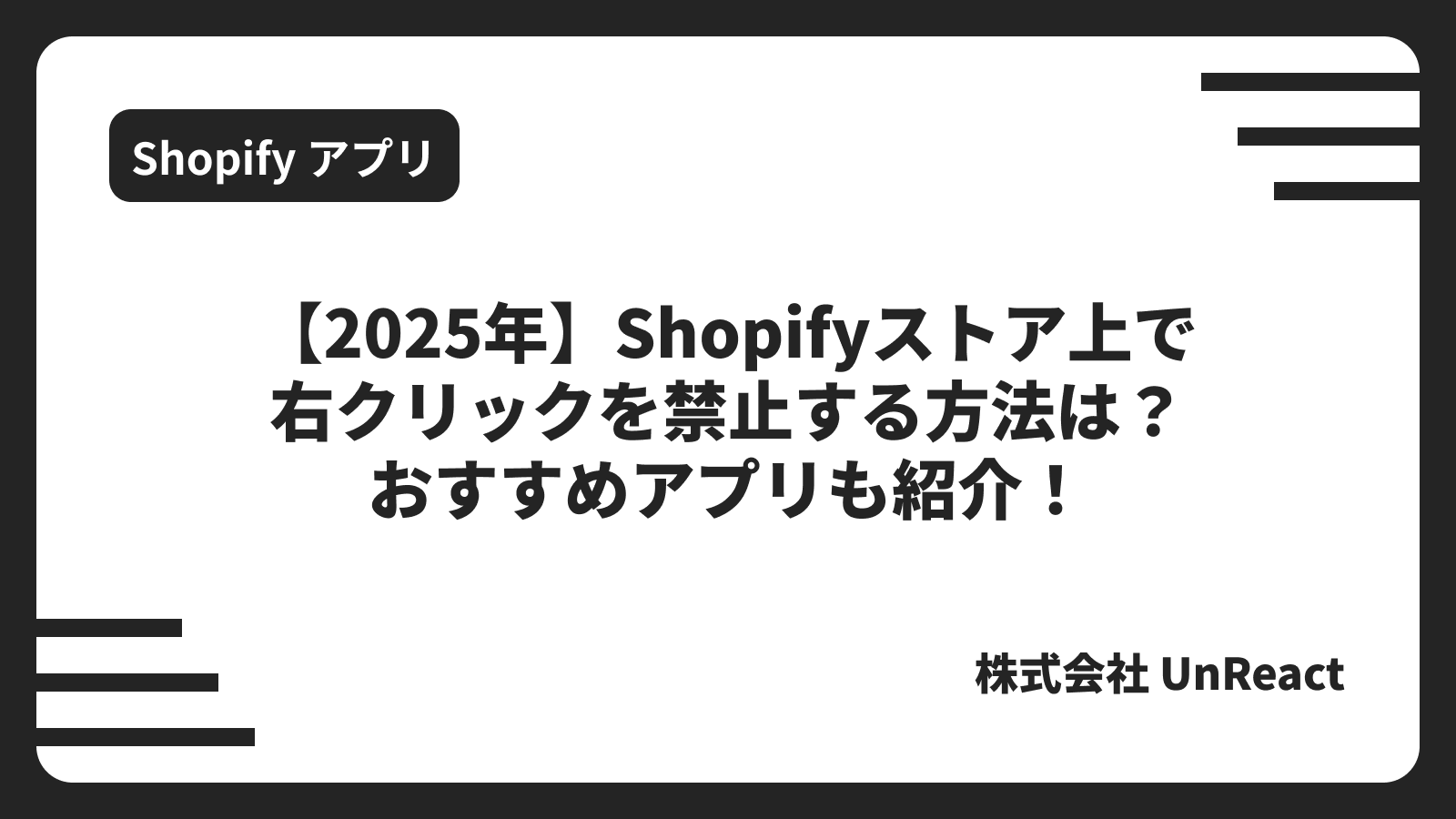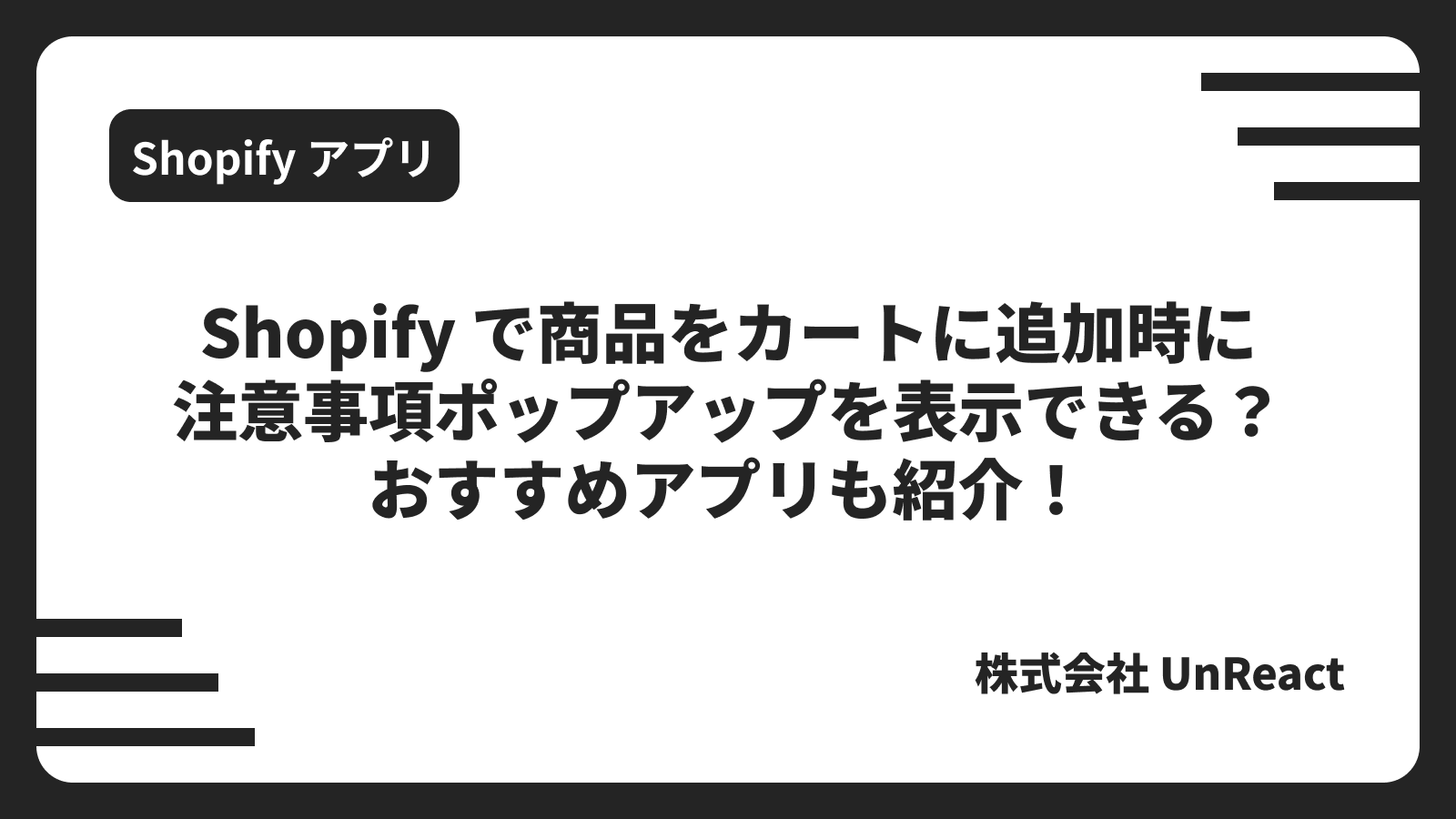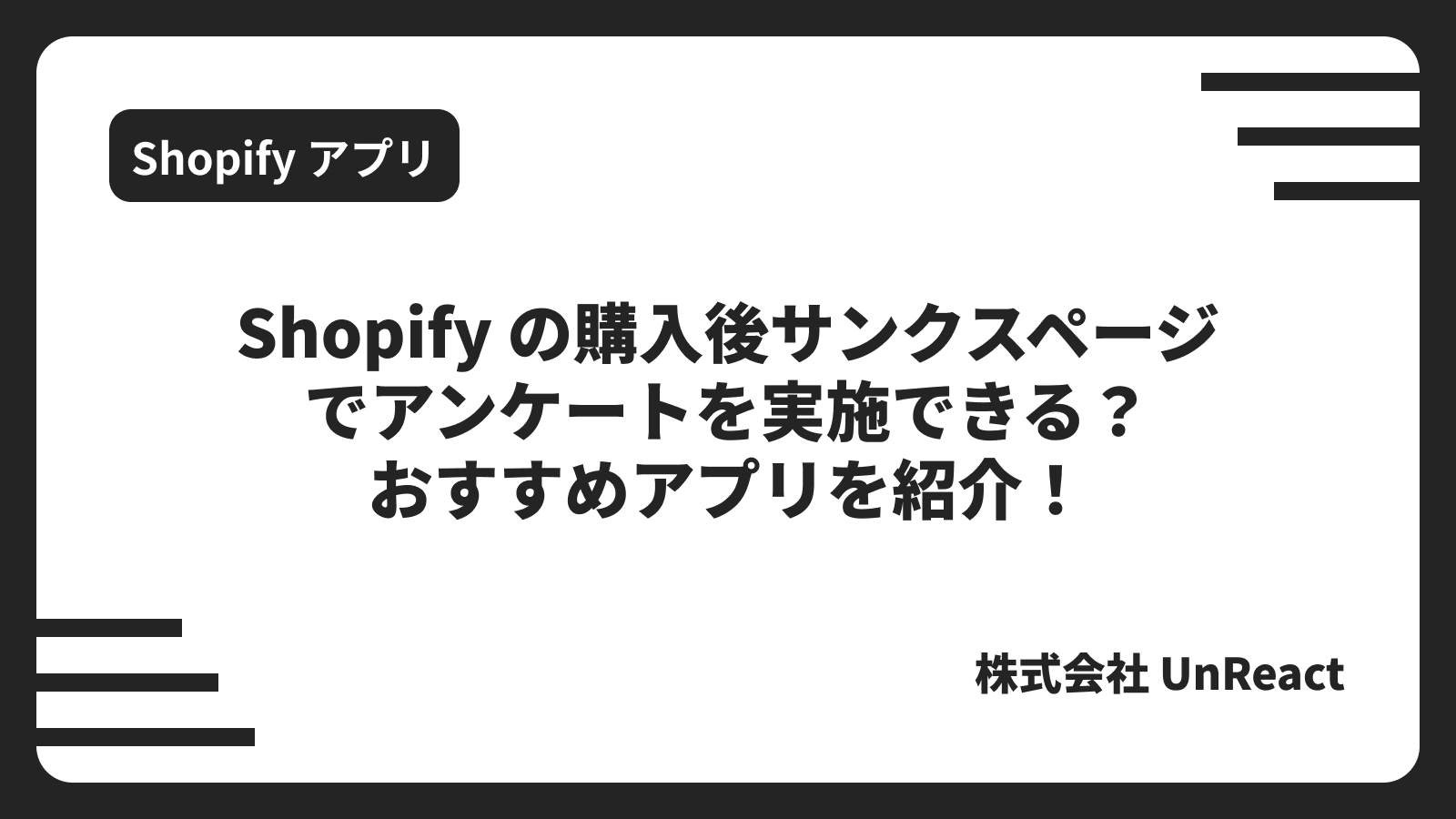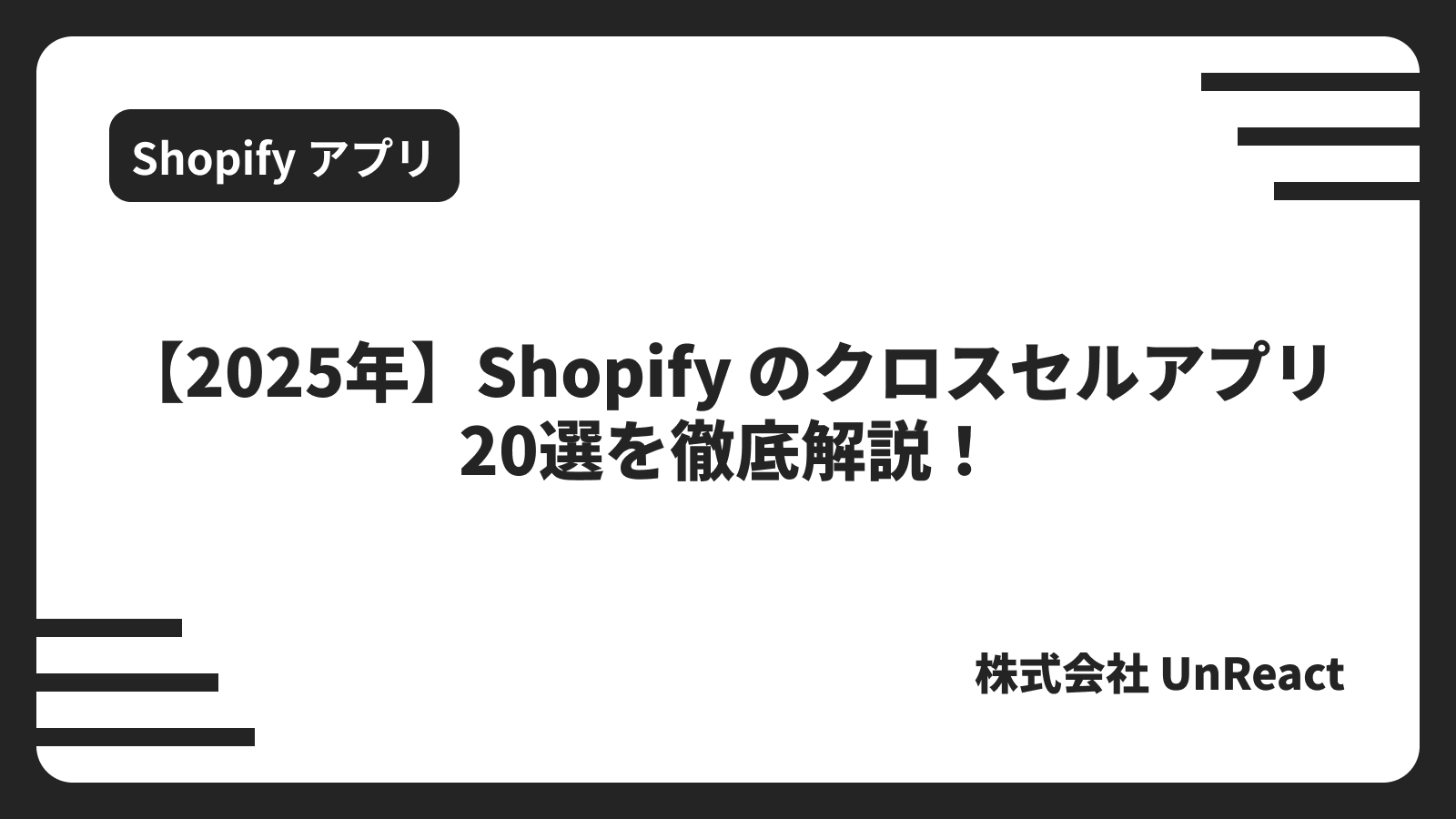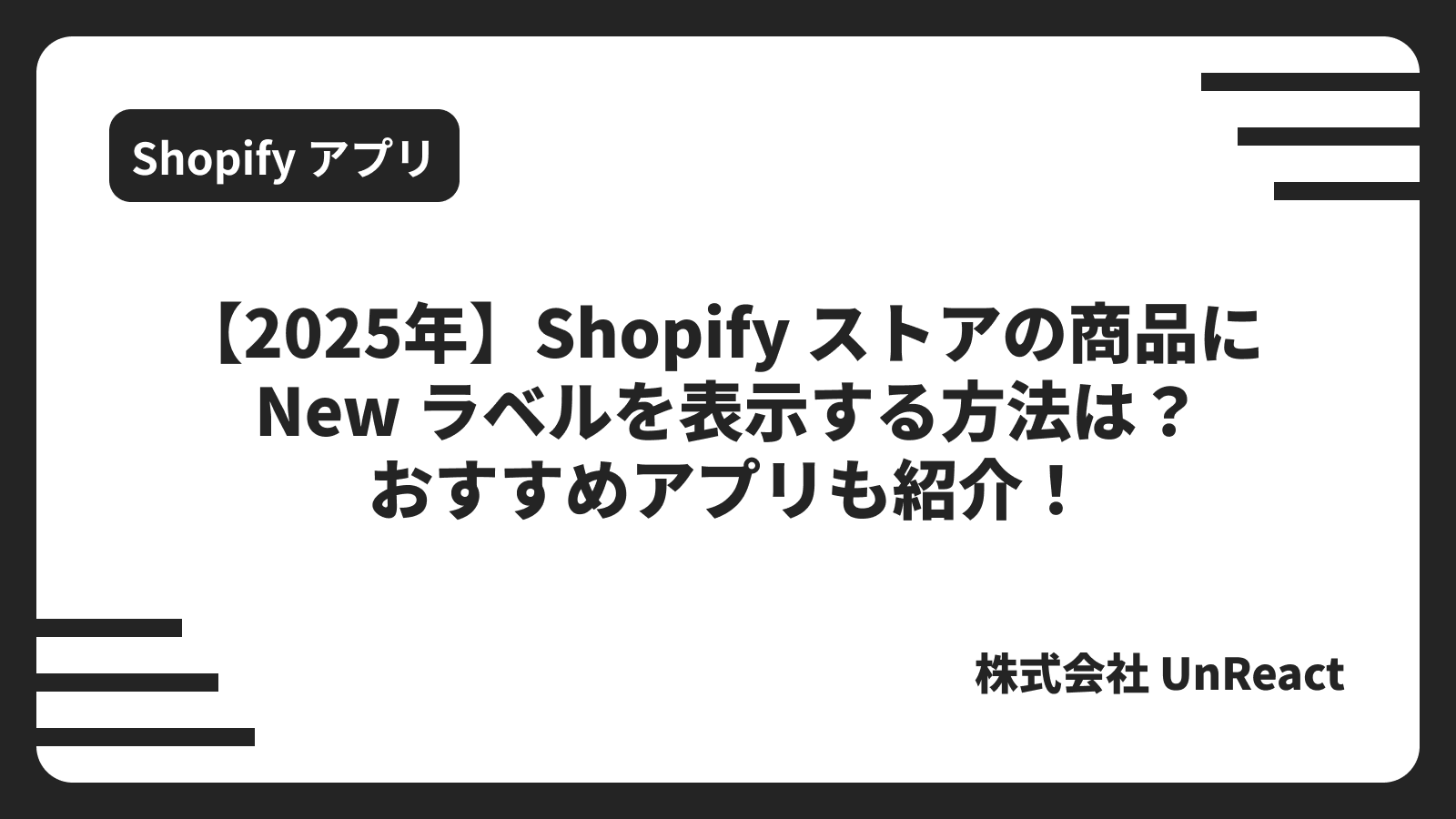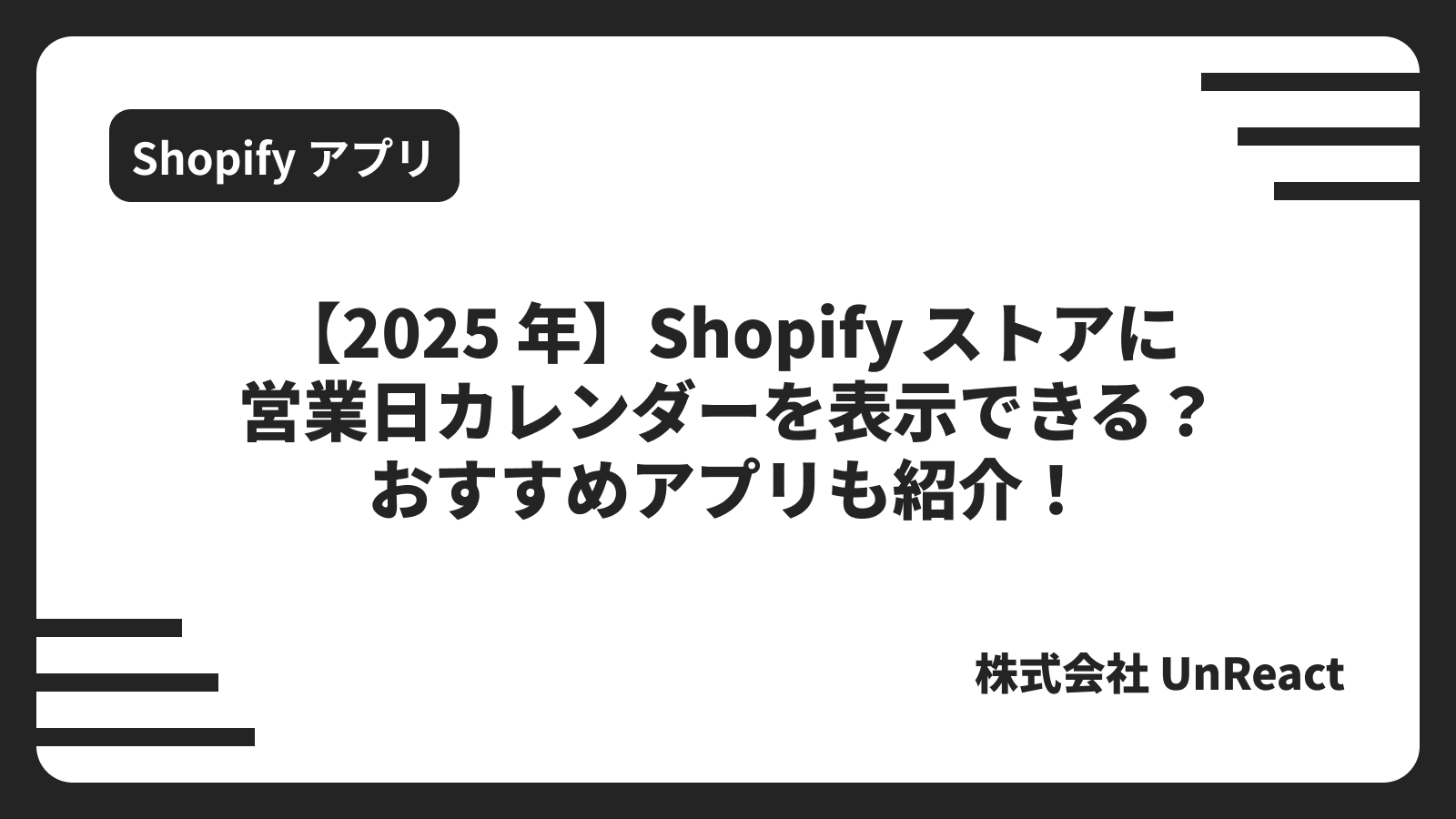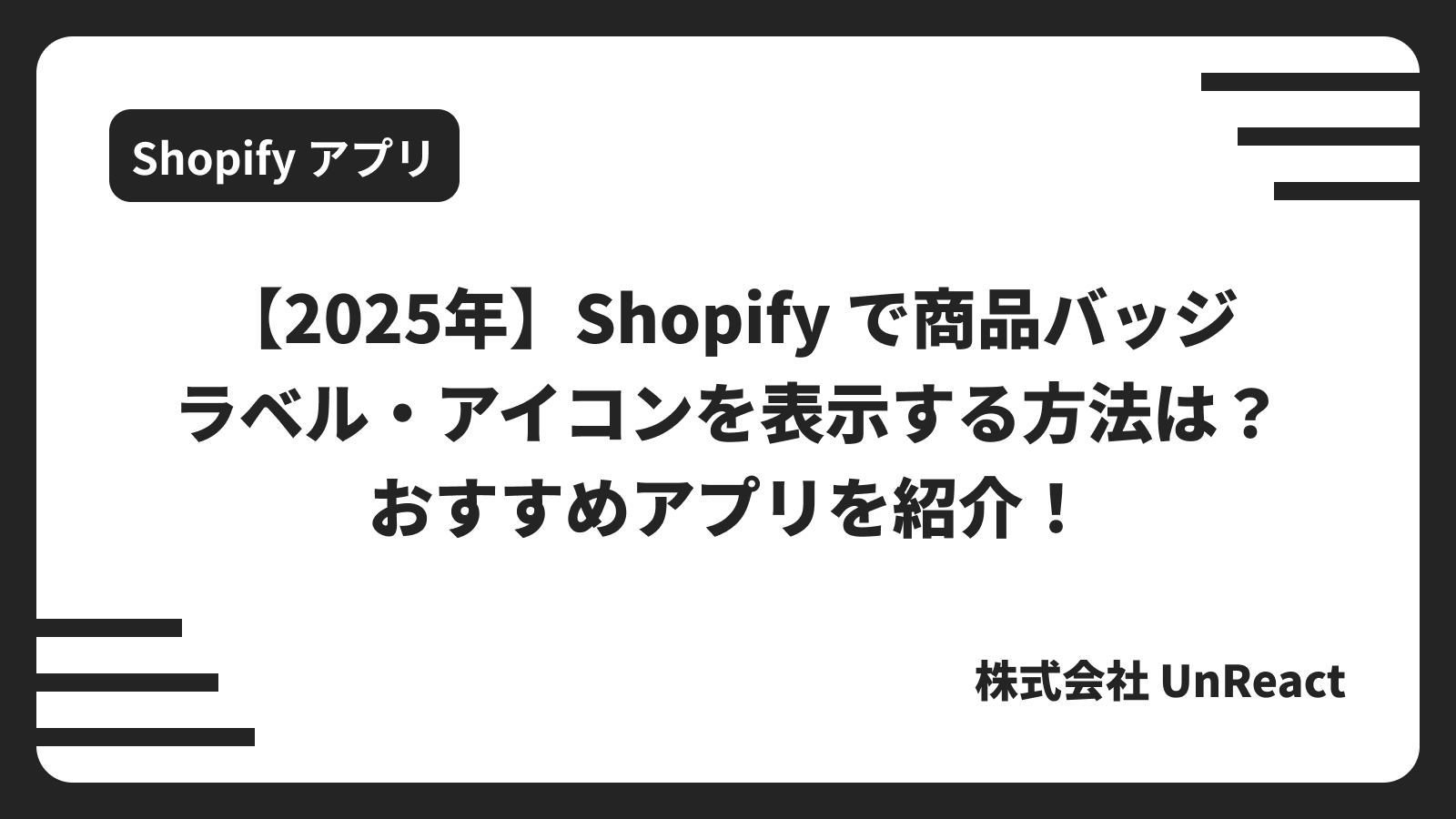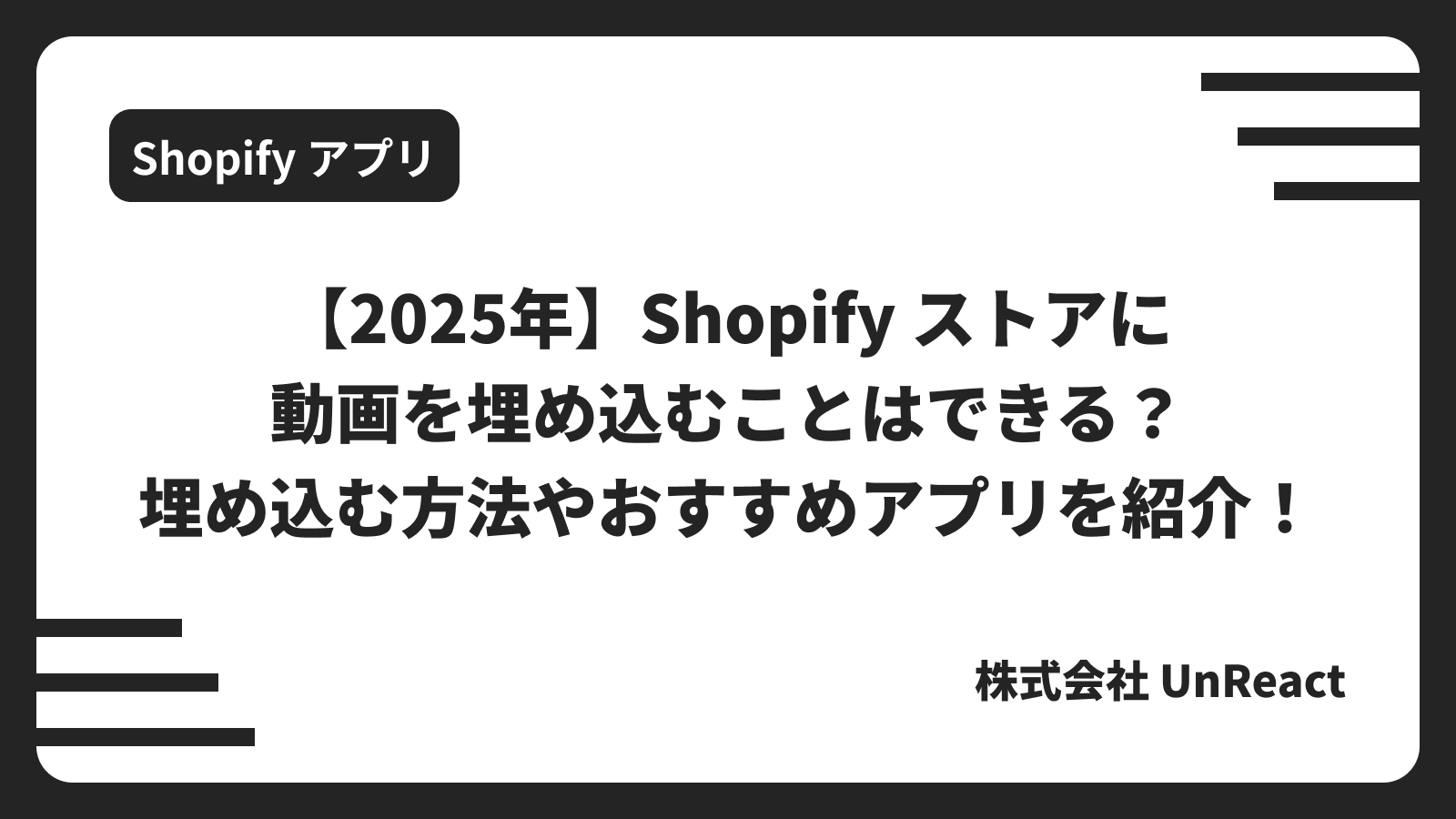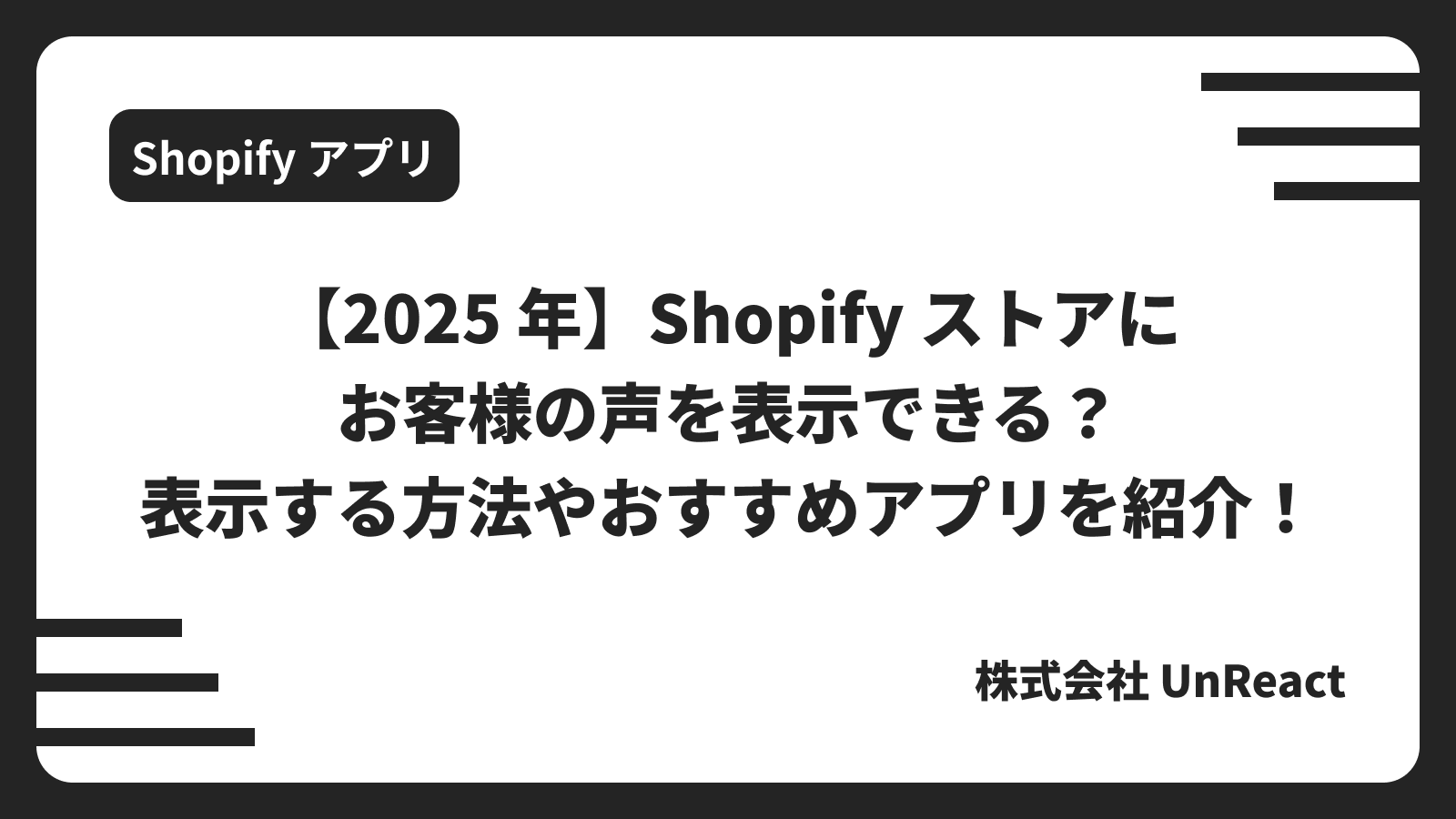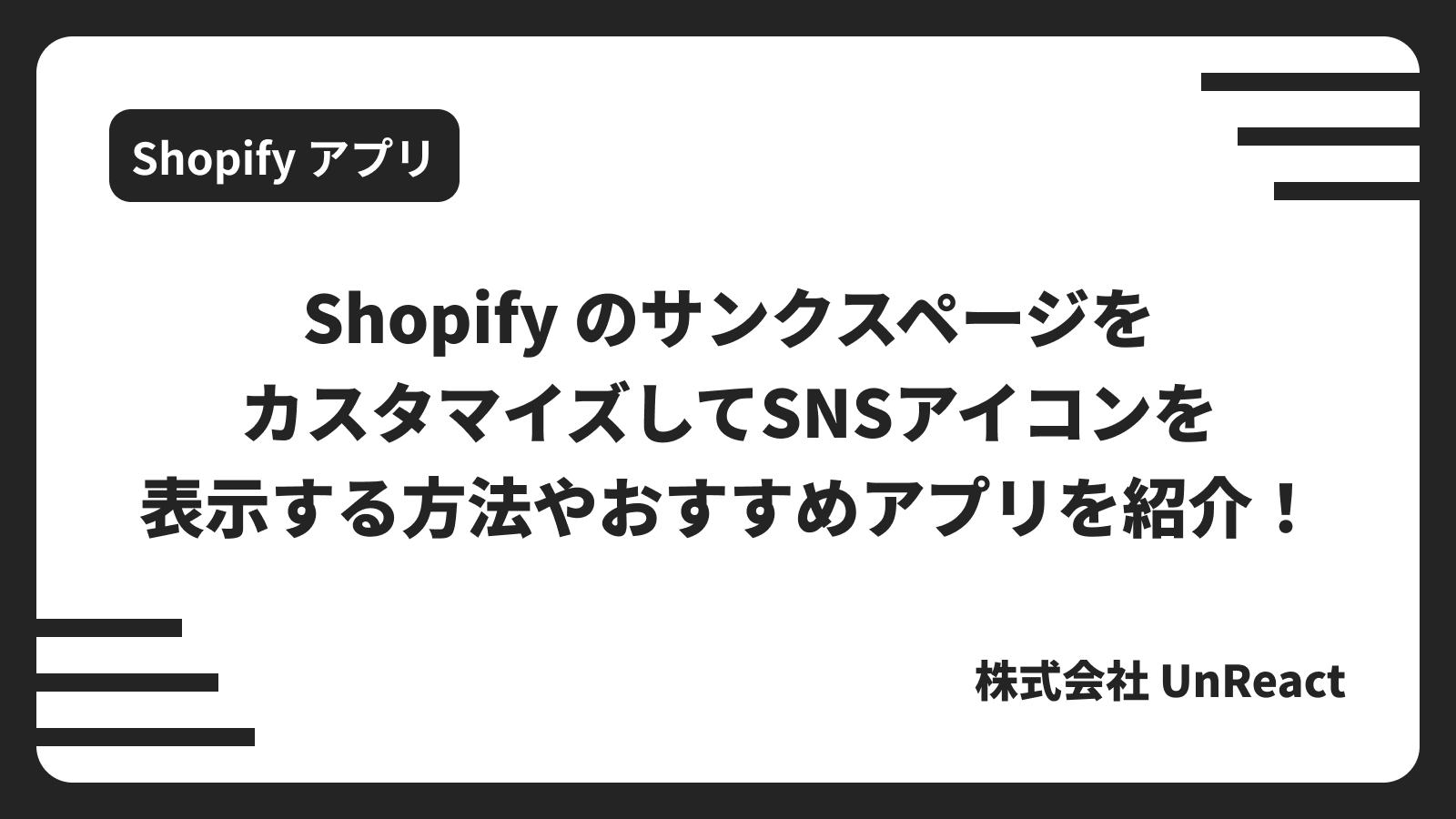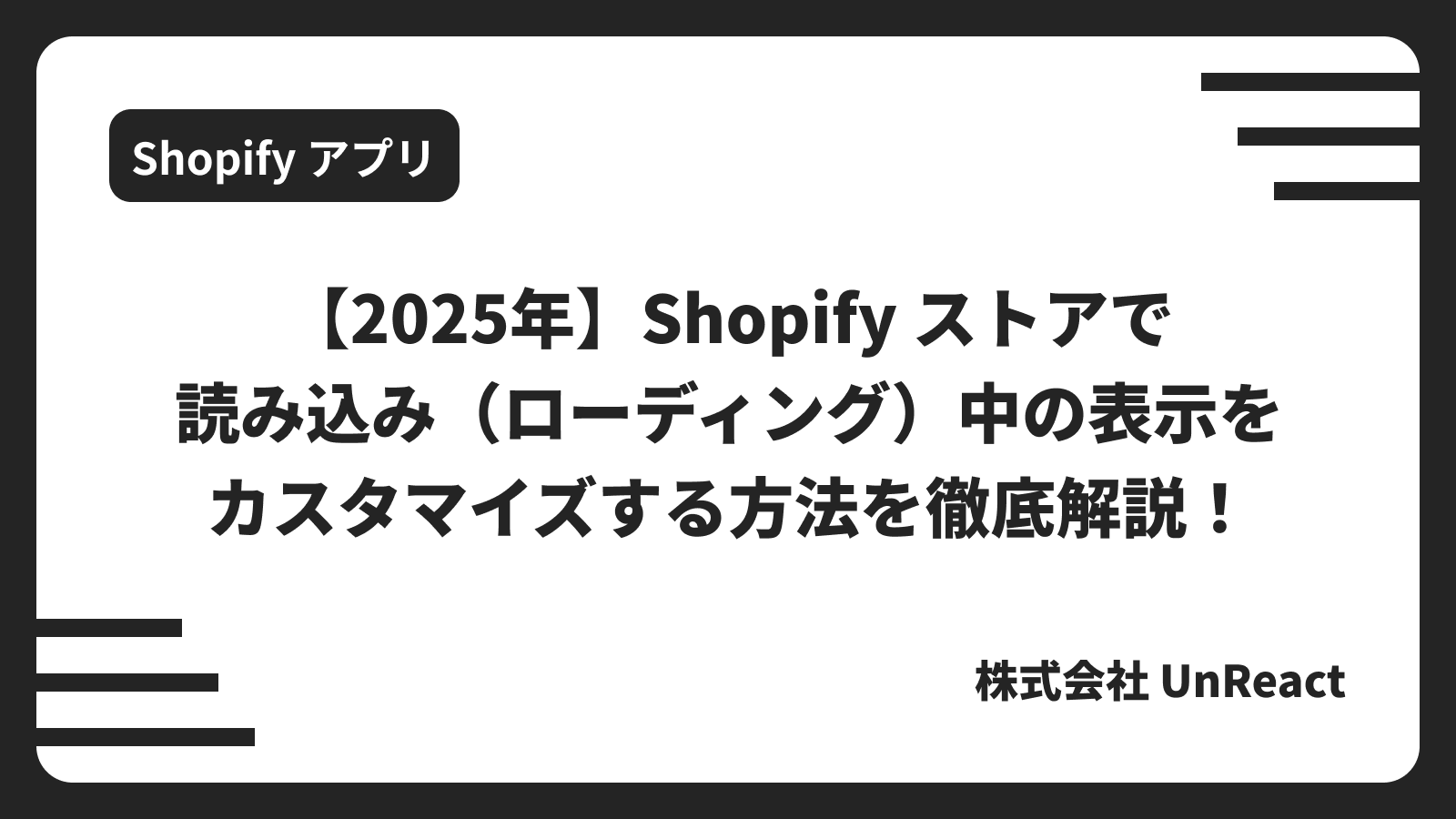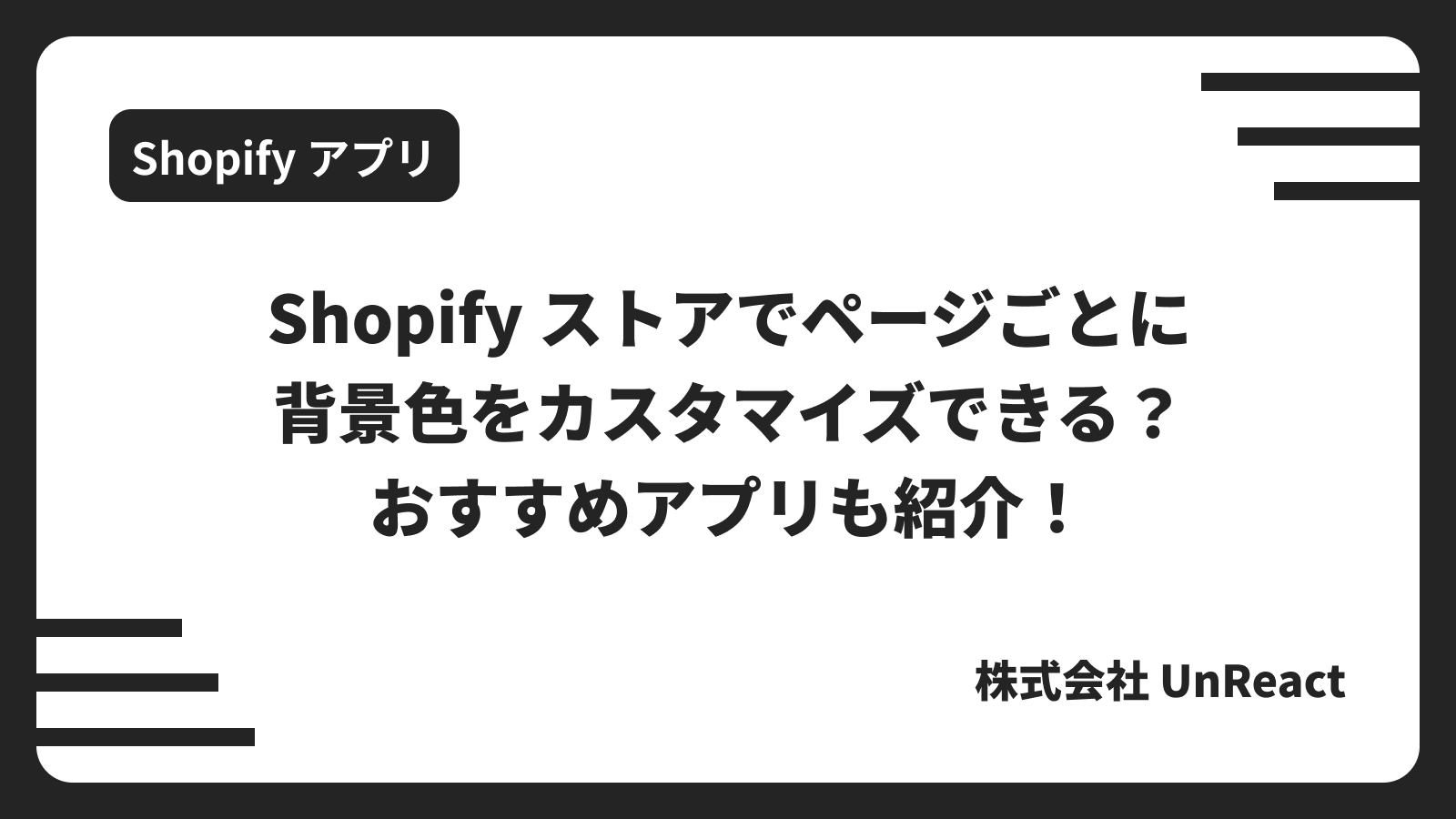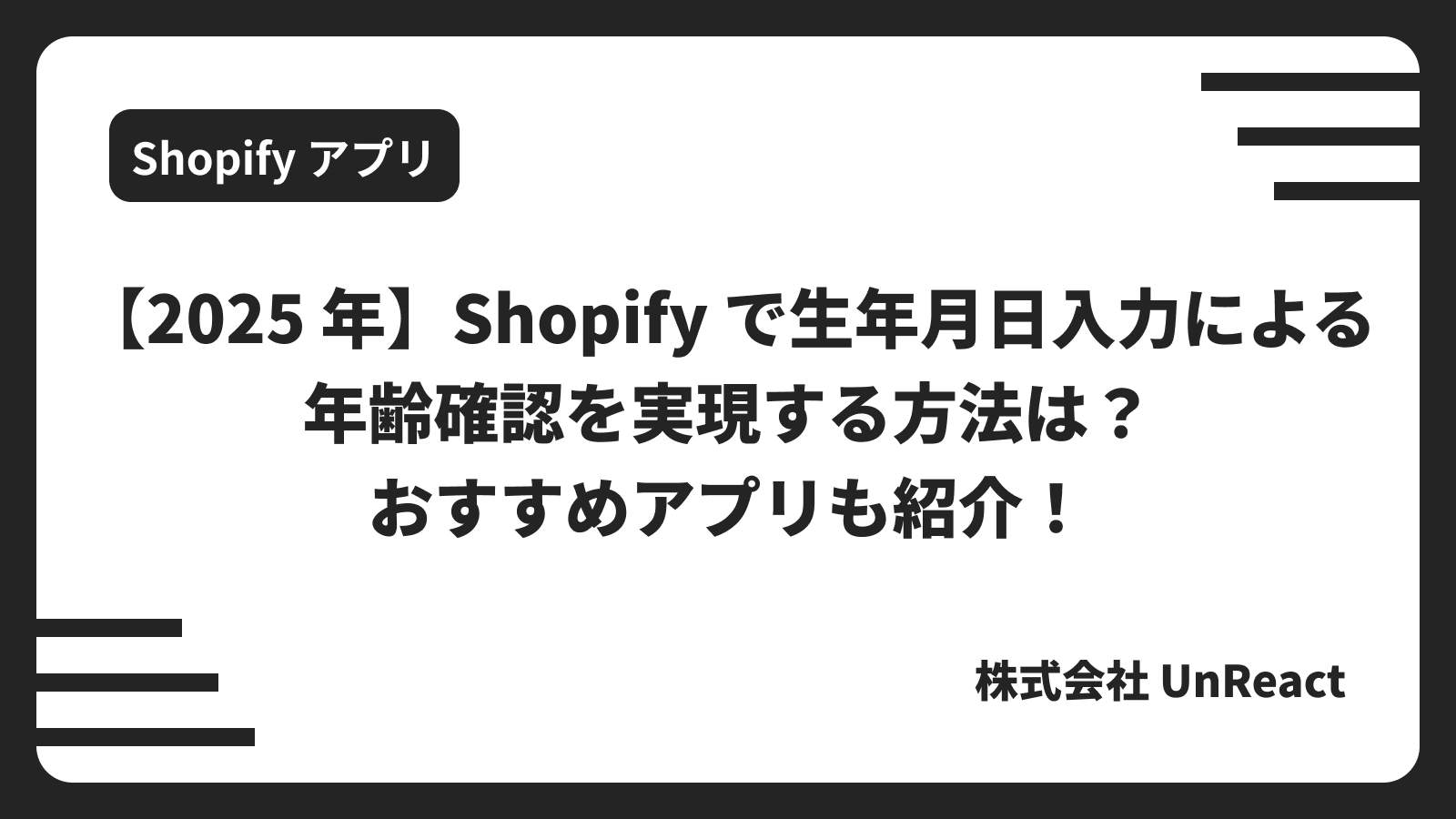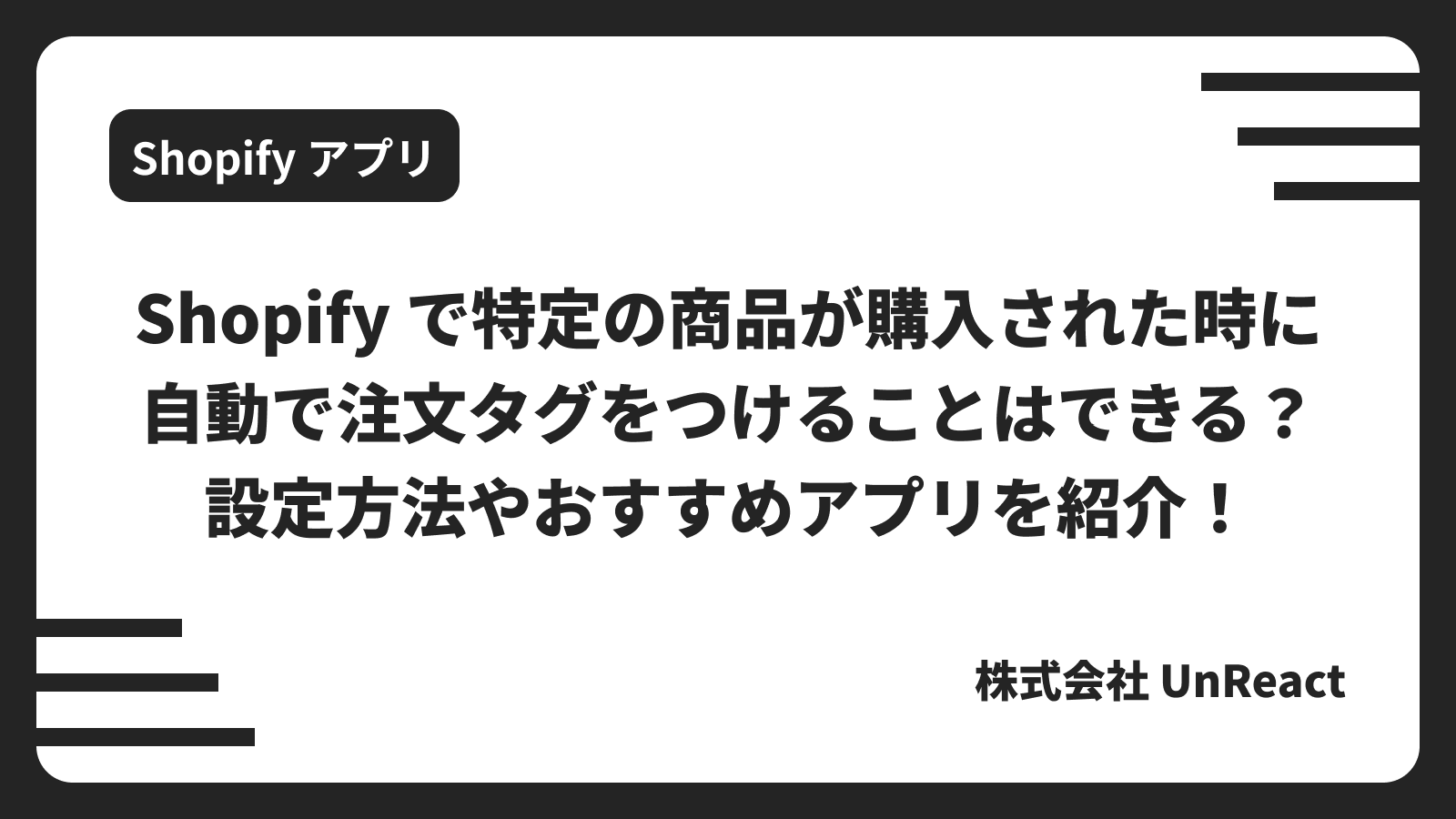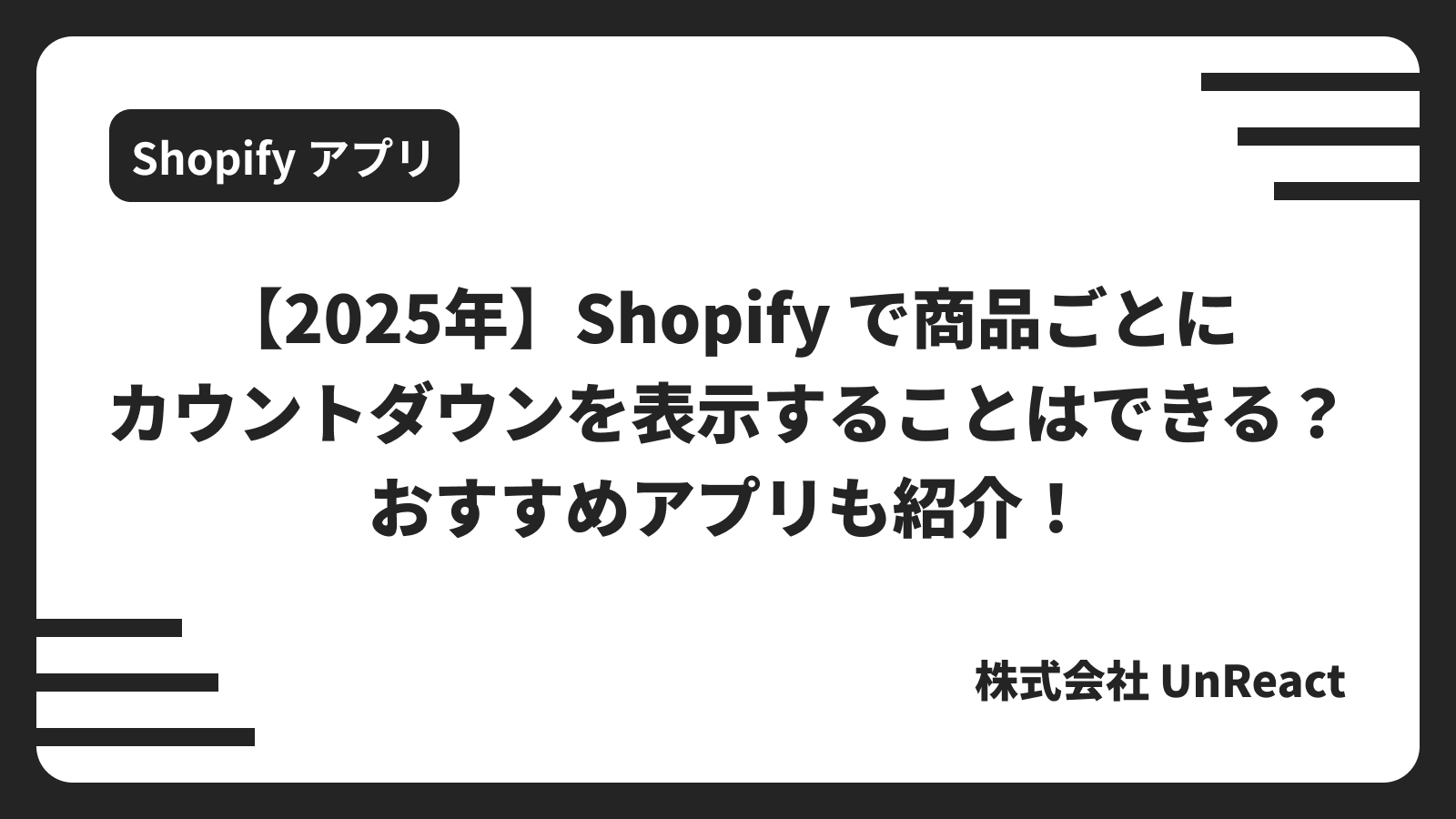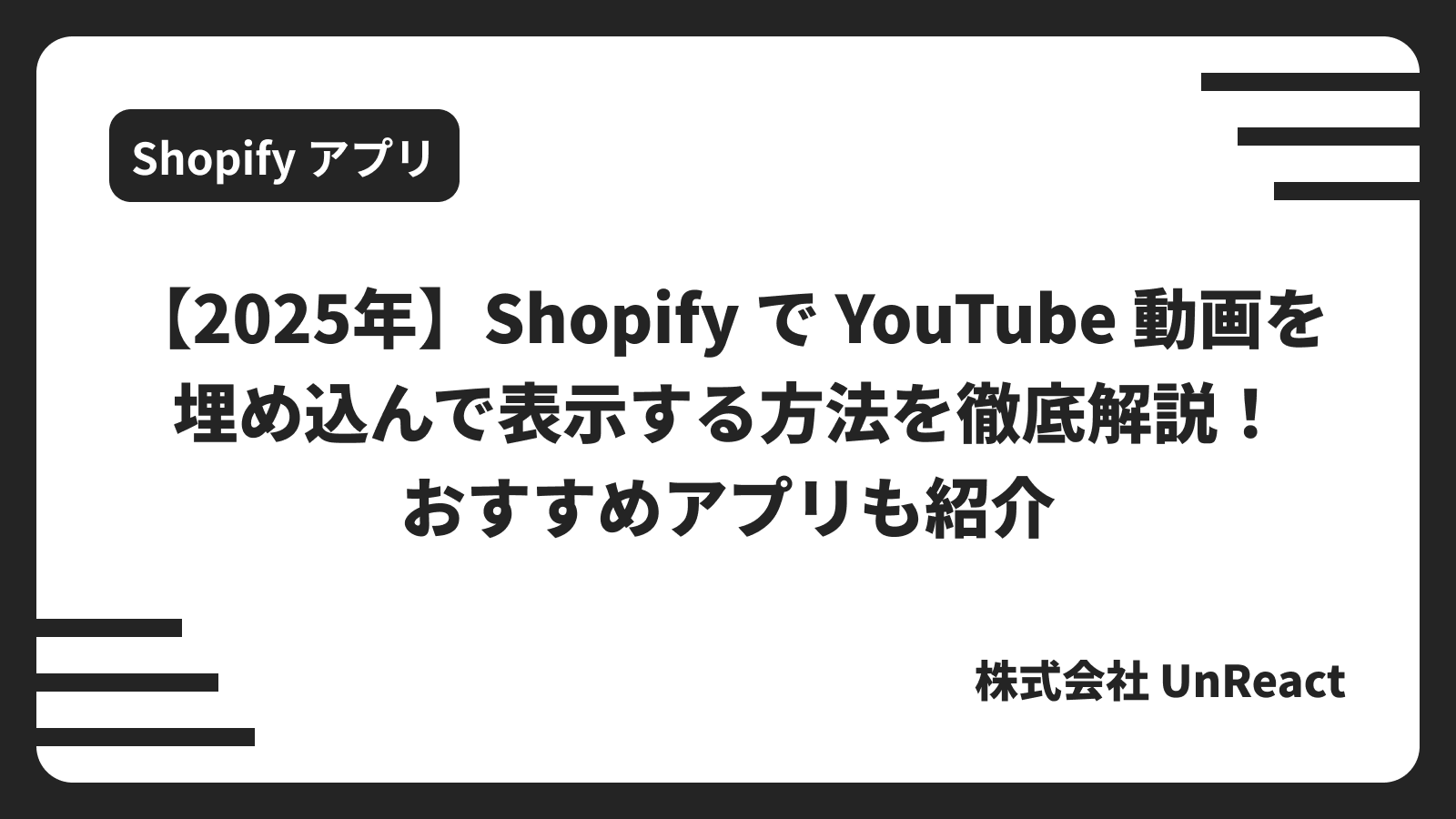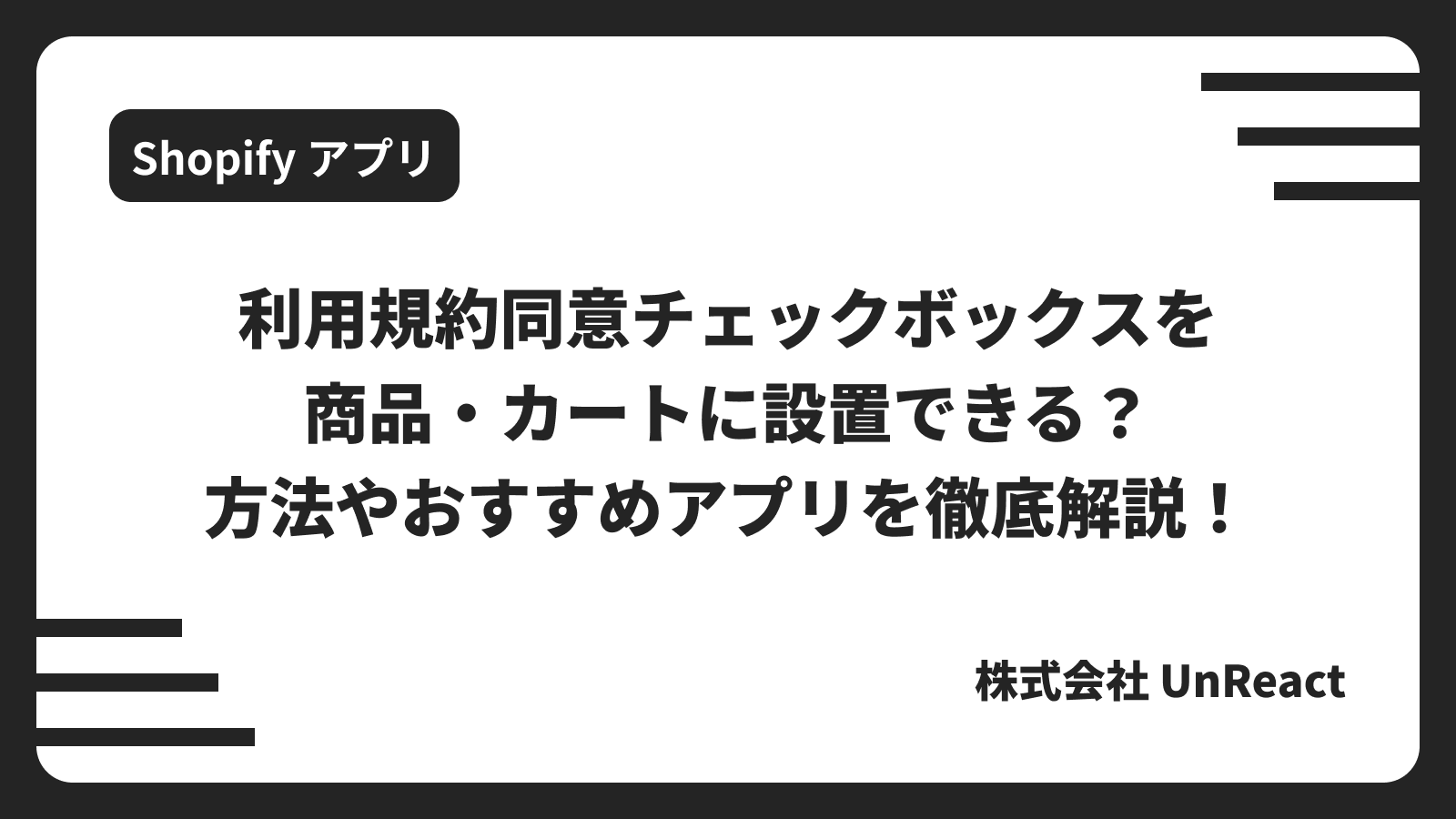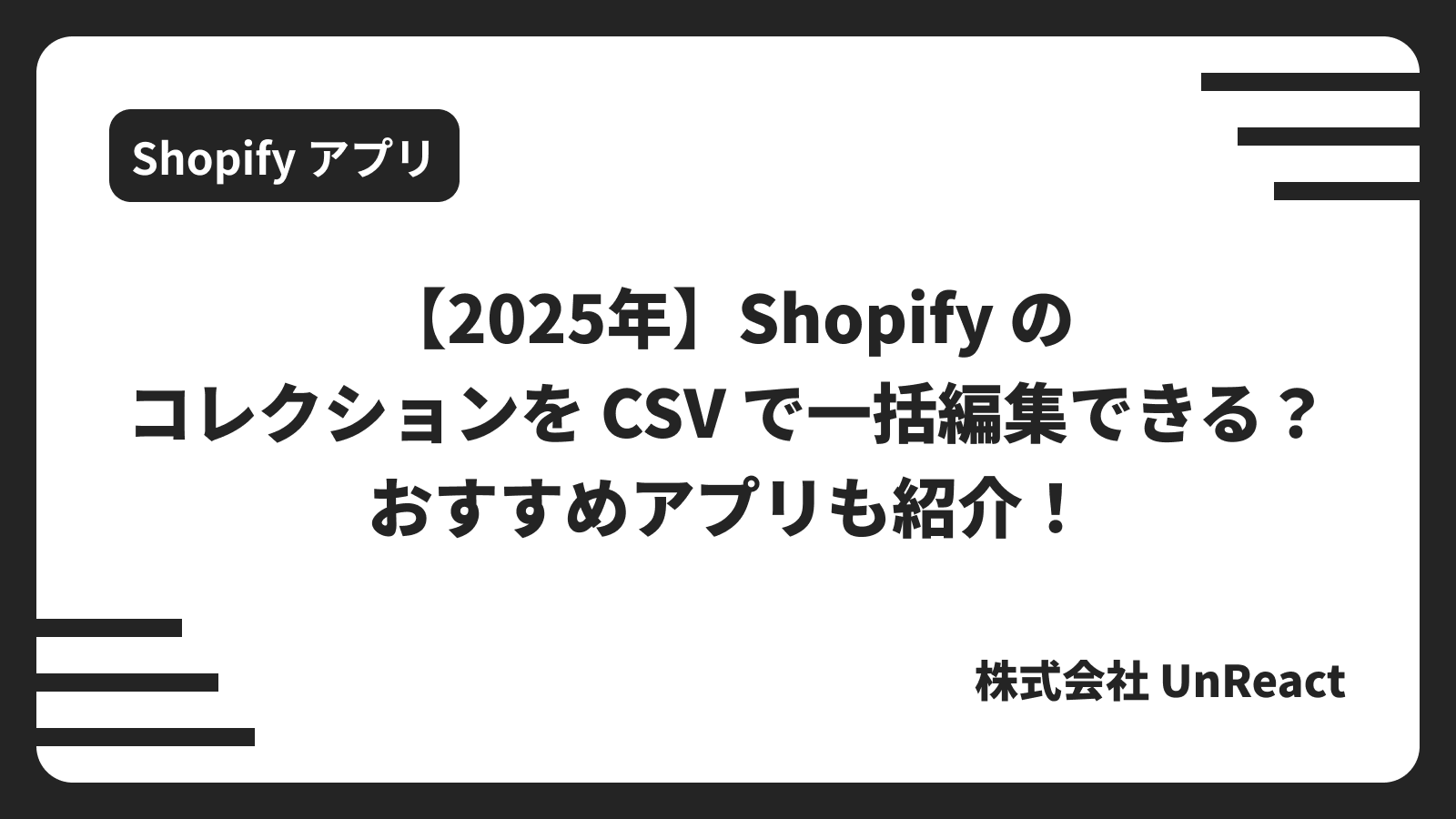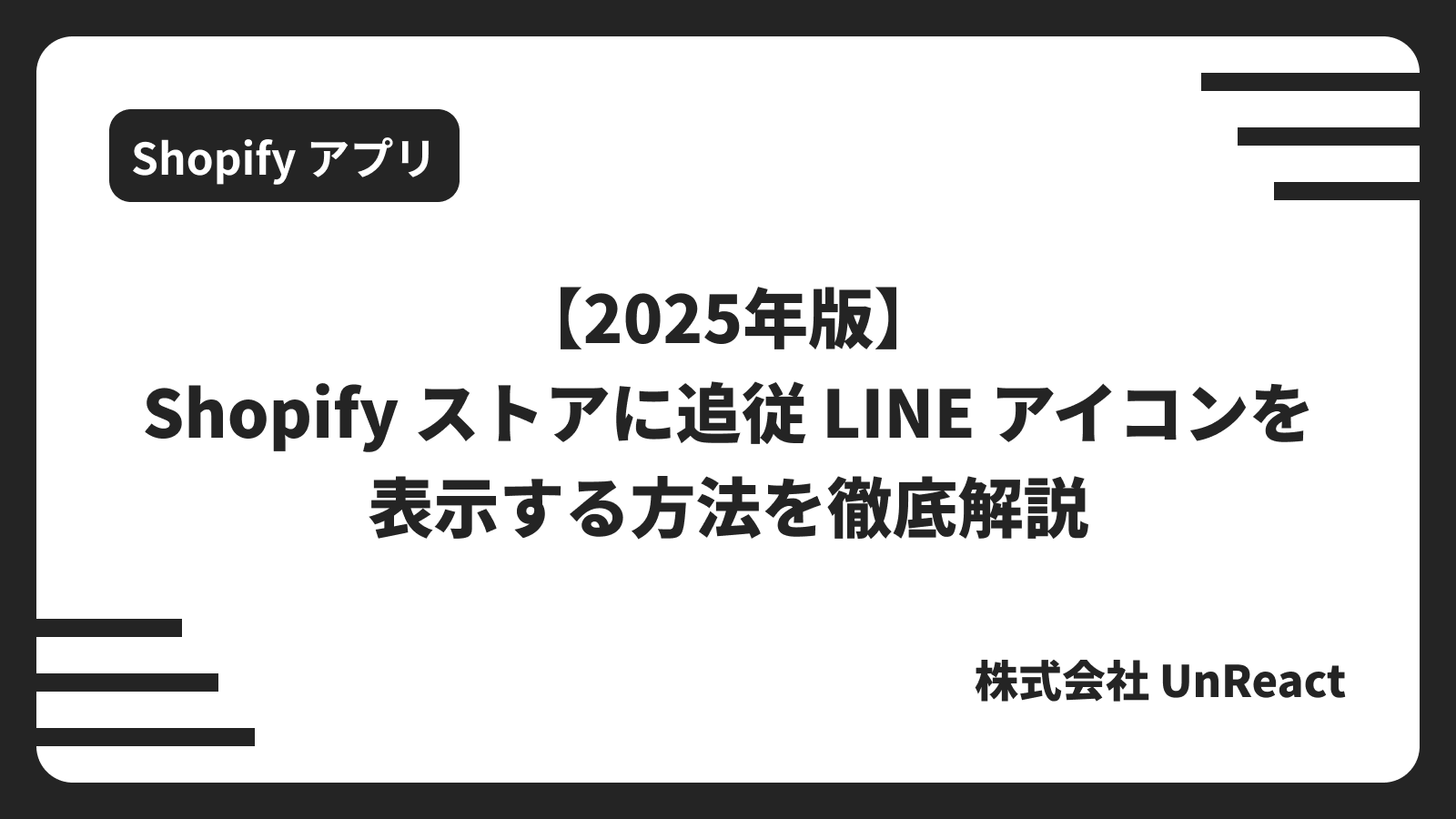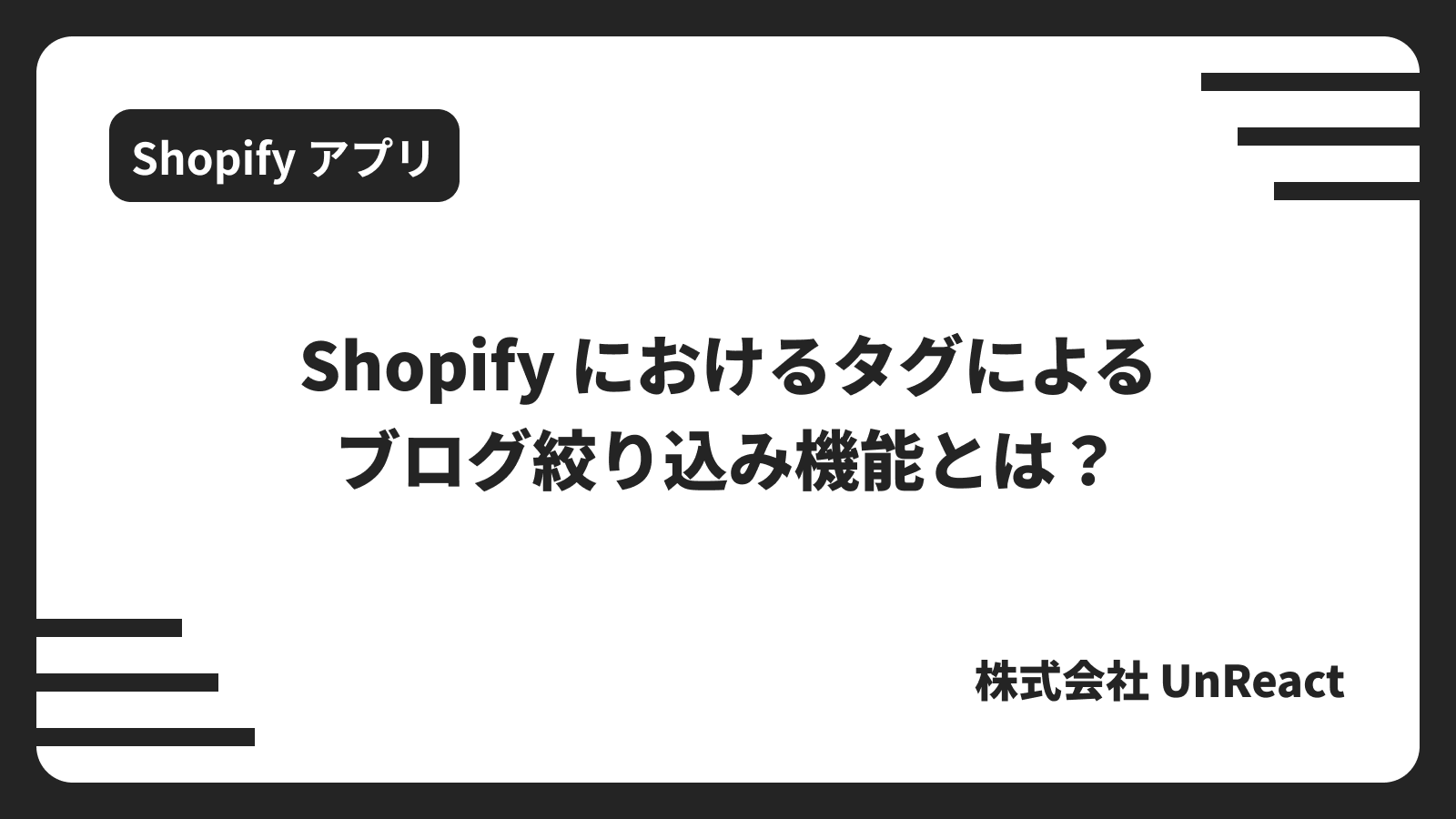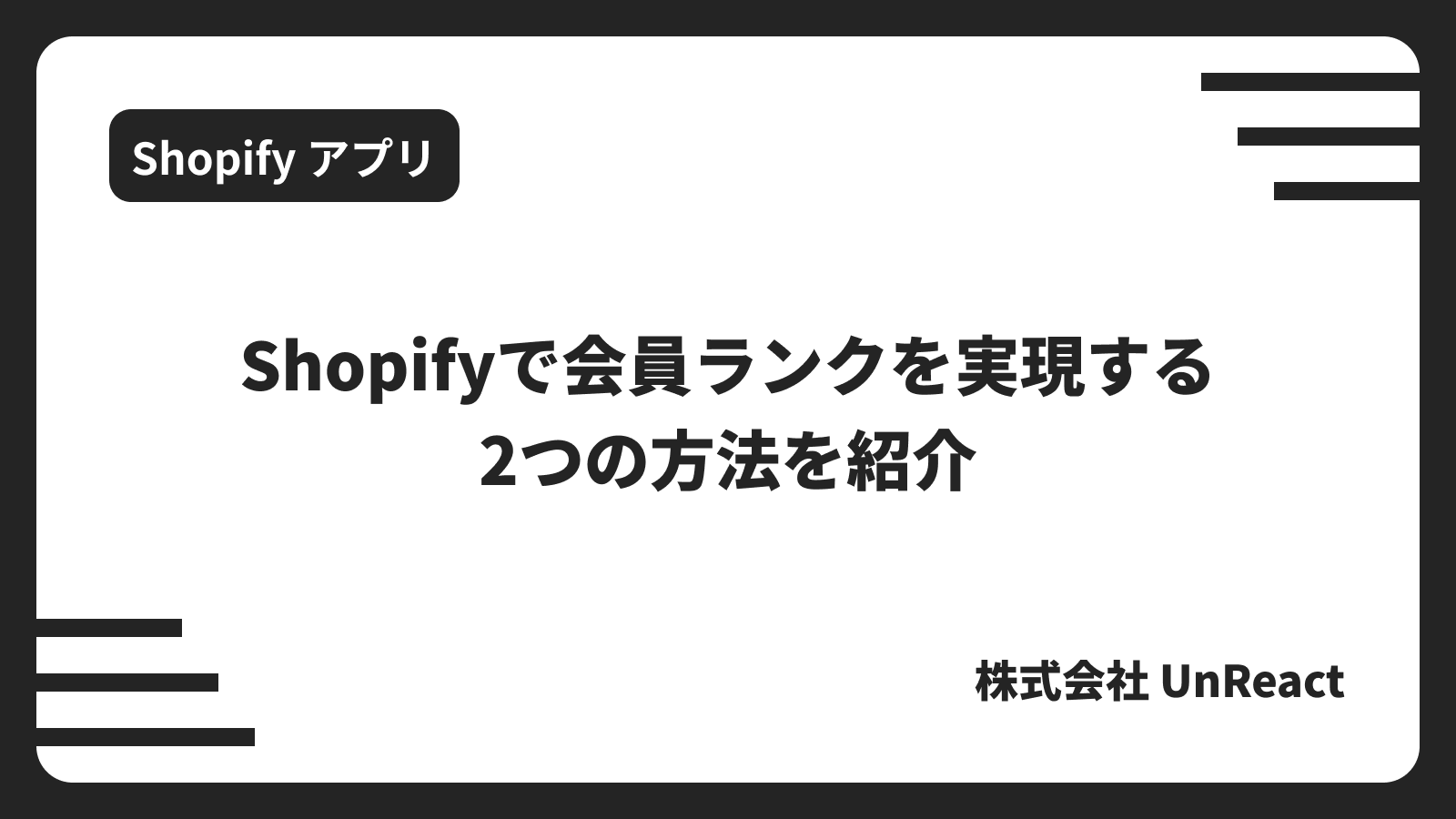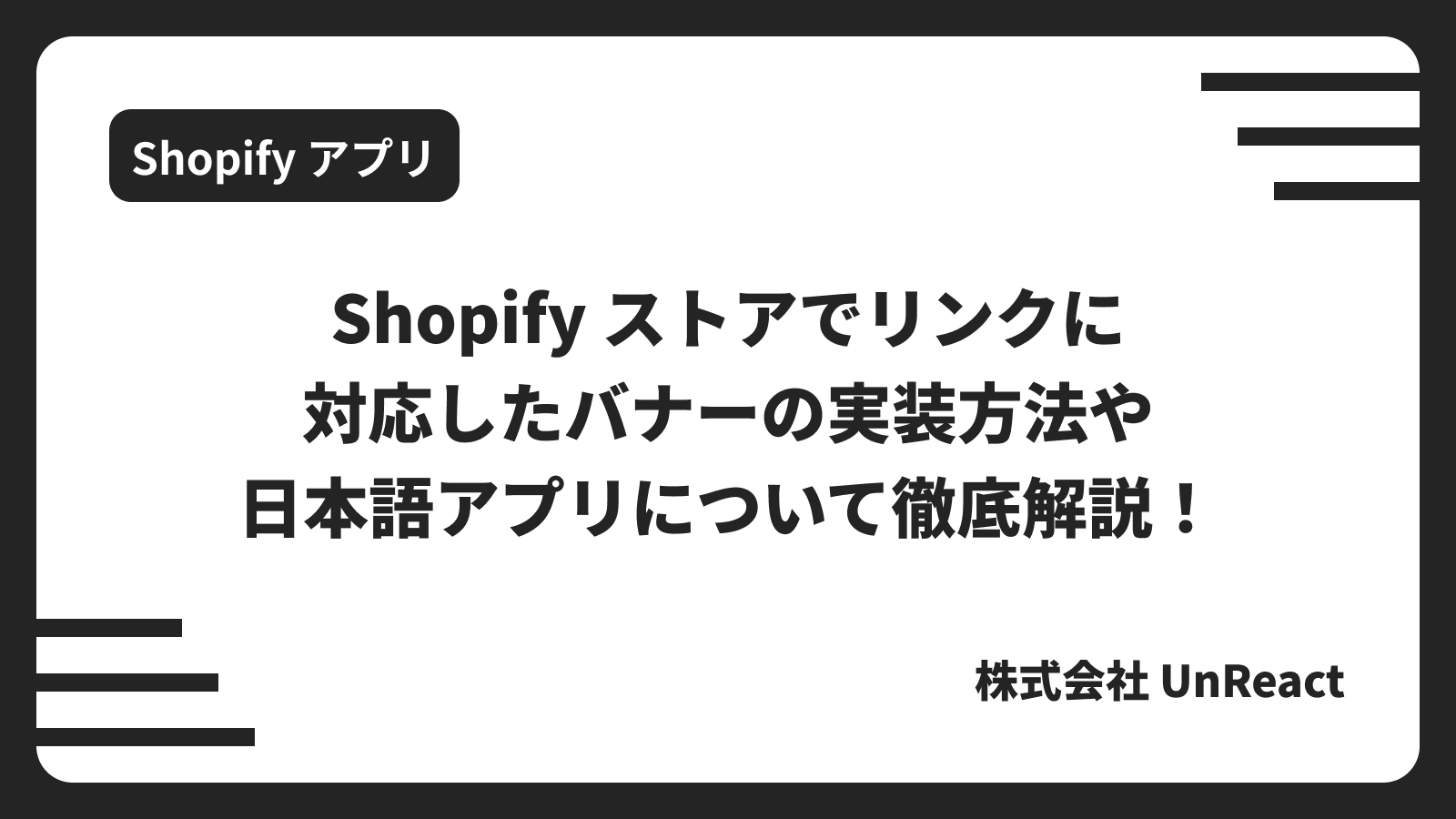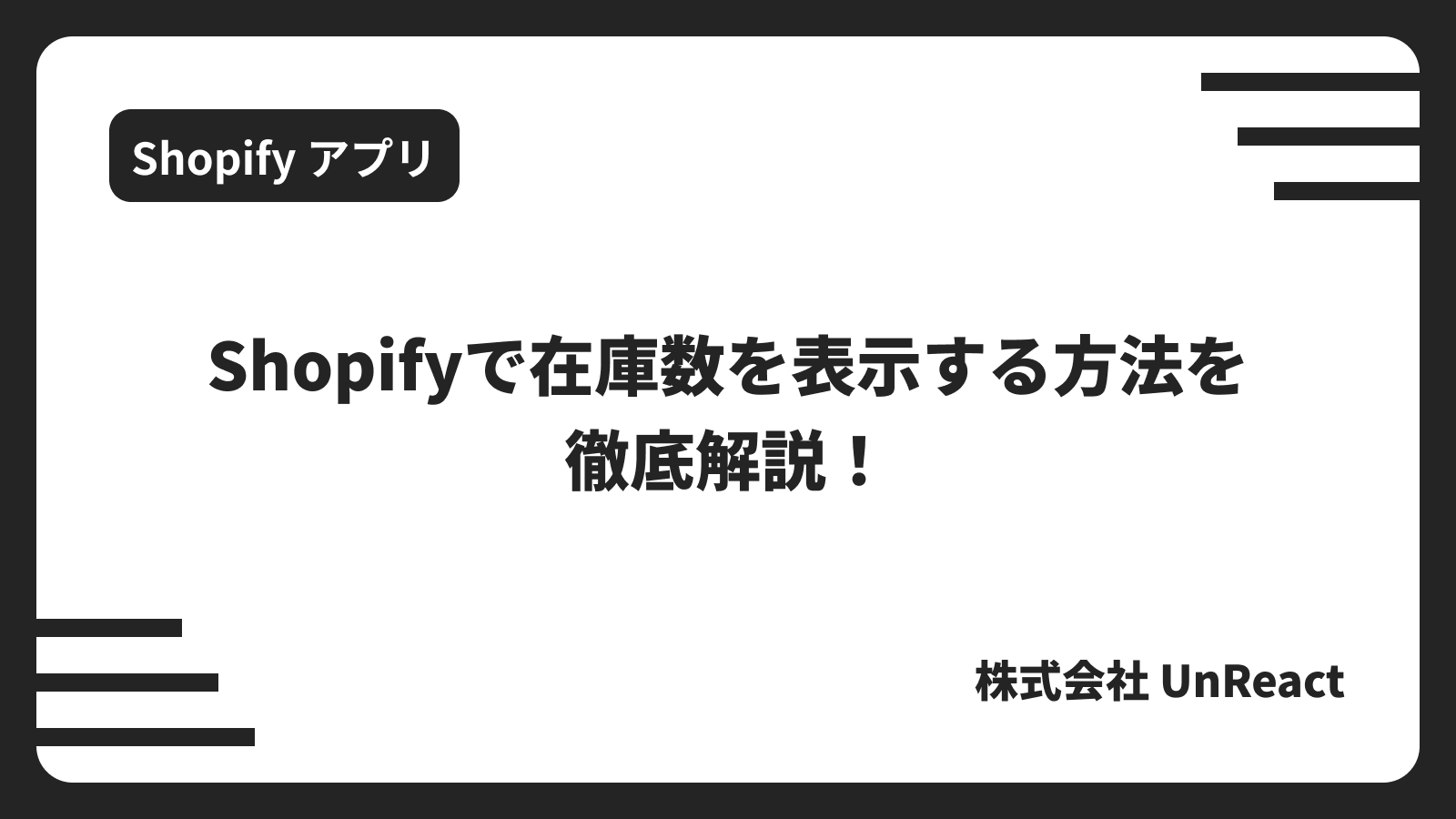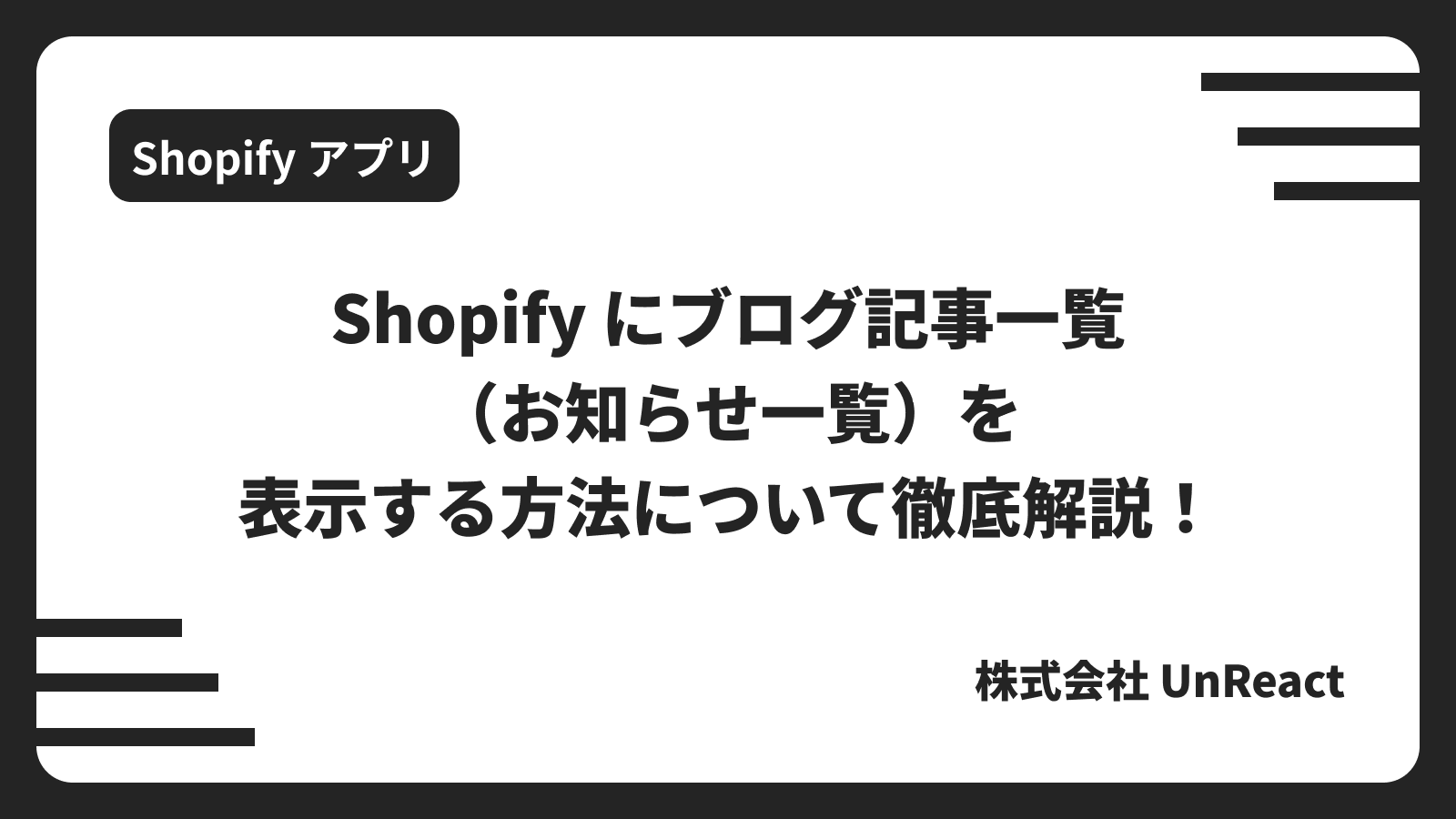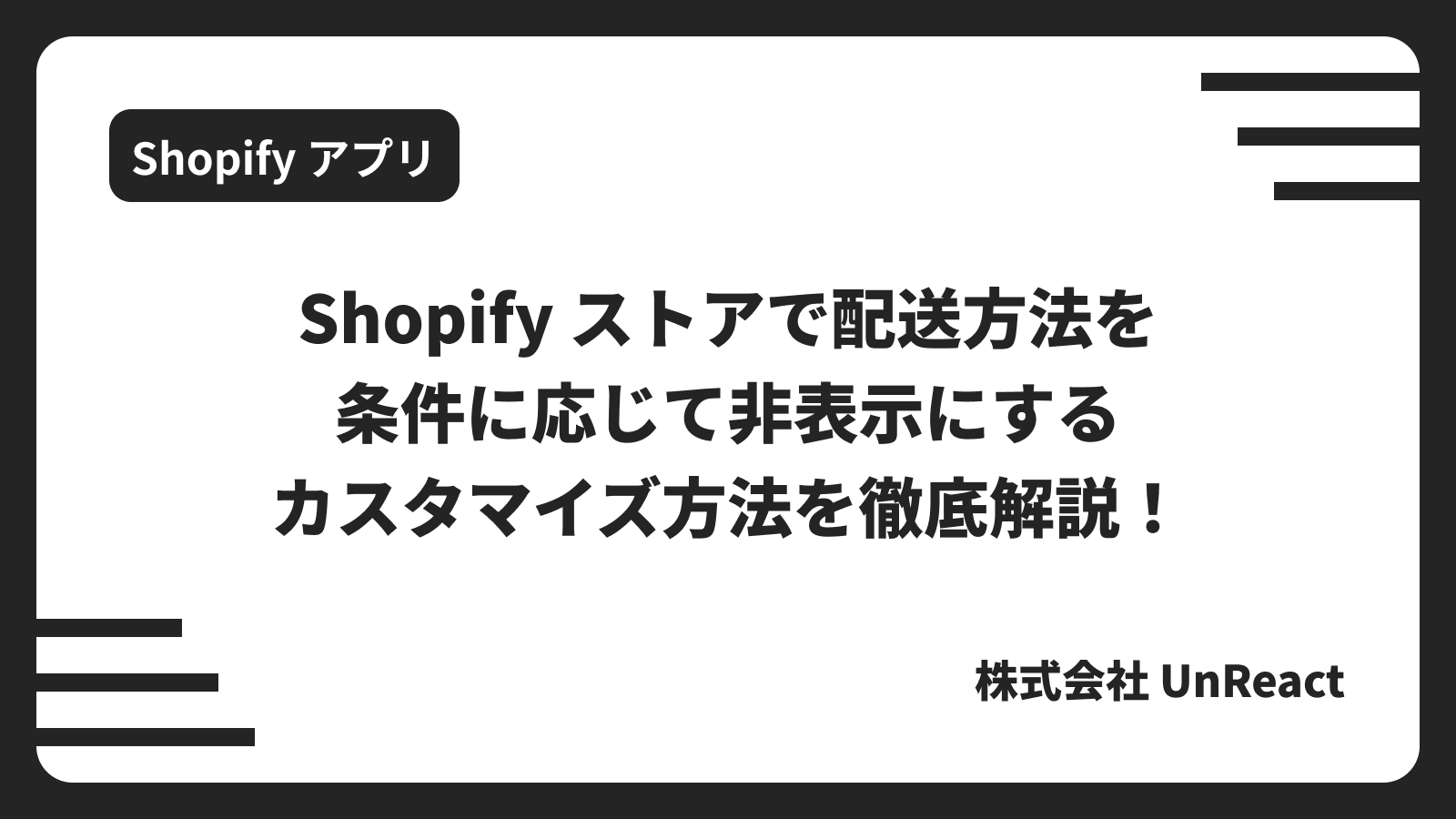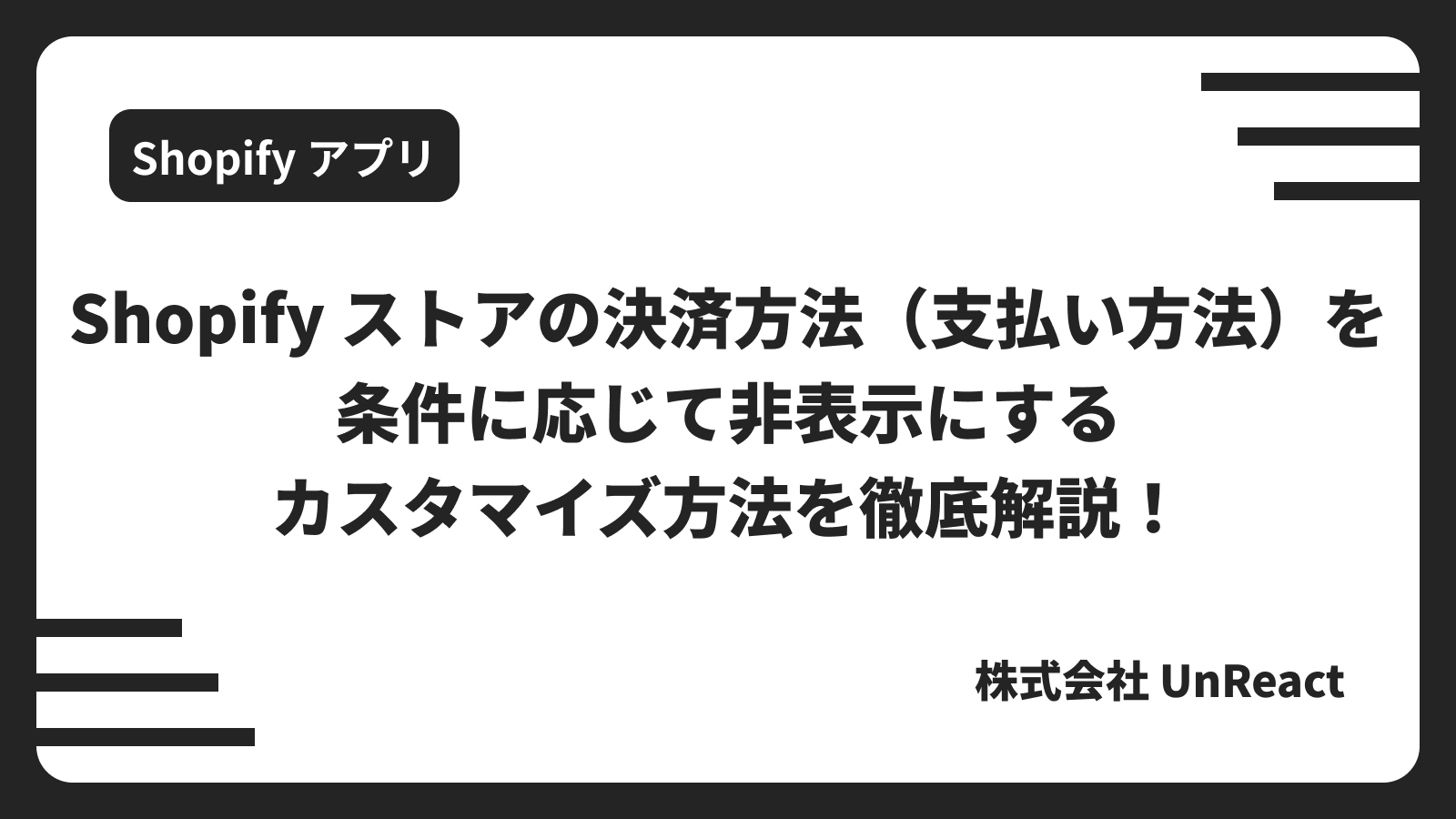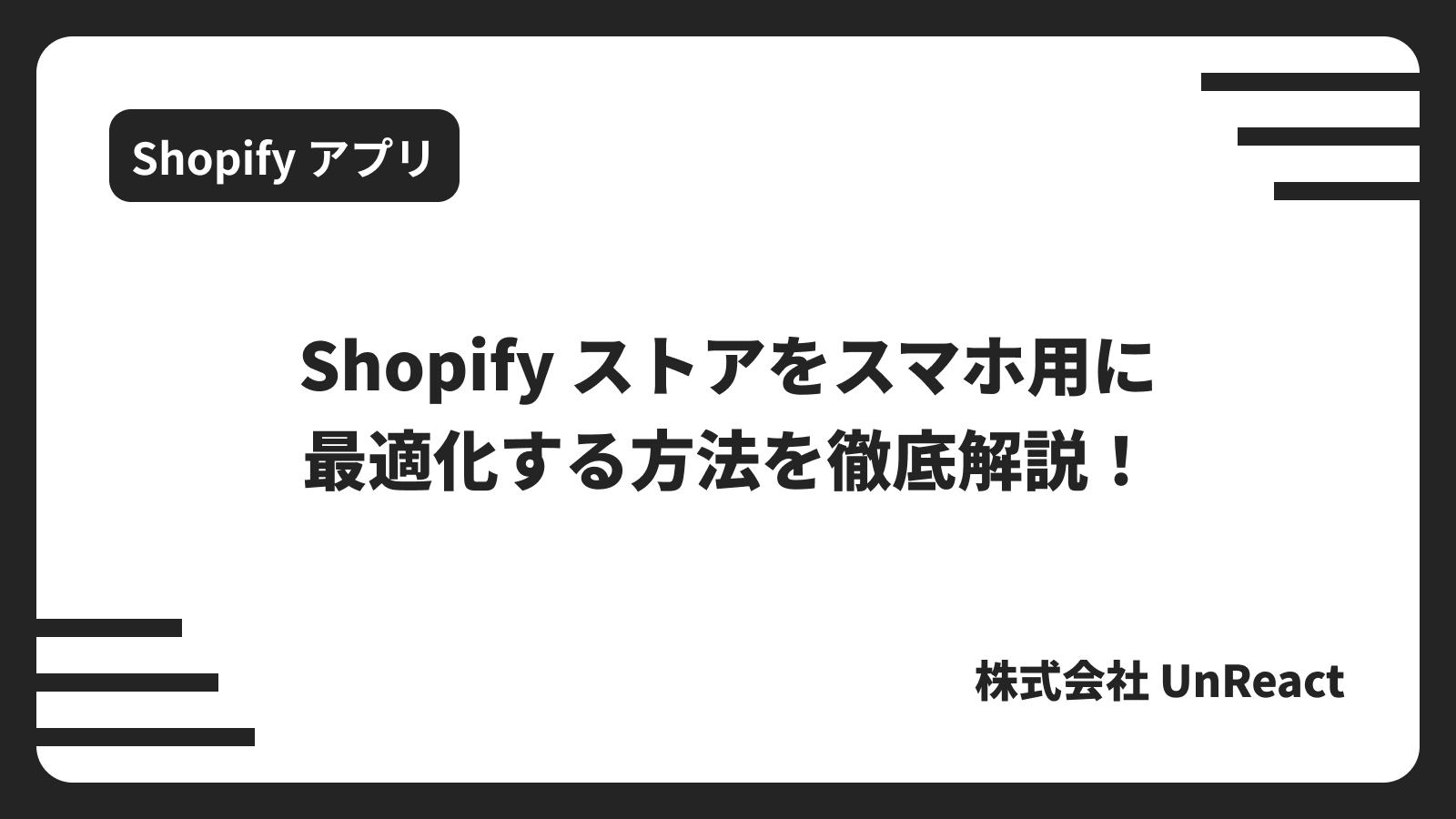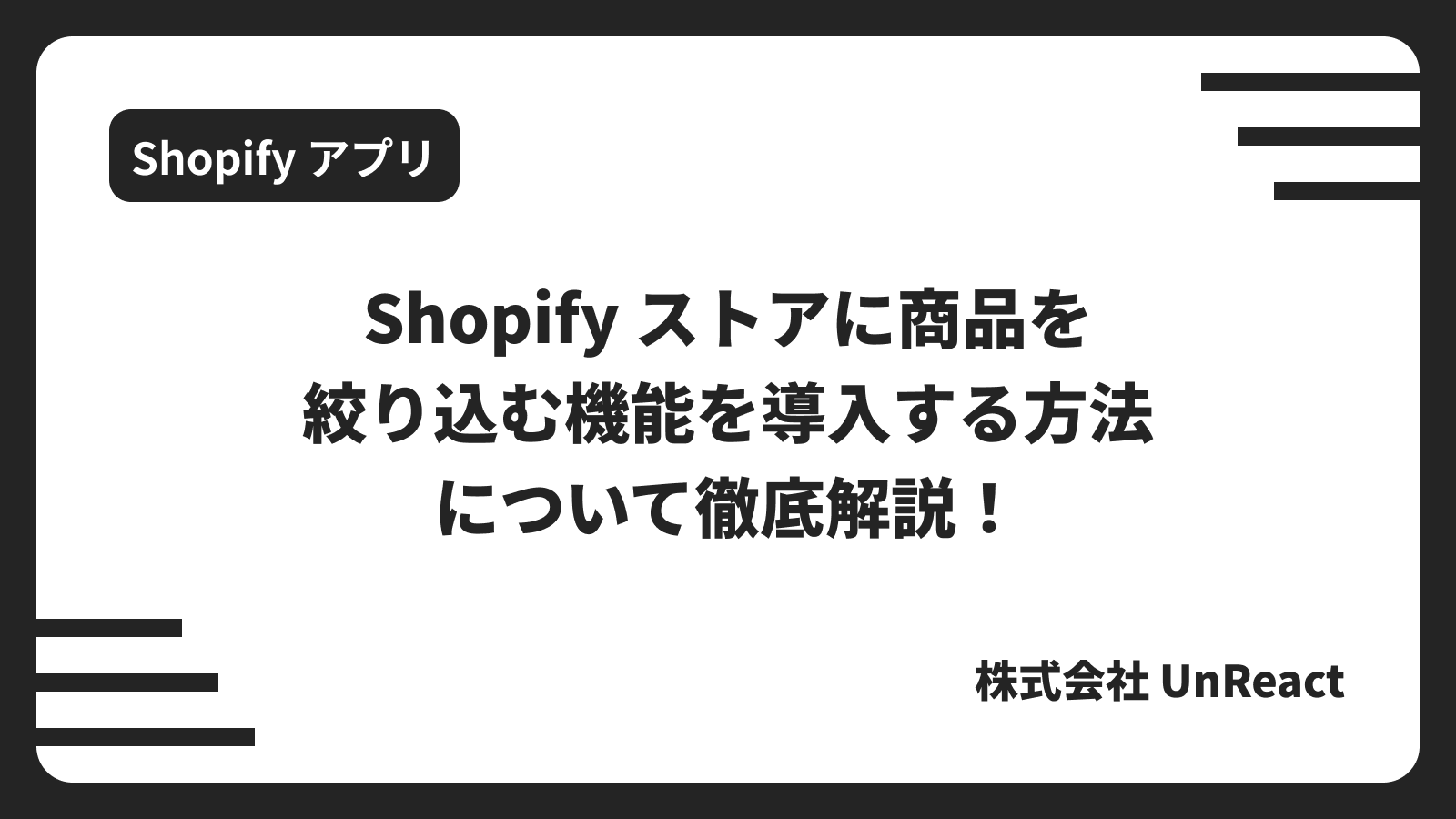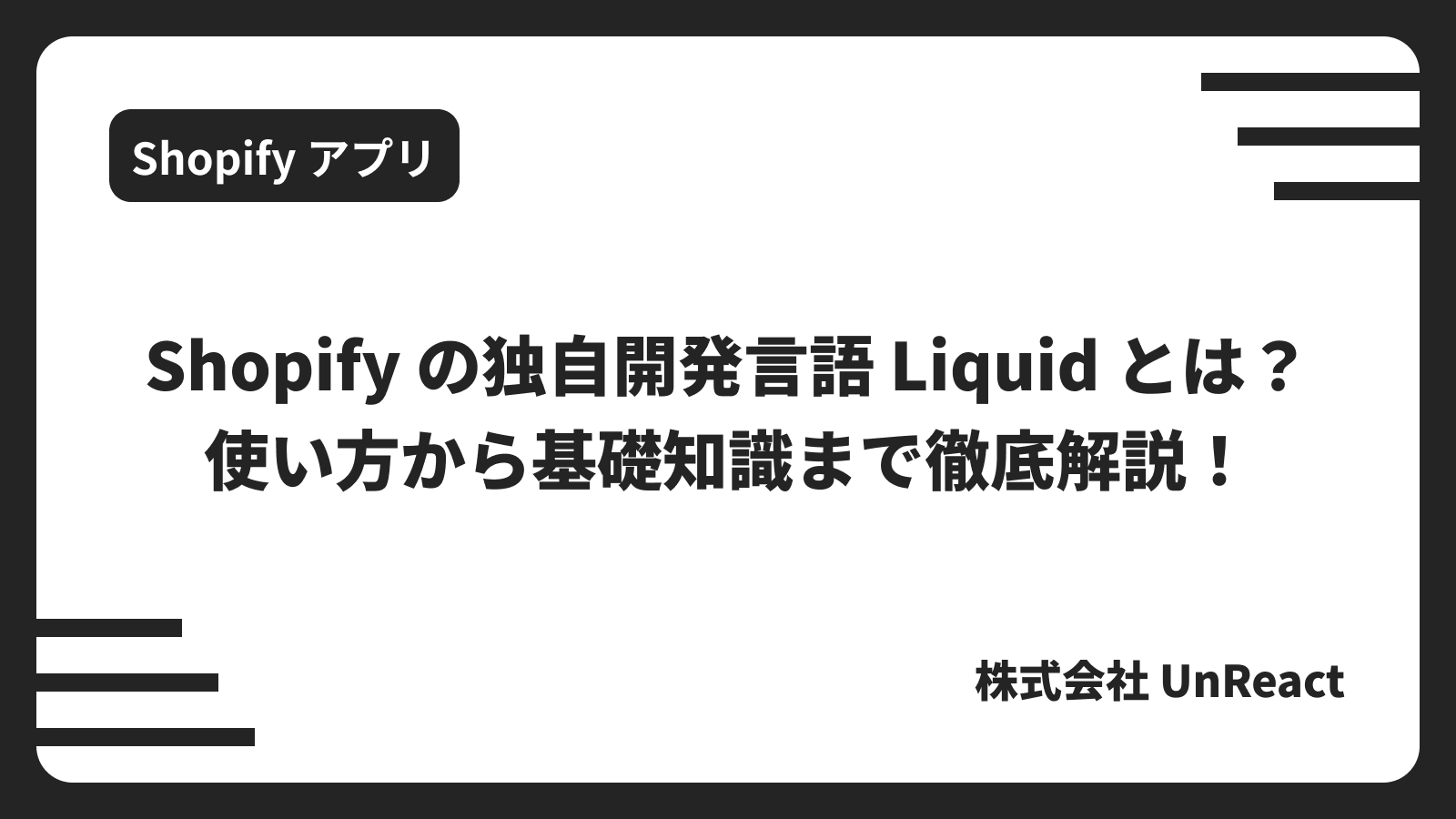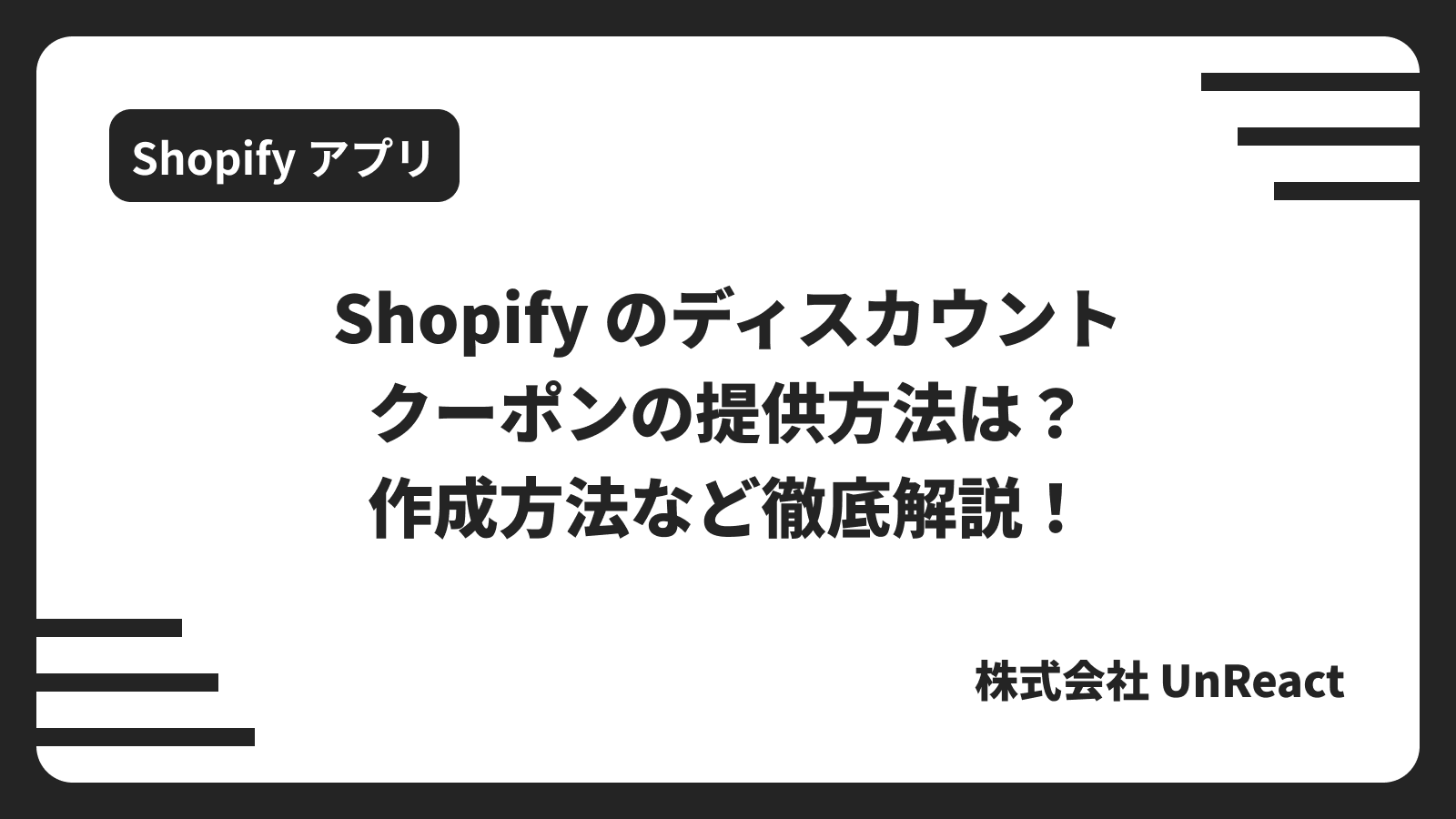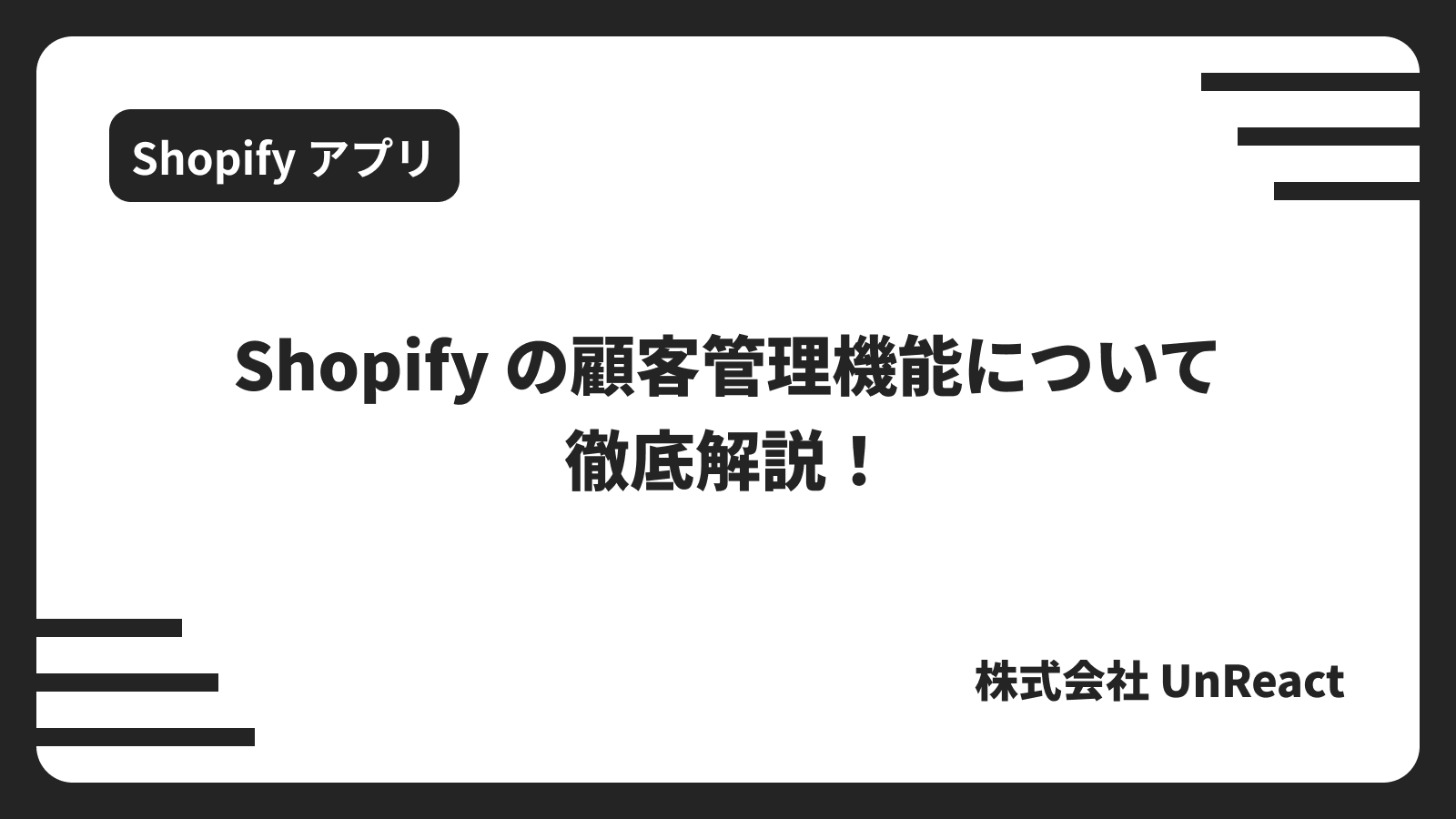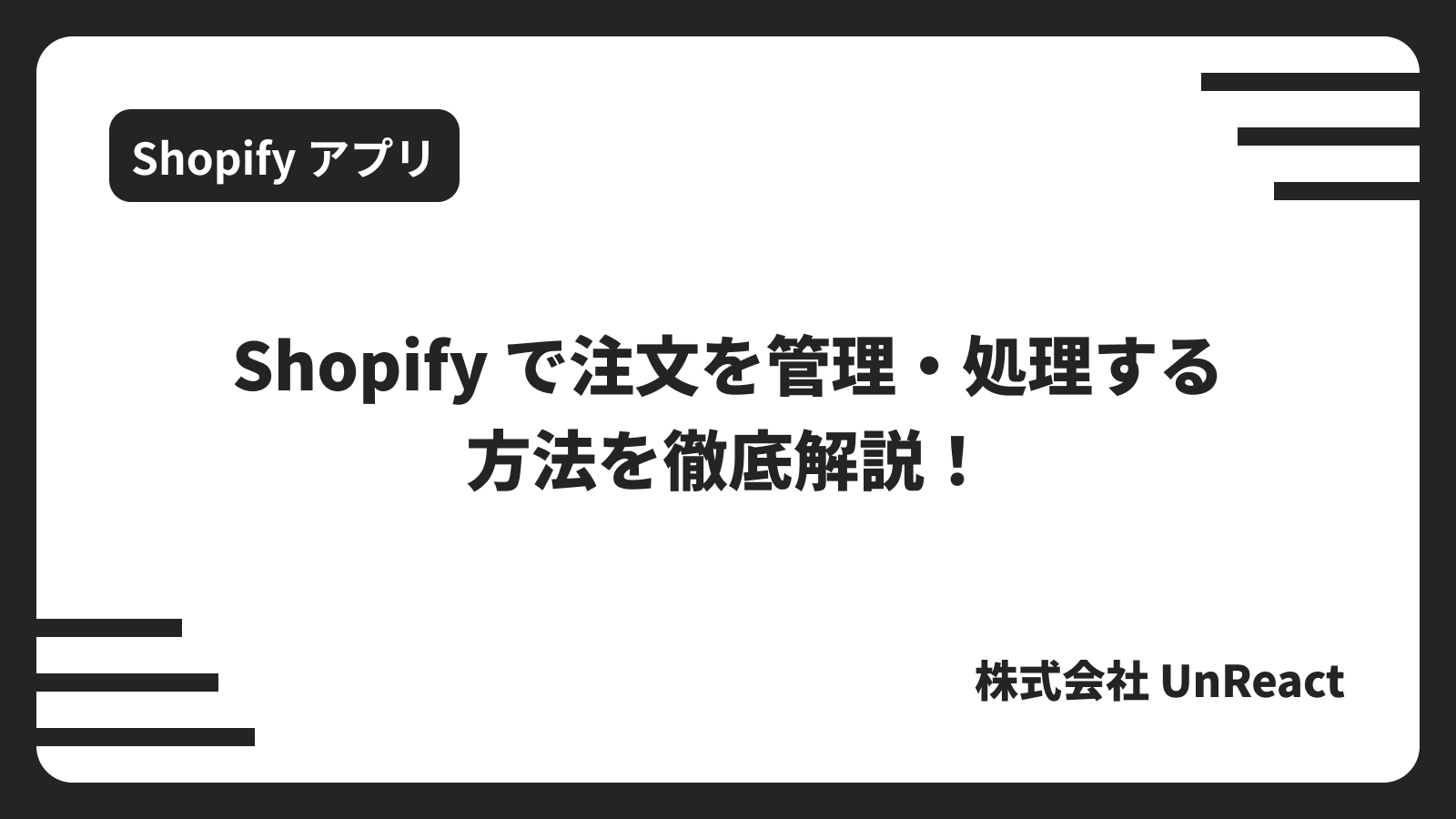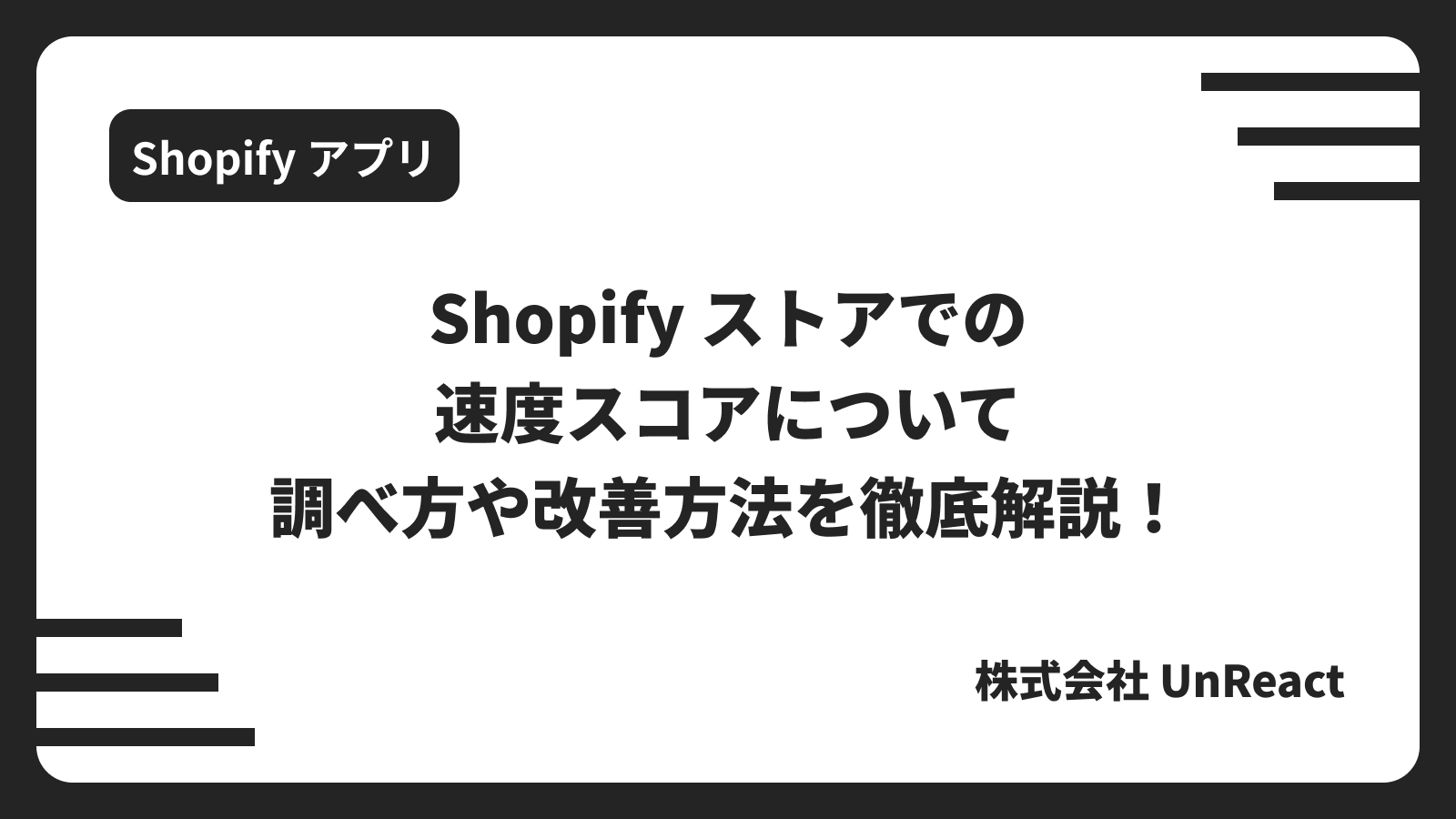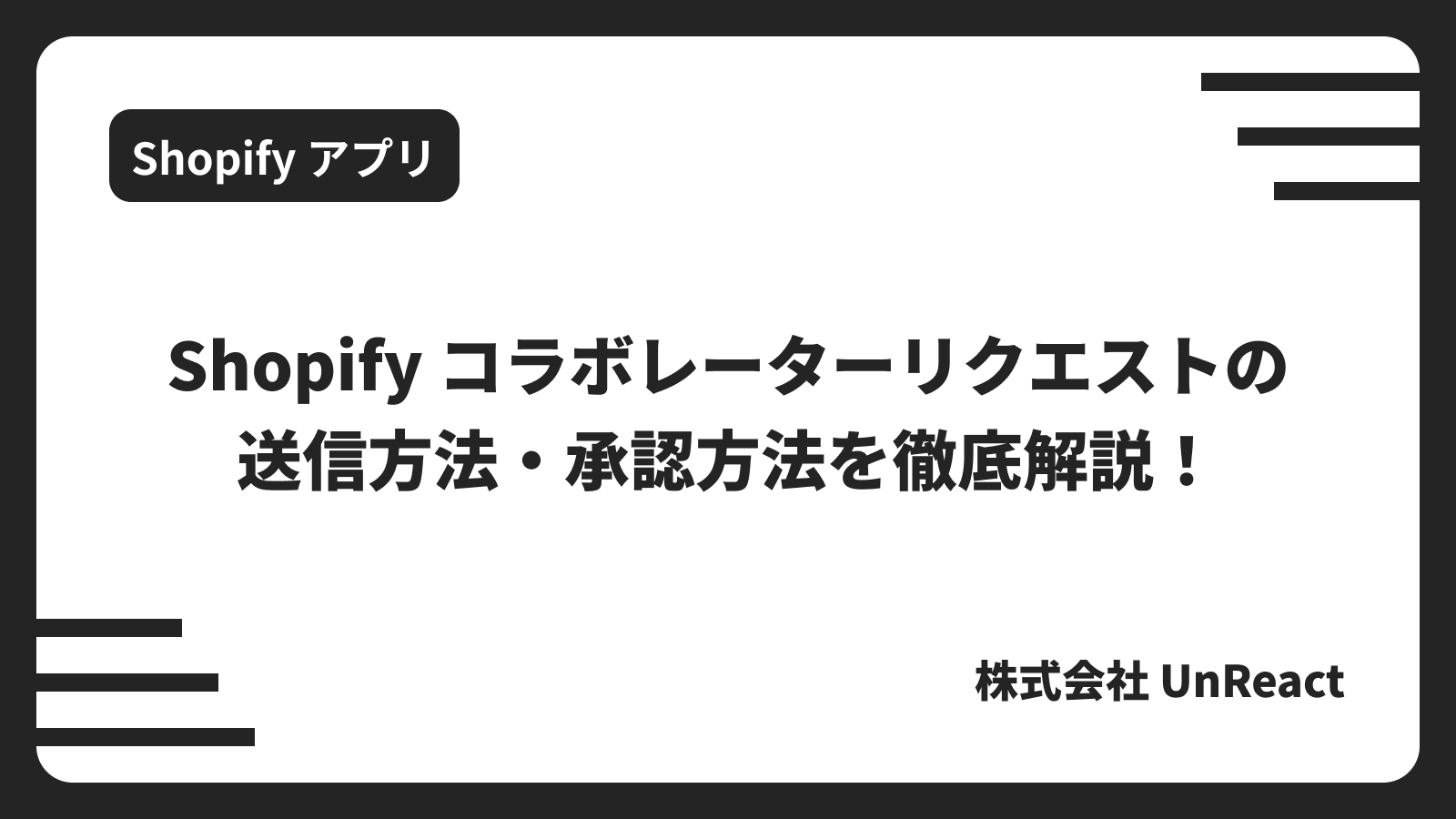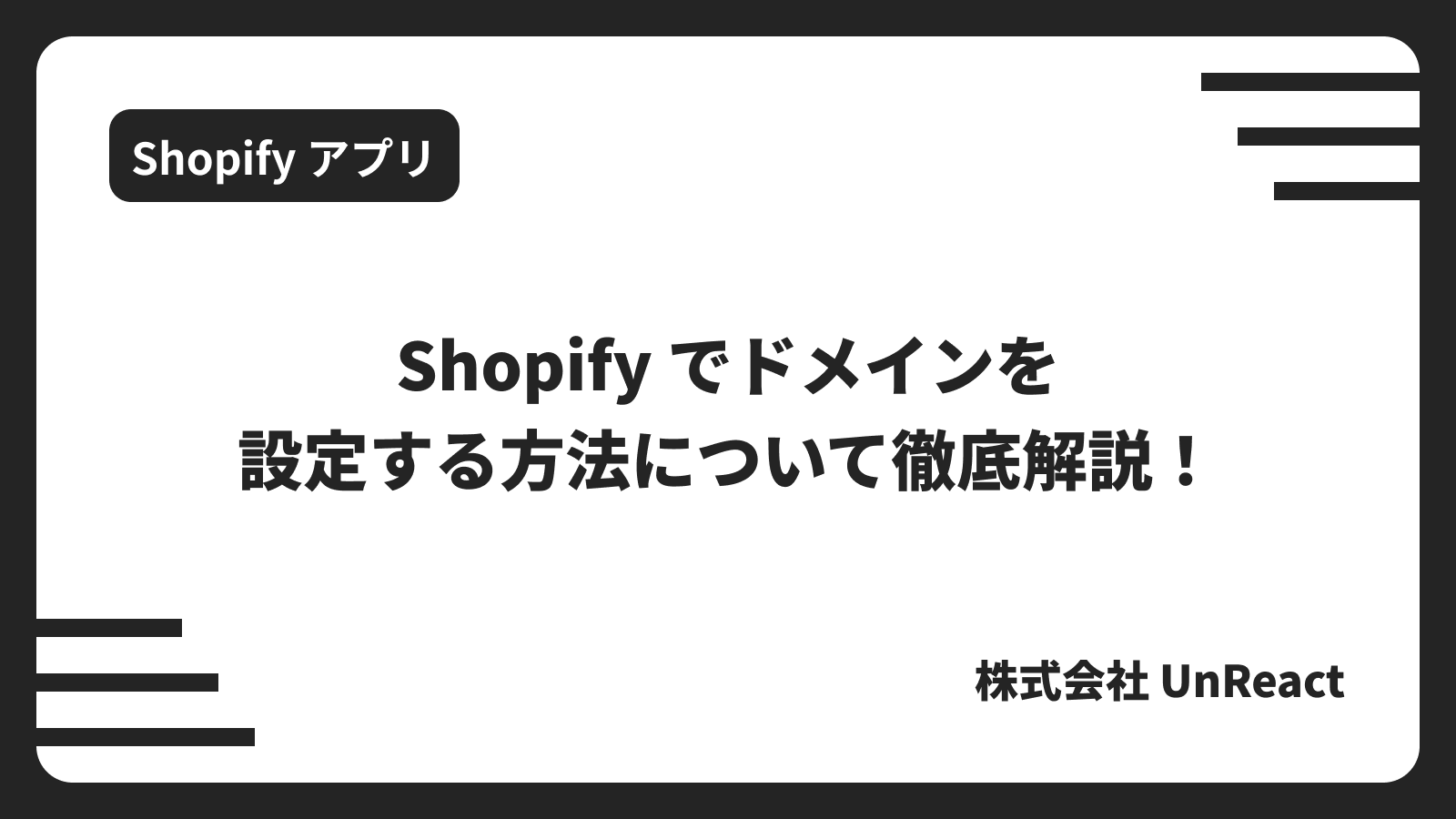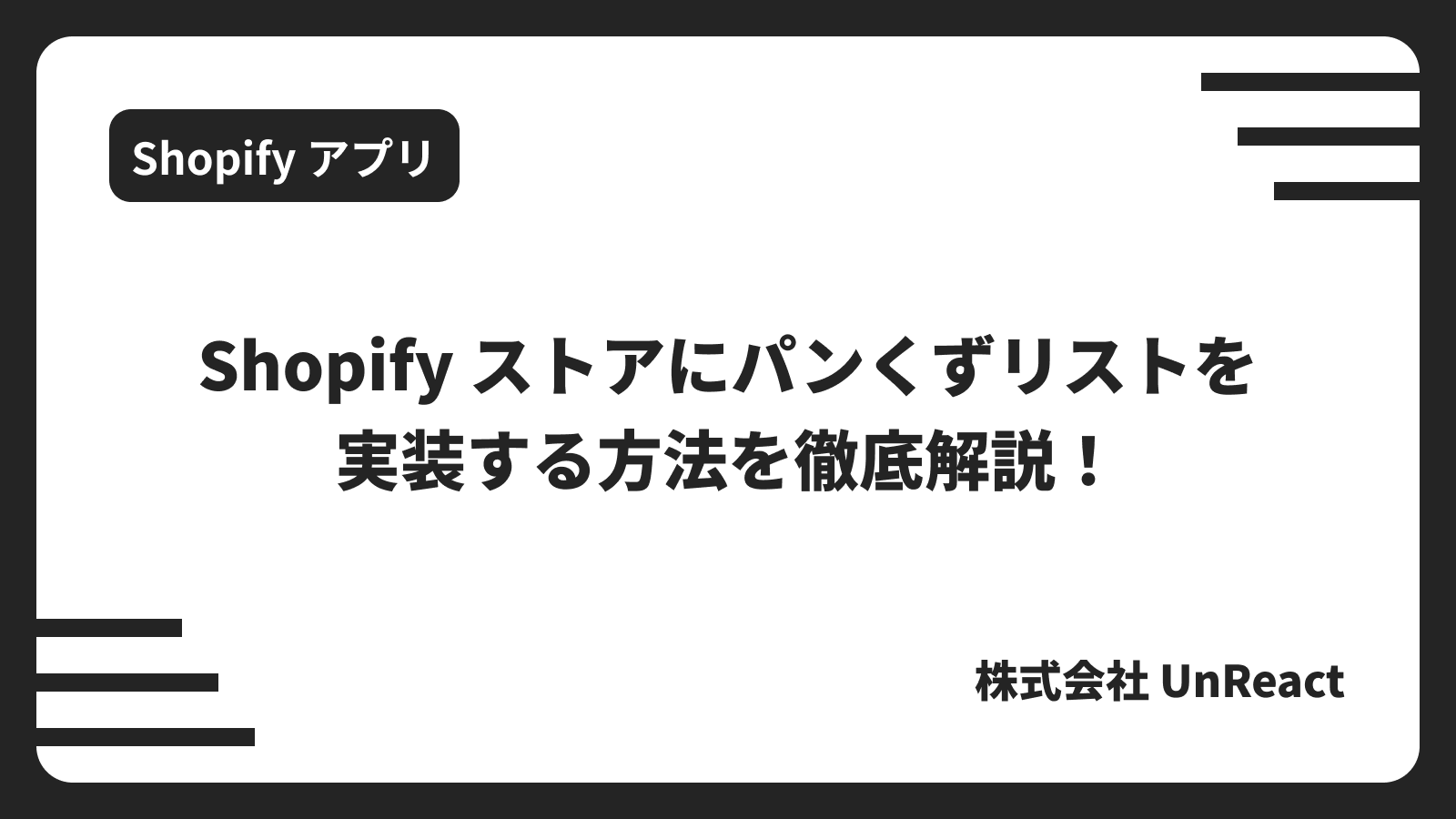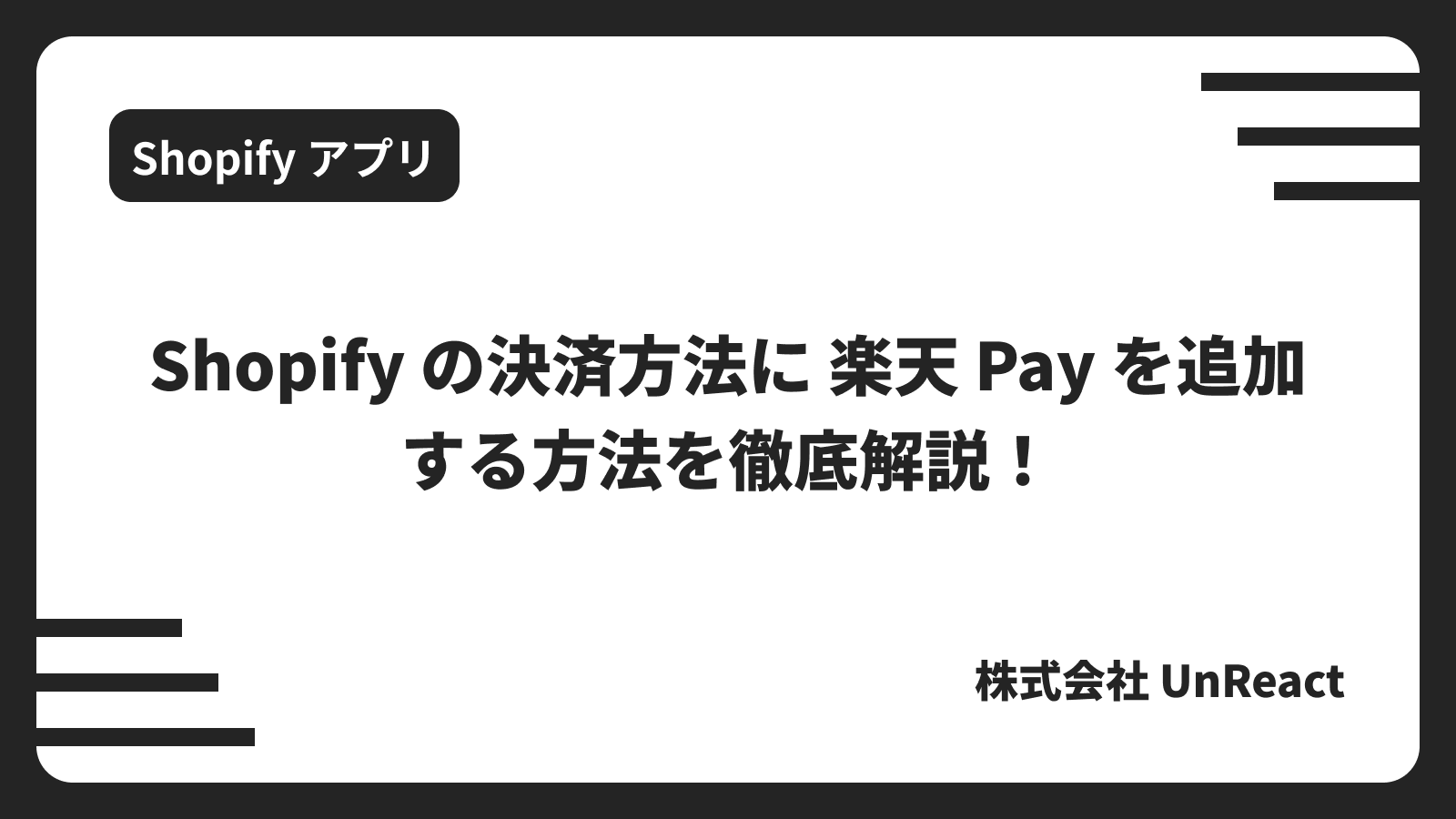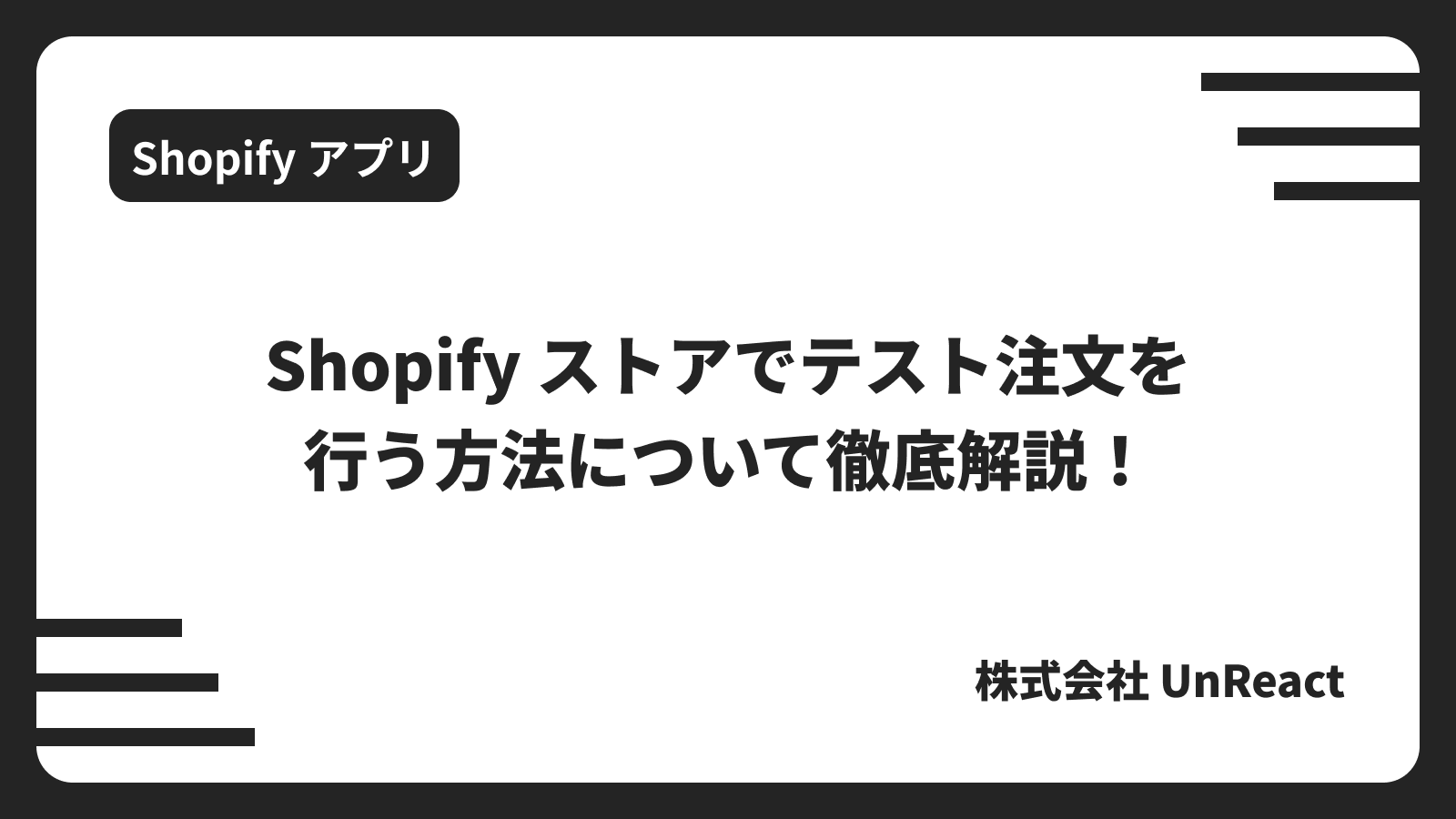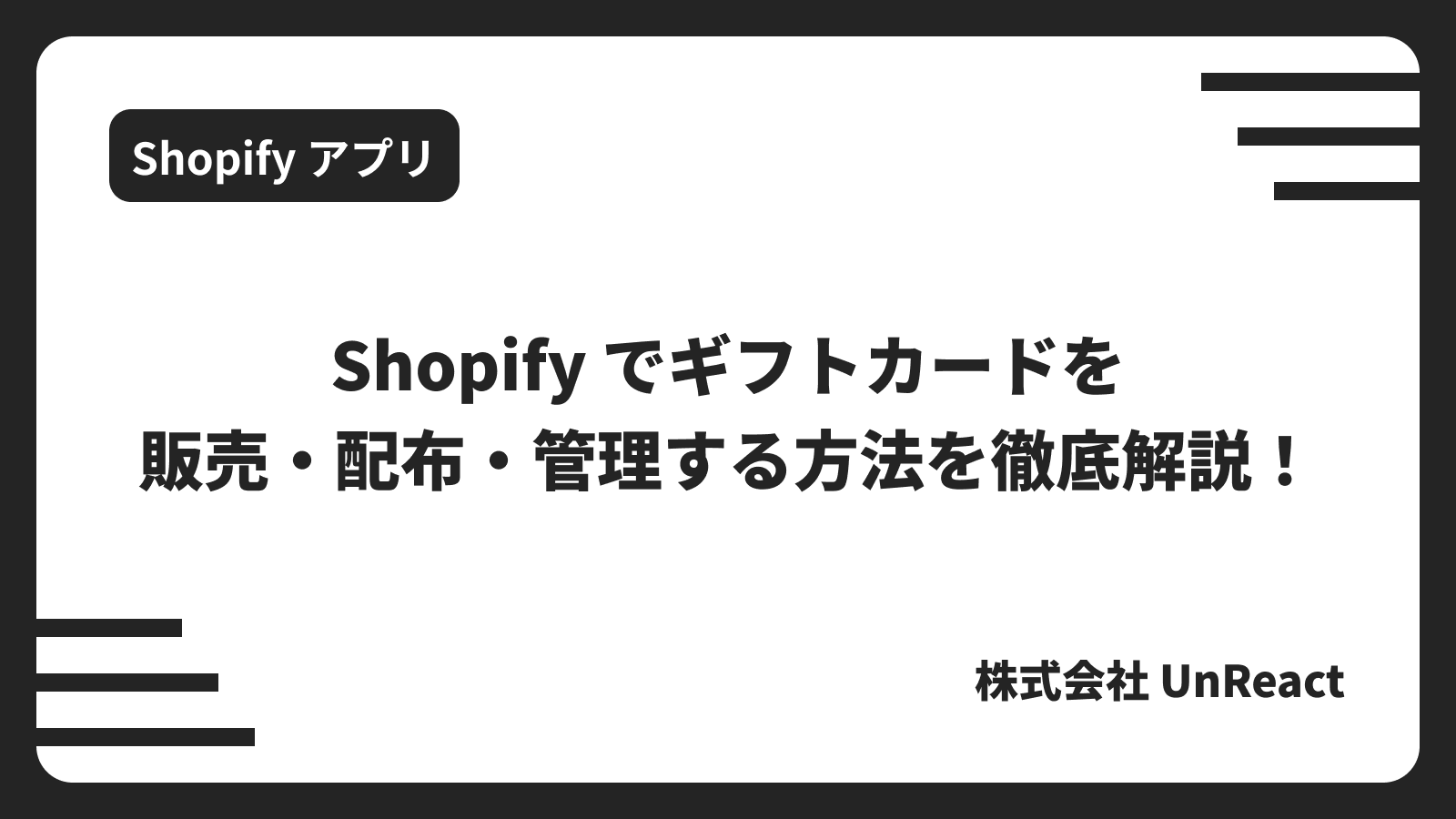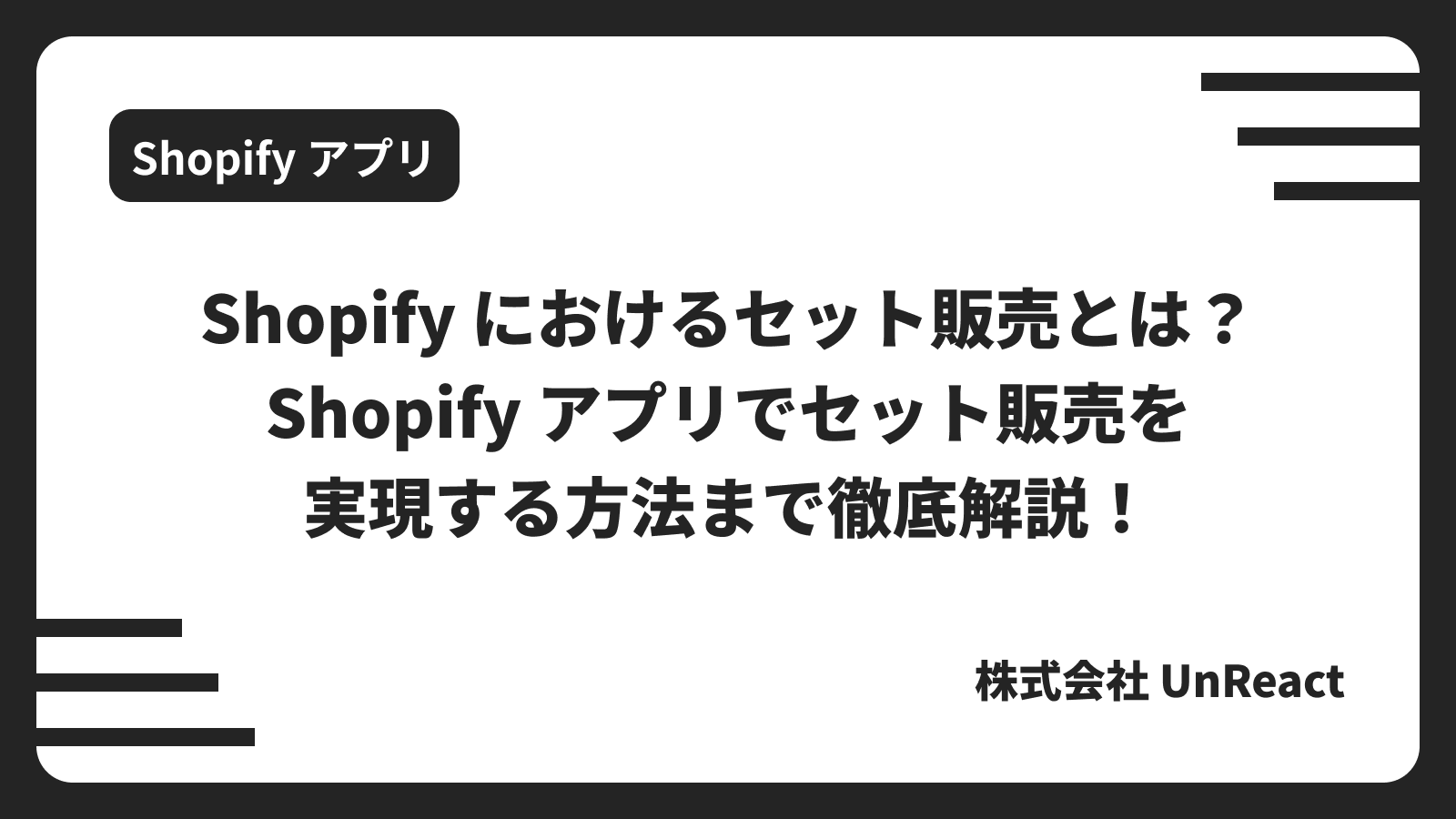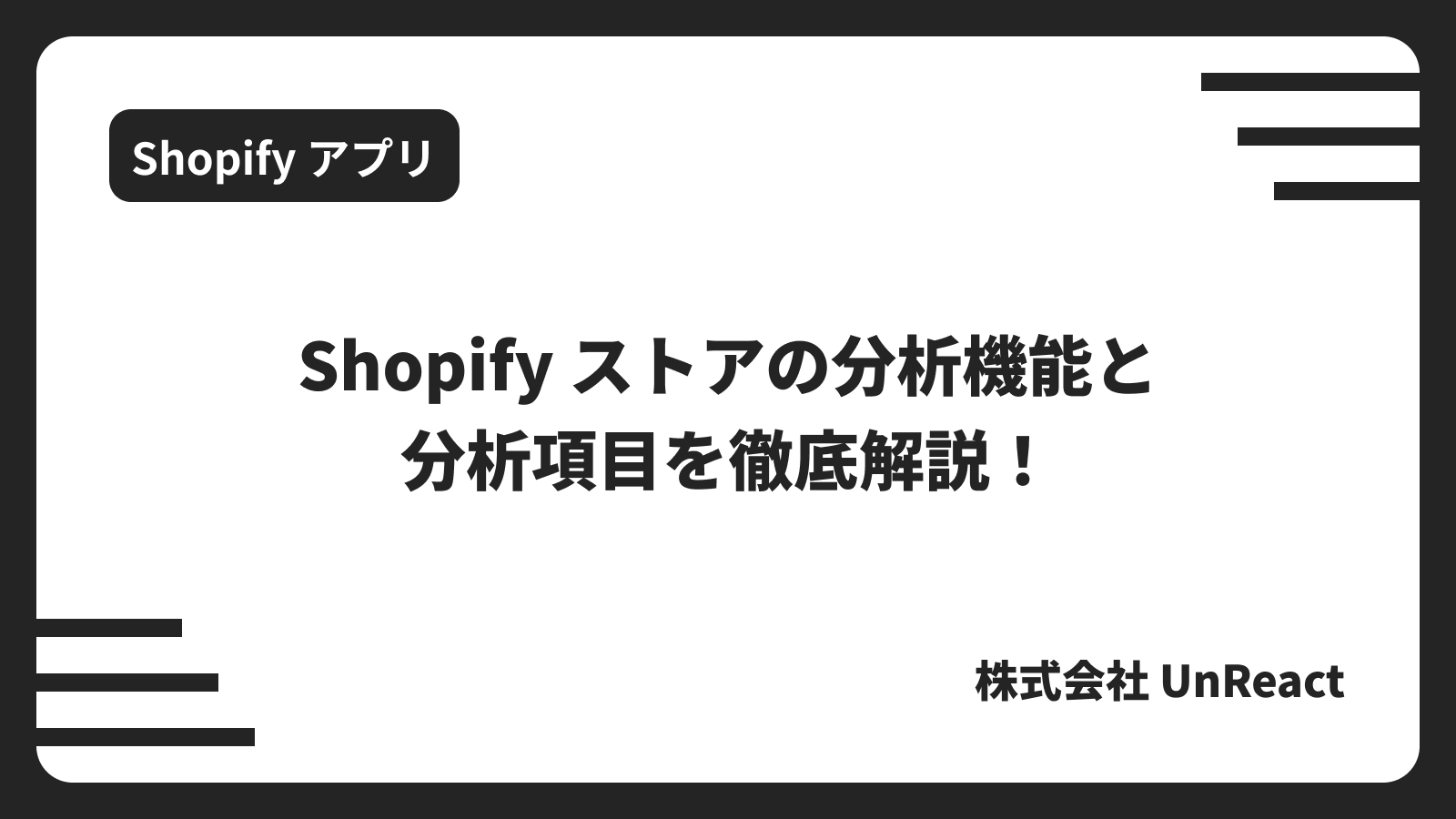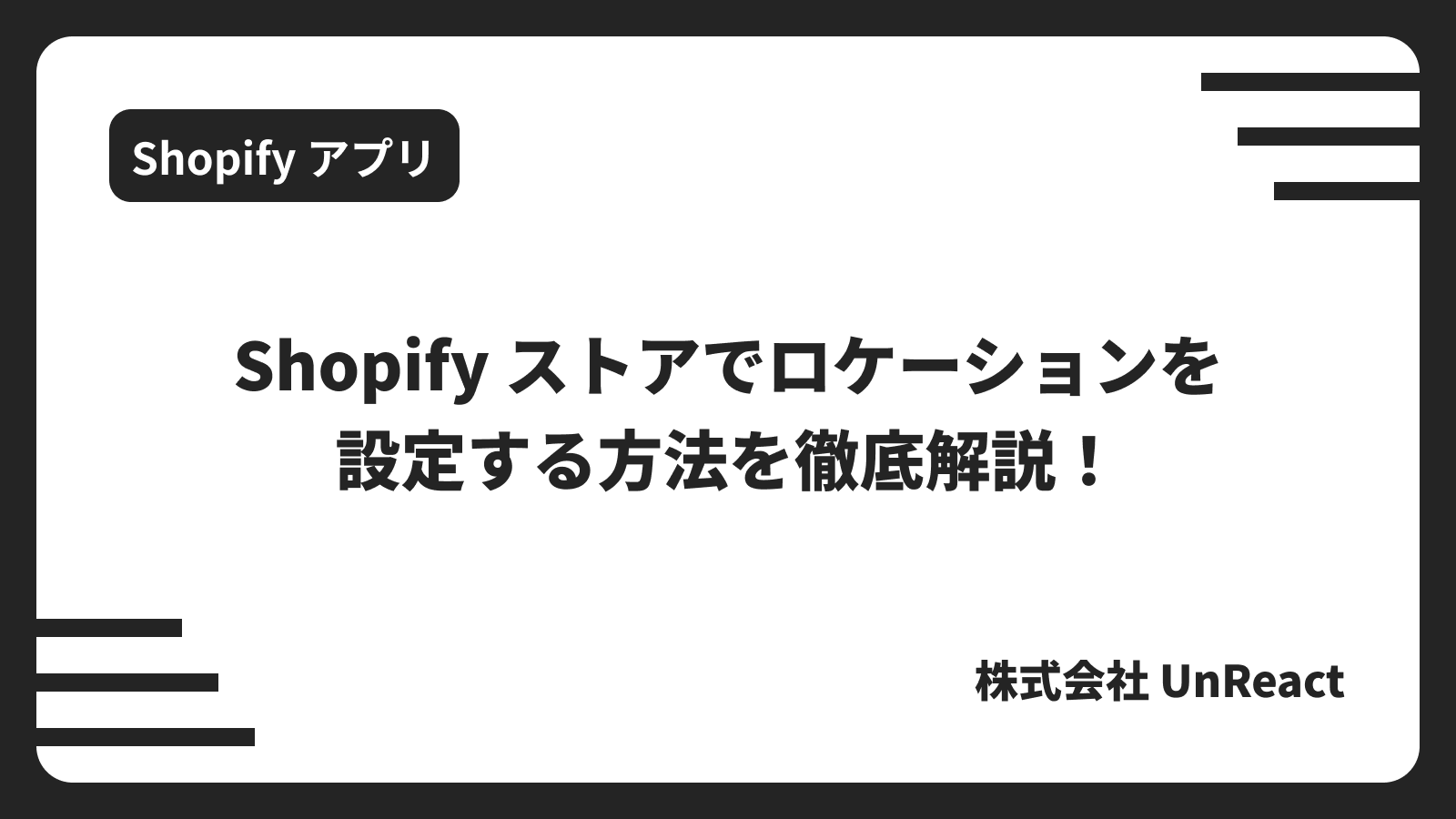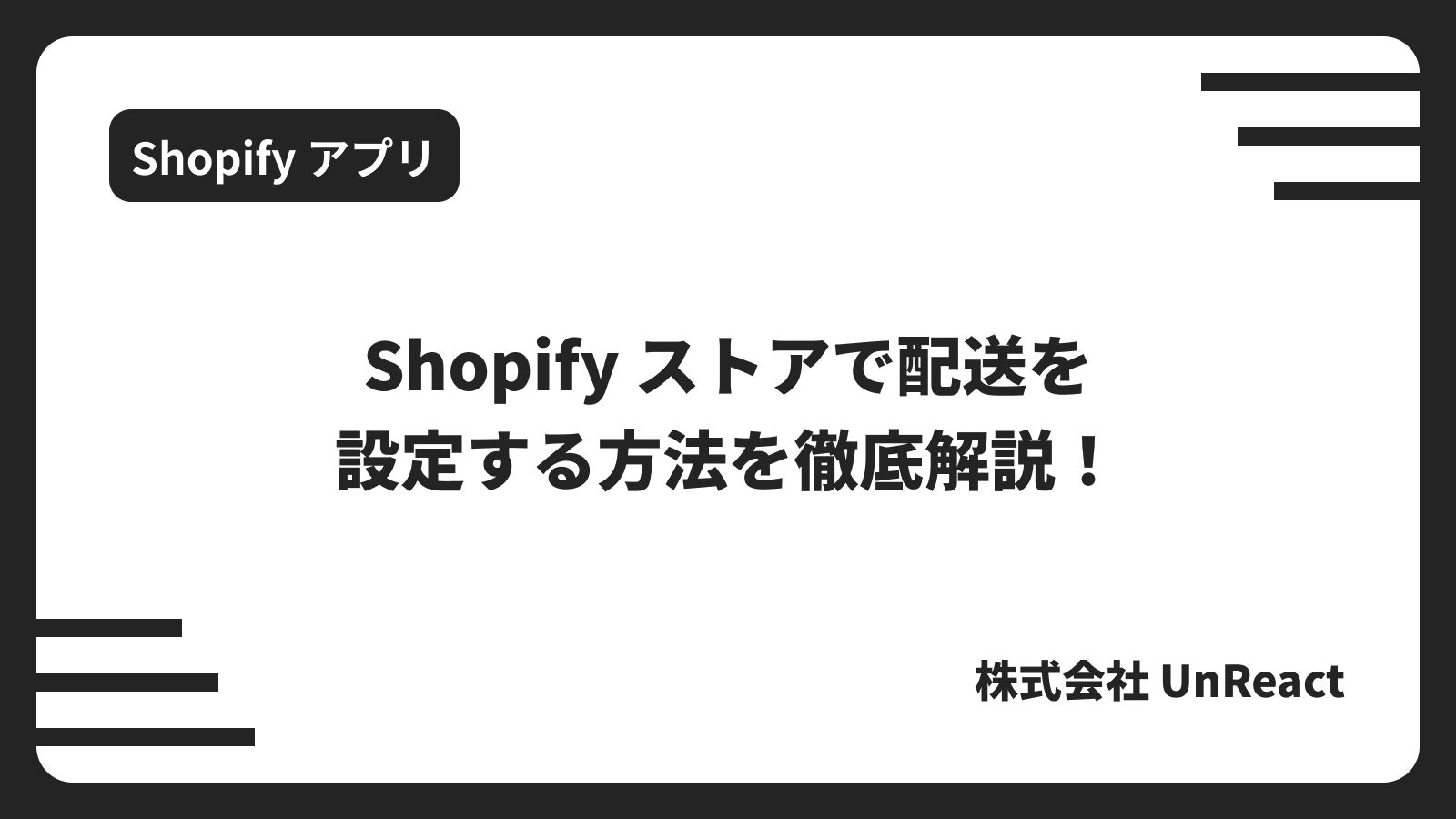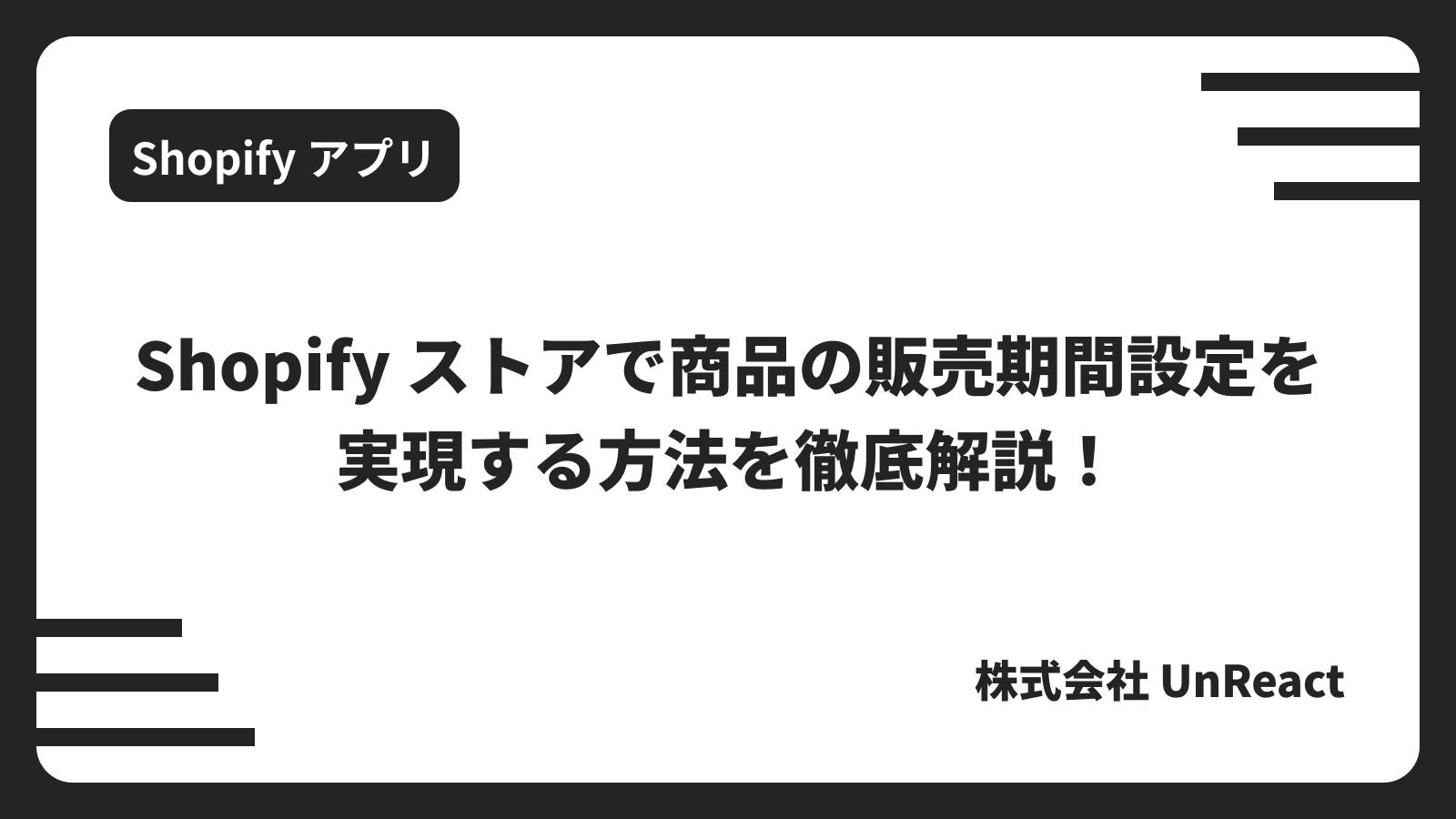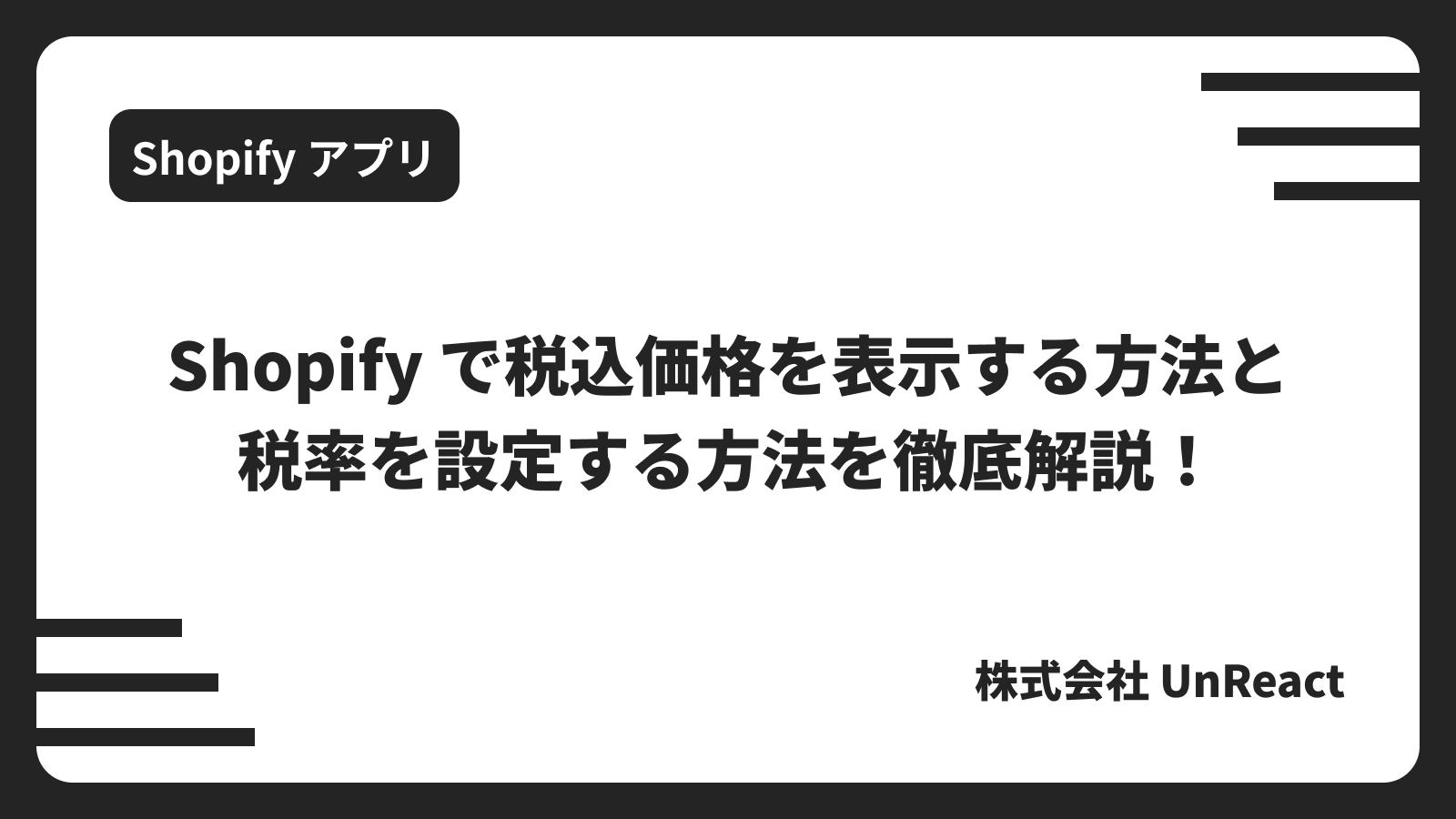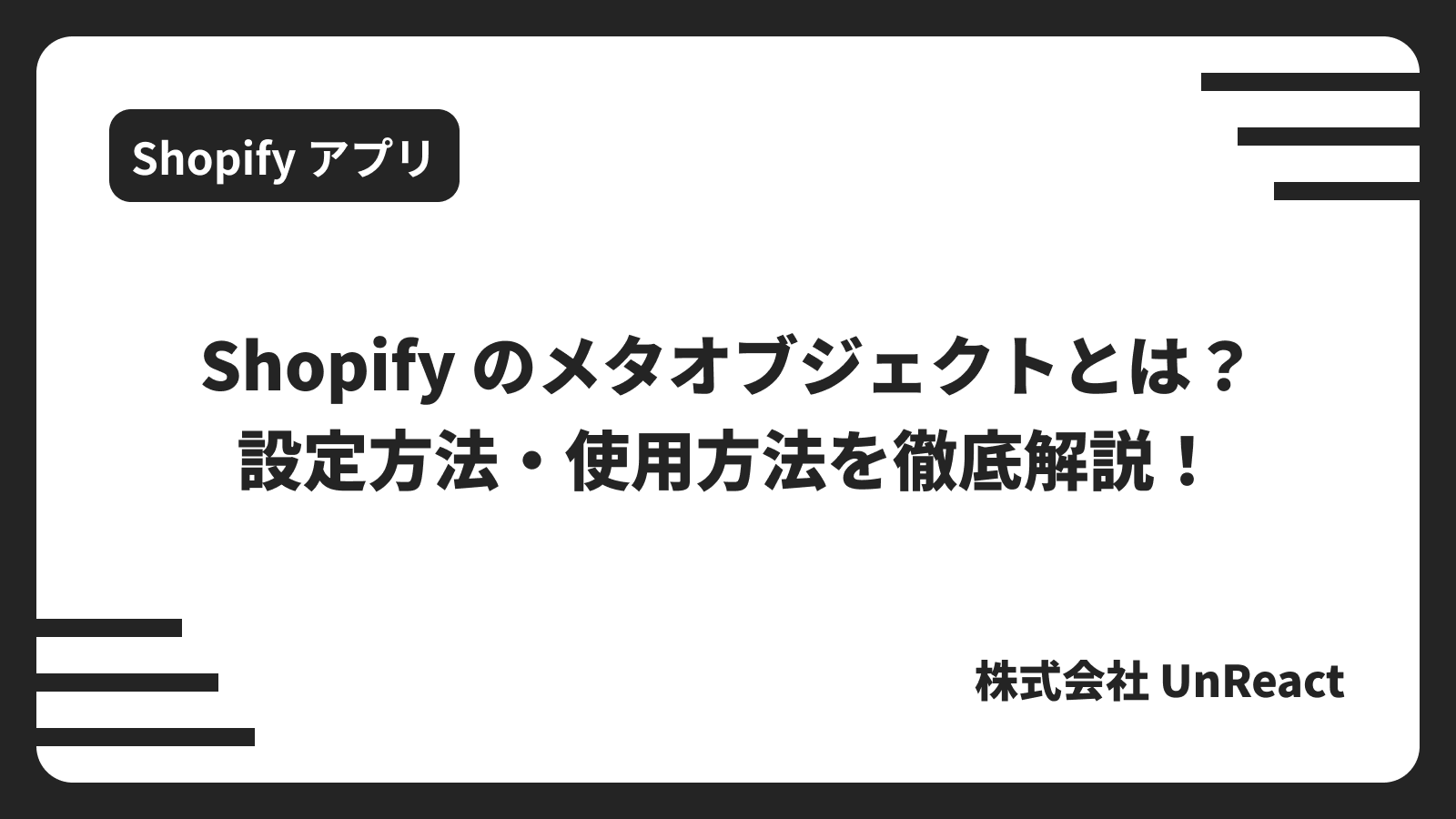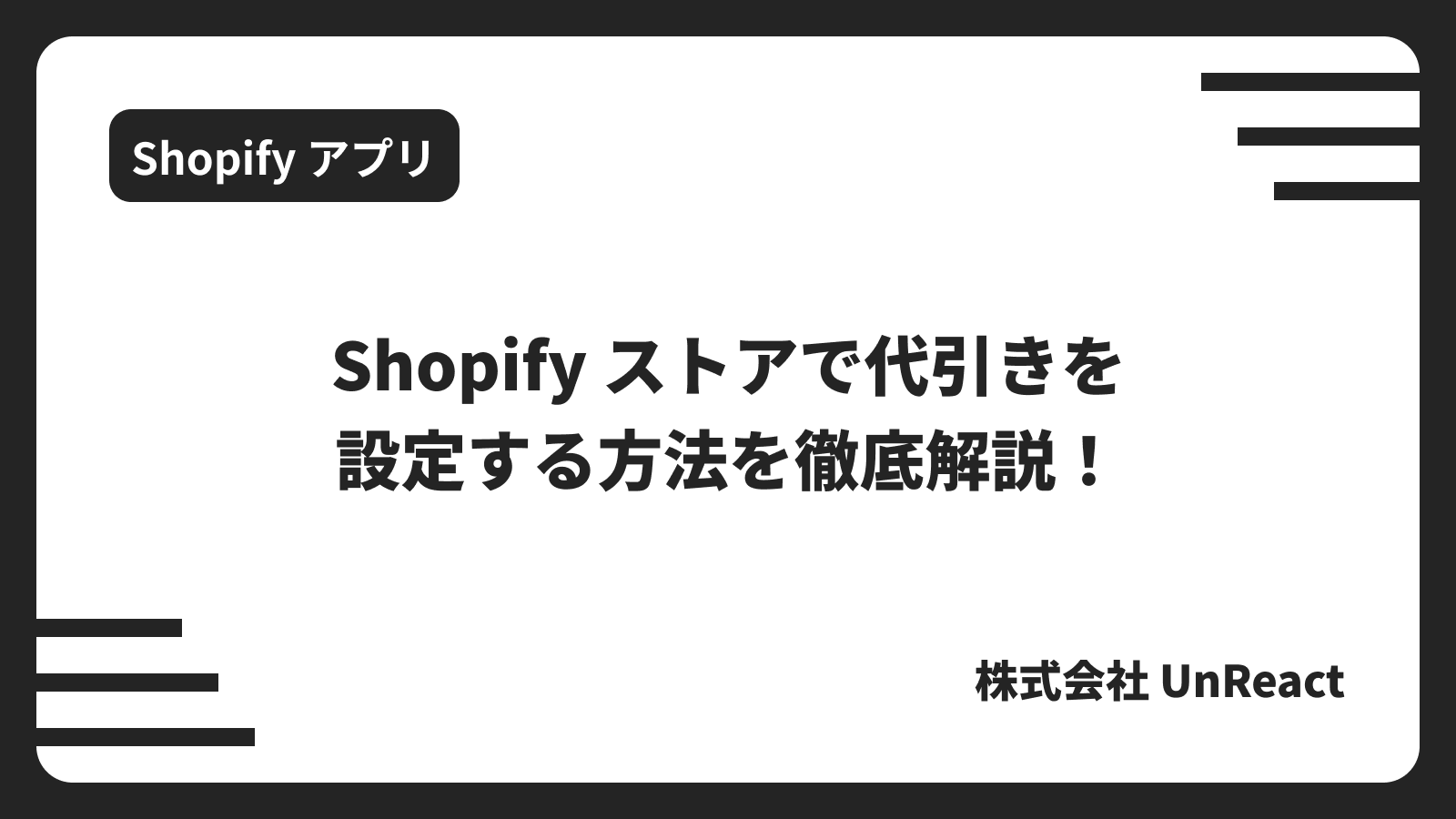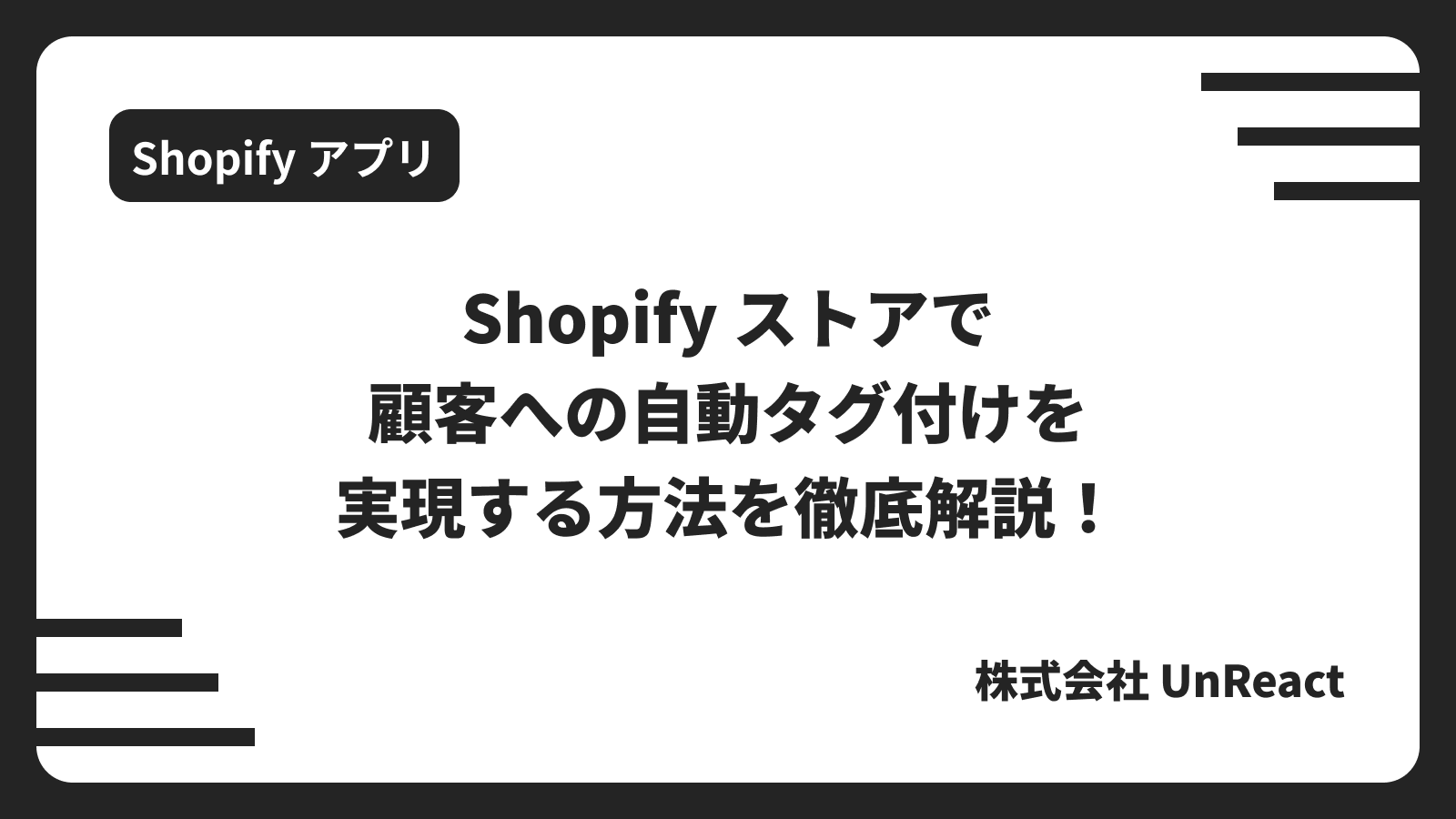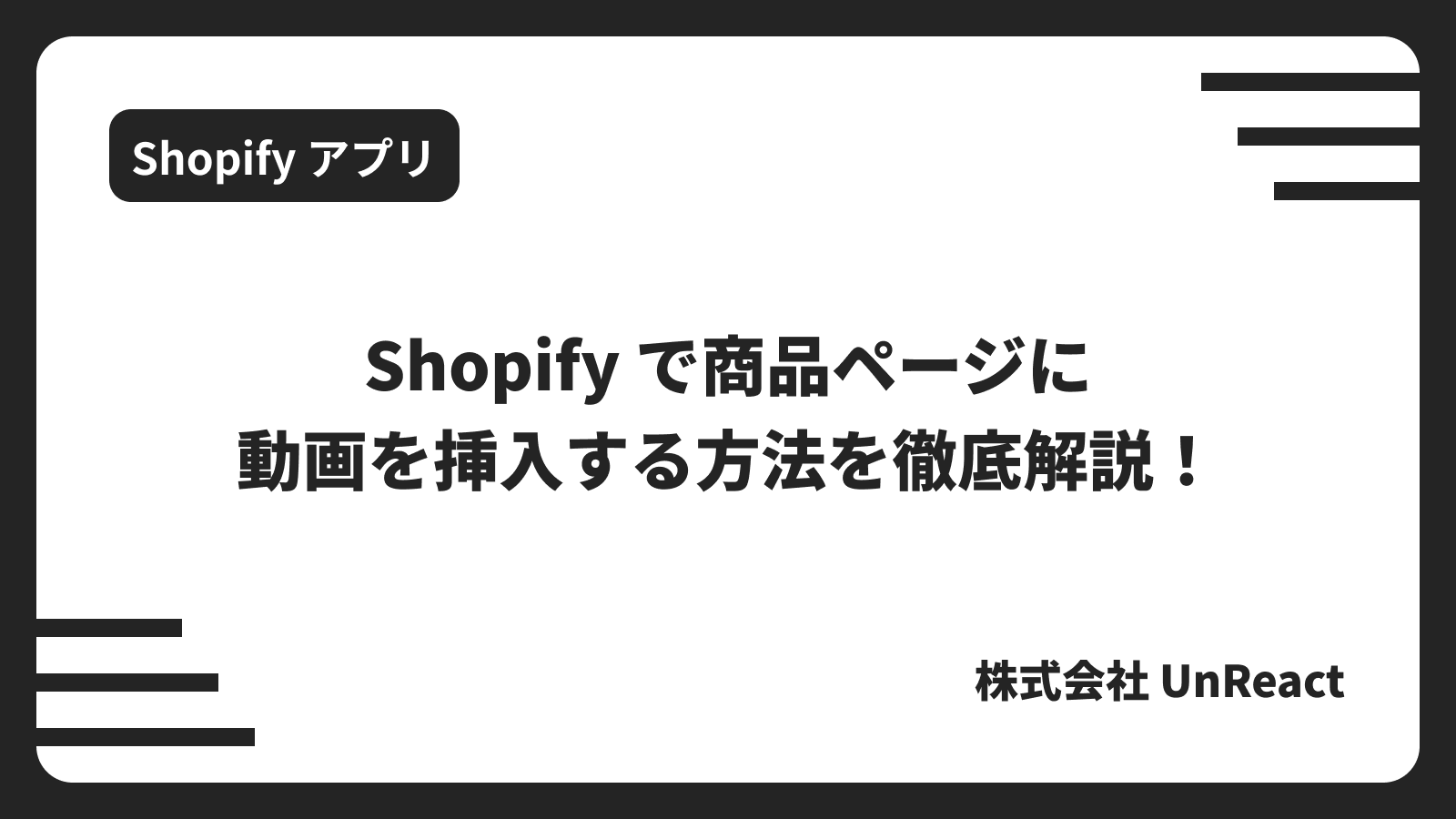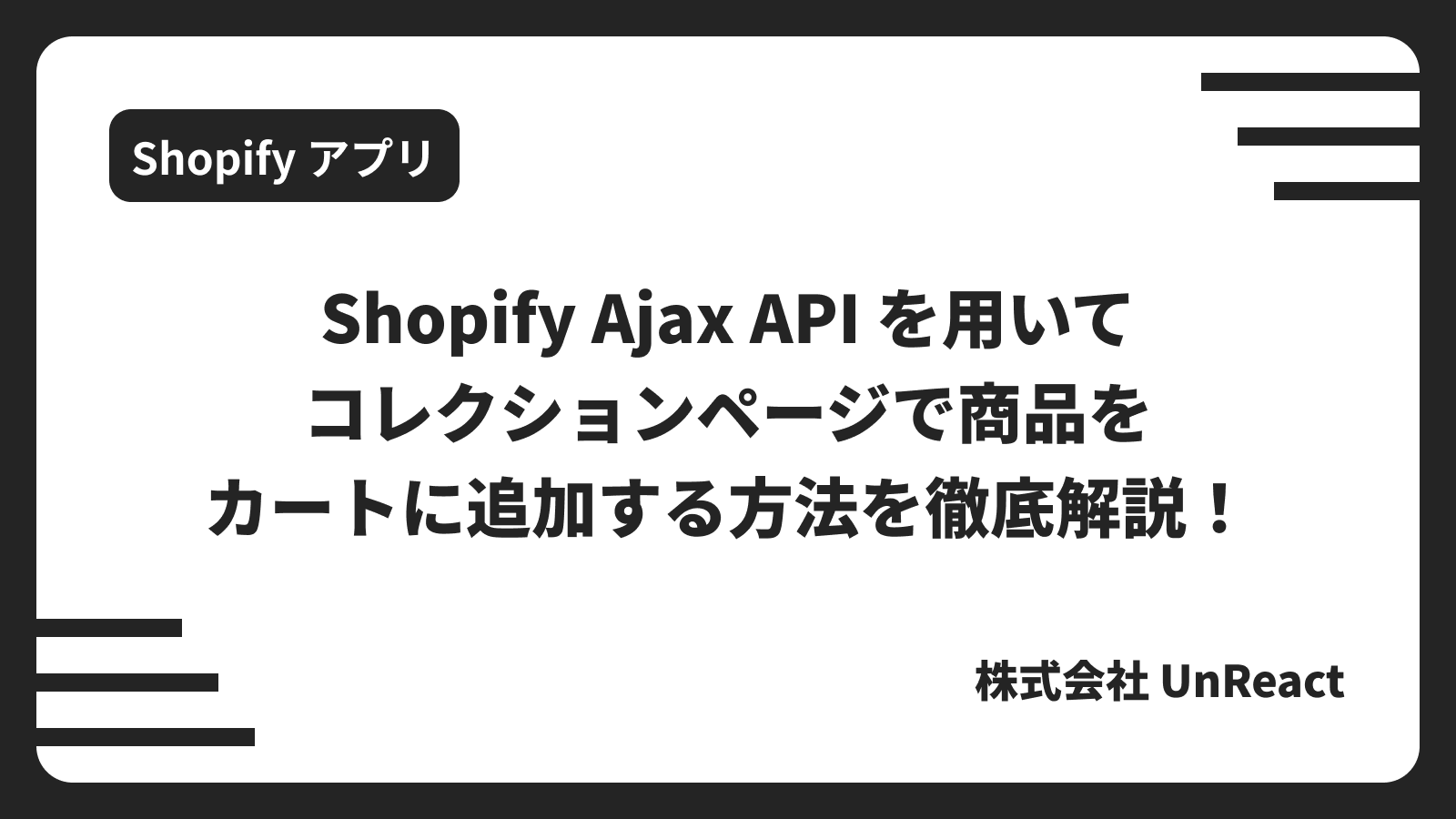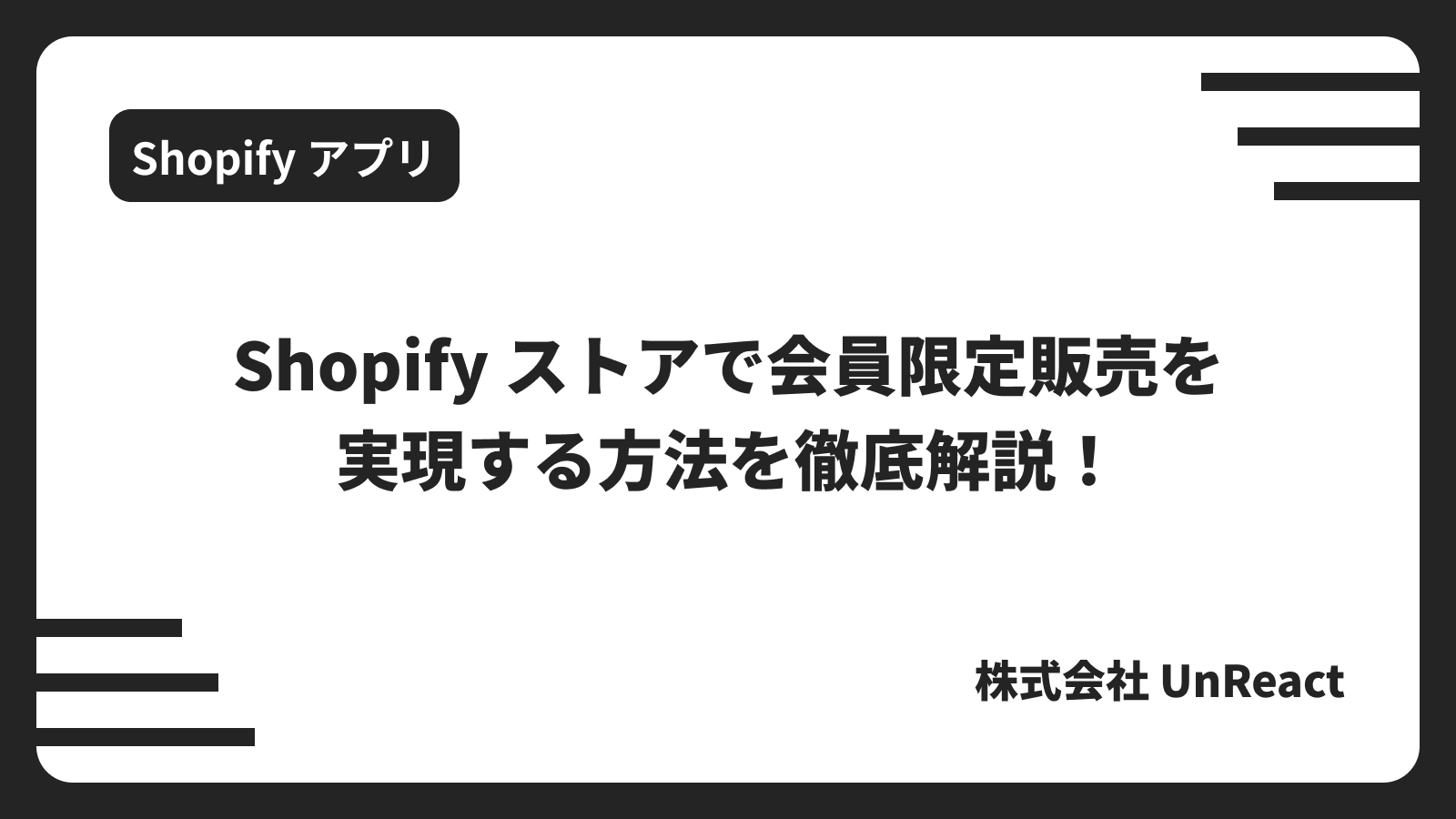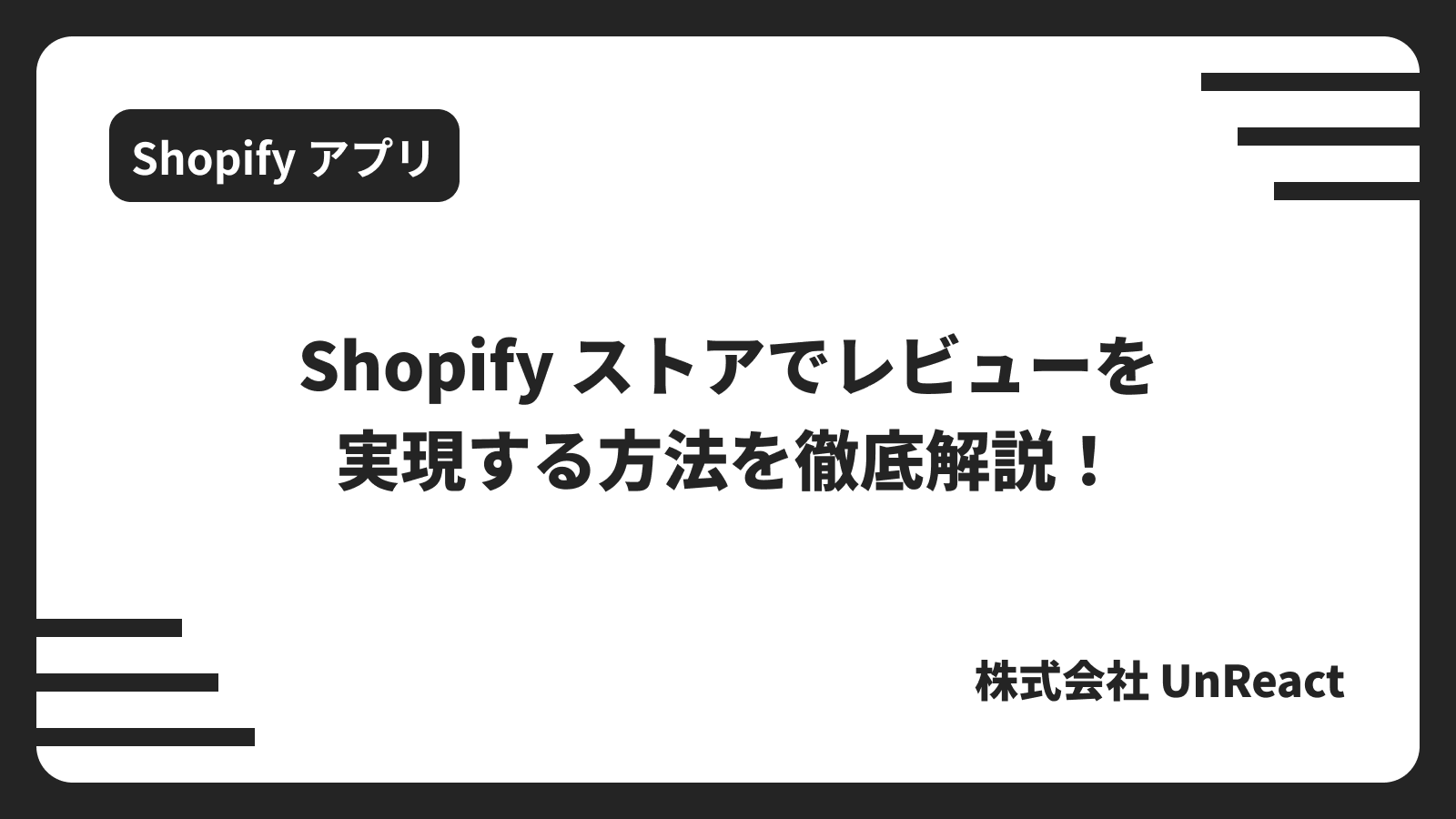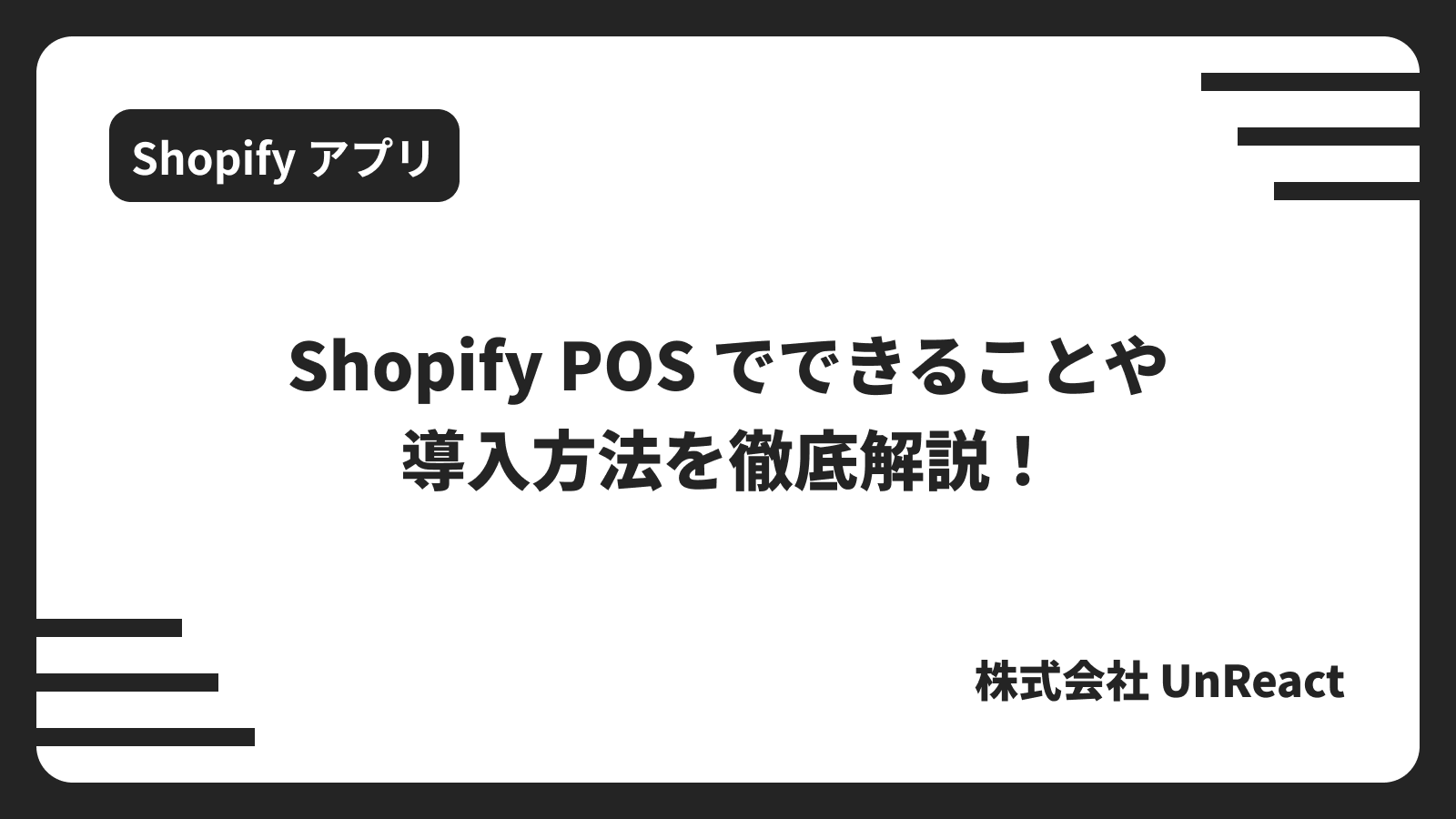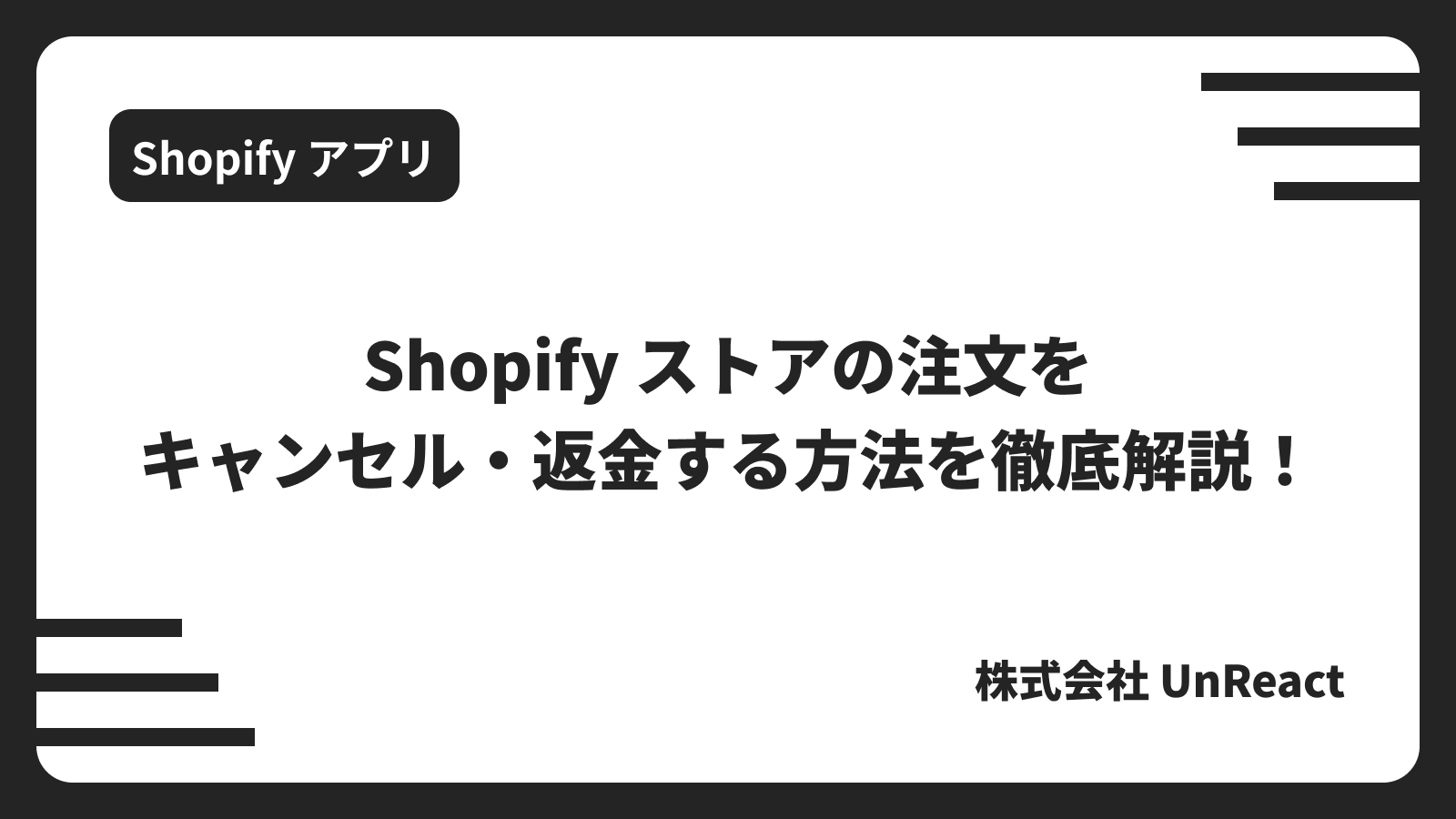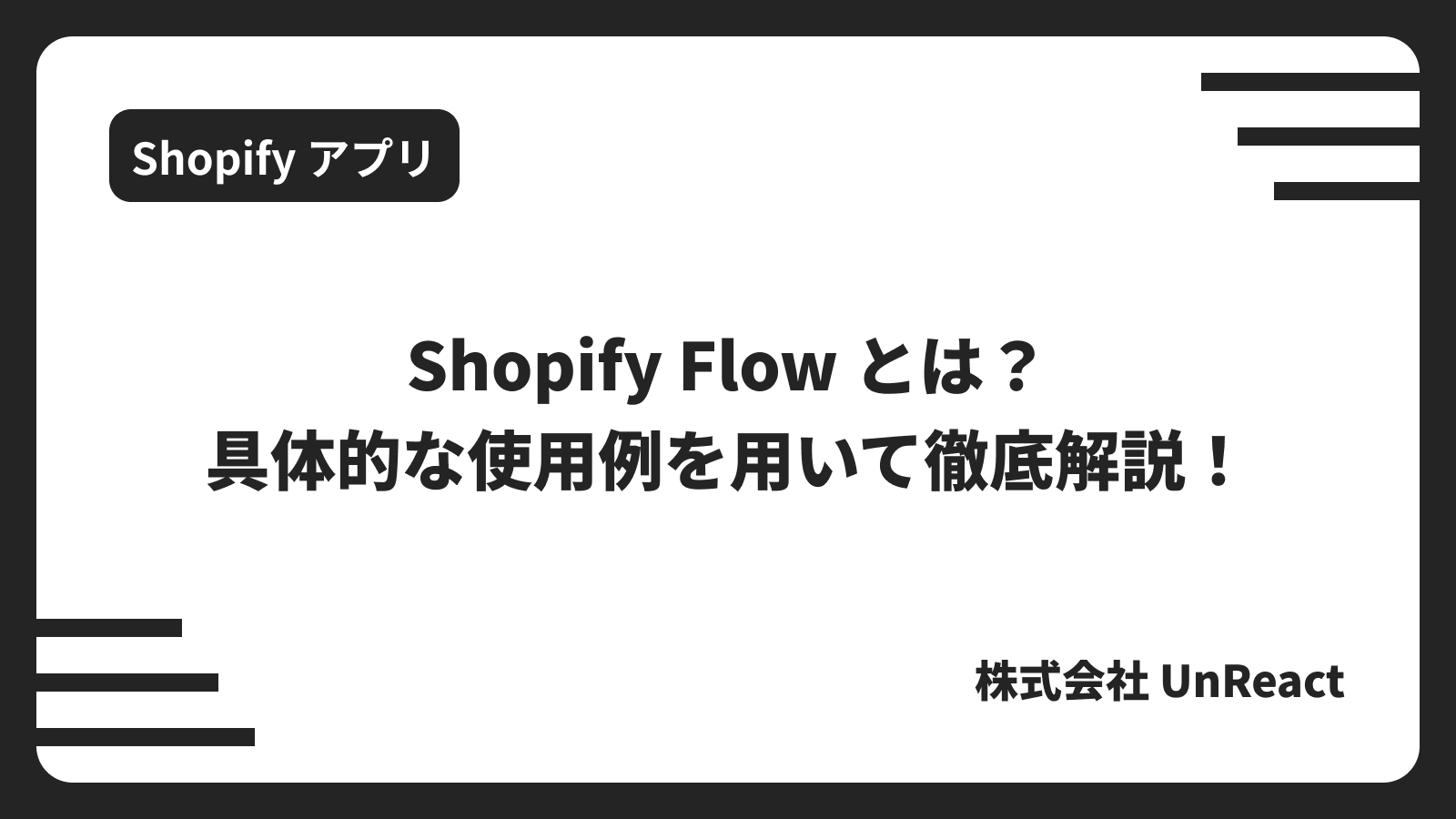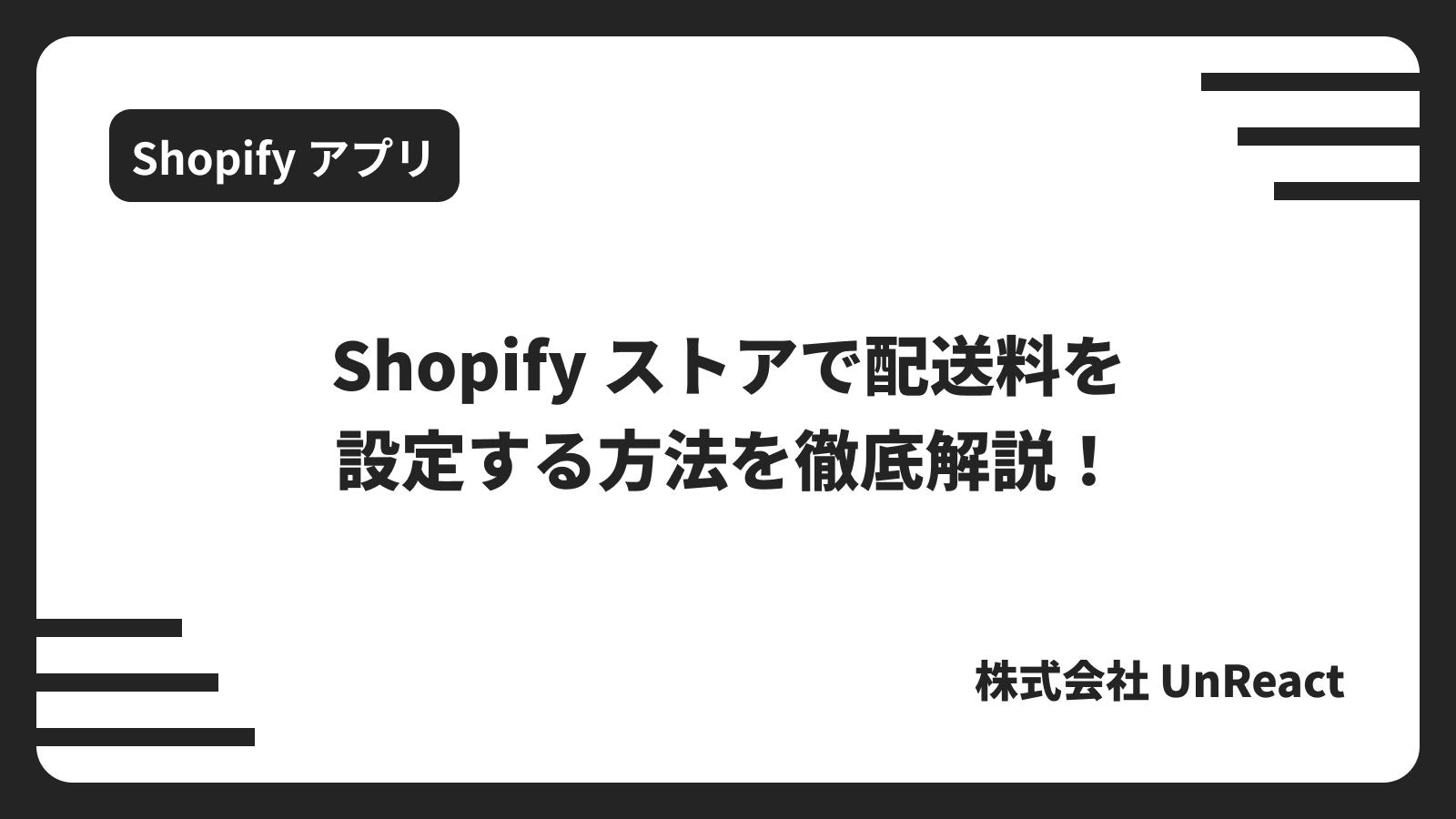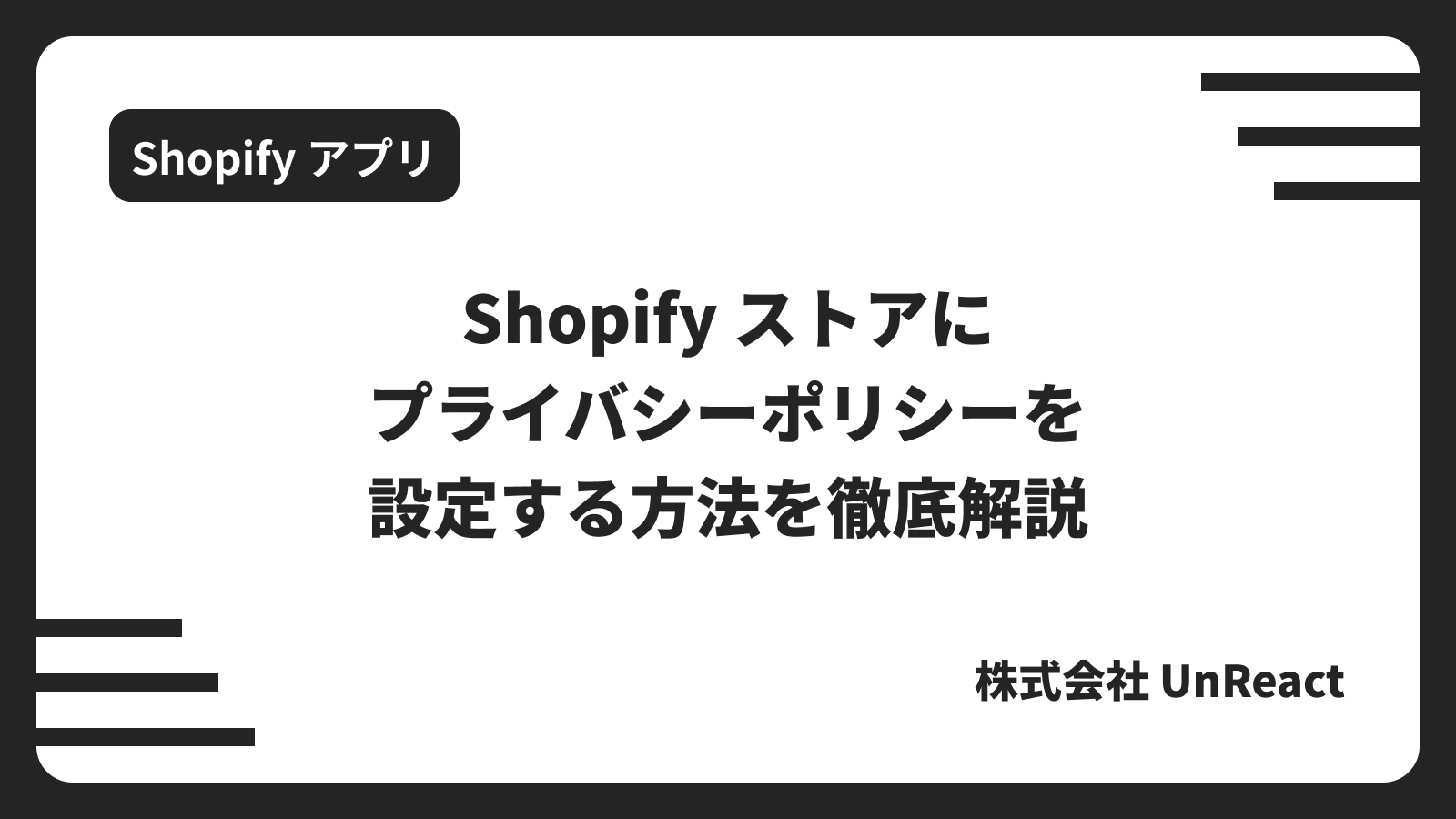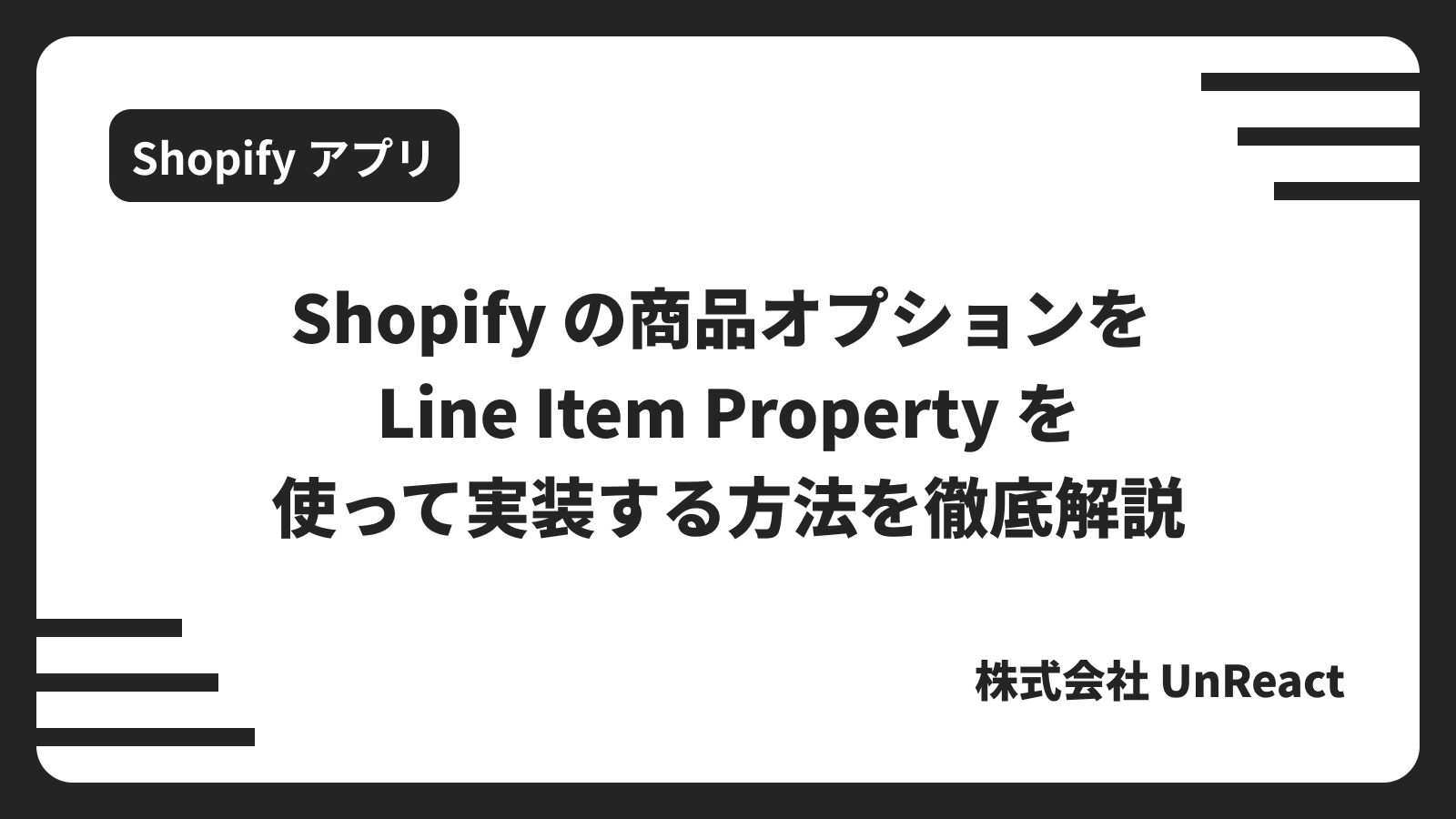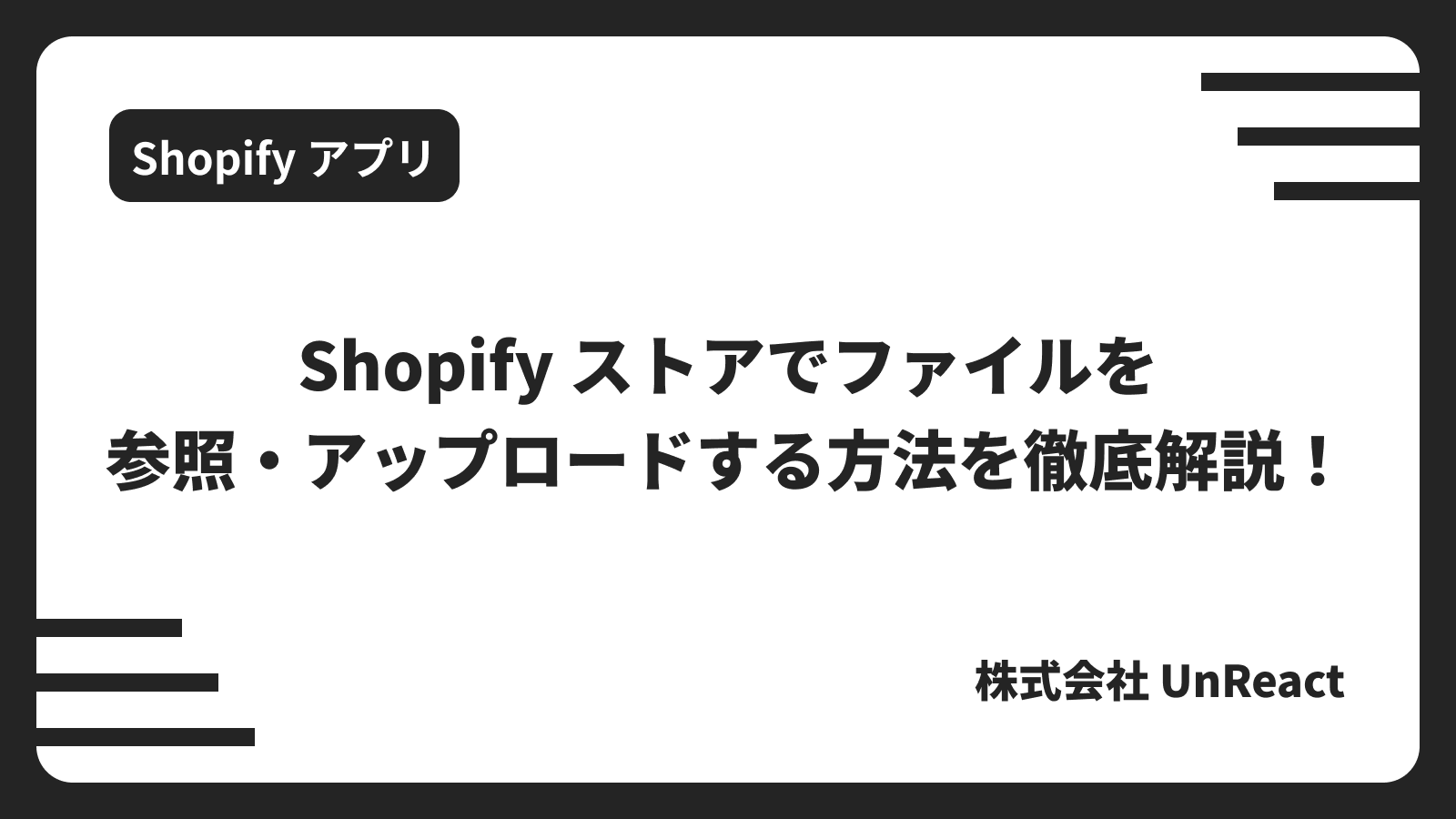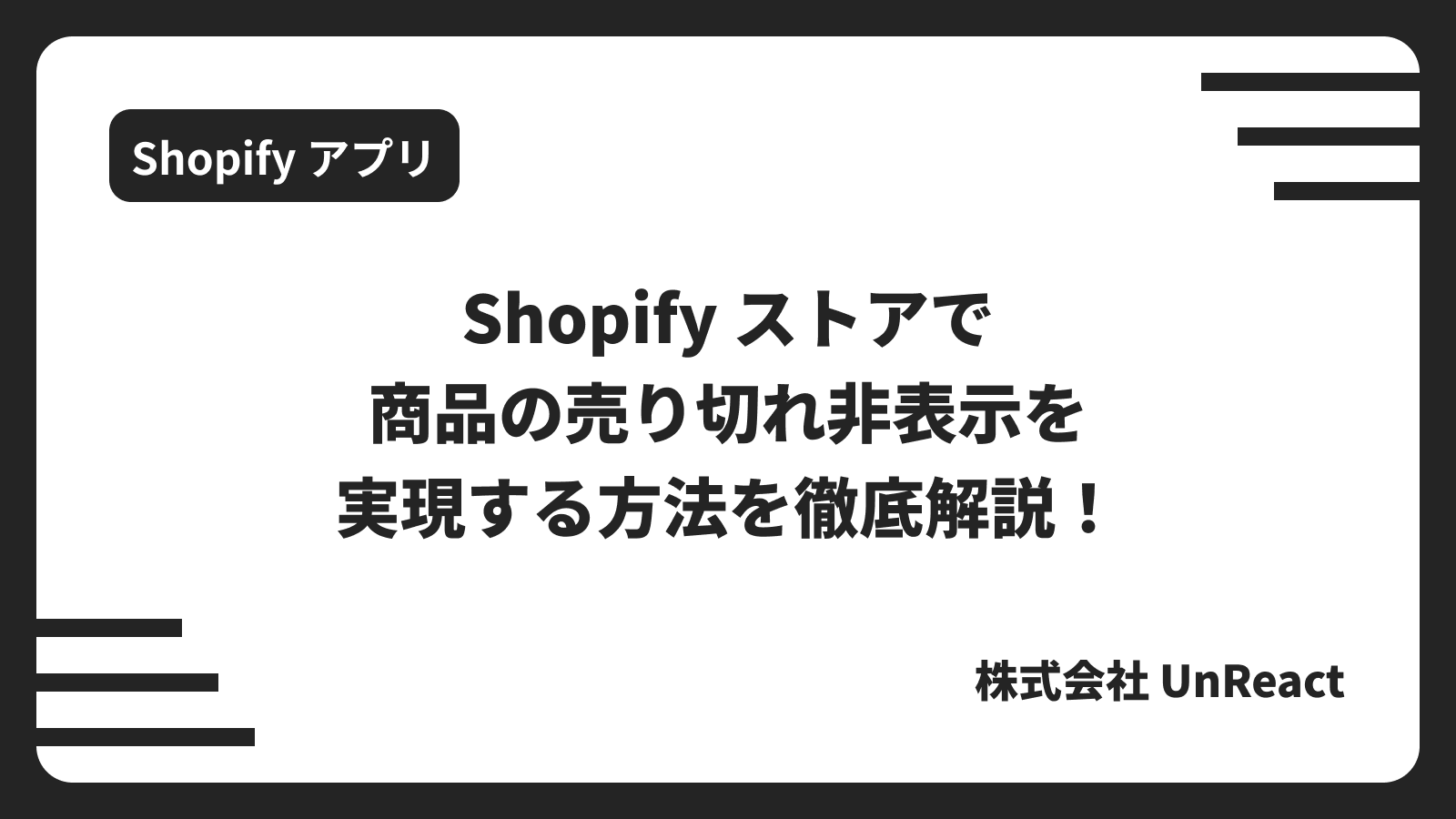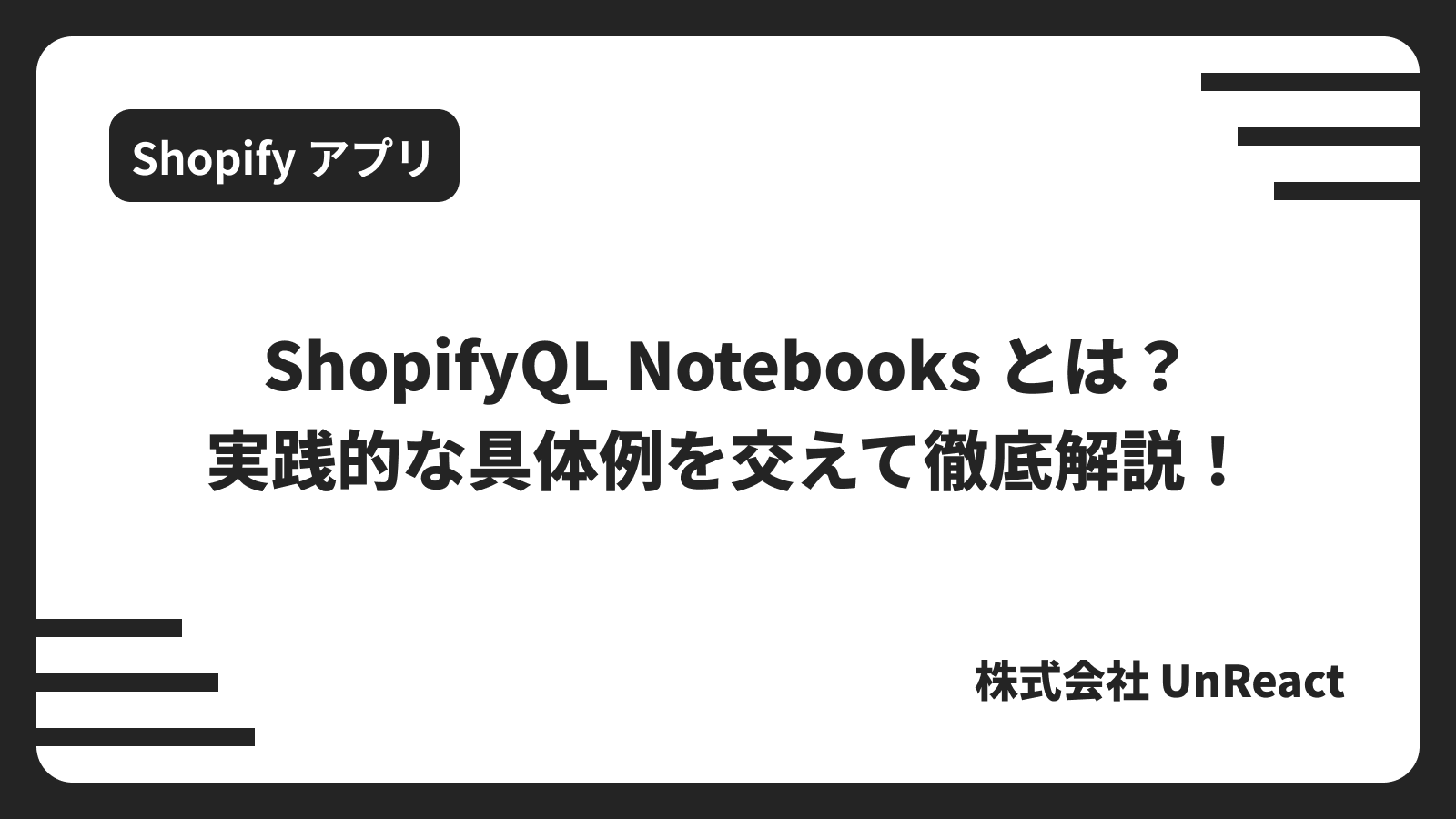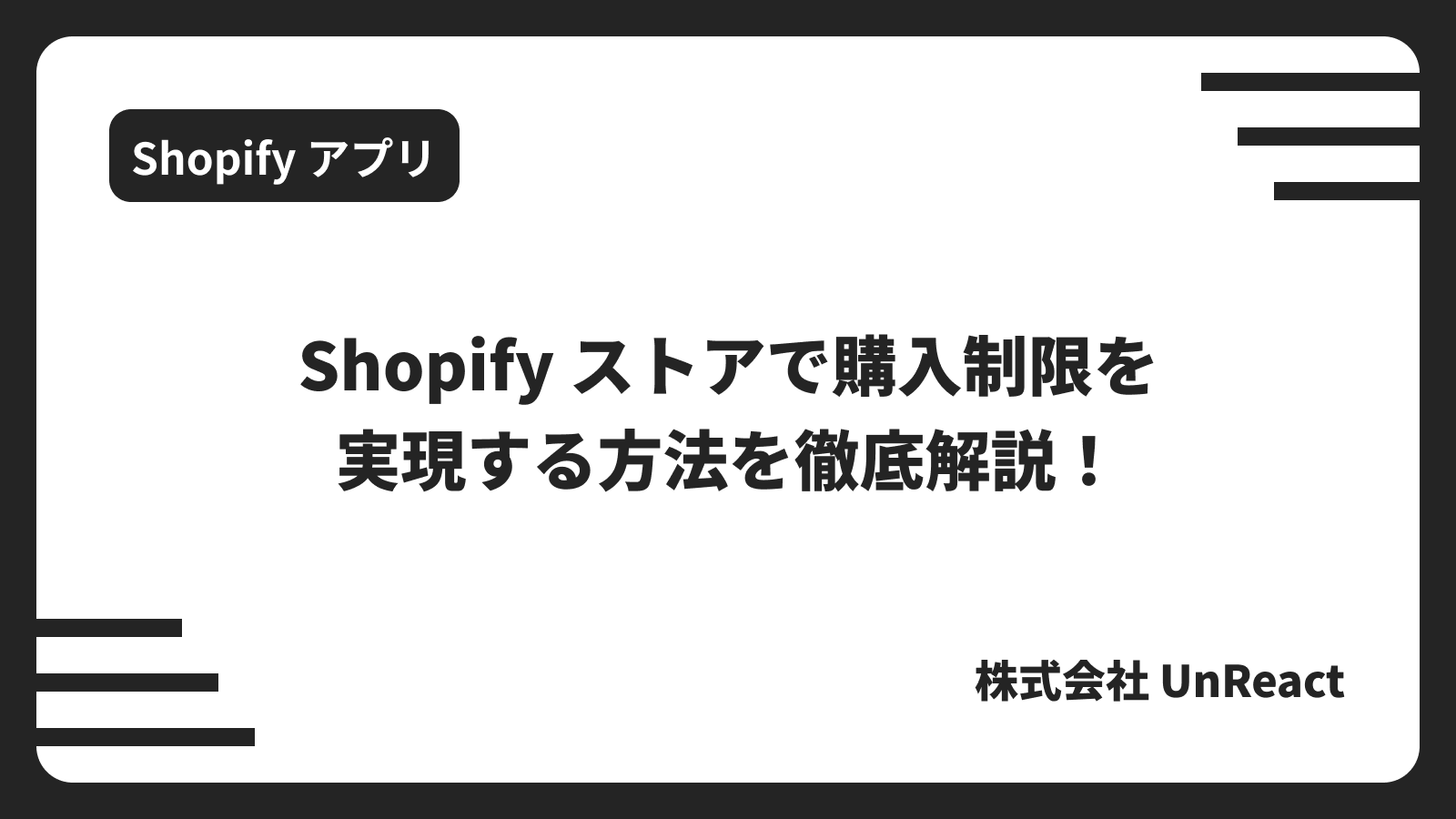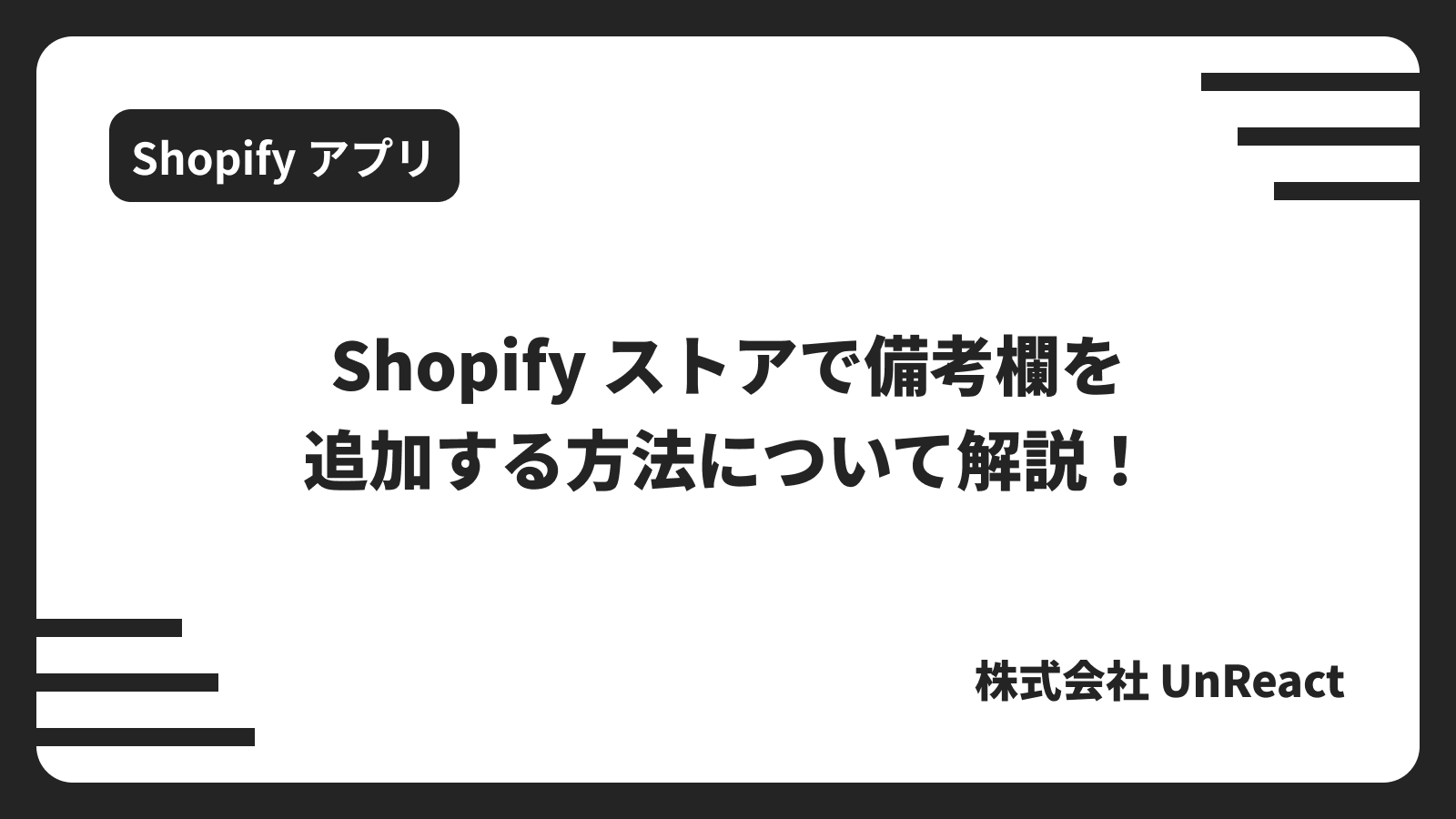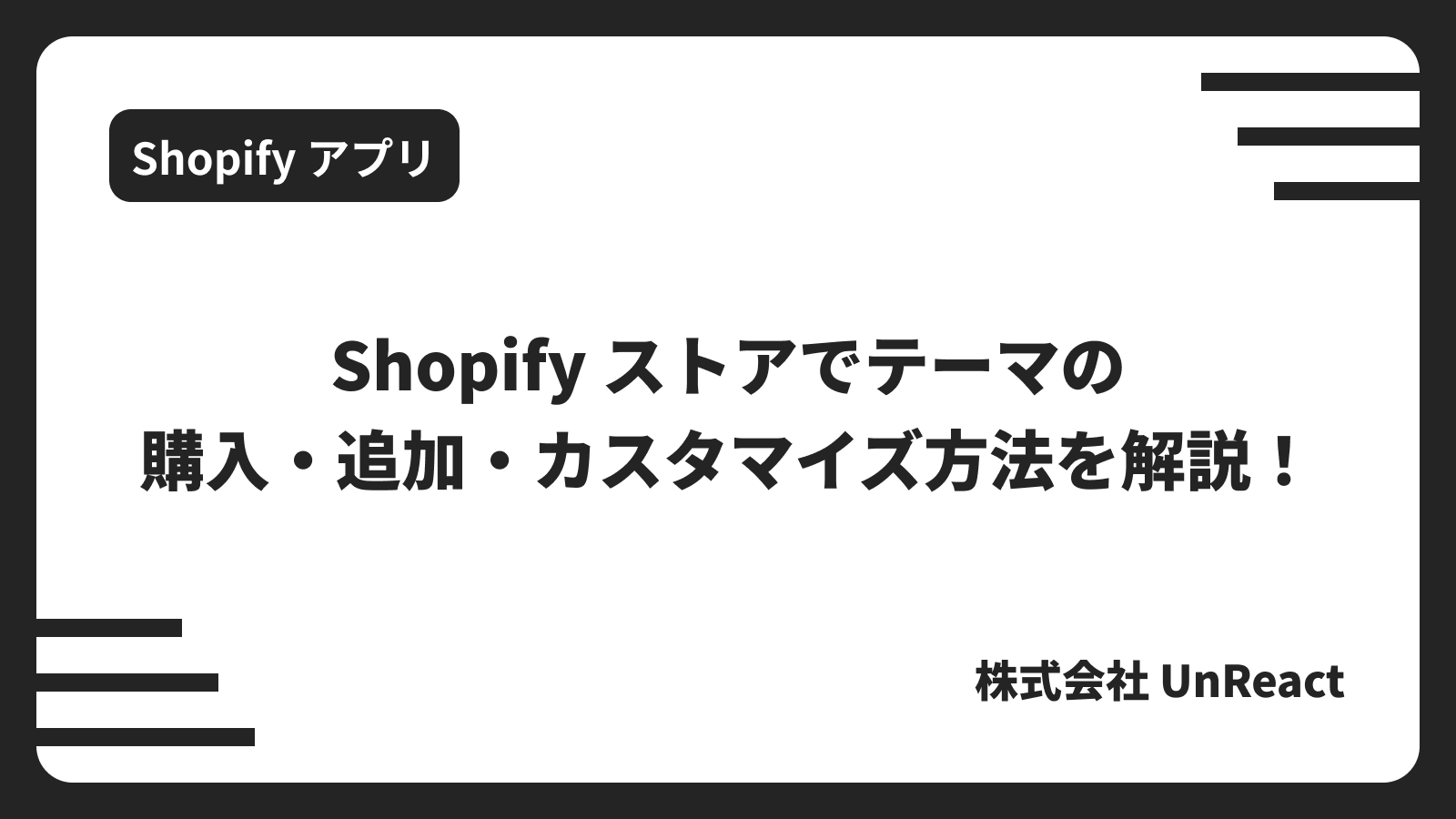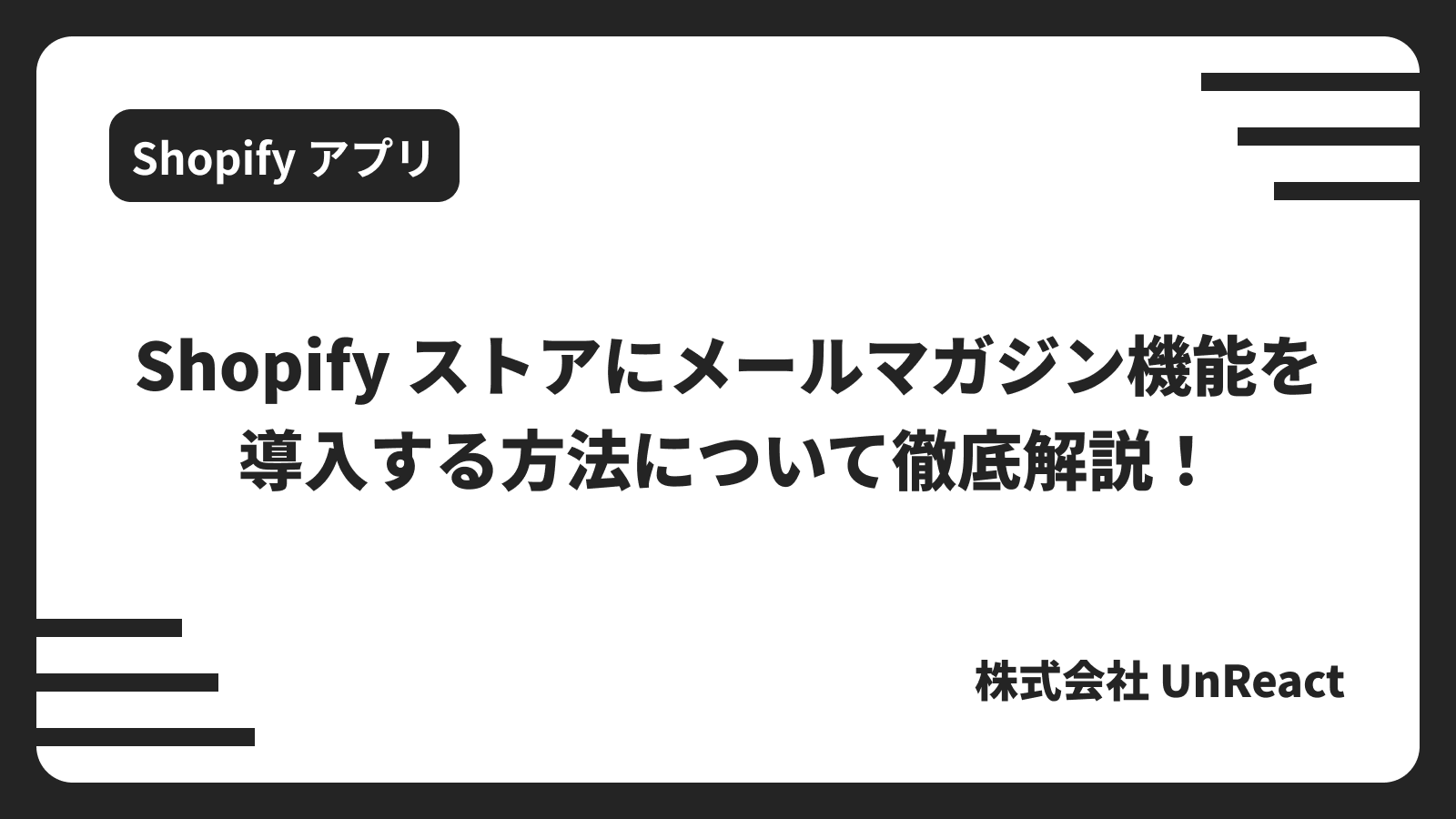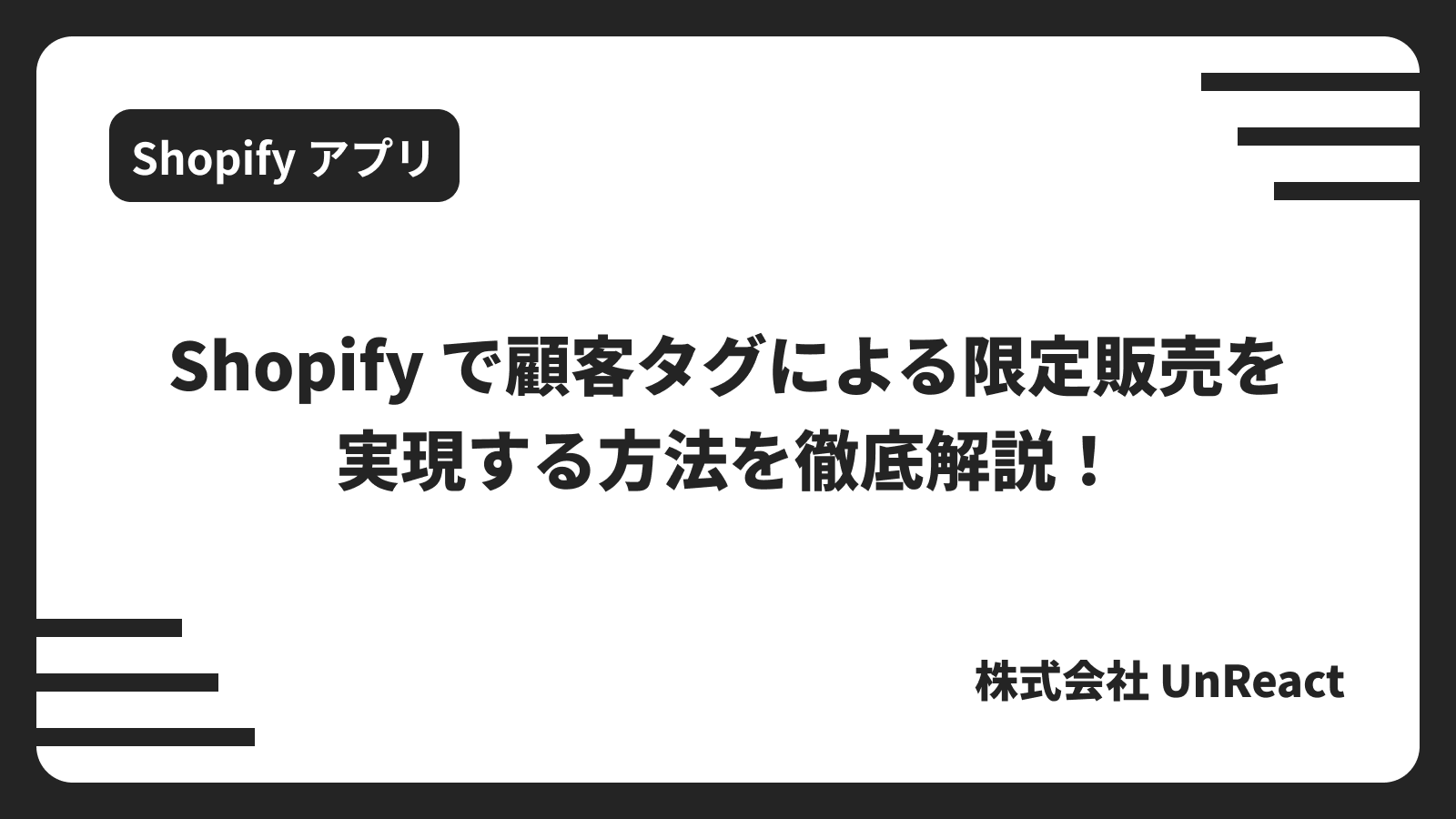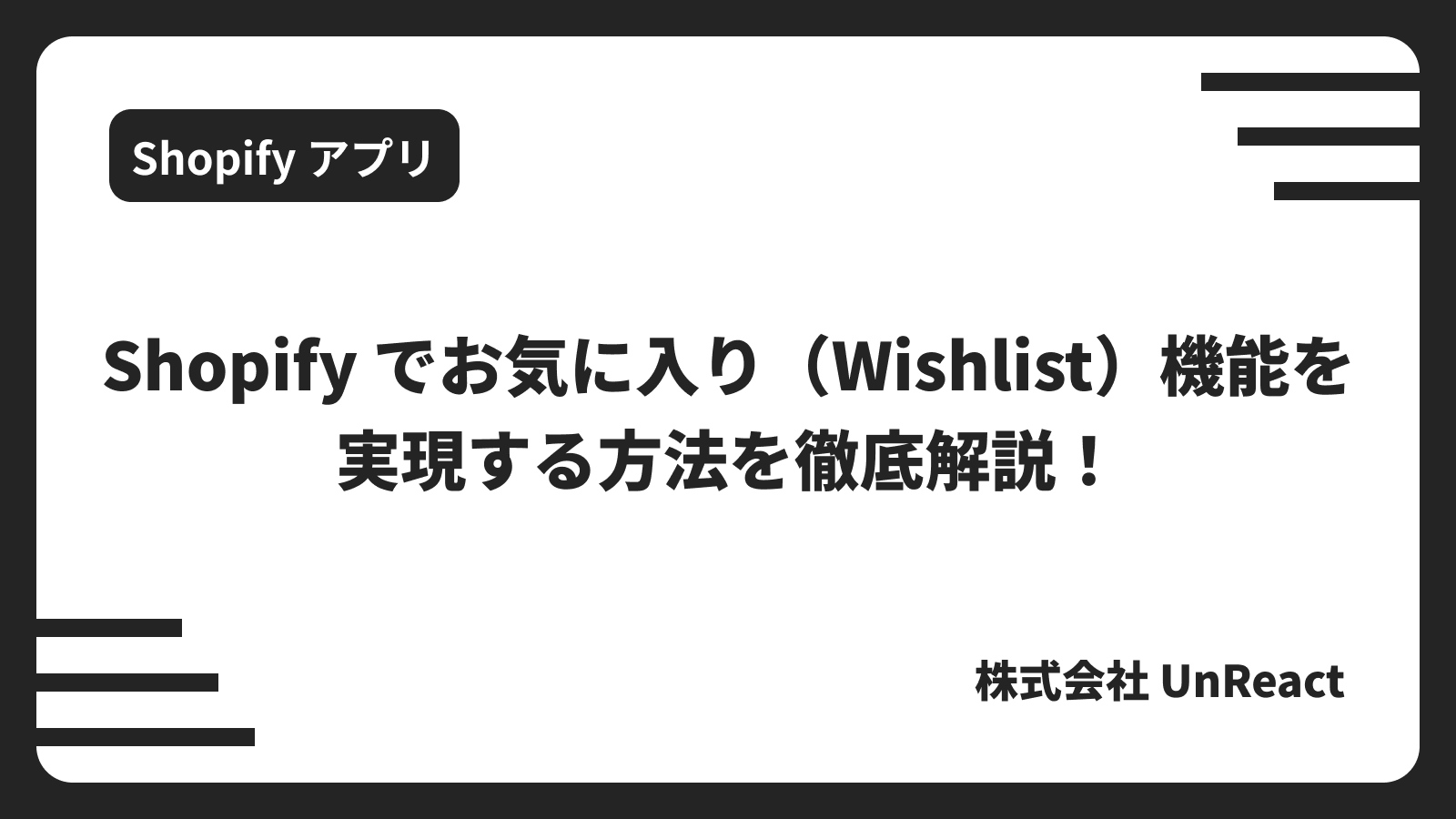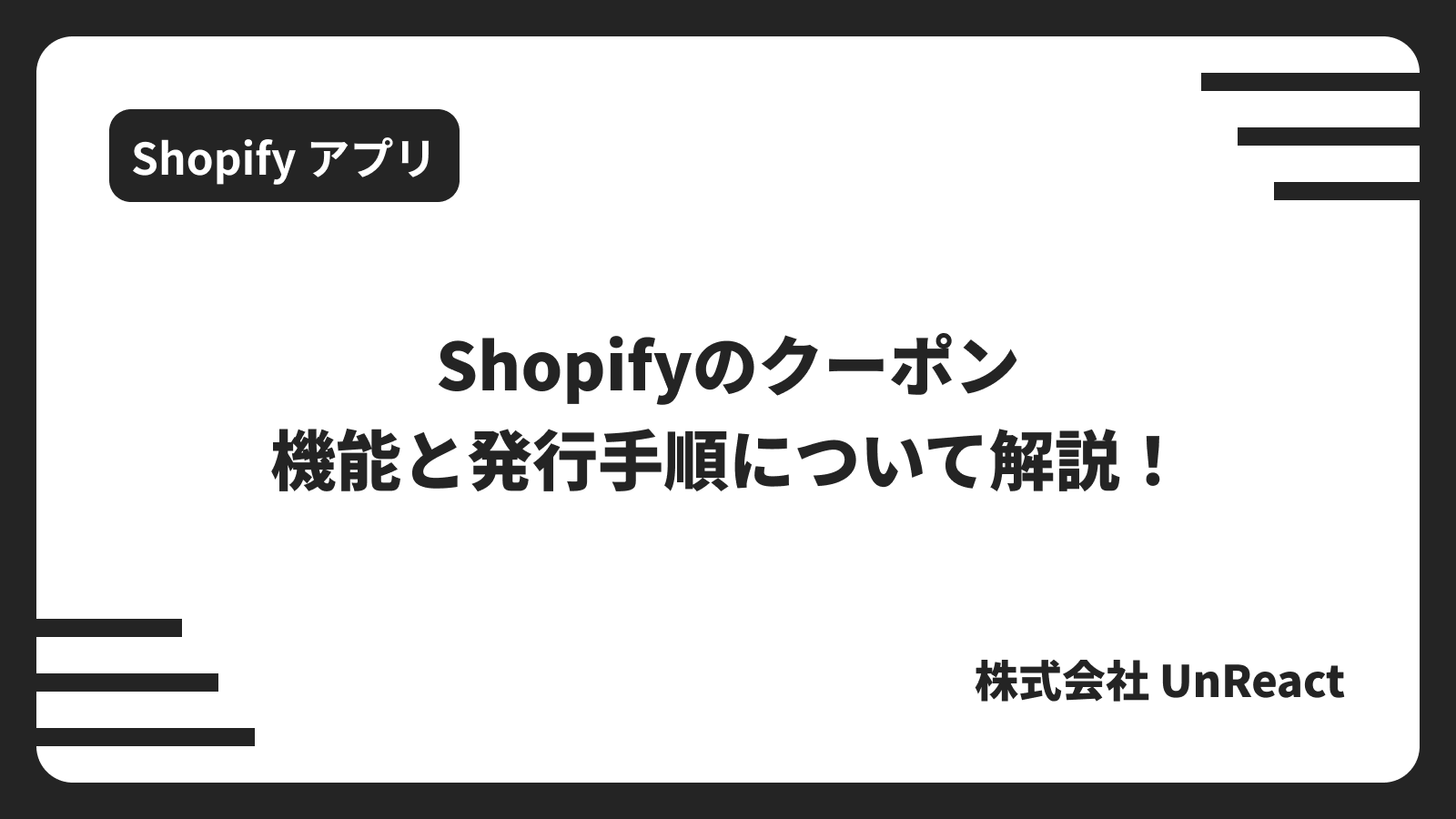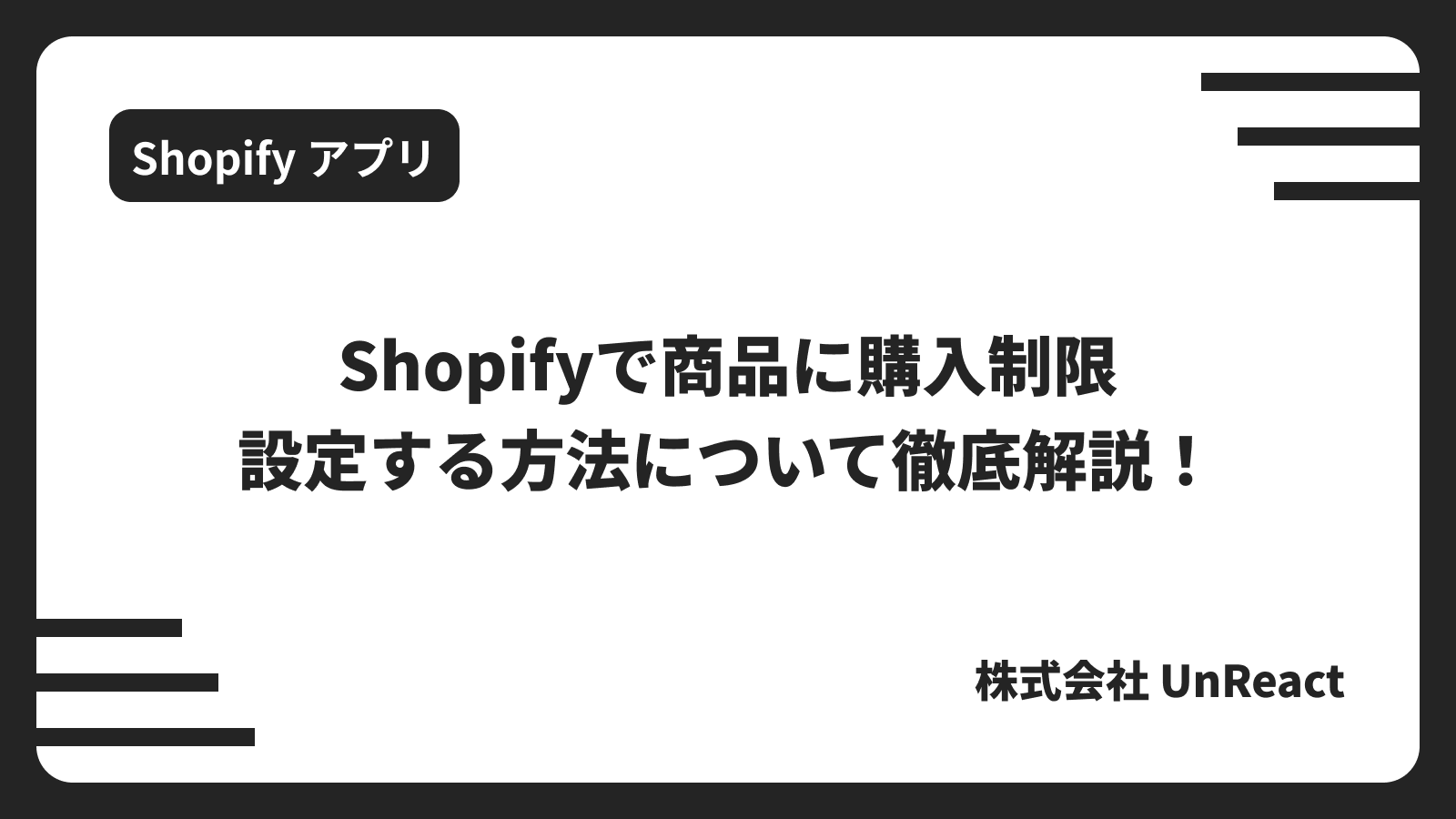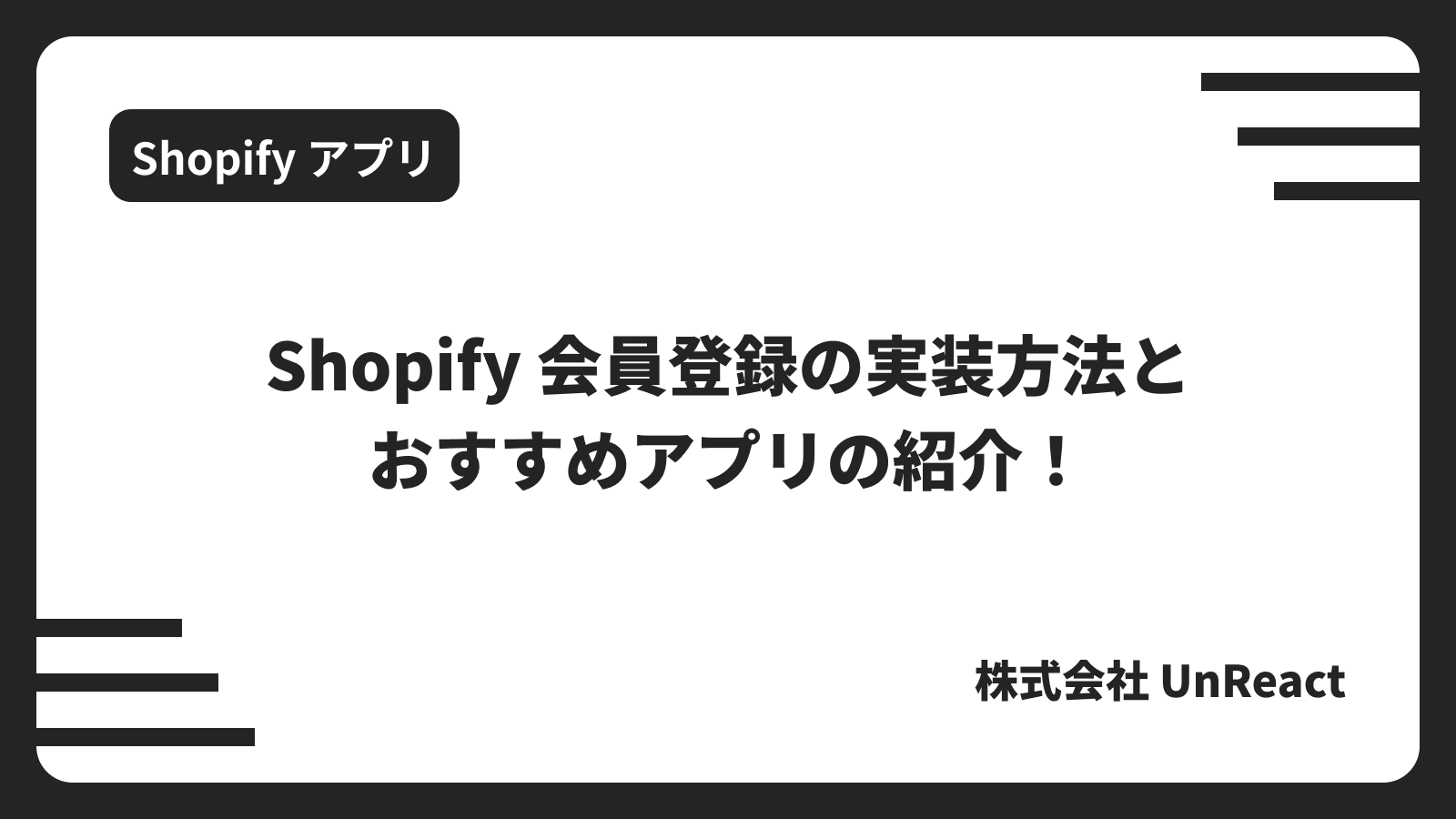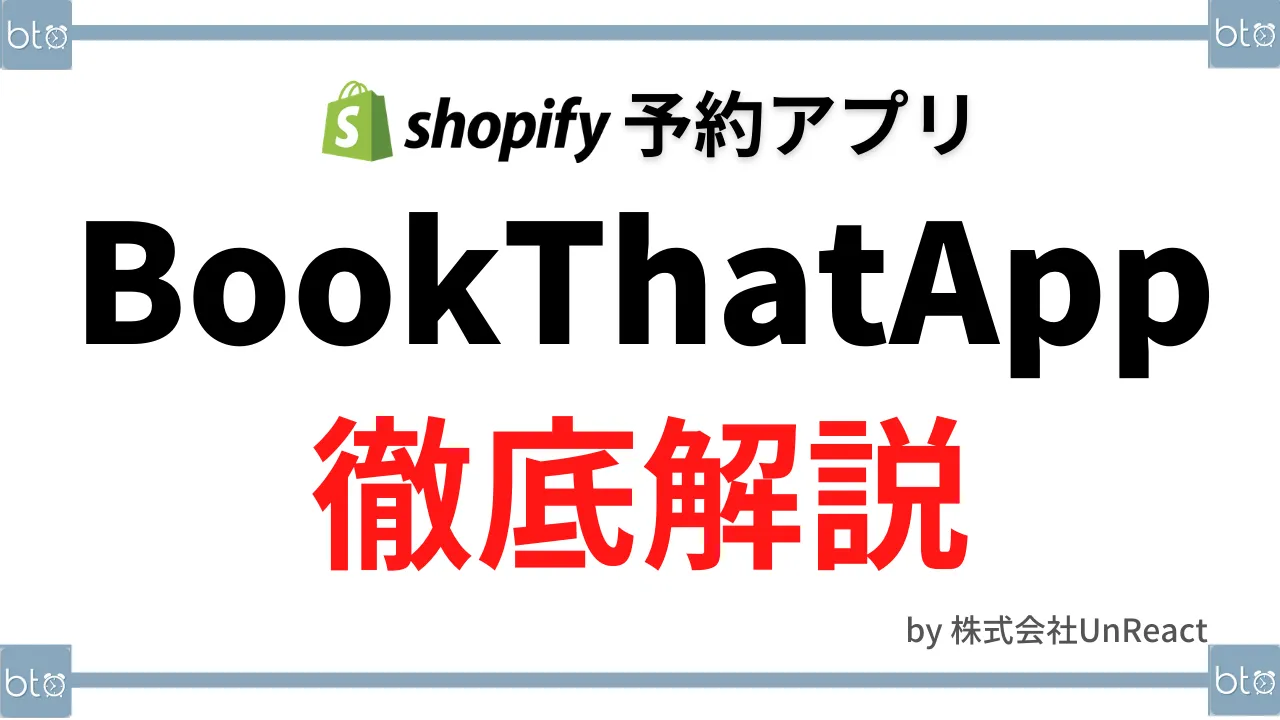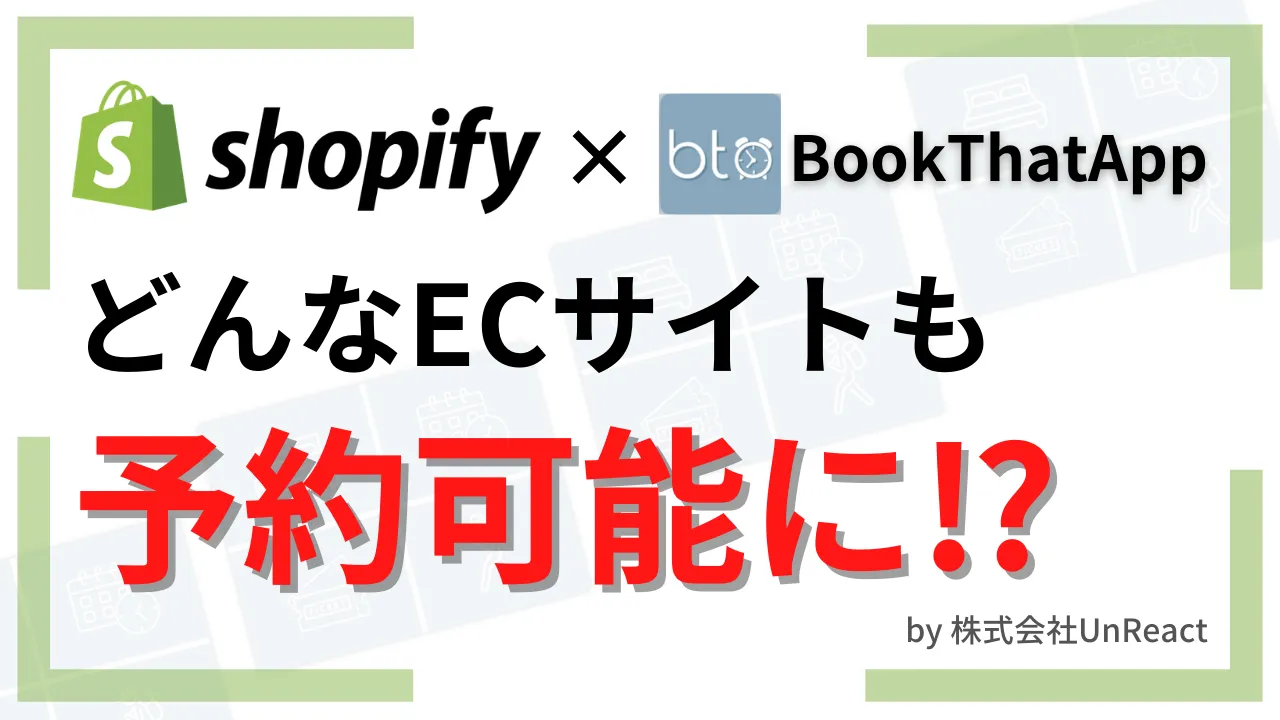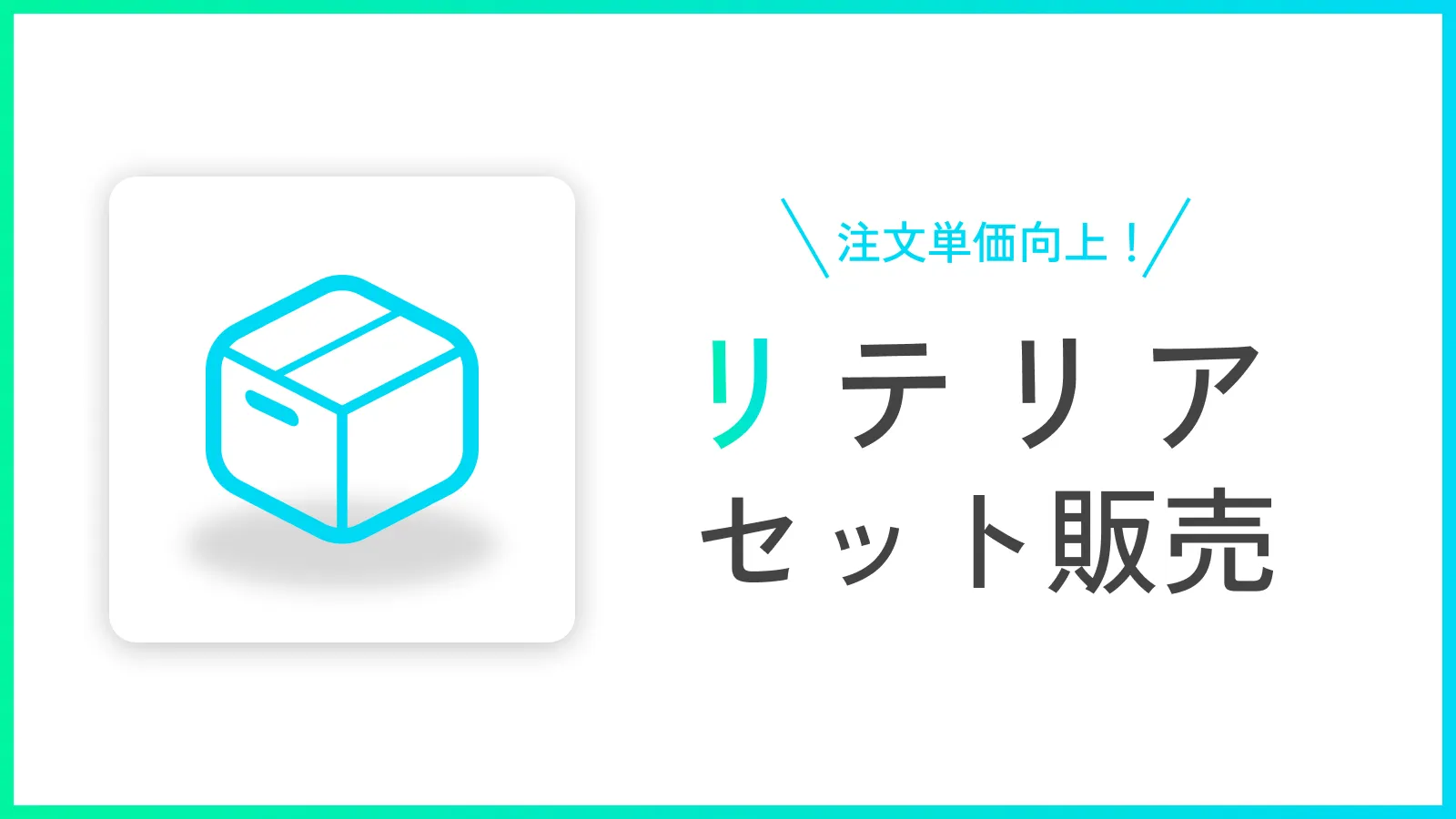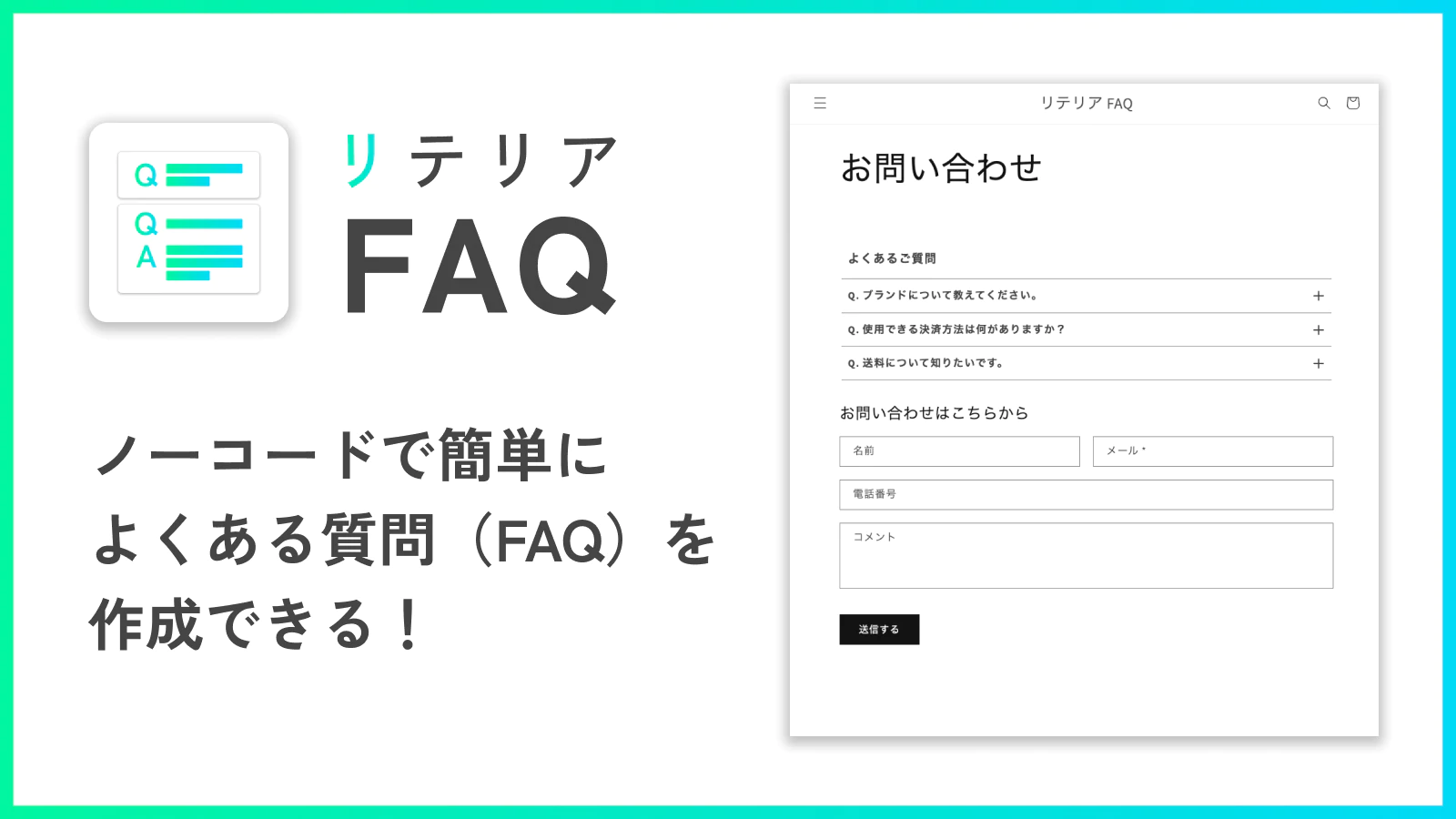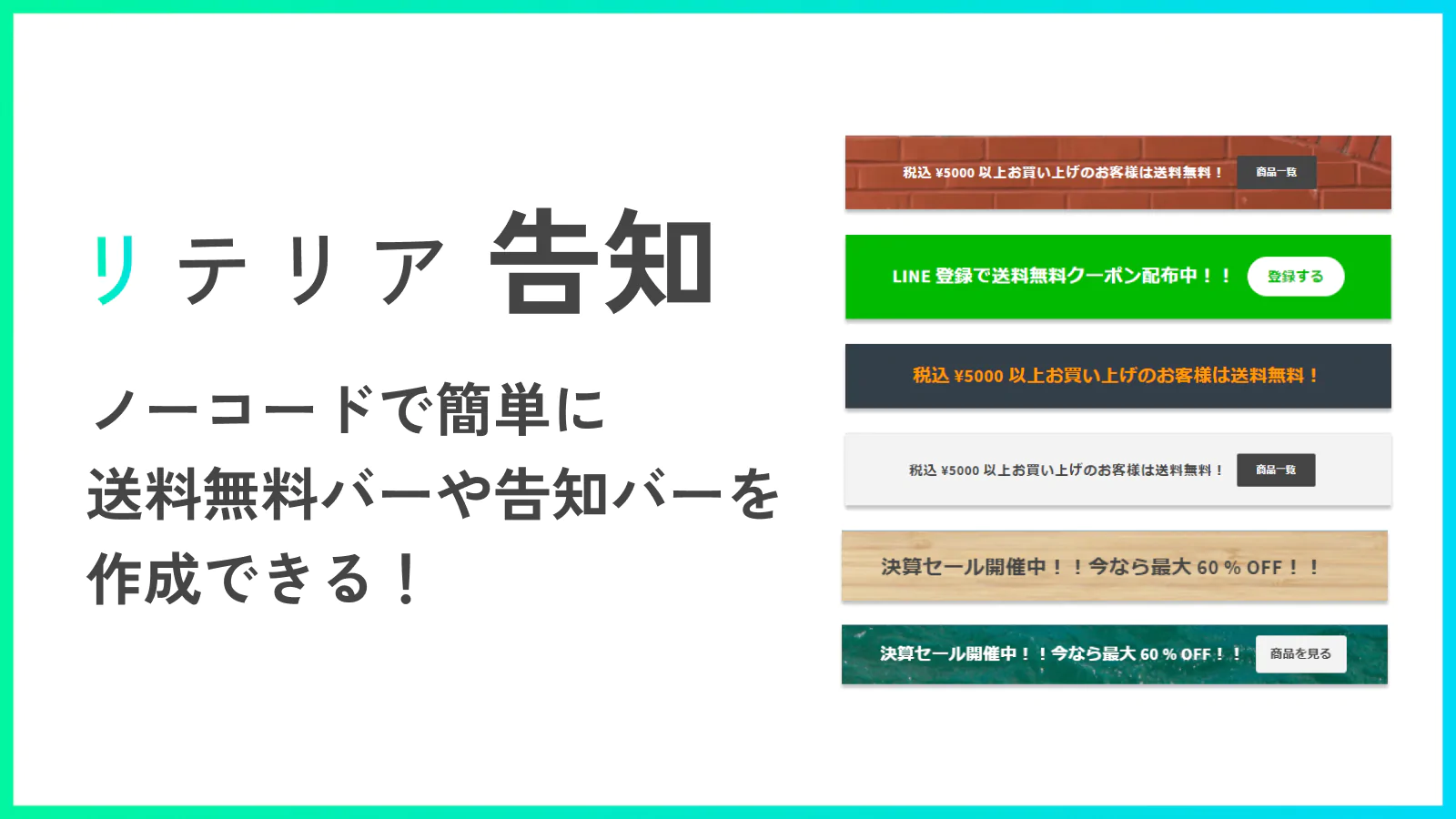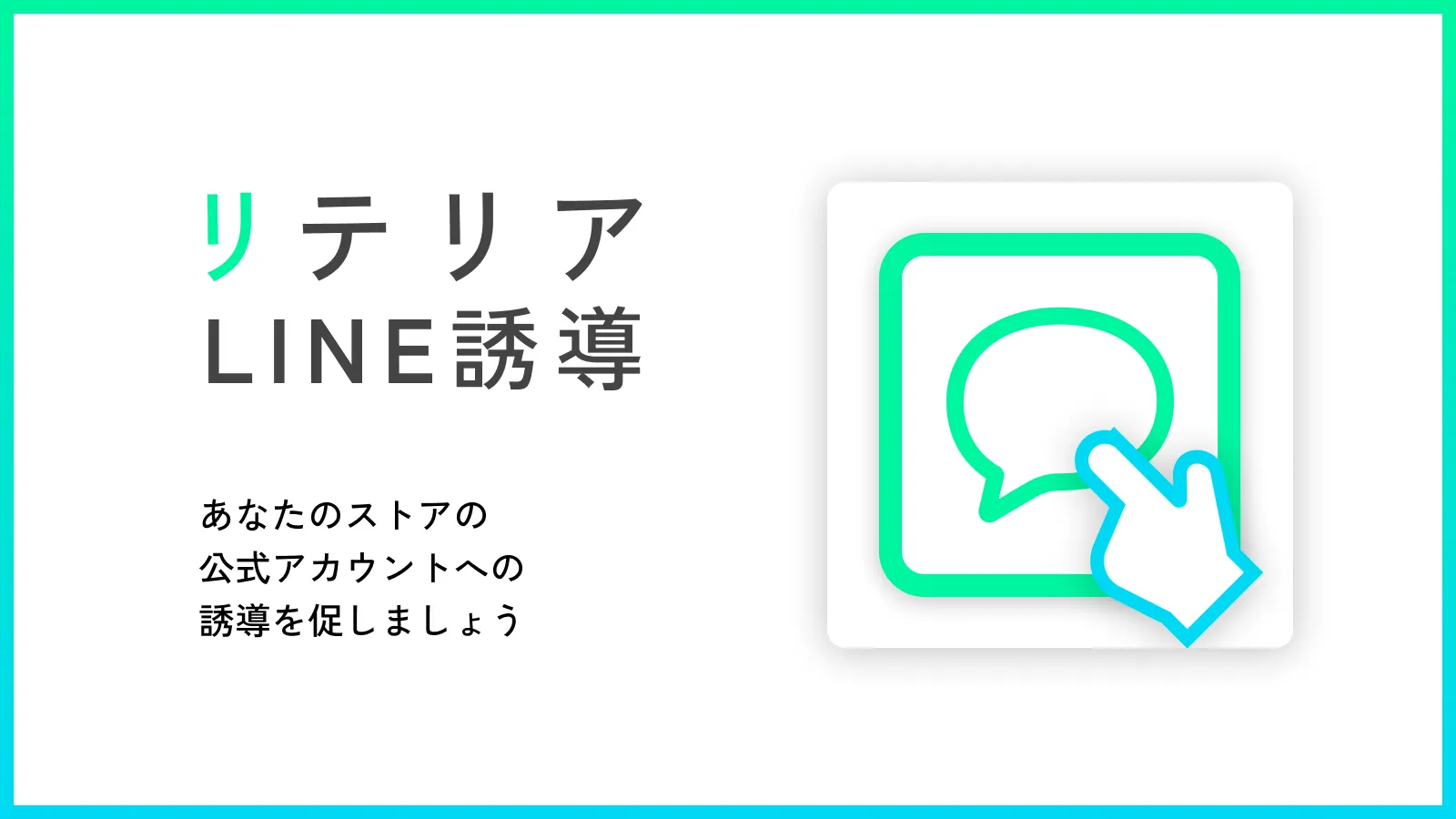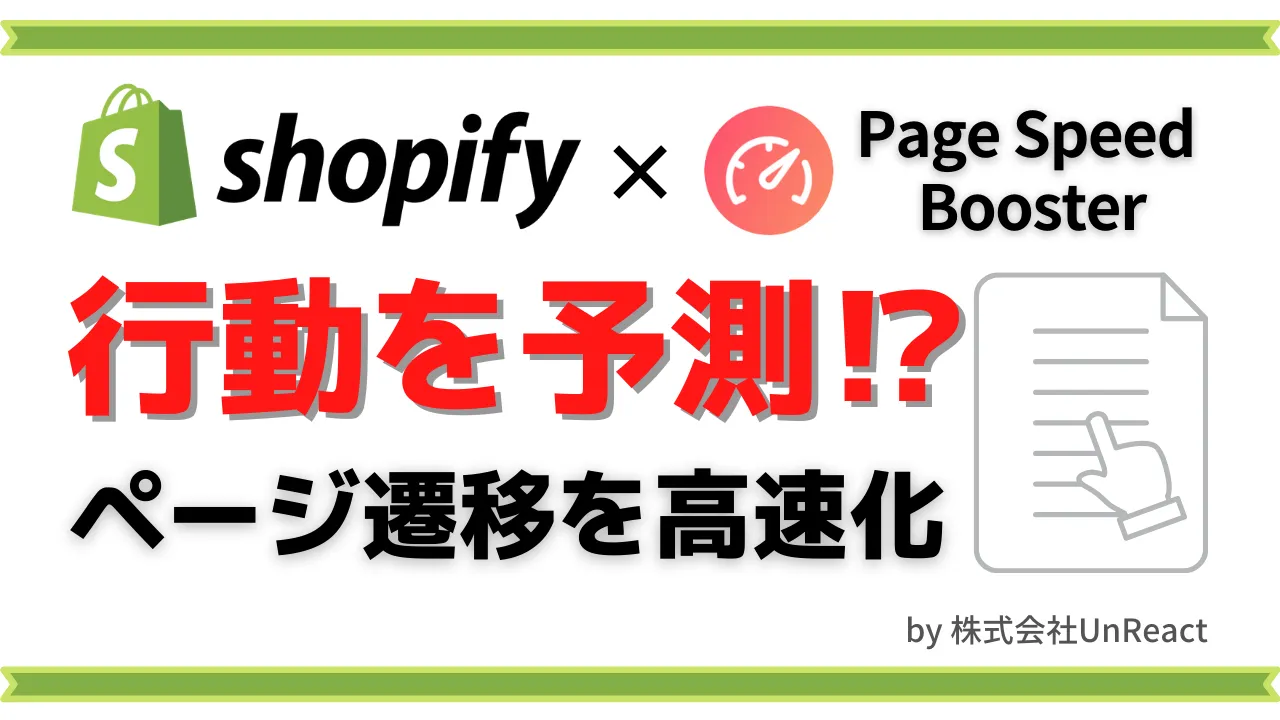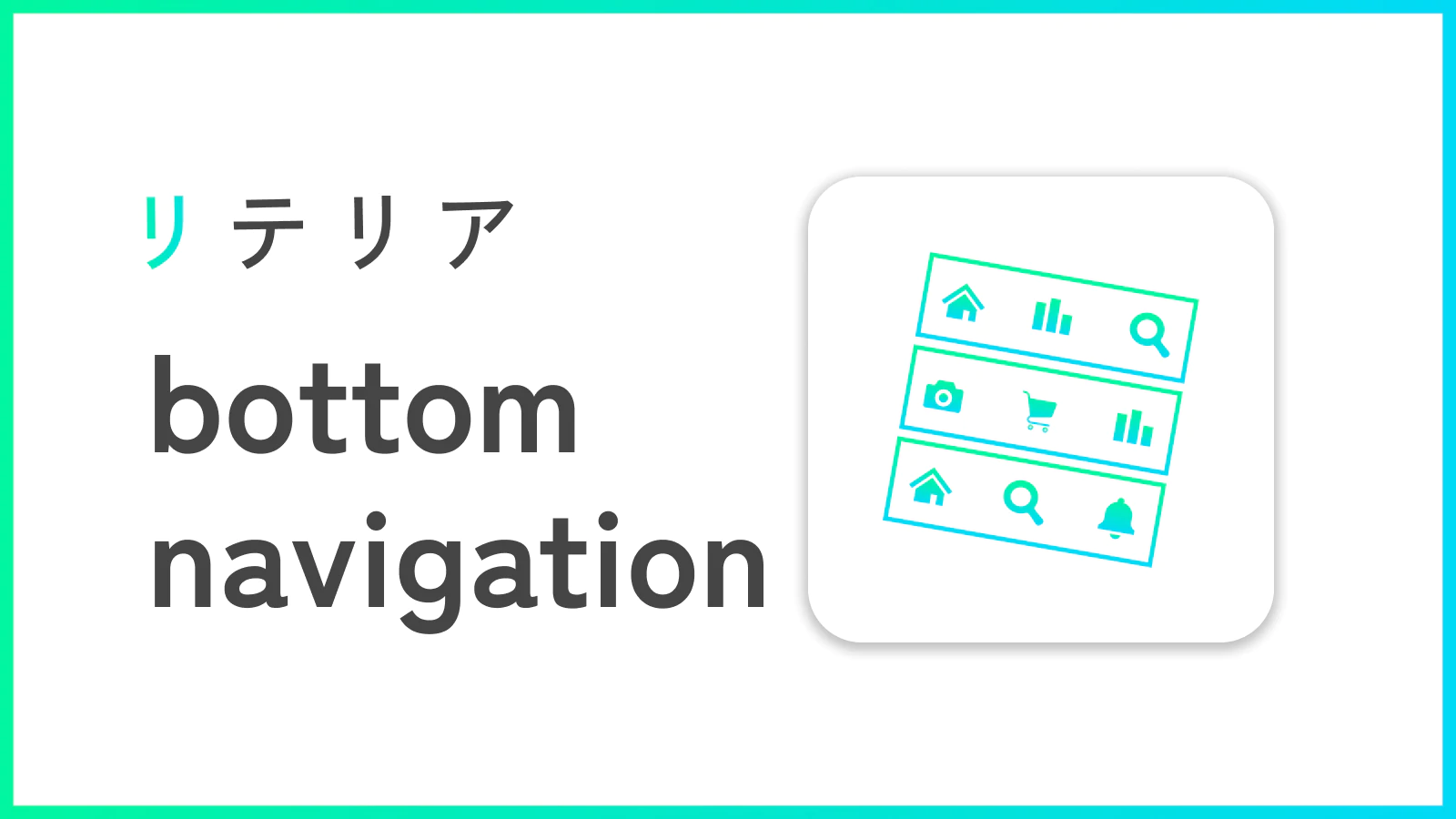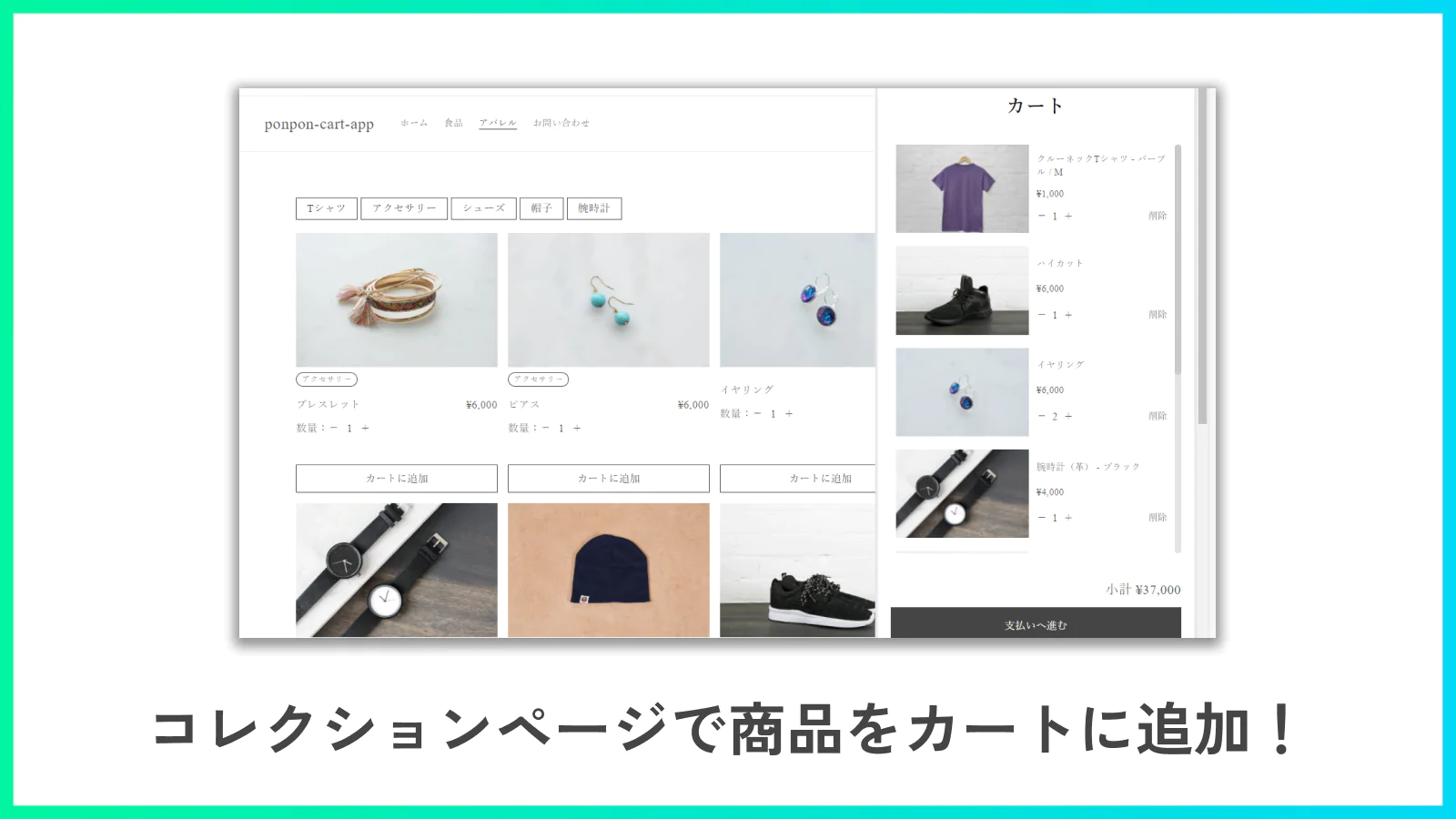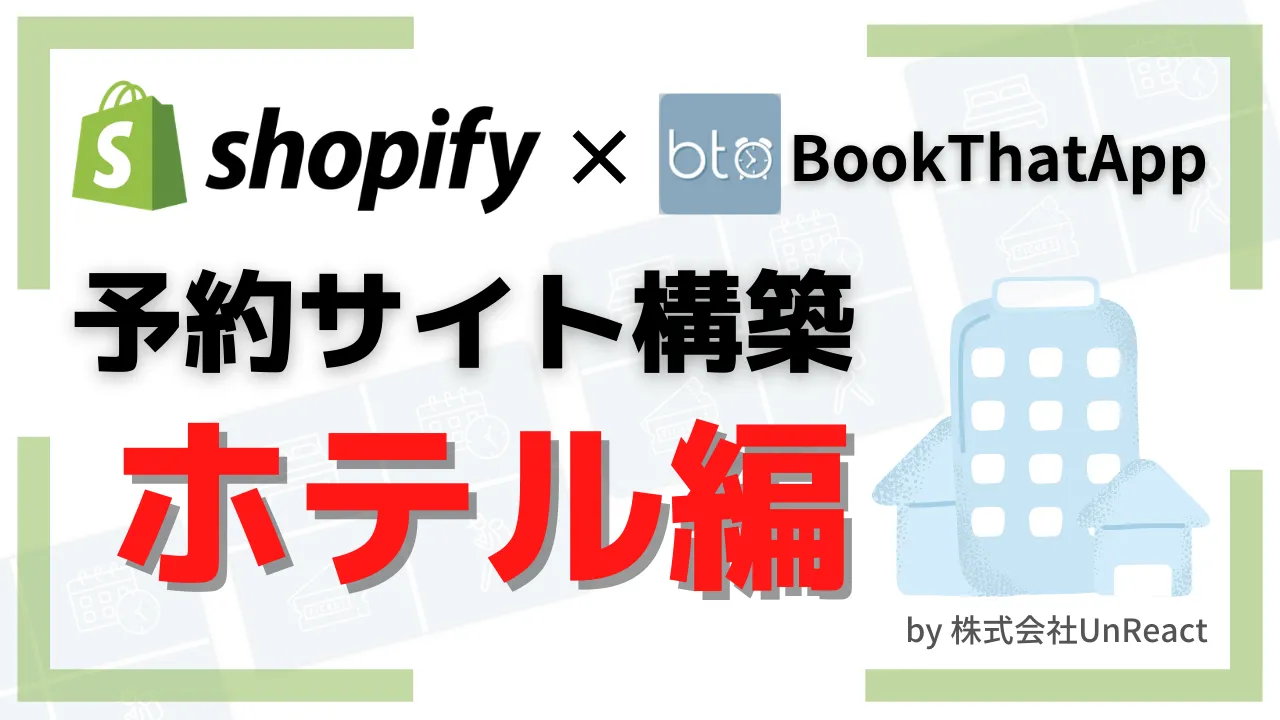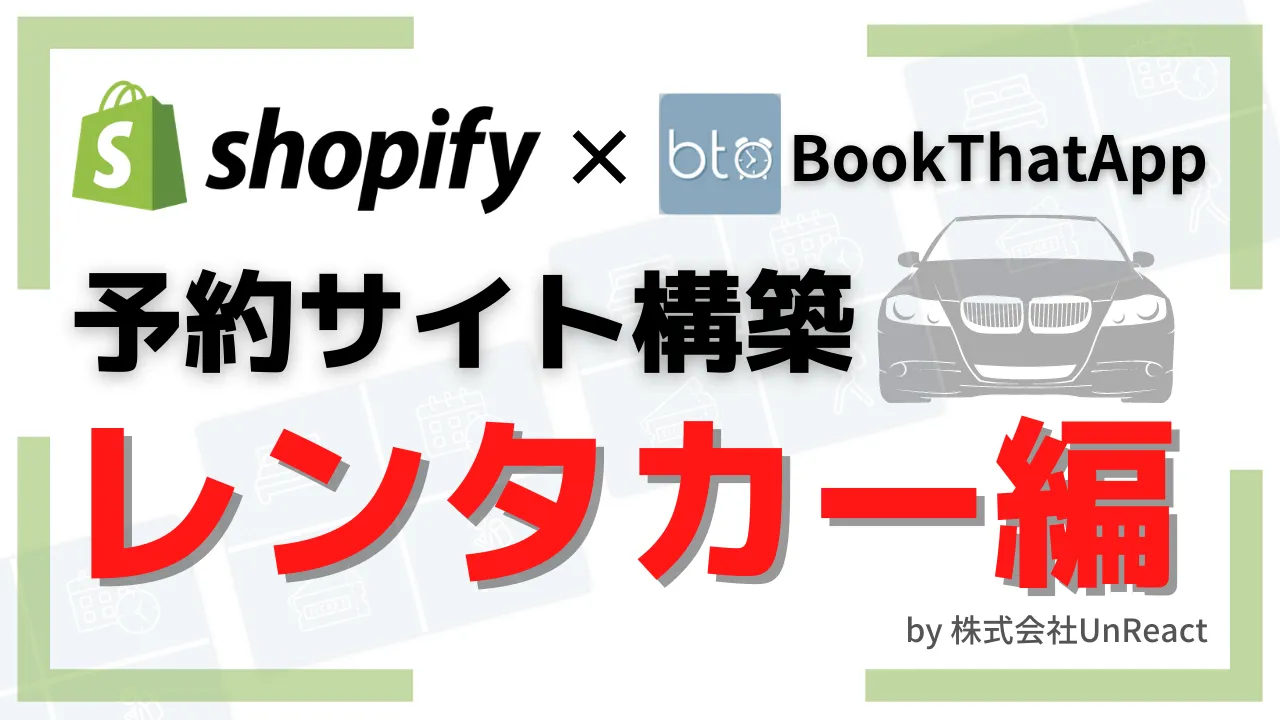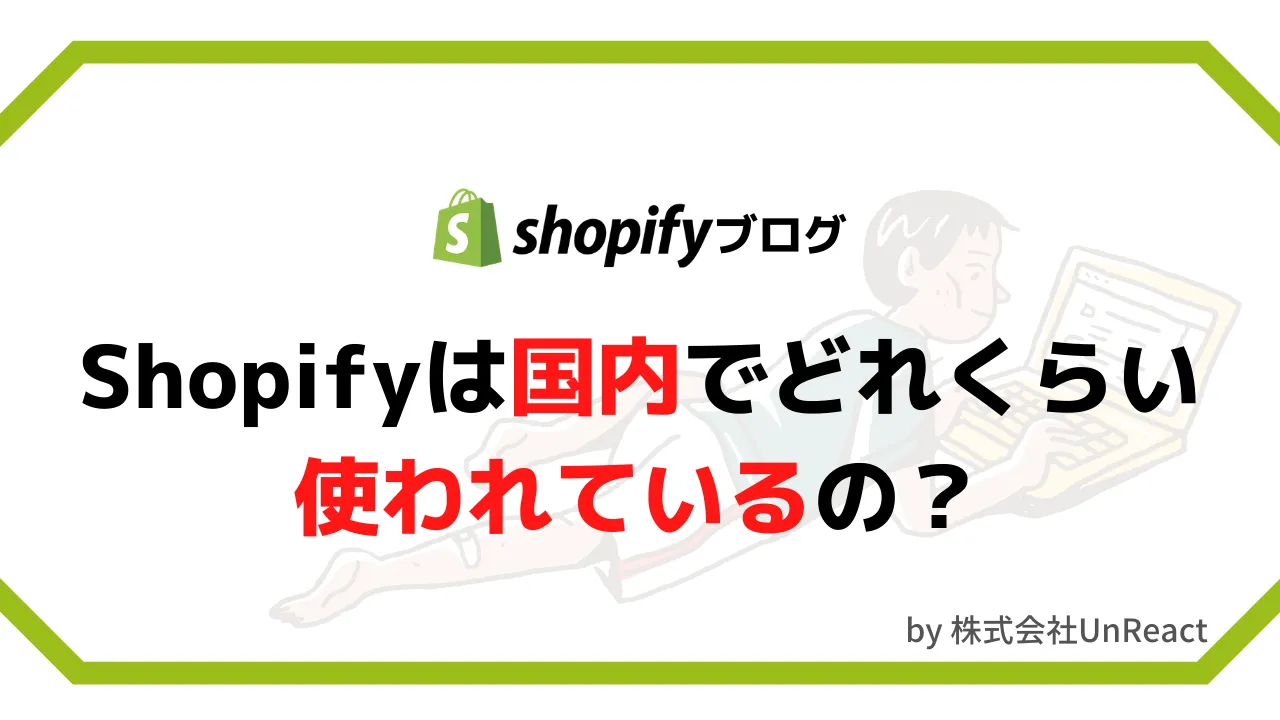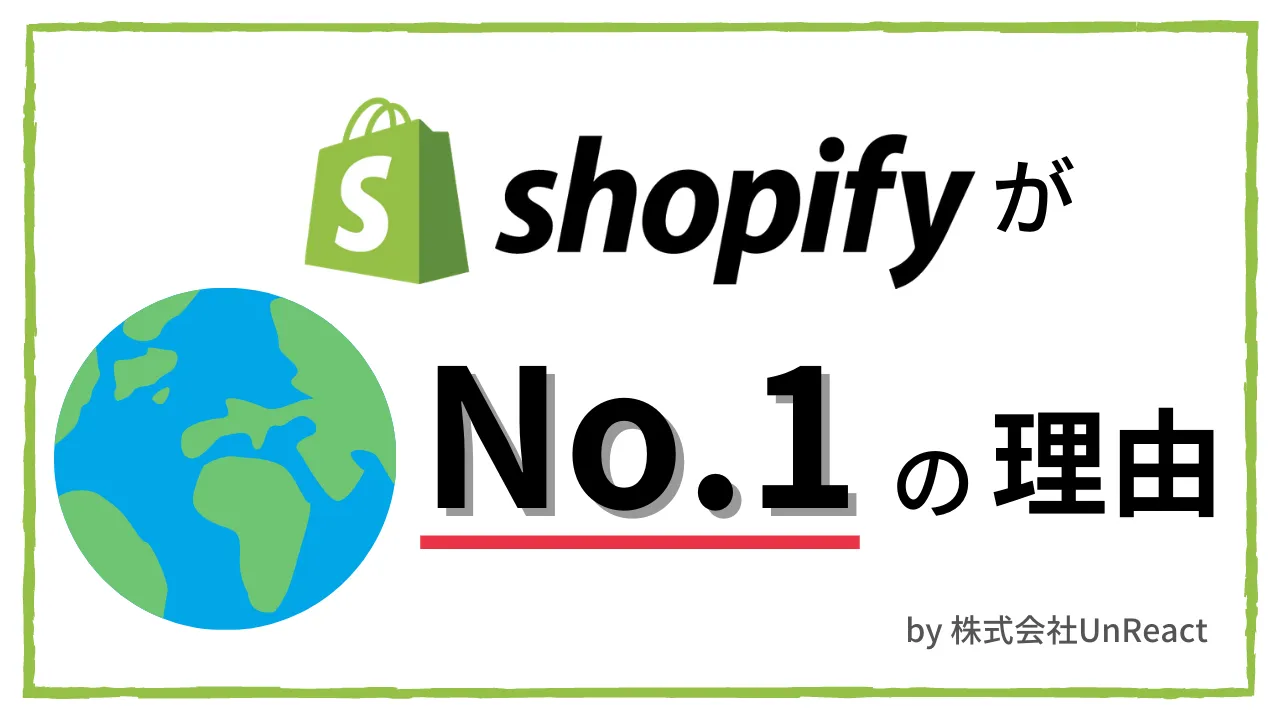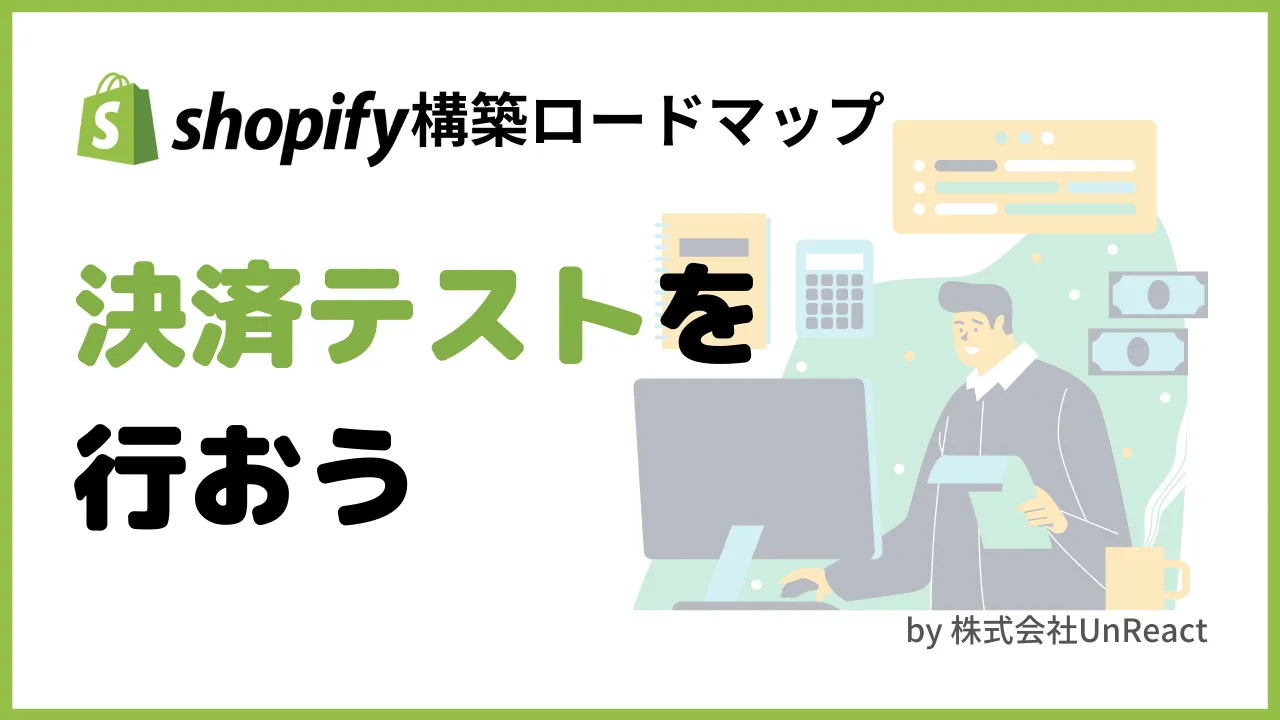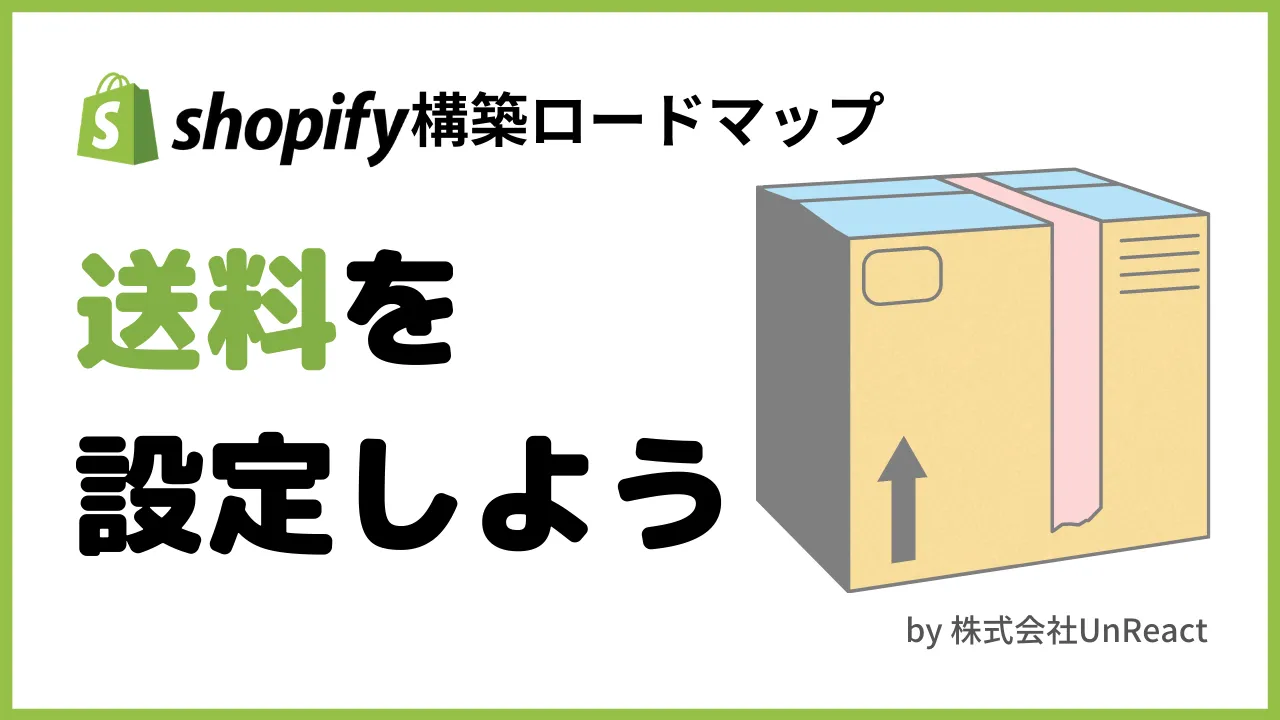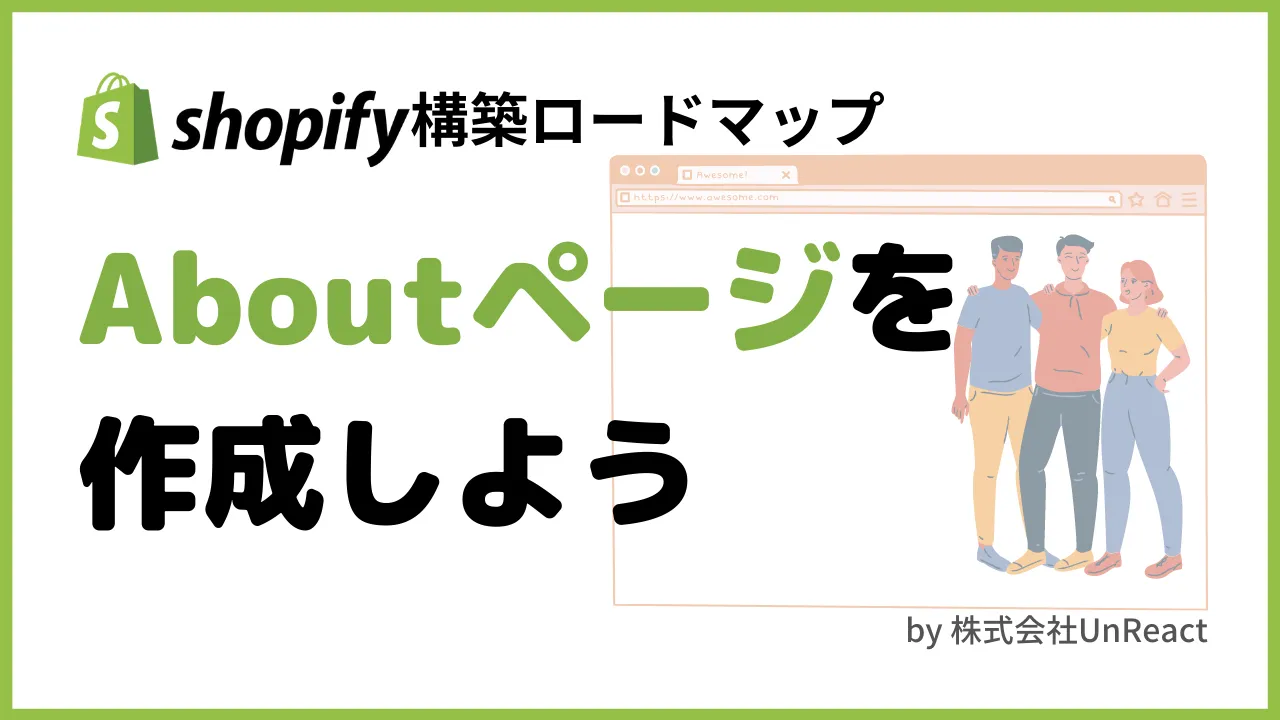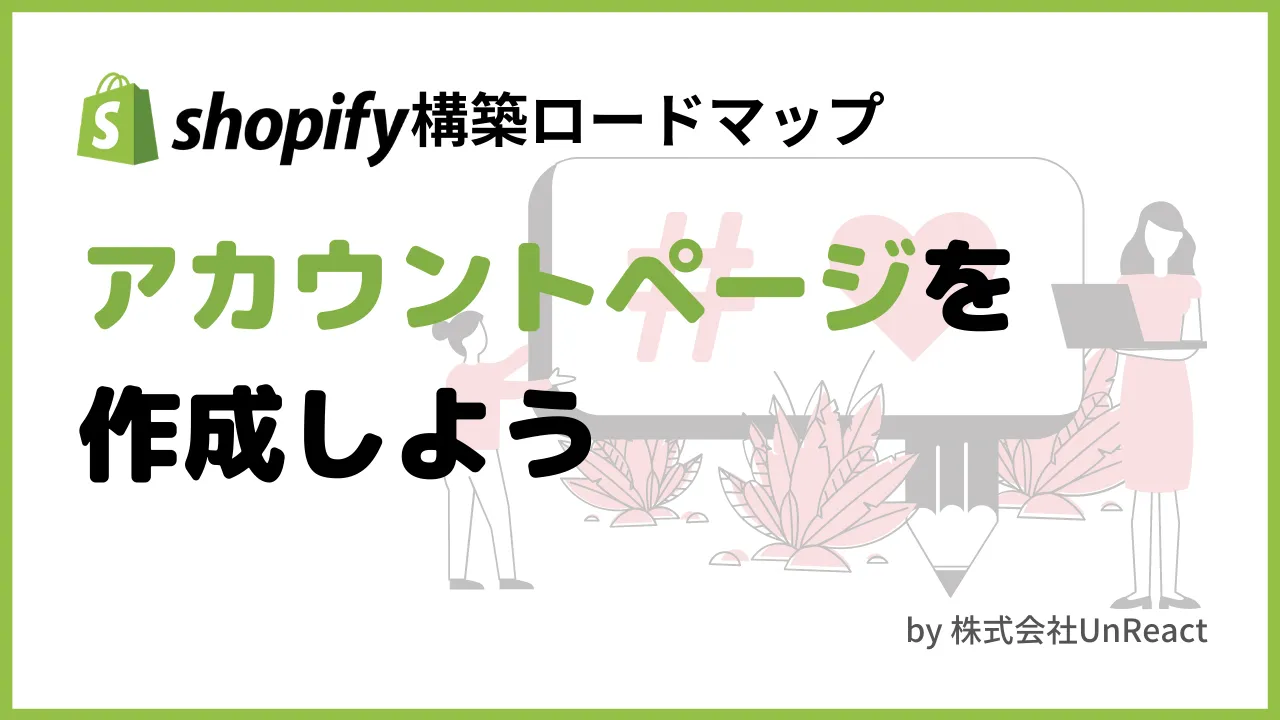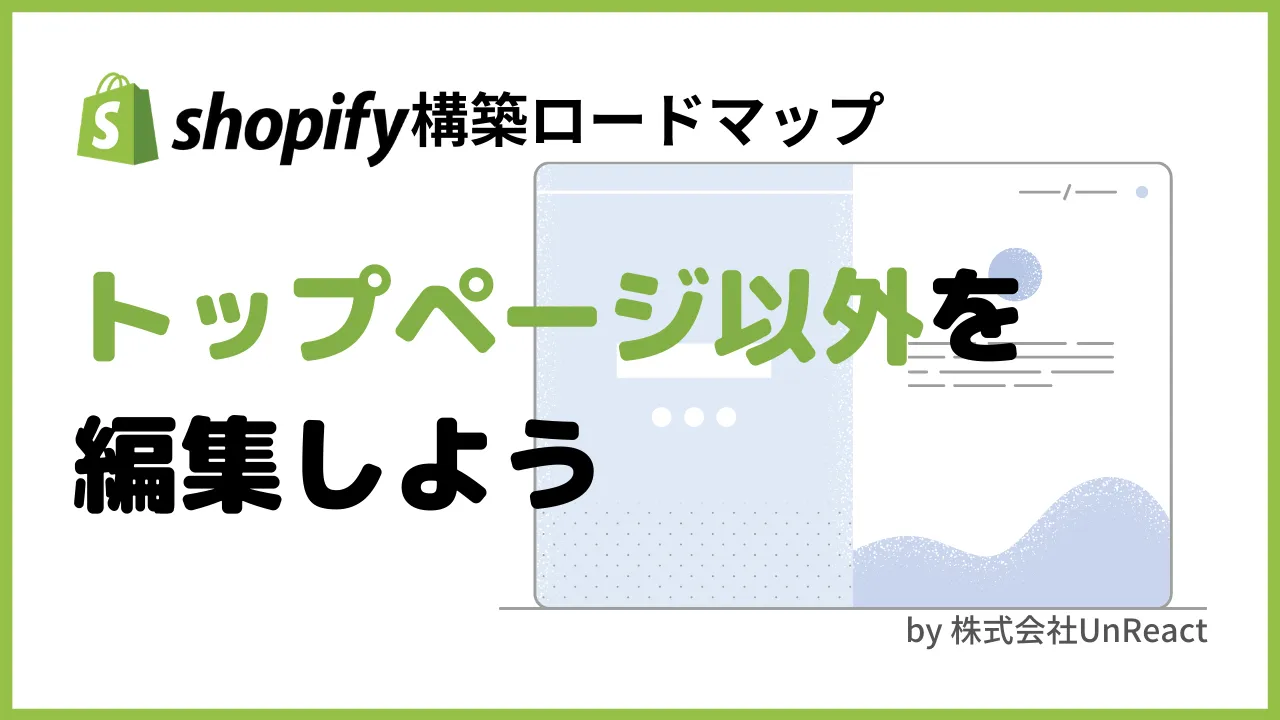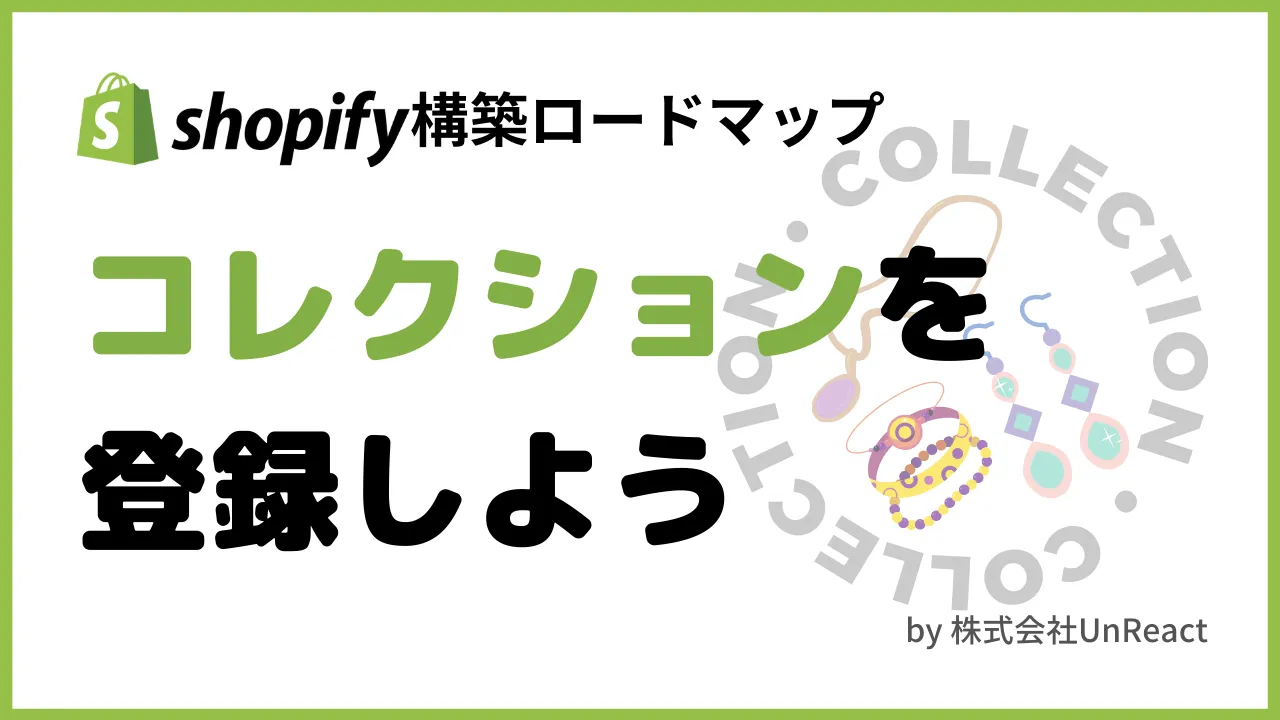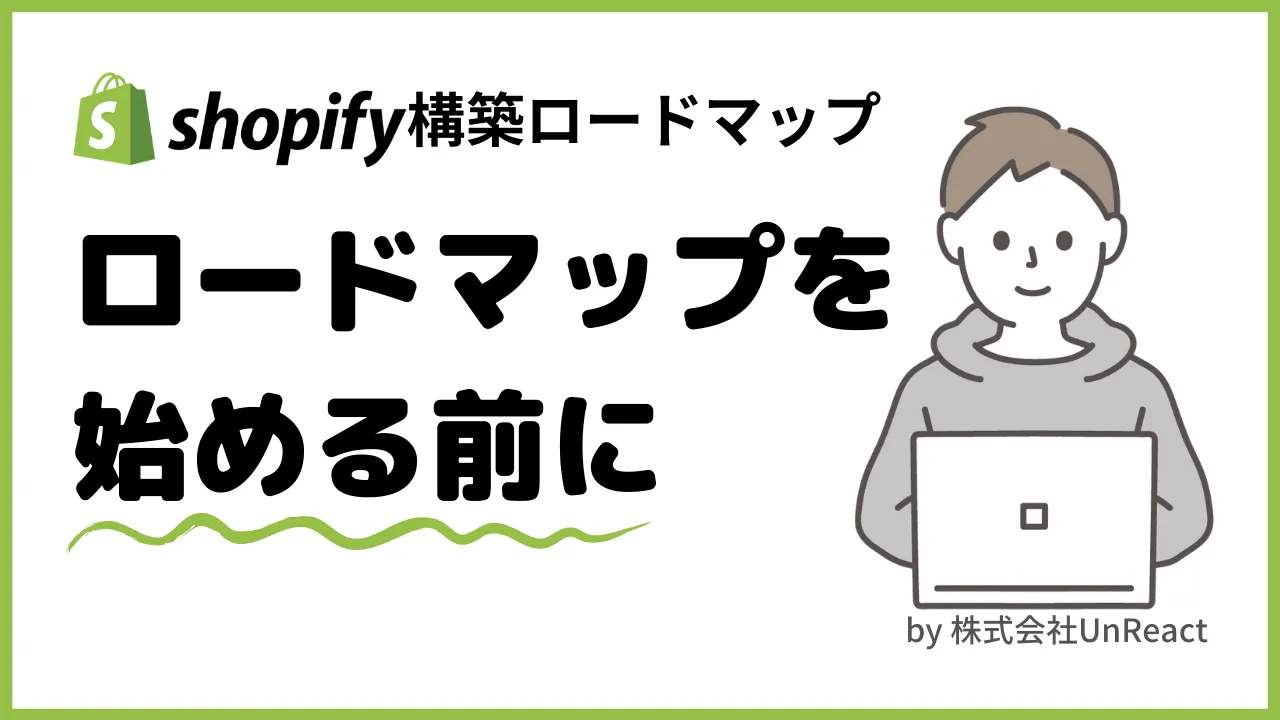【2025年】Shopify で代引き手数料を自動で計算することはできる?おすすめアプリを紹介!
目次
- はじめに
- Shopify の決済画面で代引き手数料を自動計算することはできる?
- ストアに代引き決済を導入するメリット・デメリット
- Shopify アプリを使うことで実現できる
- Shopify アプリを使って実装することによるメリット・デメリット
- おすすめ Shopify アプリ「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」の紹介
- 「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」のインストール手順と使用方法
- 運用時の注意点やトラブルシューティング
- まとめ
はじめに
2025 年現在、日本の EC 市場はさらなる拡大を続けています。海外プラットフォームをはじめ、多様なカートシステムが導入される中で、Shopify は豊富なアプリと拡張性の高さから多くの事業者に支持され、国内でも店舗数を伸ばしています。
しかし、海外発のサービスである Shopify には、日本国内の商習慣に完全対応していない部分がいくつかあります。その中でも多くの事業者が気にするのが 代引き決済 の取り扱いです。特に「代引き手数料を商品や送料と合わせて自動で計算したい」という要望は多いですが、標準機能だけでは難しい点があるのが現状です。
本記事では、Shopify で代引き手数料を自動で計算する方法 について、2025 年現在の最新動向を踏まえながら解説します。ストアに代引き決済を導入するメリット・デメリットや、具体的にどのように自動計算を実装するのか、そして実装する際におすすめの Shopify アプリとして 「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」 を紹介します。「代引き決済を取り入れたいけど、手数料計算が面倒」「Shopify で代引き決済を導入したら注文管理が煩雑にならないか不安」といった方は、ぜひ最後までお読みください。
今回は、以下の記事を参考にしています。
- Shopifyで代引き手数料を自動計算する方法について考察してみた
- Shopifyで代引き手数料を自動計算する方法5つを紹介!
- Shopify で代引き手数料の自動計算を実現できるアプリ 8 選!
- Shopify ストアで代引きを設定する方法を徹底解説!
- Shopifyで代引き手数料を自動計算できるアプリについて徹底解説|ご利用ガイド
Shopify の決済画面で代引き手数料を自動計算することはできる?
Shopify は元々、海外事業者がクレジットカードや PayPal、Apple Pay、Shop Pay などをメインに導入している背景から設計されています。そのため、日本国内の EC サイトで一般的に利用される 「代金引換(代引き)」 決済の機能が標準で充実しているとは言い難いのが実情です。
Shopify 標準機能の限界
一部の日本向け拡張機能や設定によって、代引き決済の「支払い方法」を追加することは可能です。しかし、それだけでは 「代金引換手数料を自動計算してカートや決済画面に反映させる」 というところまでは実装できません。具体的には、以下のような課題があります。
- 送料設定や割引コードとの組み合わせが複雑
一緒に合計額を算出する際、代引き手数料が優先的に加算されない場合がある。 - 支払い方法ごとに別途手数料を加算する機能がない
Shopify 管理画面上では支払い方法の選択によって自動加算する仕組みが標準では用意されていない。 - テーマやエディターでの表示の問題
無理やり代替手段で計算させると、フロント画面で誤表示やエラーが起きるリスクがある。
こうした理由から、Shopify で代引き決済を最適に導入したい場合、専用のアプリ を導入するか、カスタム開発で実装していく必要があるのです。
ストアに代引き決済を導入するメリット・デメリット
「代引き決済は日本国内では根強いニーズがある」という認識は多くの EC 事業者の共通認識でしょう。しかし、実際に導入するうえではメリットだけでなくデメリットも理解しておく必要があります。
代引き決済を導入する主なメリット

クレジットカードを使わない層への対応
クレジットカードを持たない、もしくは オンライン決済への不安 があるお客様にとって、代引きは安心して買い物できる決済手段です。幅広い顧客層を取り込むことができるため、カート離脱の防止 に役立ちます。
発送と代金回収を同時に行える
運送業者が商品を届ける際に代金を受け取るため、事業者側が新たに請求作業を行う必要がありません。後払い のような与信リスクも小さく、業務フローがシンプルになる場合もあります。
信頼感・安心感の向上
日本では代引きが昔から馴染み深い決済方法であり、「商品が届いてから支払いたい」というお客様の心理を満たせます。ブランド認知がまだ浅い EC サイトでも、代引き対応があることで安心感 を与えられます。
代引き決済を導入する主なデメリット

手数料の負担増
お客様にとっては商品代金+配送料+代引き手数料という形で合計が高くなる場合があります。事業者が手数料を一部負担するケースもあり、コストが増加しがちです。
配送時のトラブルや返送リスク
お客様が受け取りを拒否したり、連絡がつかないなどの理由で 持ち帰り・返送 が発生するリスクがあります。商品は配送業者のもとに戻り、送料が無駄になるうえに在庫管理にも影響が出ます。
決済ステータスの管理が煩雑
クレジットカード決済や銀行振込と違い、支払いが実際にいつ完了したのか 管理画面で一元的に把握するのが難しくなります。配送ステータスと決済ステータスの紐付けを明確に設計しておかないと、受注処理に混乱が生じます。
Shopify アプリを使うことで実現できる
ここで登場するのが、Shopify アプリ です。

Shopify には公式・非公式を含め豊富なアプリが存在し、その中には日本国内の商習慣に合わせて 「代引き手数料の自動計算」 を実現するものがいくつか存在します。

アプリ導入で手数料自動加算を可能に
Shopify の管理画面では標準的に「支払い方法別の手数料加算」機能がありません。しかし、アプリを導入 することでユーザーがチェックアウト中に「代引き」を選択した場合にのみ、追加の手数料を自動で加算して合計金額に反映させることができます。
たとえば、「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」 のような国内向けアプリでは、日本独特の代引き文化を想定して作られているため、煩雑なカスタマイズなし で運用をスタートできます。
Shopify アプリを使って実装することによるメリット・デメリット
アプリを用いた代引き手数料の自動計算には多くの利点がありますが、導入に際しては以下のようなメリット・デメリットを把握しておきましょう。
アプリ活用のメリット
1. コーディング不要で導入できる
Shopify アプリをインストールし、管理画面上で必要項目を設定するだけで手数料自動計算が実現します。専門的な知識が不要 で短時間で導入できるのは大きなメリットです。
2. バージョンアップへの対応が容易
テーマや Shopify 本体のアップデート時、アプリ側でも随時対応してくれる場合が多いため、手動でのコード修正が最小限で済みます。特に公式アプリストアで提供されているものはメンテナンスやサポート体制がしっかりしているケースが多いです。
3. 日本国内の商習慣に特化した機能
クレジットカード決済が中心の海外と異なり、日本では代引きの利用率が根強いです。こうした国内向けアプリは 「いつ、どのように手数料を加算するか」 といった細やかな仕様に合わせて開発されているため、現場に即した使い方ができます。
アプリ活用のデメリット
1. アプリ利用コストの発生
多くのアプリがサブスクリプション形式で運用されており、月額料金 や売上連動型の手数料が発生する場合があります。運用規模や利益を踏まえて、コストに見合うかを判断する必要があります。
2. アプリ依存度の高まり
特定のアプリを導入すると、そのアプリのバージョンアップや不具合対応に左右されやすくなります。開発が停止してしまうリスクなども完全には否定できないため、信頼性 を見極めることが重要です。
3. 他アプリとの競合リスク
Shopify で複数のアプリを併用すると、コードや機能が競合する場合があります。結合テストや表示確認を怠ると、チェックアウト画面が崩れたり誤作動が起きるリスクがあるので注意してください。
おすすめ Shopify アプリ「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」の紹介
では、実際にどのアプリを導入すればよいのでしょうか。なかでも注目度が高いのが、「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」 です。

特徴

- 日本国内向けに特化した開発
代引き手数料や消費税、送料設定など、日本の EC シーンに合わせた仕様が整えられています。 - 直感的な管理画面
コーディング不要で、初心者でも数分で導入可能。チェックアウト時に手数料が自動加算される仕組みがわかりやすく設定できます。 - 自由度の高い手数料設定
「商品代金 + 送料 + オプション費用」などから手数料を算出することが可能。ショップ独自の料金規定があっても柔軟に対応できます。 - 豊富なサポート体制
国産アプリとして、日本語での問い合わせ・トラブル対応が充実しているため、何かあったときでも安心です。
料金形態
「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」は、月額料金 6.99 ドルで利用することができます。また、7 日間の無料期間があるので、安心してテストしてからストアに導入することができます。
「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」のインストール手順と使用方法
導入の流れは公式のご利用ガイドを参考にするとスムーズです。
この記事でも、簡単にアプリの使い方について解説していきます。
1. アプリをインストールする
-
Shopify アプリストア を開き、検索バーで 「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」 を検索、もしくはこちらのリンクからアプリ詳細ページにアクセスします。

-
アプリの詳細ページに移動し、「インストール」ボタンをクリックします。

-
Shopify 管理画面で権限確認の画面が出てきますので、問題なければそのまま進み、インストールを完了します。

-
アプリの管理画面が表示されれば、インストールは完了です。
2. 代引き決済の追加
まずは、決済画面に表示する決済方法として「代引き決済」を追加していきます。
-
アプリ管理画面の「ステップ 1: 代引き決済を追加する」のリンクから、決済の設定画面を開きます。

-
決済設定画面が開いたら、手動の決済方法セクション内の「手動の決済方法」をクリックし、ドロップダウンから「代金引換」を選択します。

-
選択肢が表示されるので「代金引換」を選択します。

-
代金引換の詳細や支払いの手順を入力するためのダイアログが開きます。今回は、テストとして導入するので、入力欄はからのまま「代金引換を有効化する」ボタンをクリックします。

-
手動の決済として代金引換が追加されていれば設定はこの設定は完了です。実際には Cash on Delivery (COD) と表記されます。

3. 代引き手数料の設定
次に代引き手数料を設定していきます。
「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」では、代引き専用の配送を作成し、その価格を「送料 + 代引き手数料」とすることで、代引き手数料を自動計算して決済できるようになっています。
今回の例では、以下の条件で代引き設定を作成してみたいと思います。
- 代引き決済ではない場合は、1,000 円の「通常配送」を表示
- 代引き決済かつ注文額 8,000 円未満の場合は 1,500 円の「代引き専用の配送」を表示(通常配送料 1,000 円 + 代引き手数料 500 円)
- 代引き決済かつ注文額 8,000 円以上の場合は 2,000 円の「代引き専用の配送」を表示(通常配送料 1,000 円 + 代引き手数料 1,000 円)
それでは実際に代引き手数料を含む配送方法を追加してみます。
-
アプリ管理画面の「ステップ 2: 代引き手数料を設定する」のリンクから、配送料の設定画面を開きます。

-
「配送と配達」の設定画面が開くので、「配送」のセクションで配送プロファイルを編集します。今回は「基本の配送料(基本のプロファイル)」を編集します。(ストアの配送プロファイルに合わせて対応してください。)

-
「配送エリア」で対象の配送エリアの「送料を追加」ボタンをクリックします。

-
追加する送料の情報を入力するダイアログが開くので、以下の内容を入力します。
- 料金タイプ: 「一定料金を利用」
- 配送料: 「カスタム」
- カスタム料金の名前: 「通常配送(代引き 8,000 円未満)」
- 価格: 「1,500」

-
同様の操作で、「通常配送(代引き 8,000 円以上)」の送料も追加してください。

-
設定を保存してください。

以上で代引き手数料の設定は完了です。
4. 配送方法の非表示設定
次に、設定されている代引き手数料(配送料)を適用する条件を設定します。この設定を行うことで、注文金額に応じた代引き手数料(配送料)の出しわけを行います。
この設定項目は代引きの手数料が複数ある場合のみ必要なので、手数料設定が 1 つの場合はスキップしてください。
今回は「お買い物金額の合計」を使って 8,000 円未満の場合と 8,000 円以上の場合で設定を行います。
-
アプリ管理画面の「ステップ 3: 配送方法を非表示に設定する」の「作成する」ボタンをクリックしてください。

-
「配送方法の非表示設定作成」画面に遷移するので、それぞれ入力していきます。

-
「配送方法の非表示設定名」には、設定名を入力します。この設定名は顧客に表示されない管理用の名前です。

-
「配送方法の非表示設定を有効化する」で、非表示にする条件を有効にするかどうかを設定できます。配送方法の非表示設定を有効にしている場合のみ、条件に一致する配送設定が非表示になります。

-
「条件設定」で、配送方法を非表示にする条件を設定します。条件は複数設定することができ、すべて満たす場合に、「非表示にする配送設定」で指定した配送方法が非表示になります。

-
「非表示にする配送設定」で、条件を満たしている場合に非表示にする配送設定を選択します。非表示にする配送設定を選択するので、条件とは逆の配送方法を選択する必要がある点に注意して設定をしてください。

-
「保存する」ボタンで設定を保存してください。
-
保存すると、設定が一覧として表示されます。同様の操作で、「合計金額が 8,000 円以上のとき通常配送(代引き 8,000 円未満)を非表示」にする設置を追加してください。

表に表示されている設定をクリックすると、配送方法の編集画面に遷移します。さらに、チェックをつけることで、設定の一括削除も可能です。
以上で、非表示設定は完了です。
5. 代引き以外の決済方法の非表示
最後に、決済画面で代引き手数料を含む配送が選択された際に代引き以外の決済方法(例えばクレジットカードなど)を非表示にするための設定をしていきます。
-
アプリ管理画面の「ステップ 4: 代引き以外の決済方法を非表示にする」の「作成する」ボタンをクリックしてください。

-
「代引き以外の決済方法の非表示」で、代引き用の配送設定の名前に含まれるテキストを設定します。今回設定した 2 つの配送設定名はともに「代引き」という文字列を含んでいるので、ここでは「代引き」と設定します。代引きの配送が選択されている場合に「代引き(Cash on delivery)」以外の決済方法を非表示にします。

-
「設定を有効化する」で、設定された文字列での決済の非表示を有効にするかどうかを設定できます。

-
「保存する」ボタンで、設定を保存してください。

6. 決済画面の挙動テスト
最後に、実際に決済画面を確認して、条件に基づいた設定が適用されるかどうかの挙動テストを行います。

以上が、「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」を使った手数料の自動計算の設定例です。アプリの無料期間もありますので、気になる方はぜひアプリをインストールして試してみてください。
運用時の注意点やトラブルシューティング
アプリを使うことで手軽に代引き手数料の自動計算が可能になりますが、運用する上ではいくつか注意するポイントや、想定されるトラブル事例があります。
1. 配送方法との連携
ショップによっては複数の配送方法(通常便・クール便・メール便など)を扱う場合があります。配送方法ごとに追加料金や制限 があるとき、代引き手数料の設定と競合しないよう調整が必要です。アプリの管理画面で配送方法別に手数料を設定できるかどうか確認しましょう。
2. 他アプリとの競合
Shopify で複数の料金関連アプリ(送料割引アプリ・割引クーポンアプリなど)を導入している場合、計算の優先順位 が原因で合計金額が想定と異なることがあります。アプリ開発元に問い合わせたり、テスト注文を繰り返すなどして競合を防ぎましょう。
3. お客様への事前告知
代引き手数料が発生することを事前に明記 していないと、お客様が決済画面で「こんなに手数料が高かったのか」と驚き、カート離脱してしまう可能性があります。商品ページやヘルプページなど、わかりやすい場所で手数料の有無を告知しておくことが重要です。
4. 返送リスクの管理
代引きは、お客様が受け取らなかったり連絡が取れなかったりすると返送されてしまいます。返送コストをどのように扱うのか、返品・返金ポリシーをどのように定めるのか、事前のルール設計 を明確にしておきましょう。
まとめ
Shopify は世界的に使われる EC プラットフォームであり、日本国内でも導入事例が急増しています。その一方で、代引き手数料の自動計算 のように国内独自の商習慣には標準機能だけでは不十分な面があります。しかし、Shopify アプリを使うことで問題はほぼ解決でき、特に 「シンプル代引き|お手軽代引き手数料自動計算アプリ」 のような国産アプリであれば、日本の EC 事業者が必要とする機能を手軽に実現可能です。

代引きは、クレジットカード以外の決済手段を求める層にとっては非常に重要なオプションであり、カート離脱防止や信頼感向上にも寄与します。ただし、導入後は返送リスクやコスト増などのデメリットもあるため、運用設計 をしっかり行いましょう。トラブルを想定したルール作りやアプリ設定、他アプリとの整合性チェックを行うことで、スムーズな販売体制を構築できます。
2025 年以降の EC 市場でも、ユーザーニーズに合わせた多様な決済手段を取り入れることが競争力強化につながります。Shopify ストアで代引き手数料を自動計算したい方は、今回紹介したアプリの導入をぜひ検討してみてください。 お客様にとって安心な決済体験を提供し、売上拡大を目指していきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今回は、以下の記事を参考にしています。